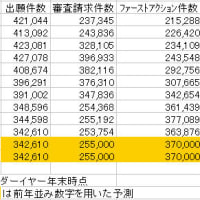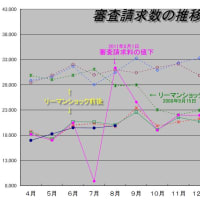事件番号 平成21(ワ)89等
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成21年11月26日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 阿部正幸
(3)上記によれば,原告は,実質的に同一の主張事実を前提とする紛争を蒸し返して,一部請求にしたり,あえて法律構成を変えるなどしたりして形式的に訴訟物が異なるものにして,勝訴の見込みのない訴訟を繰り返し提起しているといえ,第1事件に係る訴えも,上記の一環として提起されたものであると認められる。
そうすると,第1事件に係る訴えは,既に請求棄却の判決,あるいは,訴え却下の判決が確定して解決済みの事件について,あえて上記前訴事件と実質的に同一の請求及び主張を蒸し返し,前訴事件の確定判決によって,紛争が解決されたとの被告の合理的期待に反し,被告に重ねて応訴の負担を強いるものであるといえるから,訴権の濫用に当たり,許されないというべきである。
(4)以上のとおり,第1事件に係る訴えは,いずれも不適法な訴えであるから,却下されるべきものである。
2 第2事件について
(1)民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において,上記訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは,当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものである上,提訴者が,そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど,訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である(最高裁昭和60年 第122号,同63年1月26日第三小法廷判決,民集42巻1号1頁)。
そして,上記判示は,当該敗訴の確定判決に係る訴えの提起自体についての不法行為の該当性を判断する場合だけでなく,当該敗訴の確定判決後の,実質的に同一の訴訟の提起・維持に係る不法行為の該当性を判断する場合についても,妥当すると解するのが相当である。
(2)前記1で述べたとおり,原告が第1事件に係る訴えを提起することは,訴権の濫用に当たり,許されないものというべきである。
加えて,前記1(2)によれば,原告は,・・・,勝訴の見込みのない訴訟を繰り返し提起しているといえ,第1事件に係る訴えも,上記の一環として提起されたものであると認められることは,前記1(3)で説示したとおりであり,第1事件は,原告において,その主張する権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながらあえて提起し,これを維持したものであると評価せざるを得ない。
(3)以上によれば,第1事件の提起・維持は,裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものというべきであり,被告に対する不法行為を構成するものと解するのが相当である。
昭和60(オ)122,昭和63年01月26日 最高裁判所第三小法廷 判決
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成21年11月26日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 阿部正幸
(3)上記によれば,原告は,実質的に同一の主張事実を前提とする紛争を蒸し返して,一部請求にしたり,あえて法律構成を変えるなどしたりして形式的に訴訟物が異なるものにして,勝訴の見込みのない訴訟を繰り返し提起しているといえ,第1事件に係る訴えも,上記の一環として提起されたものであると認められる。
そうすると,第1事件に係る訴えは,既に請求棄却の判決,あるいは,訴え却下の判決が確定して解決済みの事件について,あえて上記前訴事件と実質的に同一の請求及び主張を蒸し返し,前訴事件の確定判決によって,紛争が解決されたとの被告の合理的期待に反し,被告に重ねて応訴の負担を強いるものであるといえるから,訴権の濫用に当たり,許されないというべきである。
(4)以上のとおり,第1事件に係る訴えは,いずれも不適法な訴えであるから,却下されるべきものである。
2 第2事件について
(1)民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において,上記訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは,当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものである上,提訴者が,そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど,訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である(最高裁昭和60年 第122号,同63年1月26日第三小法廷判決,民集42巻1号1頁)。
そして,上記判示は,当該敗訴の確定判決に係る訴えの提起自体についての不法行為の該当性を判断する場合だけでなく,当該敗訴の確定判決後の,実質的に同一の訴訟の提起・維持に係る不法行為の該当性を判断する場合についても,妥当すると解するのが相当である。
(2)前記1で述べたとおり,原告が第1事件に係る訴えを提起することは,訴権の濫用に当たり,許されないものというべきである。
加えて,前記1(2)によれば,原告は,・・・,勝訴の見込みのない訴訟を繰り返し提起しているといえ,第1事件に係る訴えも,上記の一環として提起されたものであると認められることは,前記1(3)で説示したとおりであり,第1事件は,原告において,その主張する権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながらあえて提起し,これを維持したものであると評価せざるを得ない。
(3)以上によれば,第1事件の提起・維持は,裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものというべきであり,被告に対する不法行為を構成するものと解するのが相当である。
昭和60(オ)122,昭和63年01月26日 最高裁判所第三小法廷 判決