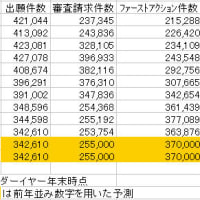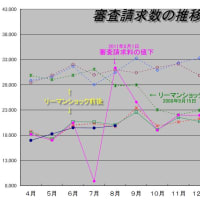事件番号 平成19(ネ)10021
事件名 補償金請求控訴事件
裁判年月日 平成21年02月26日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 中野哲弘
2 争点1(職務発明により生じた外国の特許を受ける権利の承継についての準拠法及び特許法35条の適用の有無)について
(1) 職務発明により生じた外国の特許を受ける権利等の承継の準拠法につき一審原告が,被告取扱規程により,その職務発明である本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明に係る特許を受ける権利を一審被告が承継し,一審被告がこれらについて特許出願をし,特許を得たことは,原判決の「第2事案の概要」「1 前提となる事実」のとおりであり,この承継については,その対象となる権利が職務発明についての外国の特許を受ける権利である点において,渉外的要素を含むものであるから,まずその準拠法を決定する必要がある。
上記承継は,日本法人である一審被告と,我が国に在住して一審被告の従業員として勤務していた日本人である一審原告とが,一審原告がした職務発明について被告取扱規程に基づき我が国で行ったものであり,一審原告と一審被告との間には,原判決も認定するように上記承継の成立及び効力の準拠法を我が国の法律とする旨の黙示の合意が存在すると認められる。
そして,外国の特許を受ける権利の譲渡に伴って譲渡人が譲受人に対しその対価を請求できるかどうか,その対価の額はいくらであるかなどの特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題は,譲渡の当事者がどのような債権債務を有するかという問題にほかならず,譲渡当事者間における譲渡の原因関係である契約その他の債権的法律行為の効力の問題であると解されるから,その準拠法は,平成18年法律第78号として制定された法の適用に関する通則法の第7条(同条の規定は,それ以前の法条である法例[明治31年法律第10号]7条1項とほぼ同じ。上記通則法7条は,附則2条により,遡及適用される。)により,第1次的には当事者の意思に従って定められると解するのが相当である(最高裁平成18年10月17日第三小法廷判決・民集60巻8号2853頁参照)。
本件においては,一審原告と一審被告との間には,承継の成立及び効力につきその準拠法を我が国の法律とする旨の黙示の合意が存在しているのであるから,特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題については,我が国の法律が準拠法となるというべきである。
(2) 外国の特許を受ける権利の承継に対する旧35条3項及び4項の適用につきア外国の特許を受ける権利の承継に対する旧35条3項及び4項の類推適用について
我が国の特許法が外国の特許又は特許を受ける権利について直接規律するものではないことは明らかであり,旧35条1項及び2項にいう「特許を受ける権利」が我が国の特許を受ける権利を指すものと解さざるを得ないことなどに照らし,同条3項にいう「特許を受ける権利」についてのみ外国の特許を受ける権利が含まれると解することは,文理上困難であって,外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価の請求について同項及び同条4項の規定を直接適用することはできないといわざるを得ない。
しかし,・・・そうすると,同条3項及び4項の規定については,その趣旨を外国の特許を受ける権利にも及ぼすべき状況が存在するというべきである。
したがって,従業者等が旧35条1項所定の職務発明に係る外国の特許を受ける権利を使用者等に譲渡した場合において,当該外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求については,同条3項及び4項の規定が類推適用されると解するのが相当である(最高裁平成18年10月17日第三小法廷判決・民集60巻8号2853頁)。
・・・
なお,外国特許を受ける権利の対価算定に際し,その減額要素として旧35条1項(いわゆる法定通常実施権)を考慮するのかという論点が残るが,前記のとおり,当該発明をした従業員等と使用者等との間の当該発明に関する法律関係を一元的に処理しようとする前記の立場を前提とすれば,法定通常実施権を認めない外国特許の場合であっても,少なくとも譲渡対価算定という債権関係の処理としては,旧35条1項の類推適用を肯定した上でその対価を算定すべきものと解するのが相当である。
事件名 補償金請求控訴事件
裁判年月日 平成21年02月26日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 中野哲弘
2 争点1(職務発明により生じた外国の特許を受ける権利の承継についての準拠法及び特許法35条の適用の有無)について
(1) 職務発明により生じた外国の特許を受ける権利等の承継の準拠法につき一審原告が,被告取扱規程により,その職務発明である本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明に係る特許を受ける権利を一審被告が承継し,一審被告がこれらについて特許出願をし,特許を得たことは,原判決の「第2事案の概要」「1 前提となる事実」のとおりであり,この承継については,その対象となる権利が職務発明についての外国の特許を受ける権利である点において,渉外的要素を含むものであるから,まずその準拠法を決定する必要がある。
上記承継は,日本法人である一審被告と,我が国に在住して一審被告の従業員として勤務していた日本人である一審原告とが,一審原告がした職務発明について被告取扱規程に基づき我が国で行ったものであり,一審原告と一審被告との間には,原判決も認定するように上記承継の成立及び効力の準拠法を我が国の法律とする旨の黙示の合意が存在すると認められる。
そして,外国の特許を受ける権利の譲渡に伴って譲渡人が譲受人に対しその対価を請求できるかどうか,その対価の額はいくらであるかなどの特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題は,譲渡の当事者がどのような債権債務を有するかという問題にほかならず,譲渡当事者間における譲渡の原因関係である契約その他の債権的法律行為の効力の問題であると解されるから,その準拠法は,平成18年法律第78号として制定された法の適用に関する通則法の第7条(同条の規定は,それ以前の法条である法例[明治31年法律第10号]7条1項とほぼ同じ。上記通則法7条は,附則2条により,遡及適用される。)により,第1次的には当事者の意思に従って定められると解するのが相当である(最高裁平成18年10月17日第三小法廷判決・民集60巻8号2853頁参照)。
本件においては,一審原告と一審被告との間には,承継の成立及び効力につきその準拠法を我が国の法律とする旨の黙示の合意が存在しているのであるから,特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題については,我が国の法律が準拠法となるというべきである。
(2) 外国の特許を受ける権利の承継に対する旧35条3項及び4項の適用につきア外国の特許を受ける権利の承継に対する旧35条3項及び4項の類推適用について
我が国の特許法が外国の特許又は特許を受ける権利について直接規律するものではないことは明らかであり,旧35条1項及び2項にいう「特許を受ける権利」が我が国の特許を受ける権利を指すものと解さざるを得ないことなどに照らし,同条3項にいう「特許を受ける権利」についてのみ外国の特許を受ける権利が含まれると解することは,文理上困難であって,外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価の請求について同項及び同条4項の規定を直接適用することはできないといわざるを得ない。
しかし,・・・そうすると,同条3項及び4項の規定については,その趣旨を外国の特許を受ける権利にも及ぼすべき状況が存在するというべきである。
したがって,従業者等が旧35条1項所定の職務発明に係る外国の特許を受ける権利を使用者等に譲渡した場合において,当該外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求については,同条3項及び4項の規定が類推適用されると解するのが相当である(最高裁平成18年10月17日第三小法廷判決・民集60巻8号2853頁)。
・・・
なお,外国特許を受ける権利の対価算定に際し,その減額要素として旧35条1項(いわゆる法定通常実施権)を考慮するのかという論点が残るが,前記のとおり,当該発明をした従業員等と使用者等との間の当該発明に関する法律関係を一元的に処理しようとする前記の立場を前提とすれば,法定通常実施権を認めない外国特許の場合であっても,少なくとも譲渡対価算定という債権関係の処理としては,旧35条1項の類推適用を肯定した上でその対価を算定すべきものと解するのが相当である。