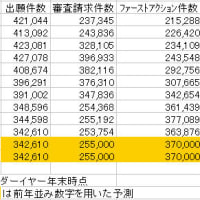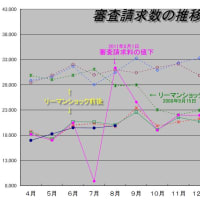事件番号 平成19(ネ)10021
事件名 補償金請求控訴事件
裁判年月日 平成21年02月26日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 中野哲弘
5 争点3-1(一審被告の包括クロスライセンス契約と利益の額の算定方式)
について
(1) 総説
ア ライセンス契約により得た利益の額
特許権者が単数の特許について競業他社とライセンス契約を締結した場合,当該契約により得られる実施料収入は,当該特許に基づいて使用者が得る独占の利益であるというべきであるから,これを旧35条4項の「その発明により使用者が得ることができる利益の額」とみることができる。
また,複数の特許発明が単一のライセンス契約(実施許諾)の対象となっている場合には,当該発明により「使用者が受けるべき利益の額」を算定するに当たっては,当該発明が当該ライセンス契約締結に寄与した程度を考慮すべきである。
イ 包括クロスライセンス契約により得た利益の額
包括クロスライセンス契約は,当事者双方が多数の特許発明等の実施を相互に許諾し合う契約であるから,当該契約において,一方当事者が自己の保有する特許発明等の実施を相手方に許諾することによって得るべき利益とは,相手方が保有する複数の特許発明等を無償で実施することができること,すなわち,相手方に本来支払うべきであった実施料の支払義務を免れることであると解することができる。
したがって,包括クロスライセンス契約においては,相互に無償で実施を許諾する特許発明等とそれが均衡しないときに支払われる実施料の額が総体として相互に均衡すると考えて契約を締結したと考えるのが合理的であるから,相手方が自己の特許発明を実施することにより,本来,相手方から支払を受けるべきであった実施料の額及び相手方から現実に支払われた実施料の額の合計額を基準として算定することも許されると解される。
(2) エレクトロニクス業界における包括クロスライセンス契約
ア エレクトロニクス業界における包括クロスライセンス契約の意義
エレクトロニクスの分野においては,一つの製品に数千にも及ぶ技術が使用されていることもまれではなく,個々の特許権を個別に行使することはその侵害の有無の調査においても,多大なコストを要する。また,個々の特許権を個別に行使することとなれば,関係各社が自社の特許をそれぞれ行使し合う結果となり,社会全体としてみると,製品化が事実上不可能となる。
したがって,お互いの特許権をまとめて許諾し合い,製品化を実現し,一社での限定された生産能力を超えて大量に製品を販売できるようにするというのが合理的な選択行動であり,エレクトロニクス業界においては,ある一定期間中にお互いに自己の保有する関連特許すべてを許諾し合う包括クロスライセンス契約を締結することが多い(乙211)。
・・・
イ エレクトロニクス業界における包括クロスライセンス契約における個々の特許の寄与度
このような包括クロスライセンス契約を締結する場合,その交渉において,多数の特許のすべてについて,逐一,その技術的価値,実施の有無などを正確に評価し合うことは事実上不可能であるから,相互に一定件数の相手方が実施している可能性が高い特許や技術的意義が高い基本特許を相手方に提示し,それら特許に相手方の製品が抵触するかどうか,当該特許の有効性及び実施品の売上高等について協議することにより,相手方製品との抵触性及び有効性が確認された代表特許と対象製品の売上高を比較考慮すること,及び,互いに保有する特許の件数や出願中の特許の件数も比較考慮することにより,包括クロスライセンス契約におけるバランス調整金の有無などの条件が決定されるものである(乙211。以下,単に提示された特許を「提示特許」といい,提示特許のうち,相手方製品との抵触性及び有効性が確認された特許を「代表特許」という。)。
そうすると,エレクトロニクスの業界のように,数千件ないし1万件を超える特許が対象となる包括クロスライセンス契約においては,相手方に提示され代表特許として認められた特許以外の特許については,数千件ないし1万件を超える特許のうちの一つとして,その他の多数の特許と共に厳密な検討を経ることなく実施許諾に至ったものも相当数含まれるというべきであるから,このような特許については,当該包括クロスライセンス契約に含まれている特許の一つであるということだけでは,上記「利益の額」を算定に当たって当然に考慮すべきであるということにはならない。
ただし,代表特許でも提示特許でもなくとも,ライセンス契約締結当時において相手方が実施していたことが立証された特許については,ライセンス契約締結時にその存在が相手方に認識されていた可能性があり,また,特許権者が包括クロスライセンス契約の締結を通じて禁止権を行使しているものということができるから,このような相手方実施特許については,代表特許でも提示特許でもなくとも,上記「利益の額」を算定するに当たって考慮することができるというべきである。
事件名 補償金請求控訴事件
裁判年月日 平成21年02月26日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 中野哲弘
5 争点3-1(一審被告の包括クロスライセンス契約と利益の額の算定方式)
について
(1) 総説
ア ライセンス契約により得た利益の額
特許権者が単数の特許について競業他社とライセンス契約を締結した場合,当該契約により得られる実施料収入は,当該特許に基づいて使用者が得る独占の利益であるというべきであるから,これを旧35条4項の「その発明により使用者が得ることができる利益の額」とみることができる。
また,複数の特許発明が単一のライセンス契約(実施許諾)の対象となっている場合には,当該発明により「使用者が受けるべき利益の額」を算定するに当たっては,当該発明が当該ライセンス契約締結に寄与した程度を考慮すべきである。
イ 包括クロスライセンス契約により得た利益の額
包括クロスライセンス契約は,当事者双方が多数の特許発明等の実施を相互に許諾し合う契約であるから,当該契約において,一方当事者が自己の保有する特許発明等の実施を相手方に許諾することによって得るべき利益とは,相手方が保有する複数の特許発明等を無償で実施することができること,すなわち,相手方に本来支払うべきであった実施料の支払義務を免れることであると解することができる。
したがって,包括クロスライセンス契約においては,相互に無償で実施を許諾する特許発明等とそれが均衡しないときに支払われる実施料の額が総体として相互に均衡すると考えて契約を締結したと考えるのが合理的であるから,相手方が自己の特許発明を実施することにより,本来,相手方から支払を受けるべきであった実施料の額及び相手方から現実に支払われた実施料の額の合計額を基準として算定することも許されると解される。
(2) エレクトロニクス業界における包括クロスライセンス契約
ア エレクトロニクス業界における包括クロスライセンス契約の意義
エレクトロニクスの分野においては,一つの製品に数千にも及ぶ技術が使用されていることもまれではなく,個々の特許権を個別に行使することはその侵害の有無の調査においても,多大なコストを要する。また,個々の特許権を個別に行使することとなれば,関係各社が自社の特許をそれぞれ行使し合う結果となり,社会全体としてみると,製品化が事実上不可能となる。
したがって,お互いの特許権をまとめて許諾し合い,製品化を実現し,一社での限定された生産能力を超えて大量に製品を販売できるようにするというのが合理的な選択行動であり,エレクトロニクス業界においては,ある一定期間中にお互いに自己の保有する関連特許すべてを許諾し合う包括クロスライセンス契約を締結することが多い(乙211)。
・・・
イ エレクトロニクス業界における包括クロスライセンス契約における個々の特許の寄与度
このような包括クロスライセンス契約を締結する場合,その交渉において,多数の特許のすべてについて,逐一,その技術的価値,実施の有無などを正確に評価し合うことは事実上不可能であるから,相互に一定件数の相手方が実施している可能性が高い特許や技術的意義が高い基本特許を相手方に提示し,それら特許に相手方の製品が抵触するかどうか,当該特許の有効性及び実施品の売上高等について協議することにより,相手方製品との抵触性及び有効性が確認された代表特許と対象製品の売上高を比較考慮すること,及び,互いに保有する特許の件数や出願中の特許の件数も比較考慮することにより,包括クロスライセンス契約におけるバランス調整金の有無などの条件が決定されるものである(乙211。以下,単に提示された特許を「提示特許」といい,提示特許のうち,相手方製品との抵触性及び有効性が確認された特許を「代表特許」という。)。
そうすると,エレクトロニクスの業界のように,数千件ないし1万件を超える特許が対象となる包括クロスライセンス契約においては,相手方に提示され代表特許として認められた特許以外の特許については,数千件ないし1万件を超える特許のうちの一つとして,その他の多数の特許と共に厳密な検討を経ることなく実施許諾に至ったものも相当数含まれるというべきであるから,このような特許については,当該包括クロスライセンス契約に含まれている特許の一つであるということだけでは,上記「利益の額」を算定に当たって当然に考慮すべきであるということにはならない。
ただし,代表特許でも提示特許でもなくとも,ライセンス契約締結当時において相手方が実施していたことが立証された特許については,ライセンス契約締結時にその存在が相手方に認識されていた可能性があり,また,特許権者が包括クロスライセンス契約の締結を通じて禁止権を行使しているものということができるから,このような相手方実施特許については,代表特許でも提示特許でもなくとも,上記「利益の額」を算定するに当たって考慮することができるというべきである。