今年も残すところ3週間。そろそろ振り返りをしたい時期になりました。今日はその第1回として「7年ぶりの夏目漱石内坪井旧居再公開」を選びました。
五高教師として熊本で4年3ヶ月を暮した漱石は、その間6回もの転居を繰り返しましたが、その中で最も長い1年8ヶ月を暮したのが5番目の内坪井旧居。2016年4月の熊本地震で大きく損壊し、ずっと休館が続いていました。この漱石旧居前は普段からよく通るので、いつから復旧工事が始まるのだろうと通る度に思っていましたが、3年前に復旧工事が始まり、今年に入ってやっと工事が完了し、漱石の誕生日である2月9日に公開を再開しました。約7年ぶりの公開です。僕自身も2016年1月に訪れて以来、7年ぶりの入館となりました。

内坪井旧居再開翌日(2023.2.10)の風景
再開後、今では毎月、漱石にちなんだ行事が行われており、10月には舞踊団花童が初めてここで公演を行ないました。漱石が熊本にいた頃、東阿弥陀寺町にあった東雲座(明治21年開業)で、鏡子夫人が女歌舞伎をご覧になったことがあるそうで、もし鏡子夫人が今回ご覧になっていれば大変喜ばれただろうと思います。
五高教師として熊本で4年3ヶ月を暮した漱石は、その間6回もの転居を繰り返しましたが、その中で最も長い1年8ヶ月を暮したのが5番目の内坪井旧居。2016年4月の熊本地震で大きく損壊し、ずっと休館が続いていました。この漱石旧居前は普段からよく通るので、いつから復旧工事が始まるのだろうと通る度に思っていましたが、3年前に復旧工事が始まり、今年に入ってやっと工事が完了し、漱石の誕生日である2月9日に公開を再開しました。約7年ぶりの公開です。僕自身も2016年1月に訪れて以来、7年ぶりの入館となりました。

内坪井旧居再開翌日(2023.2.10)の風景
再開後、今では毎月、漱石にちなんだ行事が行われており、10月には舞踊団花童が初めてここで公演を行ないました。漱石が熊本にいた頃、東阿弥陀寺町にあった東雲座(明治21年開業)で、鏡子夫人が女歌舞伎をご覧になったことがあるそうで、もし鏡子夫人が今回ご覧になっていれば大変喜ばれただろうと思います。
漱石旧居座敷で踊る舞踊団花童
今日は夏目漱石内坪井旧居で行われたイベント「漱石気分で能を楽しむ」に参加した。観世流の薬師堂隆子先生による「お能のイロハ」のお話の後、薬師堂先生と茨木國夫先生お二方により「高砂」と「井筒」の仕舞披露があった。その後、参加者全員により能の所作の基本である「カマエ」と「ハコビ」および扇のかざし方について先生の指導を受けながら体験した。能の公演は何度も拝見しているが、自ら所作をやってみたのは初めて。なかなか難しいものだ。
漱石と能については、7年前の漱石来熊120年記念年の際、演能が予定されていたにもかかわらず、実現することなく終わったことはガッカリした。新作能の企画がまとまらなかったらしいが、われわれ能楽ファンは何も新作能を期待しているわけではない。「熊野」でも「高砂」でもいいし、2002年に法政大学能楽研究所が創作した新作能「草枕」でもよかったと思う。次は来熊130年になるのか、140年になるのかわからないが、ぜひ演能を実現してほしい。そんなことを思いながら漱石内坪井旧居を後にした。

先生方による仕舞披露
漱石と能については、7年前の漱石来熊120年記念年の際、演能が予定されていたにもかかわらず、実現することなく終わったことはガッカリした。新作能の企画がまとまらなかったらしいが、われわれ能楽ファンは何も新作能を期待しているわけではない。「熊野」でも「高砂」でもいいし、2002年に法政大学能楽研究所が創作した新作能「草枕」でもよかったと思う。次は来熊130年になるのか、140年になるのかわからないが、ぜひ演能を実現してほしい。そんなことを思いながら漱石内坪井旧居を後にした。

先生方による仕舞披露
今夜のブラタモリは四国・宇和島編。個人的に興味がある地域だった。それは15年前、妻と二人で四国旅行をした時、回り切れなかったのが四国の西側地域だったから。大分の佐伯からフェリーで高知の宿毛に渡り、太平洋沿いに反時計回りに旅した。高知―徳島―香川と回り、愛媛は松山まで行った後、今治からしまなみ海道で広島の尾道に渡った。実は愛媛は内子座や高校水球で対戦していた大洲高校や宇和島城など行ってみたいところがいくつかあった。しかし、スケジュールがタイトで断念したのが心残りだった。
今夜ブラタモリで見た宇和島は、僕が抱いていたイメージと大きく異なっていた。それは、宇和島は温暖な気候のもと、豊かな田園が広がっているというイメージだったからだ。番組のキーワードだった「ギザギザ」のリアス式海岸。山が海に迫り、平地は限られ、米が作れない厳しい農業環境にありながら見事な石積みの段畑を築き上げたさつまいも畑。一方、「ギザギザ」を活用した豊かな漁業。いずれもが新鮮な驚きだった。チャンスがあればぜひ行ってみたいものだ。

今夜ブラタモリで見た宇和島は、僕が抱いていたイメージと大きく異なっていた。それは、宇和島は温暖な気候のもと、豊かな田園が広がっているというイメージだったからだ。番組のキーワードだった「ギザギザ」のリアス式海岸。山が海に迫り、平地は限られ、米が作れない厳しい農業環境にありながら見事な石積みの段畑を築き上げたさつまいも畑。一方、「ギザギザ」を活用した豊かな漁業。いずれもが新鮮な驚きだった。チャンスがあればぜひ行ってみたいものだ。

今日12月8日は太平洋戦争開戦の日。父にとって82年前のその日がどんな日だったのか、あらためて父の回顧録を読み直してみた。(2011.12.7 記事再掲)


昭和29年頃の紺屋今町周辺。白川に沿って走る道路が国道3号線。白川べりのビルが防空監視哨があった元九電熊本支店。

戦時中、父が勤務した三菱熊本航空機製作所で製造された爆撃機「飛龍」


昭和29年頃の紺屋今町周辺。白川に沿って走る道路が国道3号線。白川べりのビルが防空監視哨があった元九電熊本支店。

戦時中、父が勤務した三菱熊本航空機製作所で製造された爆撃機「飛龍」
 パソコンなどというものにかかわるようになって43年になる。その始まりは1980年、東京本社に勤務している頃だった。ちょうど会社の中で“OA化”なるものが本格的に始まり、部署内で若手だった僕は先頭を切ってパソコンの習得をせざるを得ないハメになった。社内講習が始まったが、教わることと言えば、BASIC言語によるプログラミング。およそコンピュータなどとは縁遠い人生を送っていた僕にとって悪戦苦闘の連続だった。当時のパソコンは自らプログラムを組むしか使う方法はなかったのだ。早晩挫折するのは目に見えていた。しかし、そこで踏みとどまれたのはある人のお蔭である。その人は会社の大先輩であり、かつての上司でもあった。50歳を過ぎてから一念発起して、独学でプログラミングを修得され、会社の生協のシステムを自ら開発された。その取り組む姿勢を見て、まだ若い自分がここで挫折するわけにはいかないと発奮させられた。そのお蔭で、なんとかBASICやCOBOLなどの言語を使って簡単なソフトを作れるようになった。その後、ハードとソフトの飛躍的な向上があり、苦労してプログラミングしていたソフトは、表計算ソフトなどを使えば簡単にできてしまうようになった。しかし、僕がその後の人生で、IT化の波もなんとか乗り切れたのはその先輩のお蔭と今でも感謝している。ちなみにこの先輩の娘さんが、元宝塚のトップスターだった女優の日向薫さんである。
パソコンなどというものにかかわるようになって43年になる。その始まりは1980年、東京本社に勤務している頃だった。ちょうど会社の中で“OA化”なるものが本格的に始まり、部署内で若手だった僕は先頭を切ってパソコンの習得をせざるを得ないハメになった。社内講習が始まったが、教わることと言えば、BASIC言語によるプログラミング。およそコンピュータなどとは縁遠い人生を送っていた僕にとって悪戦苦闘の連続だった。当時のパソコンは自らプログラムを組むしか使う方法はなかったのだ。早晩挫折するのは目に見えていた。しかし、そこで踏みとどまれたのはある人のお蔭である。その人は会社の大先輩であり、かつての上司でもあった。50歳を過ぎてから一念発起して、独学でプログラミングを修得され、会社の生協のシステムを自ら開発された。その取り組む姿勢を見て、まだ若い自分がここで挫折するわけにはいかないと発奮させられた。そのお蔭で、なんとかBASICやCOBOLなどの言語を使って簡単なソフトを作れるようになった。その後、ハードとソフトの飛躍的な向上があり、苦労してプログラミングしていたソフトは、表計算ソフトなどを使えば簡単にできてしまうようになった。しかし、僕がその後の人生で、IT化の波もなんとか乗り切れたのはその先輩のお蔭と今でも感謝している。ちなみにこの先輩の娘さんが、元宝塚のトップスターだった女優の日向薫さんである。
今年はまだ谷汲観音を拝観していなかったので今日、浄国寺を訪れ、1年ぶりにご尊顔を拝した。天才生人形師と謳われた松本喜三郎の最高傑作を初めて見てから13年になる。以来、拝観すること10回ほどになるが初見の時の感動は未だ覚めやらぬ。
今日は拝観しながら、谷汲観音像が表す場面設定についてあらためて思いを致した。
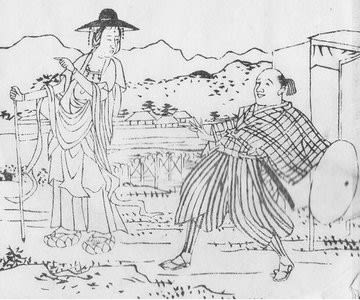
「西国巡礼三十三所観世音霊験記」は、三十三番札所「谷汲山華厳寺」(美濃國:岐阜県)で満願(結願)を迎える。
大倉太郎信満という奥州の金商人は常に大悲を深く信じていた。ある時、文殊菩薩が童子に身をやつし、霊木の松木を彫って十一面観音の像を造り信満へ賜うた。京都仁和寺に於て供養を済ませた信満は、美濃垂井までやって来たが背負った御厨子が重くなって動けなくなった。すると御厨子の中から観音像が出で賜いて、この地は有縁の地である。五里ばかり行ったところで降ろし給えと宣うた。そこが谷汲と呼ぶ地だった。信満は大悲の御心にしたがい、この地に伽藍を建立し、観音像の蓮台の下に湧き出る油によって常灯明となした。よってここを谷汲寺と号したのである。
今日は拝観しながら、谷汲観音像が表す場面設定についてあらためて思いを致した。
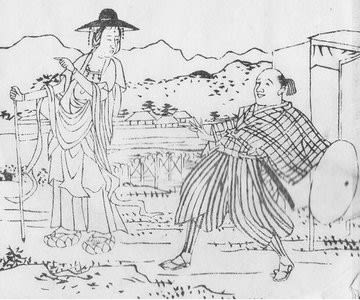
「西国巡礼三十三所観世音霊験記」は、三十三番札所「谷汲山華厳寺」(美濃國:岐阜県)で満願(結願)を迎える。
大倉太郎信満という奥州の金商人は常に大悲を深く信じていた。ある時、文殊菩薩が童子に身をやつし、霊木の松木を彫って十一面観音の像を造り信満へ賜うた。京都仁和寺に於て供養を済ませた信満は、美濃垂井までやって来たが背負った御厨子が重くなって動けなくなった。すると御厨子の中から観音像が出で賜いて、この地は有縁の地である。五里ばかり行ったところで降ろし給えと宣うた。そこが谷汲と呼ぶ地だった。信満は大悲の御心にしたがい、この地に伽藍を建立し、観音像の蓮台の下に湧き出る油によって常灯明となした。よってここを谷汲寺と号したのである。
 僕が大学を卒業した1968年、イギリスのメリー・ホプキンという女性歌手の唄う「悲しき天使(Those Were the Days)」という歌がヒットした。ビートルズのポール・マッカートニーがプロデュースしたこの曲は原曲はロシアの歌だそうだが、ちょっと悲しげな旋律が受けた。原題の「Those were the days」とは、「あの頃はよかった」というようなニュアンスの慣用句で、歌詞も若い頃をノスタルジックに思い返している心境を描いている。
僕が大学を卒業した1968年、イギリスのメリー・ホプキンという女性歌手の唄う「悲しき天使(Those Were the Days)」という歌がヒットした。ビートルズのポール・マッカートニーがプロデュースしたこの曲は原曲はロシアの歌だそうだが、ちょっと悲しげな旋律が受けた。原題の「Those were the days」とは、「あの頃はよかった」というようなニュアンスの慣用句で、歌詞も若い頃をノスタルジックに思い返している心境を描いている。下のママズ&パパスが歌う「夢のカリフォルニア」とペトゥラ・クラークが歌う「恋のダウンタウン」はともに僕が学生時代の60年代半ばにヒットした曲。この3曲を聴いているとまさに「Those were the days」の心境。いずれも胸に響く。
▼悲しき天使(Those were the days)
▼夢のカリフォルニア(California Dreamin')
▼恋のダウンタウン(Downtown)
 秋の祭りもあらかた終わり、熊本も本格的な冬の季節へと入って行く。
秋の祭りもあらかた終わり、熊本も本格的な冬の季節へと入って行く。今年もいろんな祭りが行われたが、日本の祭りは農業、就中稲作と密接につながっていることを実感する。春から初夏、田の神に豊作を祈願する祭りを行ない、秋には田の神に豊作を感謝する祭りを行なう。そしてその祭りには必ず芸能が演じられる。わが国は、縄文時代から弥生時代にかけて大陸から稲作が伝来し、稲作を中心とした農耕社会が形成された。季節季節に神を迎えて祭りを営み、祈りと感謝を歌舞音曲で表した。これがさまざまの芸能のルーツになって行った。今日もこれら季節ごとの祭りが脈々と受け継がれているのである。
秋祭りでは五穀豊穣に感謝する。
春から初夏にかけて豊作を祈願する田植祭りを行なう。
昨日、朔日詣りで藤崎八旛宮へ行く時、夏目漱石の熊本第六の旧居前を通りかかると隣接地の建物が解け、さら地になっていることに気付いた。第六旧居は熊本市が買い取って整備すると聞いているが、何か関連施設でもできるのだろうか。
それはさておき、しばし立ち止まって標柱をあらためて読んでみた。次のように書いてある。
漱石が熊本で過ごした最後の住居で、明治33年4月から熊本を去る33年7月までの3ヶ月住んだ後、上京し同年9月には英国留学へと旅立ちました。家主である磯谷氏一家の努力によって漱石のいたままのおもかげがそのまま残されています。漱石のここでの作に
「鶯も柳も青き住居かな」
「菜の花の隣もありて竹の垣」
の句があります。
最初の句を読んでふと気付いた。漱石が第五旧居に住んでいた頃に始めたといわれる謡のなかでも好んで呻っていたという「熊野」の詞章に似たような一節があったような。帰ってから調べてみた。
終盤、宗盛が熊野の東下りを許す前、熊野が世の諸行無常を儚むくだりで、「花前に蝶舞ふ紛々たる雪。」という熊野の謡に続いて、「柳上に鴬飛ぶ片々たる金」という地謡の一節がある。穿ち過ぎかもしれないが、後架宗盛とあだ名されるほど漱石が好んでいた「熊野」だけに、この一節が頭の隅にあったのかもしれない。
▼漱石第六旧居(熊本市中央区北千反畑町)

▼漱石第五旧居(熊本市中央区内坪井町)

▼漱石第三旧居(熊本市中央区水前寺公園)

この「熊野」を下敷きに作られた長唄「桜月夜」には次のような「熊野」の詞章がそのまま使われている。
それはさておき、しばし立ち止まって標柱をあらためて読んでみた。次のように書いてある。
漱石が熊本で過ごした最後の住居で、明治33年4月から熊本を去る33年7月までの3ヶ月住んだ後、上京し同年9月には英国留学へと旅立ちました。家主である磯谷氏一家の努力によって漱石のいたままのおもかげがそのまま残されています。漱石のここでの作に
「鶯も柳も青き住居かな」
「菜の花の隣もありて竹の垣」
の句があります。
最初の句を読んでふと気付いた。漱石が第五旧居に住んでいた頃に始めたといわれる謡のなかでも好んで呻っていたという「熊野」の詞章に似たような一節があったような。帰ってから調べてみた。
終盤、宗盛が熊野の東下りを許す前、熊野が世の諸行無常を儚むくだりで、「花前に蝶舞ふ紛々たる雪。」という熊野の謡に続いて、「柳上に鴬飛ぶ片々たる金」という地謡の一節がある。穿ち過ぎかもしれないが、後架宗盛とあだ名されるほど漱石が好んでいた「熊野」だけに、この一節が頭の隅にあったのかもしれない。
▼漱石第六旧居(熊本市中央区北千反畑町)

▼漱石第五旧居(熊本市中央区内坪井町)

▼漱石第三旧居(熊本市中央区水前寺公園)

この「熊野」を下敷きに作られた長唄「桜月夜」には次のような「熊野」の詞章がそのまま使われている。
春雨の降るは涙か桜花 散るを惜しまぬ人やある
都の春は惜しけれど 馴れし東の花や散る
いとまごいして東路へ 花を見捨てて帰る雁
都の春は惜しけれど 馴れし東の花や散る
いとまごいして東路へ 花を見捨てて帰る雁
今年もあっという間に師走。今日はいつものとおり藤崎八旛宮へ朔日のお詣りへ。本殿に参拝した後、末社もと思って境内を回ろうとすると、三光宮で例祭の神事が行われていた。三光宮は医薬の祖神といわれ、大己貴神と少彦名神が祭神となっている。医薬には自分も日頃お世話になっているので、神事に合わせて拝礼して後にした。
楼門前鳥居の前の参道に大型トラックが3台並んでお祓いを受けていた。今日から使う新車なのだろう。ボディのサイドパネルにNEXロジスティクスと書かれていた。トラックドライバーの人手不足に加え、来年からトラックドライバーの時間外労働の規制が強化されることなどによる「2024年問題」が懸念されており、来年は物流は大変な年になりそうだ。

三光宮例祭の神事

お祓いを受けるNEXロジスティクスのトラック
▼今月のお奨め曲 ~We're all alone~
楼門前鳥居の前の参道に大型トラックが3台並んでお祓いを受けていた。今日から使う新車なのだろう。ボディのサイドパネルにNEXロジスティクスと書かれていた。トラックドライバーの人手不足に加え、来年からトラックドライバーの時間外労働の規制が強化されることなどによる「2024年問題」が懸念されており、来年は物流は大変な年になりそうだ。

三光宮例祭の神事

お祓いを受けるNEXロジスティクスのトラック
▼今月のお奨め曲 ~We're all alone~










