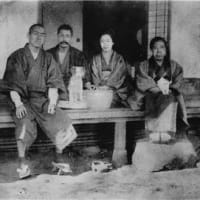全国で唯一残る「幸若舞(こうわかまい)」は2018年1月20日、福岡県みやま市の大江天満神社(瀬高町大江1488)で行われます。
お問い合わせは みやま市教育委員会・社会教育課(Tel:0944-32-9183)へ
廃れかけた幸若舞を再興したと言われる高野辰之が著した「歌舞音曲考説」(大正4年出版)には次のような一節が書かれている。
――武全盛の室町時代及び徳川の初世に於ては、武家には(幸若舞が)能楽よりも喜ばれたものである。幸若記事の記録上に見えるのでは応仁後記や前記に見えるのが最も古く、室町季世の事蹟を記した書物にはかなり多く見えている。天性峻辣の信長は殊にこの舞を喜んだのである。天澤という清洲近くの坊さんが甲斐の国へ行った時、信玄が信長の数奇は何かと聞くと、舞と小歌でござると答えた。そこで幸若太夫が来るかと聞くと、いや清洲の町人の友閑というものをたびたび呼んで舞わせられるが、中でも敦盛が一番好きで、「人間五十年下天の内をくらぶれば夢幻の如くなり」という句を吟じながら自分でも舞われると話したことが信長公記に見えている。また信長が義元を迎えて鷲津丸根を攻めにかかる時、やはりこの敦盛を舞って、前の句のところで、「夢幻の如くなり一度生を得て滅せねもののあるべきか」とて、螺を吹け具足せよとそのまま馳せ向った。――

出陣前に幸若舞「敦盛」を舞う信長(清洲城展示)
お問い合わせは みやま市教育委員会・社会教育課(Tel:0944-32-9183)へ
廃れかけた幸若舞を再興したと言われる高野辰之が著した「歌舞音曲考説」(大正4年出版)には次のような一節が書かれている。
――武全盛の室町時代及び徳川の初世に於ては、武家には(幸若舞が)能楽よりも喜ばれたものである。幸若記事の記録上に見えるのでは応仁後記や前記に見えるのが最も古く、室町季世の事蹟を記した書物にはかなり多く見えている。天性峻辣の信長は殊にこの舞を喜んだのである。天澤という清洲近くの坊さんが甲斐の国へ行った時、信玄が信長の数奇は何かと聞くと、舞と小歌でござると答えた。そこで幸若太夫が来るかと聞くと、いや清洲の町人の友閑というものをたびたび呼んで舞わせられるが、中でも敦盛が一番好きで、「人間五十年下天の内をくらぶれば夢幻の如くなり」という句を吟じながら自分でも舞われると話したことが信長公記に見えている。また信長が義元を迎えて鷲津丸根を攻めにかかる時、やはりこの敦盛を舞って、前の句のところで、「夢幻の如くなり一度生を得て滅せねもののあるべきか」とて、螺を吹け具足せよとそのまま馳せ向った。――

出陣前に幸若舞「敦盛」を舞う信長(清洲城展示)