夏目漱石内坪井旧居を訪れるといつも邸内を見た後に見ておきたくなるのが寺田寅彦ゆかりの馬丁小屋。漱石を俳句の師と仰いだ寺田寅彦(1878~1935)は物理学者であり、随筆家、俳人でもあった。彼の随筆の中には漱石について書かれたものもいくつかあり、漱石の実像を知る上でもとても貴重な作品ばかりだ。
その寺田は、当時まだ草創期にあった映画についても数多くの随筆を残している。彼の死後88年経ち、映画は著しい発展を遂げたが、彼の指摘は極めて正確に的を射ており、今日読んでも興味深い。下の文章は昭和7年8月に「日本文学」誌に寄稿した「映画芸術」と題する随筆の一部である。
◆映画と国民性
すべての芸術にはそれぞれの国民の国民的潜在意識がにじみ出している。映画でもこれは顕著に滲透(しんとう)している。アメリカ映画はヤンキー教の経典でありチューインガムやアイスクリームソーダの余味がある。ドイツ映画には数理的科学とビールのにおいがあり、フランス映画にはエスカルゴーやグルヌイーユの味が伴なう。ロシア映画のスクリーンのかなたにはいつでも茫漠(ぼうばく)たるシベリアの野の幻がつきまとっている。さて日本の映画はどうであろう。数年前の統計によるとフィルムの生産高の数字においてはわが国ははるかにフランスやドイツを凌駕(りょうが)しているようであるが、これらの映画の品等においてはどうであるか。たくさんの邦産映画の中には相当なものもあるかもしれないが、自分の見た範囲では遺憾ながらどうひいき目に見ても欧米の著名な映画に比肩しうるようなものはきわめてまれなようである。
ロシア崇拝の映画人が神様のようにかつぎ上げているかのエイゼンシュテインが、日本固有芸術の中にモンタージュの真諦(しんたい)を発見して驚嘆すると同時に、日本の映画にはそれがないと言っているのは皮肉である。彼がどれだけ多くの日本映画を見てそう言ったかはわかりかねるが、この批評はある度までは甘受しなければなるまい。なんとなればわが国の映画製作者でも批評家でも日本固有文化に関心をもって、これに立脚して製作し批評しているらしい人は少なくも自分の目にはほとんど見当たらないからである。アメリカニズムのエロ姿によだれを流し、マルキシズムの赤旗に飛びつき、スターンバーグやクレールの糟(かす)をなめているばかりでは、いつまでたっても日本らしい映画はできるはずがないのである。
剣劇の股旅(またたび)ものや、幕末ものでも、全部がまだ在来の歌舞伎(かぶき)芝居の因習の繩(なわ)にしばられたままである。われらの祖父母のありし日の世界をそのままで目の前に浮かばせるような、リアルな時代物映画は見たことがない。チャンバラの果たし合いでも安芝居の立ち回りの引き写しで、ほんとうの命のやりとりらしいものはどこにも求められない。時局あて込みの幕末ものの字幕のイデオロギーなどは実に冷や汗をかかせるものである。現代の大衆はもう少しひらけているはずであると思う。もちろん営利を主とする会社の営業方針に縛られた映画人に前衛映画のような高踏的な製作をしいるのは無理であろうが、その縛繩(ばくじょう)の許す自由の範囲内でせめてスターンバーグや、ルービッチや、ルネ・クレールの程度においてオリジナルな日本映画を作ることができないはずはない。それができないのは製作者の出発点に根本的な誤謬(ごびゅう)があるためであろう。その誤謬とは国民的民族的意識の喪失と固有文化への無関心無理解とであろう。もっとも、良い映画のできないということの半分の責任は大衆観客にあることももちろんであろうが、しかし元来芸術家というものは観賞者を教育し訓練に導きうる時にのみ始めてほんとうの芸術家である。チャップリンのごとき天才は大衆を引きつけ教育し訓練しながら、笑わせたり泣かせたりしてそうして莫大(ばくだい)な金をもうけているのである。
和歌俳諧(はいかい)浮世絵を生んだ日本に「日本的なる世界的映画」を創造するという大きな仕事が次の時代の日本人に残されている。自分は現代の若い人々の中で最もすぐれた頭脳をもった人たちが、この大きな意義のある仕事に目をつけて、そうして現在の魔酔的雰囲気(ふんいき)の中にいながらしかもその魔酔作用に打ち勝って新しい領土の開拓に進出することを希望してやまないものである。それには高く広き教養と、深く鋭き観察との双輪を要する事はもちろんである。「レオナルド・ダ・ヴィンチが現代に生まれていたら、彼は映画に手を着けたであろう」とだれかが言っているのは真に所由のあることと思われる。

夏目漱石内坪井旧居

夏目漱石内坪井旧居玄関

寺田寅彦が居候を望んだ漱石内坪井旧居の馬丁小屋

寺田寅彦の下宿先(黒髪町下立田)
その寺田は、当時まだ草創期にあった映画についても数多くの随筆を残している。彼の死後88年経ち、映画は著しい発展を遂げたが、彼の指摘は極めて正確に的を射ており、今日読んでも興味深い。下の文章は昭和7年8月に「日本文学」誌に寄稿した「映画芸術」と題する随筆の一部である。
◆映画と国民性
すべての芸術にはそれぞれの国民の国民的潜在意識がにじみ出している。映画でもこれは顕著に滲透(しんとう)している。アメリカ映画はヤンキー教の経典でありチューインガムやアイスクリームソーダの余味がある。ドイツ映画には数理的科学とビールのにおいがあり、フランス映画にはエスカルゴーやグルヌイーユの味が伴なう。ロシア映画のスクリーンのかなたにはいつでも茫漠(ぼうばく)たるシベリアの野の幻がつきまとっている。さて日本の映画はどうであろう。数年前の統計によるとフィルムの生産高の数字においてはわが国ははるかにフランスやドイツを凌駕(りょうが)しているようであるが、これらの映画の品等においてはどうであるか。たくさんの邦産映画の中には相当なものもあるかもしれないが、自分の見た範囲では遺憾ながらどうひいき目に見ても欧米の著名な映画に比肩しうるようなものはきわめてまれなようである。
ロシア崇拝の映画人が神様のようにかつぎ上げているかのエイゼンシュテインが、日本固有芸術の中にモンタージュの真諦(しんたい)を発見して驚嘆すると同時に、日本の映画にはそれがないと言っているのは皮肉である。彼がどれだけ多くの日本映画を見てそう言ったかはわかりかねるが、この批評はある度までは甘受しなければなるまい。なんとなればわが国の映画製作者でも批評家でも日本固有文化に関心をもって、これに立脚して製作し批評しているらしい人は少なくも自分の目にはほとんど見当たらないからである。アメリカニズムのエロ姿によだれを流し、マルキシズムの赤旗に飛びつき、スターンバーグやクレールの糟(かす)をなめているばかりでは、いつまでたっても日本らしい映画はできるはずがないのである。
剣劇の股旅(またたび)ものや、幕末ものでも、全部がまだ在来の歌舞伎(かぶき)芝居の因習の繩(なわ)にしばられたままである。われらの祖父母のありし日の世界をそのままで目の前に浮かばせるような、リアルな時代物映画は見たことがない。チャンバラの果たし合いでも安芝居の立ち回りの引き写しで、ほんとうの命のやりとりらしいものはどこにも求められない。時局あて込みの幕末ものの字幕のイデオロギーなどは実に冷や汗をかかせるものである。現代の大衆はもう少しひらけているはずであると思う。もちろん営利を主とする会社の営業方針に縛られた映画人に前衛映画のような高踏的な製作をしいるのは無理であろうが、その縛繩(ばくじょう)の許す自由の範囲内でせめてスターンバーグや、ルービッチや、ルネ・クレールの程度においてオリジナルな日本映画を作ることができないはずはない。それができないのは製作者の出発点に根本的な誤謬(ごびゅう)があるためであろう。その誤謬とは国民的民族的意識の喪失と固有文化への無関心無理解とであろう。もっとも、良い映画のできないということの半分の責任は大衆観客にあることももちろんであろうが、しかし元来芸術家というものは観賞者を教育し訓練に導きうる時にのみ始めてほんとうの芸術家である。チャップリンのごとき天才は大衆を引きつけ教育し訓練しながら、笑わせたり泣かせたりしてそうして莫大(ばくだい)な金をもうけているのである。
和歌俳諧(はいかい)浮世絵を生んだ日本に「日本的なる世界的映画」を創造するという大きな仕事が次の時代の日本人に残されている。自分は現代の若い人々の中で最もすぐれた頭脳をもった人たちが、この大きな意義のある仕事に目をつけて、そうして現在の魔酔的雰囲気(ふんいき)の中にいながらしかもその魔酔作用に打ち勝って新しい領土の開拓に進出することを希望してやまないものである。それには高く広き教養と、深く鋭き観察との双輪を要する事はもちろんである。「レオナルド・ダ・ヴィンチが現代に生まれていたら、彼は映画に手を着けたであろう」とだれかが言っているのは真に所由のあることと思われる。
寺田寅彦が好んだフランス映画「パリの屋根の下」(ルネ・クレール監督)から

夏目漱石内坪井旧居

夏目漱石内坪井旧居玄関

寺田寅彦が居候を望んだ漱石内坪井旧居の馬丁小屋

寺田寅彦の下宿先(黒髪町下立田)
















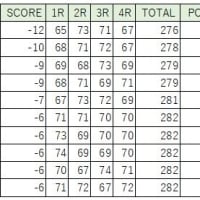
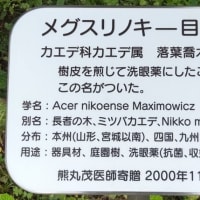

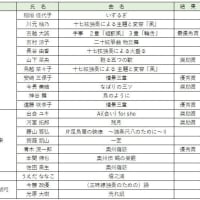
歴史半分、創作半分の1年間のドラマだと特に視聴者には受け入れがたくなるのではないか?1年間という期間が長すぎるのではないか?と常々思っているのですが・・・。
私は観ていますが、時々何を描いているのか、登場人物の関係も分からなくなってしまいます。
そして、寺田寅彦が書き下ろした時代の映画の話なんでしょうが、上の「パリの屋根の下」の動画とウイキペデイアのストーリーを斜め読みしましたが、寺田が記している程度の映画はどれとどれかは知りませんが、寺田以後には製作されているのではないか?という疑問もわきました。
海外で賞獲った作品がいいとも思えませんが、それなりに発展した映画は存在すると私は想像します。
チャップリンの映画の幾つかは観てはいますが、その作品群がいつの世にでも受け入れられるものでもない気もします。
軍人だった父は「独裁者 (映画)」を鑑賞してとても喜んでいましたが、イタリア在住の78歳くらいの絵を描くご婦人はチャップリンに偏見を持っていました。
FUSAさんが感じられる寺田寅彦の「映画芸術」の意図するところからは、外れているのかも知れませんが、私は上記のような印象を持ちました。
有難うございました。
寺田寅彦の随筆は彼が生きた時代、特に大正から昭和初期の映画の話ですから、今とは映画界も時代背景も大きく異なることは認識した上で読んでいます。
映画そのものよりこの時代にこれほど映画について研究していた、しかも全く畑違いでありながら、という人がいたことは驚きです。
おそらく彼よりも私の方が何倍もの本数を見ていると思いますが、これほど研究分析を踏まえた文章はとても書けません。
寺田寅彦は57歳で亡くなっていますが、あと30年せめて20年生きてもらって、その後の日本映画の発展を見てもらいたかったなぁと思います。