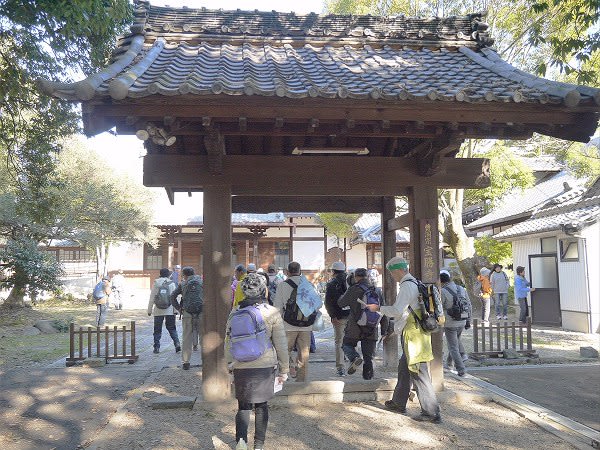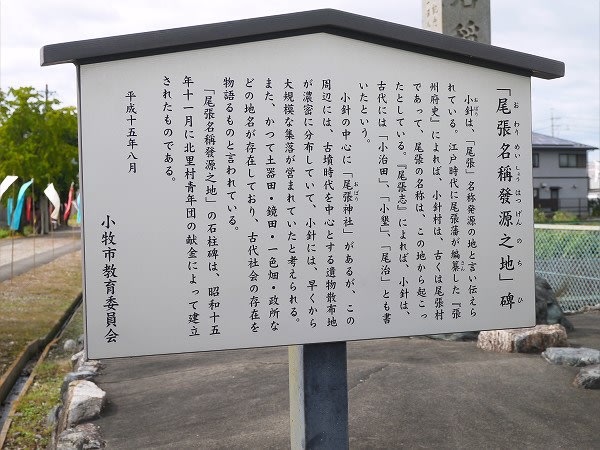一宮友歩会の7月例会に参加しました。今回は名古屋市西区を歩くもので、名鉄東枇杷島駅が集合場所で名鉄栄生駅がゴールでした。梅雨の時期であり、天気が悪く参加者が少人数でした。それでも、名城公園のでは明日から大相撲が開かれる運びとなっていました。
名鉄東枇杷島駅(スタート) ― 枇杷島スポーツセンター ― 八坂神社 ― 押切公園 ―
旧志水家車寄 ― 丹羽長秀邸址 ― しゃんしゃん馬の碑 一 江川の碑 ― 蜂谷宗意宅址
― 興西寺 ― 弁天通り ― 名城公園 ― 名城公園フラワープラザ ―
ドルフィンズアリーナ ― 宗春横丁 ― 堀川堀留の碑 ― 鴫塚 ― 地蔵院 ―
産業技術記念館 ― 名鉄栄生駅(ゴール)

今回のコース地図です。
名鉄東枇杷島駅から名鉄栄生駅までで、11キロとなっていますが、清音寺に寄ったりしていないので10キロ程でしょう。
http://www.geocities.jp/jk2unj/datagazou/75map.pdf
枇杷島スポーツセンター
スタート地点が名鉄東枇杷島駅となっていましたが、出発式を行うので、枇杷島スポーツセンターからのスタートと成りました。
(09:25)
枇杷島スポーツセンターはプールや競技場の有る場所でした。
歩き出しました。
県道、名古屋祖父江線を歩いています。
八坂神社
(09:33)
最初に寄ったのが八坂神社です。
境内に四角い鉄板が有ります。
提灯の柱立てる為のモノです。
大祭の写真が掲示して有ります。
5月の第3土曜日。
祭りが盛大に行われます。
美濃路を歩きます。
サボテンに花が咲いています。
このサボテン。
短針丸と言う種類だと教えて貰いました。
旧志水家車寄
(10:01)
旧志水家車寄へ来ました。
旧志水家車寄の説明です。
丹羽長秀邸址
丹羽長秀邸址で、街中にポツンとありました。
しゃんしゃん馬の碑
(10:08)
しゃんしゃん馬の碑ですが、風雨で字が読み難くなっています。
しゃんしゃん馬の碑の説明です。
江川の石碑
江川の碑です。
江川の碑の横に有った弁天通りの説明です。
それに、浄心。ここに市電の車庫がありました。
(10:23)
弁天通りを歩きます。
蜂谷宗意宅址
蜂谷宗意宅址。
門だけが残り、説明板が有りました。
弁天通り
弁天通りの案内図です。
可愛い大黒様。
こんな七福神が並んでいます。
名城公園
(10:58)
名城公園に入ってきました。
名城公園フラワープラザ
花に囲まれたフラワープラザです。
アメリカフヨウだと思います。
(11:14)
名古屋城が見えます。
この城。
やがて壊されます。
太鼓櫓と幟旗。
明日から始まります。
ドルフィンズアリーナ
愛知県体育館ですが、名が売られてドルフィンズアリーナとなっています。
明日から大相撲が始まります。
宗春横丁
(11:25)
宗春横丁の中を通り抜けます。
堀川堀留の碑
名古屋城の築城の時に開削された堀川。
その堀川の解説です。
(12:02)
もう直ぐゴールと言うところで雨が降り出しました。
産業技術記念館
(12:11)
解散式を行う産業技術記念館に到着です。
感想
天候が悪く、午後から降雨が予想されました。それで、予定のコースを早く廻りました。
そのため、少人数の参加者でした。
明日から大相撲が始まります。毎年、この時期に名古屋を歩くと、大相撲の時期棚と言う気がします。
名古屋城の近くで住宅地の中であっても、いろいろの旧跡がありました。