グリム童話の初版の第1巻が出版されたのが、1812年、
第2巻が出版されたのが、1815年です。
つまり、昨年から来年にかけて「グリム童話誕生200年」の記念すべき年です。
ドイツにおいても、いろんな記念行事やら、グリム童話にまつわる記念出版が目白押しです。
ところで、私たち「グリムと民間伝承研究会」では、
グリムと民間伝承にかかわる記念論文集を刊行しました!

溝井裕一編 『グリムと民間伝承 東西民話研究の地平』 麻生出版 5000円(税別)
<竹原威滋先生退官記念論文集>
(入手方法)
■本屋を通じて購入することができます。
注文の際、JRC(取次店)経由でとおっしゃってください。
■麻生出版に直接注文する場合はメールかFAXでお願いいたします。
メール:asao_pub@yahoo.co.jp FAX: 044-989-1454
割引注文書は下記のサイトをクリック:
書店直通注文書
まず、本の装丁を見てください。
表紙カバーの、オモテには、ゲッティンゲンの市役所前の噴水、「ガチョウ番の娘」の像が載ってます。
そのウラには、シュタイナウの市役所前の噴水、「カエルの王さま」のお姫さまとカエルがいますね。
それはともかく、本体は570ページもある20本の論文が載っています。
目次を載せましょう!
-----------------
竹原威滋 グリム童話とカルヴァン派と近代―「幸せハンス」(KHM83)と「貧乏人と金持ち」(KHM87)をめぐって―
野口芳子 グリム童話における七の数字について ―不運な七の出現を巡って―
浜本 隆志 グリム童話の同類結婚と日本昔話の異類結婚 ―ヨーロッパと日本の動物観とのかかわりから―
松村國隆 中世の遍歴作家 デァ・シュトリッカーの「三つの願い」
大野寿子 グリム兄弟「こびと」像にみる古の世界と自然との共生 ―メルヘン、伝説、神話テキストをてがかりに―
溝井裕一 狩猟伝説と異界 ―グリム伝説集を中心とした考察―
斧原孝守 東アジアからみた「赤ずきん」(KHM26)の原型 ―「赤ずきん」と「老虎外婆」との比較―
久保華誉 白雪姫の身代わりになった動物 ―日本人のイメージをめぐって―
金城ハウプトマン朱美 グリム兄弟のメルヒェン「ヘンゼルとグレーテル」 ―その成立と現代ドイツにおける受容―
鶴田涼子 ドイツ文学のなかの「ねずの木の話(KHM47)」
梶田純子 オレンツァロ ― バスクの「歳神」伝承
天沼春樹 物語の迷宮へ
岩瀬ひさみ ヘンワイフまたはヤハリシュ・ウルラル ―継母の相談役―
佐藤結佳 「クラバート」伝説の特徴 ―ATU325「魔法使いとその弟子」類話比較より―
永池健二 消えた幽霊の足
齊藤 純 神野山と「天狗さんの石合戦」―大和高原における「山の争い」伝説の展開―
鵜野祐介 「鼠の嫁入り」の起源と構造 ―伝承文学にみる「子どものコスモロジー」―
阿部奈南 世間話「口裂け女」に関する一考察
間宮 史子 Vorstellungen von Raum und Zeit in der Anderswelt im japanischen Volksmärchen
<献辞> ロルフ・W・ブレードニヒ 親愛なる同僚、竹原先生へ
<特別寄稿> ハンス=J・ウター 愚か者につける薬はない― ノルウェーの「笑い昔話」に関する小論―
----------------
論文名をよくご覧ください。
グリム童話や伝説にかかわるもの、現代伝説、グリム童話と日本の民話の比較研究など多方面にわたっています。
最後には、あのATU民話話型カタログの著者:ウター教授も笑い話についての論文を特別寄稿してくれています。
編者は、関西大学の准教授、溝井裕一先生です。
編者のことばを「はじめに」から一部引用します:
----------------
タイトルにもあるように、この本がテーマとするのは「グリム」と「民間伝承」である。
グリムというとドイツのイメージが先行しがちだが、それだけでなく他のヨーロッパ諸国やアジアの民間伝承もとりあげている。
この本が企画された2012年は、奇しくもグリム兄弟が『子どもと家庭のメルヒェン集』を出版してから200年目にあたる。
本書におさめられた諸論文は、象徴史、ひとと自然の関係史、ドイツ文学、比較民話学、日本民俗学といった分野に大別されようが、
いずれも、かならずしもこのカテゴリーにとどまるものではないことも強調しておきたい。
それぞれの論文が、いかにひとつの分野や国の枠にとどまらないテーマをあつかっているかは、
じっさいに読み進めていく過程でおのずからあきらかとなるはずである。
そもそも民間伝承は、国境をこえ、各文化に適応しながら語りつがれてきたものである。
それゆえ、その研究もまた、常に既存の枠をこえていくよう運命づけられているのであろう。
この本をとおして、民間伝承研究のさまざまなアプローチや、そこに秘められた可能性についてご理解を深めていただければ幸いである。
----------------
書名の副タイトル「東西民話研究の地平」が示しているように、ある意味、日本におけるグリム研究の最先端の論文集です。
ぜひ、お読みいただければ、幸いです。
第2巻が出版されたのが、1815年です。
つまり、昨年から来年にかけて「グリム童話誕生200年」の記念すべき年です。
ドイツにおいても、いろんな記念行事やら、グリム童話にまつわる記念出版が目白押しです。
ところで、私たち「グリムと民間伝承研究会」では、
グリムと民間伝承にかかわる記念論文集を刊行しました!

溝井裕一編 『グリムと民間伝承 東西民話研究の地平』 麻生出版 5000円(税別)
<竹原威滋先生退官記念論文集>
(入手方法)
■本屋を通じて購入することができます。
注文の際、JRC(取次店)経由でとおっしゃってください。
■麻生出版に直接注文する場合はメールかFAXでお願いいたします。
メール:asao_pub@yahoo.co.jp FAX: 044-989-1454
割引注文書は下記のサイトをクリック:
書店直通注文書
まず、本の装丁を見てください。
表紙カバーの、オモテには、ゲッティンゲンの市役所前の噴水、「ガチョウ番の娘」の像が載ってます。
そのウラには、シュタイナウの市役所前の噴水、「カエルの王さま」のお姫さまとカエルがいますね。
それはともかく、本体は570ページもある20本の論文が載っています。
目次を載せましょう!
-----------------
竹原威滋 グリム童話とカルヴァン派と近代―「幸せハンス」(KHM83)と「貧乏人と金持ち」(KHM87)をめぐって―
野口芳子 グリム童話における七の数字について ―不運な七の出現を巡って―
浜本 隆志 グリム童話の同類結婚と日本昔話の異類結婚 ―ヨーロッパと日本の動物観とのかかわりから―
松村國隆 中世の遍歴作家 デァ・シュトリッカーの「三つの願い」
大野寿子 グリム兄弟「こびと」像にみる古の世界と自然との共生 ―メルヘン、伝説、神話テキストをてがかりに―
溝井裕一 狩猟伝説と異界 ―グリム伝説集を中心とした考察―
斧原孝守 東アジアからみた「赤ずきん」(KHM26)の原型 ―「赤ずきん」と「老虎外婆」との比較―
久保華誉 白雪姫の身代わりになった動物 ―日本人のイメージをめぐって―
金城ハウプトマン朱美 グリム兄弟のメルヒェン「ヘンゼルとグレーテル」 ―その成立と現代ドイツにおける受容―
鶴田涼子 ドイツ文学のなかの「ねずの木の話(KHM47)」
梶田純子 オレンツァロ ― バスクの「歳神」伝承
天沼春樹 物語の迷宮へ
岩瀬ひさみ ヘンワイフまたはヤハリシュ・ウルラル ―継母の相談役―
佐藤結佳 「クラバート」伝説の特徴 ―ATU325「魔法使いとその弟子」類話比較より―
永池健二 消えた幽霊の足
齊藤 純 神野山と「天狗さんの石合戦」―大和高原における「山の争い」伝説の展開―
鵜野祐介 「鼠の嫁入り」の起源と構造 ―伝承文学にみる「子どものコスモロジー」―
阿部奈南 世間話「口裂け女」に関する一考察
間宮 史子 Vorstellungen von Raum und Zeit in der Anderswelt im japanischen Volksmärchen
<献辞> ロルフ・W・ブレードニヒ 親愛なる同僚、竹原先生へ
<特別寄稿> ハンス=J・ウター 愚か者につける薬はない― ノルウェーの「笑い昔話」に関する小論―
----------------
論文名をよくご覧ください。
グリム童話や伝説にかかわるもの、現代伝説、グリム童話と日本の民話の比較研究など多方面にわたっています。
最後には、あのATU民話話型カタログの著者:ウター教授も笑い話についての論文を特別寄稿してくれています。
編者は、関西大学の准教授、溝井裕一先生です。
編者のことばを「はじめに」から一部引用します:
----------------
タイトルにもあるように、この本がテーマとするのは「グリム」と「民間伝承」である。
グリムというとドイツのイメージが先行しがちだが、それだけでなく他のヨーロッパ諸国やアジアの民間伝承もとりあげている。
この本が企画された2012年は、奇しくもグリム兄弟が『子どもと家庭のメルヒェン集』を出版してから200年目にあたる。
本書におさめられた諸論文は、象徴史、ひとと自然の関係史、ドイツ文学、比較民話学、日本民俗学といった分野に大別されようが、
いずれも、かならずしもこのカテゴリーにとどまるものではないことも強調しておきたい。
それぞれの論文が、いかにひとつの分野や国の枠にとどまらないテーマをあつかっているかは、
じっさいに読み進めていく過程でおのずからあきらかとなるはずである。
そもそも民間伝承は、国境をこえ、各文化に適応しながら語りつがれてきたものである。
それゆえ、その研究もまた、常に既存の枠をこえていくよう運命づけられているのであろう。
この本をとおして、民間伝承研究のさまざまなアプローチや、そこに秘められた可能性についてご理解を深めていただければ幸いである。
----------------
書名の副タイトル「東西民話研究の地平」が示しているように、ある意味、日本におけるグリム研究の最先端の論文集です。
ぜひ、お読みいただければ、幸いです。













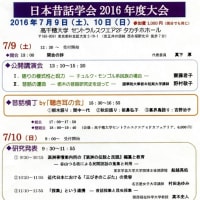






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます