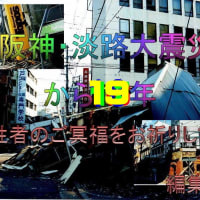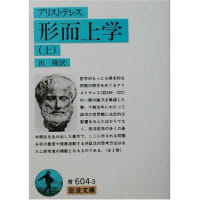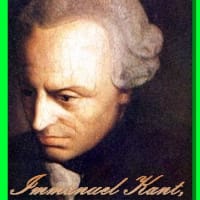フランコ・モディリアーニとの共同研究、企業の資金調達に関する理論(モディリアーニ・ミラー理論=MM理論)によって、一九九〇年にノーベル経済学賞を受賞したシカゴ大学のマートン・ミラーは、堂島会所後を訪問して献花したという。ミラーのこの行為が日本のいわゆる金融の自由化(実態は、先物とレバリッジの解禁)の幕を開けたのである。
マートン・ミラーに流れ、ミラーからマイロン・ショールズに流れる考え方の変化について説明しておこう。
大きな流れは、経済学にあった所得論が、消費の大きさがどこで決まるかといった消費関数論に次第に変わっていき、消費の大きさの議論が資産保有の動機論に移り、資産保有論が、金融資産の保有論に集中してきたという点にある。
マクロ経済学で議論されていたのは、「所得が増加すると、消費も増加する。しかし消費の増加は所得の増加に及ばない」という、ケインズの消費に関する「絶対所得仮説」というものの当否を巡るものであった。
例えば、フランコ・モジリアーニ(Franco Modigliani)は、過去の所得水準の記憶とか、所得の変動などの記憶が、消費行動に習慣性を与えるという消費に関する「習慣仮説」を打ち出した。人々の消費行動は、過去の最高所得の記憶によってもっとも大きな影響を受ける。過去、高所得によって高い水準の消費を経験したことのある人は、その後、所得が減少しても、預金を切り崩してこれまでの消費水準を維持してしまう。節約しなければならないという考えが脳裏によぎりながらも、それまでの消費水準を落とすことになかなか踏み切れないのである(Modigliani, F.[1948])。
ジェームズ・デューゼンベリー(James S. Duesenberry)もケインズ的な絶対所得仮説を修正して、社会の平均的所得と消費、そして過去の記憶に基づく消費行動を論じた。消費に関する「相対的所得仮説」と言われるものがそれである(Duesenberry, J.[1949])。
流動資産を考慮したとき、ケインズ的絶対所得仮説は十分現実分析に使用可能であるとして、ケインズを擁護したのが、ジェームズ・トービン(James Tobin)であった(Tobin, J.[1951])。しかし、トービンのケインズ擁護の論文は、フリードマンによる統計作成の弱さへの罵倒によって一蹴されてしまった感がある(Friedman, Milton[1957])。
フリードマンは、所得を「恒常所得」と「一時所得」に分ける。所得の長期的なトレンド線を描き、トレンド線上にあるものを長期所得、トレンド線から離れたものを「一時所得」と定義した。トレンド線よりも下にあれば、一時所得はマイナス、トレンド線より上にあれば、一時所得はプラスであるというように、一時所得を理解する。
一般的に、高所得者層は一時所得が大きく、それが恒常所得を高くさせている。低所得者層は逆に、一時所得がマイナスであるケースが多い。そのために、恒常所得も低くなる傾向がある。所得を構成するものは、人的資本(給与などの報酬)と並んで資産である。
消費も「恒常消費」と「一時消費」に区分される。「恒常消費」は、恒常所得に比例する。「一時消費」は一時所得に比例するわけではない。高い一時所得者の一時消費は、社会的平均よりも大きく、一時所得がマイナスの人は消費を控えてしまう。したがって、一時所得と一時消費との関係は、ケインズの描いた消費関数に近くなる。しかし、恒常消費は時間を通じて安定的なトレンド線を示す。これがフリードマンの「恒常所得仮説」である(ibid.)。
ライフサイクルによって、所得と消費との関係は変動する。時々の所得というフロー面だではなく、ストック面(貯蓄、固定資産、金融資産など)を加味して、年代ごとに異なる消費性向に注目して、人の生涯を通じる消費動向を理論化しようとしたのが、モディリアーニである(Modigliani, F.[1966])。
貯蓄動向との関係で消費を見るという点では、消費関数議論は日常感覚に近づいたが、しかし、この当たりから経済学の関心が、社会全体の構造分析ではなく、金融資産保有形態の分析に傾斜することになった。
しかも、戦後ずっと右肩上がりの価格を継続し、したがって、所得の増加を保証していた株式価格の大暴落が、オイル・ショックを引き金として発生した。この環境下で所得増との関連だけで金融資産を扱う傾向に対抗して、リスクなり不確実性を、マイナス面からだけ見るのではなく、その存在を逆手に取って、儲け口として受け取るという発想の逆転が試みられ、社会全体の潤滑油としての金融ではなく、金融商品に投資する人々の所得は保障されているのだという理論がもてはやされるようになった。
一九五二年という、一九七三年の株価大暴落より二〇年前のH・M・マーコビッツ(Harry M. Markowitz)のポートフォリオ分散投資論が突如脚光を浴びるようになったのは、そうした株価動向の激変時を反映するものであった(Markowitz, H.[1952])。そして、マーコビッツは、論文発表からじつに三八年後の一九九〇年、「資産形成の安全紙を高めるための一般理論」形成に貢献したとして、スウェーデン銀行から、「ノーベルを記念する経済学賞」を授与された。このときにともに授与されたのは、マートン・ミラー(Merton H. Miller)、W・F・ミラー(William F. Sharpe)であった。
このときのノーベル賞が、リスクを取ることが儲けに繋がるという金融技術開発にお墨付きを与えることになったのである。
一九三〇年代、四〇年代の経済学は、ケインズやヒックスに代表されるように、株式や債券を売買するだけの金融市場をカジノとして軽蔑していた。しかし、投資家はリスク分散を図っているはずなので、理論は、リスクを排除すべき要素として退けるのではなく、リスクにも価値があること、待つか、逃げるかなどの判断にも価値があることを説くべきである。そのことによって、金融関係者にリスクを取ることの意義に気付かせ、カジノと言われる屈辱から、科学的思考術の開発者としての自覚をもたらすべきであるとの理解が定着させられたのである。
リスクのない(リスクフリー)金融資産とリスクのある金融資産を組み合わすポートフォリオが望ましいと簡単に言われても、膨大な組み合わせのすべてに数値を与えるなどは不可能である。つまり、原型のポートフォリオ理論を証券業界が実用化できるためには、リスクとリターンをシンプルな数式で表すことができる手法が必要である。
これを提供したのが、ウィリアム・シャープ(Sharpe, William[1963][1964][1970])である。
将来受け取ることのできる現金(将来キャッシュフロー)を保証する資産を現時点で売買しようとするとき、その資産の現在価値(価格)は、いくぶん、割り引かれて付けられるはずであるが、それには、どういう計算方法があるのかといったことが、証券売買の基本的な考え方である。
ちなみに、証券業界では、「価格」を「価値」と表現する。「企業価値」とは、企業が発行する株式の総「価格」のことである。株価の時価総額の高い企業ほど「企業価値」が高いとされている。奇妙な格付けである。それはけっして企業が社会に貢献する度合いを測る価値ではない。
それはともかく、リスクとリターンとの関係を計測するにあたって、もっとも重要な要素は、将来受け取る金額をどの程度割り引いて現在に現金で受け取るには、正しい割引率がなにかということである。一年後に受け取ることのできる一一〇万円の年率割引率が一〇%であれば、現時点で一〇〇万円となる。割引率を取引に参加する利害関係者がどの程度なら納得するのかが、証券業者の技術になる。
この割引率は、リスクの大きさに依存するとされた。リスクのない(リスクフリー)金融資産を想定した将来の受け取り現金から、リスク回避のためにリスクテーカーに支払う費用を差し引いた後に受け取ることのできる将来の現金を「期待収益率」という。一年後の満期で一一〇万円を受け取ることのできるリスクフリーの金融資産を現在買おうとする投資家が、現在、その金融資産を買って二〇%の収益率を実現させようとすれば、現時点で一〇〇万円ではなく、九一万六〇〇〇円ならその金融資産を買おうとする。この二〇%が期待収益率である。
そして、この期待収益率が顧客の「リスク認識」になる。ここにリスク認識をめぐる一種の意図的操作がある。「期待収益率」=「リスク認識度」とし、「期待収益率」が高いほど、現時点の価格は安くなる。逆に言えば、リスクが高くなるほど「収益率」が高くなる。高い収益率を得ようとすればリスクの高い金融資産を購入すべきであるということになる。「期待収益率」=「リスクの高さ認識」がすべての操作の基本形である。ここで問題にされるリスクは、日常感覚でいうリスクとはかなり異なったものである。リスクフリー資産のもたらす収益よりも大きな収益を取ろうとすることがリスクというのである。最低水準で保証されている収益よりも大きな収益をもとうとする期待がリスクと呼ばれるように転倒した発想がここではなされている。
株式投資に例えれば、ある企業株を買う投資家の期待収益率が高まれば、その株の現在価格は下落せざるを得ないということになる。日常感覚からすれば、ある企業への投資はリスクが高いから、その企業の株価が下がるという理屈になるのに、証券業者の思考様式に沿えば、投資家の期待収益率が高くなったので、株価が下がってしまうので、株価の下落は投資家の要求が強すぎるからであるということになってしまう。
ノーベル賞を得たシャープの「資本資産評価モデル」(CAPM=Capital Asset Pricing Model)とは、リスクが高いほど収益率は高いということを示す考え方であるが、リスクとは期待収益率と同義である。これは一種の論点搾取である。
その前提条件がすごい。四つある。
1、投資家は、期待収益率、分散、共分散について共通の予想をもつ。これは、市場全体のリスクの大きさ、株価のばらつき(分散)、ばらつきの変化方向(共分散)に関する情報を、市場参加者のすべてがもっているという想定である。現実にはそのようなことはありえないのに、まずこの想定をCAPM理論は置いてしまう。信じられないのは、投資家がそのような強い前提をもつCAPM理論を神様扱したことである。
2、投資家は、効用を最大にする行動を取る。そうした投資家の行動によって、金融資産の受給は均衡する。現実には、株式などの市場価格は安定的に均衡するどころか、変動率を日々拡大する。暴騰と暴落を目まぐるしく繰り返すのが最近の株式市場である。にもかかわらず、CAPM理論は、正常な姿の需給均衡、つまり、さざ波の均衡化を想定してしまっている。はたして、リスクは正しく計量化されてきたのであろうか。
3、市場に存在する証券の数量は変わらない。どうしてこんなに市場の実態を裏切るような想定が堂々とまかり通っていたのであろうか。現実には、未公開株の上場とか、ベンチャー・キャピタルの株式公開とかによって、証券会社は膨大な手数料を稼いできたのではなかったのか。市場に登場する株式の数量、種類を絶えず増やすことに証券業界は腐心してきたのではなかったのか。
4、市場は完全である。つまり、多数の投資家が存在するので、特定の投機家の売買によって市場の株価は影響されない。情報も完全に市場全体で把握されている。これは完全に「ためにする論理」である。実際には、ソロスなどのカリスマの動向に、多数の投資家は乗ろうとしてきた。巨大ヘッジファンドが世界中を荒らし回ってきた。にも関わらず、特定の人間が市場を左右することなどはないし、ファンドの手口はすべて既知であるというとんでもない前提をCAPMは置いたのである。ファンドは、こに理論に従って営業してきたと言えるのだろうか。逆に、情報操作にやっきとなり、市場をますます不完全なものに、つまり、激動の頻度を多く、変動幅を大きくするように努めてきたのではなかったか。
分析すべきは、理論の正しさ、現実適応性ではない。こうした理論を神格化する業者たちを大衆が信頼してきたことの心理構造であったはずである。
この理論のポイントは、三つある。1、資本市場線(CML=Capital Market Line)、2、β(ベータ)計算、3、個別証券の収益率、がそれである。
1、資本市場線。これは、リスクとリターンとの関係を表せば直線になるとする仮定である。マーコヴィッツはリスクのある資産のみで、リスクとリターンとの関係を表現したので、資本市場線は曲線になっていた。シャープはこれにリクスフリー資産を導入し、この資産との関係で表現される直線になる資本市場線を想定した。登場するキー概念は、(1)リスクフリー資産の期待収益率。(2)市場全体のポートフォリオ(リスクのみがある資産)の期待収益率。(3)市場全体の期待収益率とフリーリスク資産の期待収益率との差。これがプラスにならなければならない。つまり、リスクフリー資産の期待収益率よりも高い収益率を得るためのポートフォリオの選択が推奨されている。ここには、リスクの高い資産ほど高いリターンを得るという、結論がすでにここに確定させられている。(4)市場全体のポートフォリオのリスク。(3)の値を(4)の値で割ったものが、資本市場線である。その値はX軸にリスクの大きさ、Y軸に期待収益率を取れば、リスクとリターンとの関係は右上がりの直線になる。リスクフリー資産とは、国債などの安全な(低リスク)を指し、リスクが低いのでリターン(期待収益率)が低いのも当然であるという仮定が置かれている。リスクフリー資産は、どんな金融資産に投資しても、最低限のリターンを得ることができる資産と同じ意味である。リスクフリー資産のリターンを上回りたければ、リスクの高い金融資産を選択すべきだという主張が、モデルには最初から設定されてしまっている。
リスクフリーを加味しない、つまり、リスクを含む資産のリスクとリターンとの関係は、マーコビッツが想定したように曲線である。この曲線で表現される資本市場線とリスクフリーとの差を数値化した直線で表現された資本市場線との接点で、現実の期待収益が決まるというのである。
直線で表した資本市場線とは、リスクの価格を表現している。つまり一単位のリスクでどの程度の期待収益(市場全体のポートフォリオの期待収益から市場全体のポートフォリオのリスクを差し引いたもの)があげられるかといった数値がリスクの価格なのである。
これに購入単位、つまりリスクの単位を乗じたものが「リスクプレミアム」とされる。リスクを負担することによって得ることができるリターンがこのリスクプレミアムなのである。最低限のリターンを得る投資よりも高い収益を得るためにリスクを取る。その行為によって、どの程度、リスクフリー資産投資よりも高いリターンを得るかを知る指標がこのリスクプレミアムである。いうまでもなく、ここにもリスクを取らねば高いリターンを得ることはできないとのモデル設計が行われているのである。
2、βの計算。適用される割引率は次の計算式と等しい。上記のリスクプレミアムにβを乗じた値にリスクフリー資産のリターン率を足した計算式がそれである。β値が高いほど割引率が高いとされる。そして、マーケットリスクプレミアム市場全体のポートフォリオの収益率が一%変化したときに、投資家が投資している個々の証券の収益率が何%変化したかの値がβ値である。βは、市場で普通の形でもたらさられるリターンの何倍をファンドマネジャーの個人の力量で確保できたかという指標であるとされている。証券投資におけるファンドマネジャーの技術をランクづけてきたのが、このβ値である。
β値が一のときは、市場全体の収益と個別証券の収益は同じ水準にある。つまり、ファンドマネジャーの力量は平均的なものである。β値が一より大きく、例えば二であれば、市場平均の二倍のリターンをもたらし、ファンドマネジャーの貢献が大である。逆に一より小さければ、市場平均を下回るために、ファンドマネジャーの力量が小さいことを表している。
これは奇妙な論理である。割引率とは投資家から見た期待収益率のことであり、それはリスクの高さに等しい。そして、その大きさが資金を投資された受けて側から見ての資本コストであるという、こんな馬鹿げた等式が成立するものなのだろうか。β値とは株価の変化率そのものではないか。そして、株価を変動させるのがリスク(=期待収益率)とされるが、そのリスクは、言葉本来の意味でのリスクではなく、将来受け取る固定されたリターンを、現在、大幅に割り引いて受け取ることに投資家が合意しただけのことなのに、それが言葉本来の意味でのリスクにすり替えられてしまう。株価が乱高下すればするほど高いβ値が得られる。相場を荒れたものにするのがファンドマネジャーの高い技術であることになってしまう。
また、企業の株に投資している投資家はそれぞれ異なる期待収益率をもっているはずである。デイトレード情報に多額の情報料を払っている投資家の期待収益率は総じて高いであろう。しかし、長期間のうち、じっくりと市況を見て、一回だけの勝負をする投資家もいる。後者の場合、期待収益率など度外視している。必ず値上がりするだろうとの確信をもって特定の企業に投資するのである。そうした個々の差を無視して、市場全体が同じ方向に動くものと決めつけて、市場全体の期待収益率を想定するなど、そもそも現実性をもつものだろうか。
もっと基本的な疑問がCAPMにはある。どうして、割引率が株価の変動率と連動するのであろうか。どうして株価が企業価値になるのであろうか。株価はあくまでも価格である。それを企業価値と言い切ることにどれほどの意味があるのか。ライブドアの株式の時価総額がNTTのそれを上回ったことがある。ライブドアの企業価値がNTTよりも高いと断言されれば、誰でもその胡散臭さを感じたはずである。
現実には、証券会社は、先物を売買するとき、現物株の価格づけを行わねばならない。その価格付けははたして、正しく行われているのだろうか。正しい数学モデルで行われているのだろうか。そのモデルがCAPMであると対外的に広言されているだけのことではないのか。そういう使われ方をCAPMがされてきただけではないのか。要するにノーベル賞の権威を傘にして正しい割引率(値引率)の計算を行っているという口実にCAPMが使われてきたのではないだろうか。おそらく、証券会社による実際の割引率の算定は、企業秘密なのであろう。CAPMへの疑問については、板倉雄一郎氏の解説に触発された(板倉雄一郎「CAPMを笑う」『KISS(Keep it simple, stupid)』第20号、2005年3月3日;http://www.yuichiro-itakura.com/archives/2005/03/03-0855.html)。