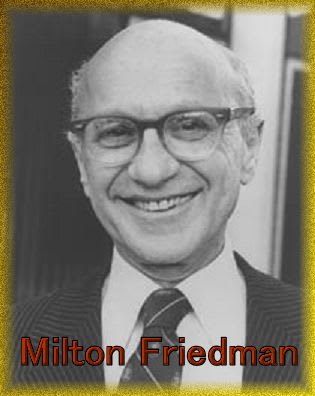私が学んでいた一九六〇年代の大学では、その時点における「現代資本主義」とは「管理通貨体制」(Managed Monetary System)と教えられてきた。その心は、金兌換の義務を米国が負い、対ドル固定相場をその他の国が負い、攪乱的な資本移動を禁止して、金融は生産的な部門に安定的に注ぐことにある。そうしたシステム、つまり、通貨が管理されているのが現代資本主義であると理解されていたのである。戦前の投機的なホット・マネーの動きを禁止しなければ資本主義体制はもたないし、米国も、他の国も金融におけるモラルを守るというのが管理通貨体制の基本形だと教えられてきた。
いまでは、「管理通貨体制」という言葉は死語になった。それがいつからかはまだ確かめてはいないが、少なくとも最近の学生に、戦後は「管理通貨体制」だったのだよと言っても、いぶかしがられるのがおちだろう。いつの間にか、若い学生は、旧い因習的な日本の経済体制が、自由の国、米国との接触の下で、合理的開明的なシステムになった。そうした方向に向かって一直線に移行してきたのが、戦後経済の歴史である。
それは市場を熟知する経済の専門家たちが、頑迷な官僚の思考を打破する過程であった。このような理解の仕方に若者たちが浸るようになった。米国がつねに革命者であり、それに抵抗する国の政府には、権力にしがみつく保守反動派というレッテルが貼られるようになった。とくに、日本では小泉ブーム、小泉チルドレンの登場によって、そうした思考が主流になってきた。
経済は一瞬たりとも立ち止まることなく、変化して止まない。そして、変化し終わった後は、元に戻すことはほぼ絶望的である。しかし、旧いシステムから新しいシステムへの変化を、進歩と決めつける思考方法には慄然とする。歴史は度々退化するのである。
管理通貨体制から金融のファンド化体制への移行を、私は歴史の退歩と理解している。しかし、現在のファンド化体制を昔の管理通貨体制に戻すことは不可能であろう。とは言え、将来は誘導できるはずのものである。奈落に向かって突き進むいまの体制を別の方向に向けることは可能なはずである。
一九六〇年代、カレンシー・ボード(通貨局)体制を基礎に置く英国ポンドの没落は明らかであった。事実、一九六八年に英国通貨当局は、スエズ以東から撤兵するとの方針を公にして、ポンドを国際通貨の座から降ろしてミニ・ブリテンの国民通貨にする意図であることも示した。カレンシー・ボードとは、英国の植民地に設定されていた通貨発行システムであった。植民地が稼いできた米ドルは、カレンシー・ボードに吸収され、そのドルをイングランド銀行に預託させる。植民地は預託したドルを対価に自国通貨の発行が許されるという体制がカレンシー・ボード・システムであった。こうしてイングランド銀行に蓄積されたドルを、英国は対外赤字の決済に使っていたのである。そうして使われたドルは、英国政府がドルを預託した植民地に返却されなければならない負債となる。それはポンド建てで表示されたポンド残高と呼ばれた。
植民地が植民地の地位に留まるかぎり、ポンド残高の返済は行われなかったが、植民地が独立国になり、カレンシー・ボードを廃止して自己の中央銀行をもつようになると、植民地はポンド残高の返済を英国政府に迫るようになる。しかし、英国政府には支払えるドルがない。一九六〇年代、英国の植民地は相次いで独立していった。ここに、ポンドの没落は必至だったのである。
ポンドが没落過程に入った一九六〇年代後半に、もし、いまのようなポンド先物市場が存在しておれば、投機家は確実に儲けていたであろう。
こうした情況を見たミルトン・フリードマンが、ポンドの空売りをしようと、一九六七年一一月に、シカゴ中の主要なすべての銀行を訪問してポンドの先物の売りを申し込んだ。銀行からの返答は、通貨の先物は特定の顧客か商業目的に制限されたものなので、フリードマンの取引の申し出を受けることはできないというものであった。さらに、「連銀は(イングランド銀行も)先物取引を好まないだろう」とも言われてしまった。
彼はカンカンにになって怒り、当時彼が隔週で担当していた『ニューズウィーク』(Newsweek)のコラムで鬱憤をぶちまけた(Friedman, M. & R. Friedman[1998], p. 351)。
これが、アカデミズムの世界でフリードマン破門説を生み出した。フリードマンがナイトから波紋されたと噂されたのである。その後、彼は、ブレトンウッズ体制下の固定相場制の撤廃を執拗に求めるコラム記事を『ニューズウィーク』誌に積極的に寄稿する。.
そうしたフリードマンの行動を苦々しく見ていたのは、宇沢弘文氏であったという。内橋克人氏が宇沢氏から聞いたことだがと断られて次のように書いている(内橋克人[2006])。
「近々イギリスのポンドが切り下げられることが確実にわかっていたのですが、ポンドが切り下げられる前に今の価格で空売りしておけば、実際に切り下げられたときには確実に儲かるのです。そこでフリードマンは銀行に行って、『一万ポンド空ウリしたい』と申し出たわけです。ところがその銀行のデスクはフリードマンの申し出に対して、『われわれはジェントルマンだから、そういうことはやらない』と言って断ったのです」(同、九六ページ)。
「ジェントルマン」だからと言って断った銀行は、コンチネンタル・イリノイ銀行であり、この銀行は投機目的の融資を禁止する一九三四年のグラス・スティーガル法に従ったと内橋氏は解説している。
「しかし断られたフリードマンはかんかんになって帰ってきて、ランチの席で宇沢さんを含む同僚の教授たちに向かって『資本主義の世界では、儲かるときに儲けるのがジェントルマンなのだ』と真っ赤になって大演説をぶったそうです」(同、九六ページ)。
「このエピソードを見ても、フリードマンは先物による商品や通貨の取引は、投機によるものも含めて全面的に自由化すべきだと考えていたことがわかります」(九七ページ)。
「この話には後日談があって、シカゴ学派の指導者の1人でフリードマンの先生でもあったフランク・ナイトがこうした話を聞いて激怒し、フリードマンとスティグラーを『今後、自分のところで博士論文を書いたと言うことを禁止する』と言って破門してしまったというのです」(九七ページ)。
「ジェントルマン」云々とか、ナイトから波紋されたこととかについて、田中秀臣氏がそうした事実はなかったとご自身のブログ(Economics Lovers Live)で反論されている(「フランク・ナイトは本当にミルトン・フリードマンを破門したのか?」;http://d.hatena.ne.jp/tanakahidetomi/20061122)。
宇沢氏と田中氏のどちらが正しいのかを判定する手段を私はもたない。しかし、フリードマン夫妻の『幸運な二人―思い出』(Two Lucky People―memoirs)は「グーグル・ブックス」のウェブサイトで閲覧できるが、この間の経緯を記述している第二一章「政策論争への参加」(Participating in the Public-Policy Debate, pp. 333-65)は掲載されていない。
問題は、破門されたこと、銀行から紳士ではないと非難されたか否かという点にあるのではない。そんなことはどうでもいいことである。人格攻撃は不毛である。重要なことは、フリードマンの力で固定相場制度が正式に放棄され、シカゴ商品取引所(CME=Chikago Mercantile Exchange)が創設されたことである。
「一九六八年に私はニクソン大統領に私信を送りました。金とドルのつながりを今すぐに断ち切って、金ドル交換制をやめるべきだと伝えたのです。残念ながら提案は受け入れられませんでした」(相田・[1999b]、八一ページ)。
NHK取材陣は、この言葉の重大性に気づかず、CME内に通貨先物取引を新設するために接近してきたレオ・メラメッド(Leo Melamed)との出会いを聞いただけで引き下がっている。
そして、規制緩和を求めるフリードマン、「政府の「規制は最低限にとどめ、自由な市場のもとで通貨の価格を決めるべき」だというフリードマンを持ち上げたのである。
国際通貨の一角を担うポンドがその座から降りようとしているとき、ドルは、ポンド後の負担を一身に引き受けなければならない運命にあった。そうなることからは逃げたかったのが、ニクソン政権の本音であったろう。
しかし、ベトナム戦争の激化によって、ドルは奔流のごとく海外に流出した。しかも、金との交換性を約束している政府の公的ドルの流出であった。金兌換の義務を放棄して米政府はドル価値下落を放置するのではないかと諸外国は疑心悪鬼になっていた。
米政府の外交は行き詰まっていたのである。そして、一九七一年八月一五日、米政府は義務を放棄した。これを政府規制という悪から自由市場という正義に経済体制が移行したとして手放しでフリードマンを称えて見せたのが、NHK『マネー革命2』であった。