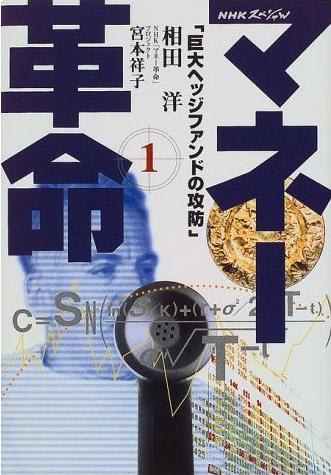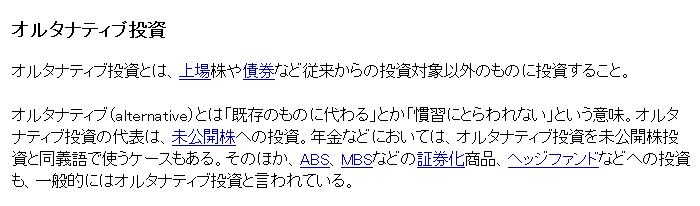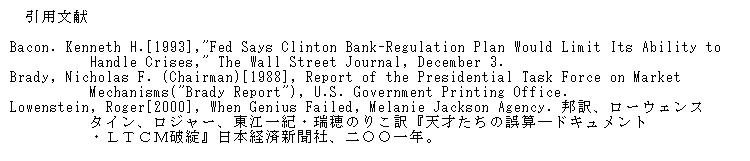投機に人生を賭ける若者に共通する型がある。
まず、人間の投機行動をパターン化してコンピュータにインプットする。その型の分類は、大学で学んだ「計量心理学」等々の、新しい理論に基づく。
つまり、人生経験から人間の心理を学ぶのではなく、大学で流行する新理論とコンピュータへの信頼によって、人間心理を理解する。
もちろん、この場合の人間心理とは、相場に反応する投機家心理に限定されるものであるが、人間を怖ろしく単純化して理解してしまっている。
NHKの『マネー革命1』で著名なファンドマネジャー、ロイ・ニーダーホッファー(Roy Niederhoffer)の自信溢れる言葉が紹介されている。ハーバード大学で専攻した「計量神経科学」を投資に応用しているというのである。
「このビジネスを始めたのは一九九三年(本山が付加、二八歳)のことでした。市場の『恐怖』や『変わりやすさ』や『感情的な反応』などをコンピューターで分析すれば、独創的な取引手法が編み出せると考え、それを使えばお金が稼げると考えました」。
「(計量神経科学は)人間の行動の一つ一つを説明するのにとても有効な学問でした。例えば、人は恐れを感じると、どうしたらよいのかわからなくなります。周囲を見回して『周りのみんなと同じことをしよう』とうろたえます。その翌日になって、ふたたび周囲を見回し、『私はそれほどうろたえる必要はなかった。少し待ってみよう。それにしても昨日は誰もがあんなに怯えていたのに、今は安心しているとはどうしたことだ』と言いながら、今度は買う気になってしまうのです。こうしてパニックと安心感が交互に遅い、二、三日間は相場が下がったり上がったりするのです」。
「こうしたサイクルをコンピューターのプログラムに組み込むことで、相場の動きを的確に予測し、儲かる取引ををしようというわけです」(相田・宮本[1999a]、二三六ページ)。
実際に、彼らが、人間心理をコンピュータで解析しているのか否かについては分からない。いたずらな揚げ足取りは生産的ではないことを承知しつつも、これではケイ線分析とどこが違うのかと嫌みの一つも言いたくなる。少なくとも、「最新の」「科学」なるキャッチフレーズが、出資者を募る武器になっているとしか私には思われない。薄暗いところで若い女性を「コンピュータ占い」をするとして勧誘する行為とほとんど同じことではないのか。
実際に使われている手法は、情報を誰よりも先に入手することである。
「人間は客観的な予測や、長期的な予測を正確にするのは不得意なんです」(同、二四〇ページ)。
としてコンピュータ解析の威力を説明した後、ロイはまったく反対のことを言う。
「相場はどんどん変わっていきますから、私たちの取引には長期の予測よりも、三〇分後、数時間後、数日後といった、短期の予測が必要なんです。そこで、市況の予測も三〇分から数時間、せいぜいで数日間の範囲で行っています」。
「『次の数時間のうちに市場で起きる可能性があるのは何か』を知るための道具が私たちのシステムなんですが、それに使える過去の統計がないときには答えが出せません」(同、二四六ページ)。
本当に揚げ足取りで恥ずかしいが、「『計量神経科学』をお使いではなかったのですか?」と言いたくなる。
他人が使うデータは使用しない。自分たちが独占できる情報でなければならない。全員が見ることのできるモニターが出たときには、市場はその先を行ってしまっているとして、次のようにロイの仲間のマイケル・ラストは言う。
「僕たちはニュースに頼って取引するより、自分たちのシステムで取引するほうがうまくいくと信じています。・・・誰も知らないよい情報でよい予測をすることが秘訣なんですね」(同、二四八ページ)。
情報の独占などできるものだろうか。彼らのコンピュータ解析は情報の独占を彼らにもたらしているのだろうか。
しかし、彼らはとてつもなく重要なことをさらりと言ってのけた。金融市場はゼロサム・ゲームだと断定し、多数派にはつかないとした。誰も使っていない情報を自分たちだけが使うなんて恐ろしくないかとのNHK取材陣に対して次のように答えた。
(ロイ)「いや、怖くはありませんよ。あえて人と違うことをしたいと思っています。それが私たちの戦略です。金融市場はゼロサム・ゲーム。敗者の金はそっくり勝者が取るのが鉄則です。しかも、損をするのは常に多数派です。特に先物市場では勝つか、負けるかしかないんです。ブローカーや法律家など、手数料を取る人たちの儲けが、どこから来ているか知っていますか。その金は多数派が損した金なんですよ。それから、取引所やローカル・トレーダーが稼ぐ金もまた、多数派が損した金なんです。多数派がやっていることこそが危険だと考えるべきなんです。だから、あえて多数派とは反対のことをする。それが私たちの主義なんです」(同、二四九ページ)。
しかし、独自の情報の独占というからには、自分たちのコンピュータ解析に対する強い信頼からくる発言だと思ってしまうが、実際には、「なーんだ」ということであった。シカゴの商品先物取引所などにブローカーを常駐させて、電話で知らせるというのである。モニターに映し出されるよりも、あるいは、ウエブサイトで情報が流されるよりも、四秒は早く「モルガン・スタンレーが米国債を二〇〇〇万ドル買った」という情報を得ることができる。指数先物は米国債に連動するので、この四秒の間に先物を買えばよいというのである(同、二五〇ページ)。画面を見て取引する人よりも取引所の生の声を〇・五秒でも早く知ることが大事だというのである。生の声とは、取引所に常駐させているブローカーの電話から流れる取引の熱気のことである。
「このように取引所の生の声を直接聞いていると、画面を見て取引する人たちよりも〇・五秒ほど早く価格を知ることができるんです」(同、二五〇ページ)。
これが豪語された「情報の独占」のことなのだろうか。
(ロイ)「これは私たちが独自に発見したことなんですが、『市場にパニックが起きると人間の行動が最も予測しやすくなる』ということです。そこで、私たちはコンピューターを使って『恐怖の度合いを数値化』して、その『量的な変化』を見ながら、市場に何が起こるかを予測するんです」(同、二五五~五六ページ)。
では、今日は、大勝利だったのですねとの取材陣の質問に対して、
「いえ、残念ながら、今日はあまりうまくいきませんでした。私たちのシステムがあまり正確な判断を下せなかったんです。今日は負けを認めなければなりません」(同、二五六ページ)。
彼らは、『ウォール・ストリート・ジャーナル』の朝刊で、「FED、数か月早く利上げを検討する」という観測記事の反応に失敗したのである。他人が使う情報は無視すると豪語しながら、この情報に飛びついただけでなく、ありふれた観測記事への対応に失敗したことは、彼らが豪語するシステムが単なるキャッチ・コピーであったことを示している。
今回は、品性において劣る文を書いてしまった。深謝。
引用文献
相田洋・宮本祥子[1999a]、『マネー革命1―巨大ヘッジファンドの攻防』NHK出版。