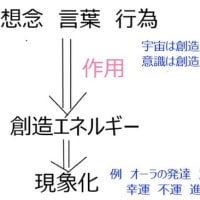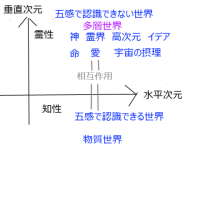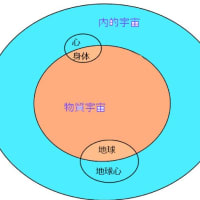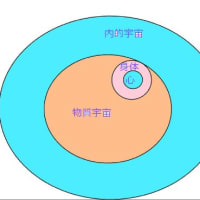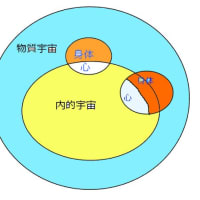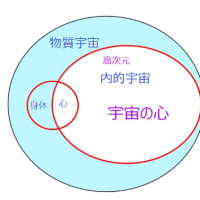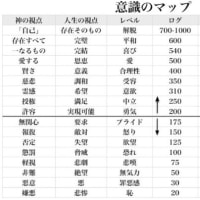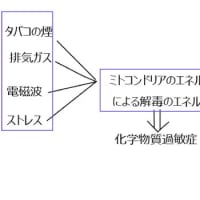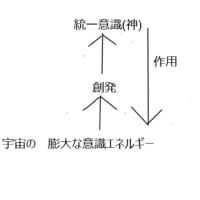日本大百科全書(ニッポニカ)の解説
認知科学
にんちかがく
cognitive science
認知心理学、人工知能(学)、言語学、認知神経科学、哲学などにまたがる学際的基礎科学。人間および、より一般的な意味での「知能・認識」の理解・解明を目ざす。その意味で認知心理学と同じ目的をもつといえるが、方法論、とくにその理論的側面においては、コンピュータ上へのモデル化を中心に、より高度な形式性を要求する特徴がある。
1960年代から1970年代にかけて、アメリカの認知心理学では、認識された情報や体得された情報、すなわち広義の「知識」knowledgeが、心の内部でどのように処理され、「表象・表現」representされ、そして、利用されているのかという疑問が大きく取り上げられるようになってきた。この疑問の解明には、心の内部過程をブラックボックスとしたまま「刺激stimulus→反応response」の対応関係のみを把握しようとしてきた従来の行動主義的方法論では対処できず、内部知識の構造と働きを明確に説明できる動的なプロセス・モデル(コンピューテーショナル・モデル)の提案が望まれるようになった。この種のモデルの構築は、人間の知的能力の「代行や増強」を目的とするものではないが、コンピュータ上へ組み込むことが要求されるため、当初から人工知能(学)と強いつながりをもつことになった。また、当初、知識の内部表現についての基本的アイデアは、理論言語学における意味表示(表現)理論を参考にしたものが多かったため、認知科学と理論言語学との関わりも大きなものとなった。
このような経緯のもとに認知心理学、人工知能(学)、理論言語学の3分野を中心とした学際的研究交流の気運が高まり、アメリカでは1977年に学術雑誌『認知科学』Cognitive Scienceが発刊され、1979年には学会も設立された。その後、20世紀を代表する新しい科学の一つとして世界的に広がり、日本でも1983年(昭和58)に日本認知科学会が設立された。その後、1990年代以降、fMRI(functional Magnetic Resonance Imaging:機能的磁気共鳴画像)、MEG(Magnetoencephalograph:脳磁図)、NIRS(Near-Infrared Spectroscopy:近赤外線分光分析)など脳活動の特徴を可視化する方法の進歩に伴い、人間の高次心理過程と中枢神経系との対応関係の解明を目ざす認知神経科学が急速に発展した。今日では、欧米の有力大学を中心に、それらの脳メカニズム研究をも取り込んだ形で「認知科学」を標榜(ひょうぼう)する研究・教育プログラムが数多く見受けられるようになっている。
認知科学の成果としては、初期には、サイモンの流れをくむ一群の思考過程のモデル化研究、シャンクRoger C. Schank(1946― )を中心とした文章(テキスト)や会話の理解と生成の過程についての理論化など、記号的人工知能symbolic AIと連動した成果が代表的であった。その後1980年代に入り、マクレランドJames L. McClelland(1948― )とラメルハートDavid E. Rumelhart(1942―2011)の主導による並列分散処理の計算パラダイム(神経回路網モデル、コネクショニストモデル)による新しい認知モデル化研究が勃興(ぼっこう)し、知覚、記憶、学習、言語理解など各種の認知現象の理論的説明に大きく寄与した。
今日の認知科学は、上述した認知神経科学をはじめ、より幅広く、文化人類学、教育学、そして、認識論、身体論、科学方法論などの哲学的考察までを含んだ学際的基礎科学として成立している。その今後としては、心と脳の「知」cognitionの側面に限らず、「情」emotion, affectionの側面の解明へも大きく広がって行くことが予想される。[阿部純一]
認知科学
にんちかがく
cognitive science
認知心理学、人工知能(学)、言語学、認知神経科学、哲学などにまたがる学際的基礎科学。人間および、より一般的な意味での「知能・認識」の理解・解明を目ざす。その意味で認知心理学と同じ目的をもつといえるが、方法論、とくにその理論的側面においては、コンピュータ上へのモデル化を中心に、より高度な形式性を要求する特徴がある。
1960年代から1970年代にかけて、アメリカの認知心理学では、認識された情報や体得された情報、すなわち広義の「知識」knowledgeが、心の内部でどのように処理され、「表象・表現」representされ、そして、利用されているのかという疑問が大きく取り上げられるようになってきた。この疑問の解明には、心の内部過程をブラックボックスとしたまま「刺激stimulus→反応response」の対応関係のみを把握しようとしてきた従来の行動主義的方法論では対処できず、内部知識の構造と働きを明確に説明できる動的なプロセス・モデル(コンピューテーショナル・モデル)の提案が望まれるようになった。この種のモデルの構築は、人間の知的能力の「代行や増強」を目的とするものではないが、コンピュータ上へ組み込むことが要求されるため、当初から人工知能(学)と強いつながりをもつことになった。また、当初、知識の内部表現についての基本的アイデアは、理論言語学における意味表示(表現)理論を参考にしたものが多かったため、認知科学と理論言語学との関わりも大きなものとなった。
このような経緯のもとに認知心理学、人工知能(学)、理論言語学の3分野を中心とした学際的研究交流の気運が高まり、アメリカでは1977年に学術雑誌『認知科学』Cognitive Scienceが発刊され、1979年には学会も設立された。その後、20世紀を代表する新しい科学の一つとして世界的に広がり、日本でも1983年(昭和58)に日本認知科学会が設立された。その後、1990年代以降、fMRI(functional Magnetic Resonance Imaging:機能的磁気共鳴画像)、MEG(Magnetoencephalograph:脳磁図)、NIRS(Near-Infrared Spectroscopy:近赤外線分光分析)など脳活動の特徴を可視化する方法の進歩に伴い、人間の高次心理過程と中枢神経系との対応関係の解明を目ざす認知神経科学が急速に発展した。今日では、欧米の有力大学を中心に、それらの脳メカニズム研究をも取り込んだ形で「認知科学」を標榜(ひょうぼう)する研究・教育プログラムが数多く見受けられるようになっている。
認知科学の成果としては、初期には、サイモンの流れをくむ一群の思考過程のモデル化研究、シャンクRoger C. Schank(1946― )を中心とした文章(テキスト)や会話の理解と生成の過程についての理論化など、記号的人工知能symbolic AIと連動した成果が代表的であった。その後1980年代に入り、マクレランドJames L. McClelland(1948― )とラメルハートDavid E. Rumelhart(1942―2011)の主導による並列分散処理の計算パラダイム(神経回路網モデル、コネクショニストモデル)による新しい認知モデル化研究が勃興(ぼっこう)し、知覚、記憶、学習、言語理解など各種の認知現象の理論的説明に大きく寄与した。
今日の認知科学は、上述した認知神経科学をはじめ、より幅広く、文化人類学、教育学、そして、認識論、身体論、科学方法論などの哲学的考察までを含んだ学際的基礎科学として成立している。その今後としては、心と脳の「知」cognitionの側面に限らず、「情」emotion, affectionの側面の解明へも大きく広がって行くことが予想される。[阿部純一]