今日はミニアートのバンタム BRC-40を紹介します。月刊ホビージャパン2011年2月号に作例として掲載されたものです。
キットをストレートに製作し、簡単なベースに乗せました。全景はこんな感じです。

タイトルは、編集部が付けてくださった誌面の見出しがとても面白かったので、作品が帰ってきたあとで拝借して付けました。

要するに、道に迷ってるわけですね(笑)
キットは繊細・精密で組み立てもそんなに難しくなくて、とてもよくできてます。ミニアートのキットを組むのはこれが初めてだったのですが、出来のよさにびっくりした記憶が。グリルのスリットもびしっと決まってます。

モールドもメリハリの効いたシャープな感じで、塗装のやりがいがあります。ピンクと水色が混じった変な迷彩ですが、これは塗装図のまんまです。目を引く模型栄えする色調ですね。

裏の足回りもばっちりです。

エンジンもきちんと入ってます。コードとか追加するととてもいい感じになるのでは。

道標は薄い木の板で自作。地名は、グーグルマップで北アフリカの辺りをうろうろしてそれっぽいものを適当に書いてます。便利な時代になったものです。イメージは明らかに「気分はもう戦争」の扉絵からですね。今見て気づきました(笑)

このキット、車両もいいのですが、フィギュアも素晴らしいです。
3体で、しかも車両の上だけでドラマが生まれてます。しかもシリアスじゃなくてちょっと面白い(笑)
こういうのはミニアートの面目躍如といったところですね。塗装図には、カラーで徽章の類も細かく描かれているのもほんとありがたいです。なので、出来るだけきちんと塗りました。

ただ、車体とのフィッティングが悪いので、結構な微調整が必要です。とはいえミニアートのプラはとてもやわらかいので、ちょこちょこ根気よく調整すれば収まってくれます。
ほんと、このフィギュアたちはおもろいです。ミニコント入ってますよね。
 「チミチミ、ウチらはどこに向かっとるんだね」
「チミチミ、ウチらはどこに向かっとるんだね」

「え、、、?知らないっすよ」

「マジで?」

「腹減ったなあ、、、」
てな感じですかね。
こちらが誌面です。1Pです。名前が間違ってますが、まあ、そういうこともあります。
バンタムはウイリスMBなどのいわゆるジープの原型となった車両です。ちょっとマイナーなので、キットが出たこと自体喜ばしいことですし、さらに高品質な内容なのはとても嬉しいことですね。この流れで丸っこくてかわいいバンタム一号車とか出してほしいところですが、さすがに無理ですね(笑)
で、ジープ系の車両でぜひキットがほしいのがトヨタAK-10です。1944年に作られた和製ジープです。「四式小型貨物車」として制式採用されたものの、5台だけ作られて量産前に終戦になりました(こんなのばっか)。イラストにしてみました。
陸軍から「ジープみたいな車両がほしいから作りなはれ。でも、ジープに似たらあきまへんで」という禅問答みたいな指示を受けてトヨタが製作(気の毒だ、、)。結果、今製造したとしてもジープ社からギリギリ訴えられなさそうな実に素敵な車両となりました。この車両での経験が、後のトヨタのジープやランクルの開発に生かされたそうです。そう考えると、陸軍のムチャ振りは意味のないことではなかったわけですね。多分。
特徴的な一つ目のライトは、ジープに似せないための配慮のようで、もちろん資材の節約という目的もあったと思います。陸王軽四軌で使われたリーディングアーム式のサスペンション(えらそうに書いてますが、どんな仕組みなのかよく知りません(笑))を採用したため、前輪が前方に突き出し、ちょっとアンバランスな感じになってます。それやこれやで、なんとも日本軍らしいスタイルで、ほんとキットがほしいです。が、まあでも、さすがにキット化は無理でしょうねえ、、。
ただ、小さい車両なので作ろうと思えば作れそうではあります。本土決戦ジオラマにぴったりの車両なので、ずっと製作を検討してるのですが、残念ながら公になってる写真は二枚しかないのです。図面とかはトヨタに残ってそうな気もするんですけどね、、、。写真から無理やり作っちゃおうかな、、、。ちなみに、ジープに似すぎて没にされたプロトタイプもめちゃくちゃ素敵なので、興味のある人は検索してみてください。
というわけでまた。AK-10の概要については「図説 四輪駆動車」(山海堂)を参考にしました。
キットをストレートに製作し、簡単なベースに乗せました。全景はこんな感じです。

タイトルは、編集部が付けてくださった誌面の見出しがとても面白かったので、作品が帰ってきたあとで拝借して付けました。

要するに、道に迷ってるわけですね(笑)
キットは繊細・精密で組み立てもそんなに難しくなくて、とてもよくできてます。ミニアートのキットを組むのはこれが初めてだったのですが、出来のよさにびっくりした記憶が。グリルのスリットもびしっと決まってます。

モールドもメリハリの効いたシャープな感じで、塗装のやりがいがあります。ピンクと水色が混じった変な迷彩ですが、これは塗装図のまんまです。目を引く模型栄えする色調ですね。

裏の足回りもばっちりです。

エンジンもきちんと入ってます。コードとか追加するととてもいい感じになるのでは。

道標は薄い木の板で自作。地名は、グーグルマップで北アフリカの辺りをうろうろしてそれっぽいものを適当に書いてます。便利な時代になったものです。イメージは明らかに「気分はもう戦争」の扉絵からですね。今見て気づきました(笑)

このキット、車両もいいのですが、フィギュアも素晴らしいです。
3体で、しかも車両の上だけでドラマが生まれてます。しかもシリアスじゃなくてちょっと面白い(笑)
こういうのはミニアートの面目躍如といったところですね。塗装図には、カラーで徽章の類も細かく描かれているのもほんとありがたいです。なので、出来るだけきちんと塗りました。

ただ、車体とのフィッティングが悪いので、結構な微調整が必要です。とはいえミニアートのプラはとてもやわらかいので、ちょこちょこ根気よく調整すれば収まってくれます。
ほんと、このフィギュアたちはおもろいです。ミニコント入ってますよね。
 「チミチミ、ウチらはどこに向かっとるんだね」
「チミチミ、ウチらはどこに向かっとるんだね」
「え、、、?知らないっすよ」

「マジで?」

「腹減ったなあ、、、」
てな感じですかね。
こちらが誌面です。1Pです。名前が間違ってますが、まあ、そういうこともあります。

バンタムはウイリスMBなどのいわゆるジープの原型となった車両です。ちょっとマイナーなので、キットが出たこと自体喜ばしいことですし、さらに高品質な内容なのはとても嬉しいことですね。この流れで丸っこくてかわいいバンタム一号車とか出してほしいところですが、さすがに無理ですね(笑)
で、ジープ系の車両でぜひキットがほしいのがトヨタAK-10です。1944年に作られた和製ジープです。「四式小型貨物車」として制式採用されたものの、5台だけ作られて量産前に終戦になりました(こんなのばっか)。イラストにしてみました。

陸軍から「ジープみたいな車両がほしいから作りなはれ。でも、ジープに似たらあきまへんで」という禅問答みたいな指示を受けてトヨタが製作(気の毒だ、、)。結果、今製造したとしてもジープ社からギリギリ訴えられなさそうな実に素敵な車両となりました。この車両での経験が、後のトヨタのジープやランクルの開発に生かされたそうです。そう考えると、陸軍のムチャ振りは意味のないことではなかったわけですね。多分。
特徴的な一つ目のライトは、ジープに似せないための配慮のようで、もちろん資材の節約という目的もあったと思います。陸王軽四軌で使われたリーディングアーム式のサスペンション(えらそうに書いてますが、どんな仕組みなのかよく知りません(笑))を採用したため、前輪が前方に突き出し、ちょっとアンバランスな感じになってます。それやこれやで、なんとも日本軍らしいスタイルで、ほんとキットがほしいです。が、まあでも、さすがにキット化は無理でしょうねえ、、。
ただ、小さい車両なので作ろうと思えば作れそうではあります。本土決戦ジオラマにぴったりの車両なので、ずっと製作を検討してるのですが、残念ながら公になってる写真は二枚しかないのです。図面とかはトヨタに残ってそうな気もするんですけどね、、、。写真から無理やり作っちゃおうかな、、、。ちなみに、ジープに似すぎて没にされたプロトタイプもめちゃくちゃ素敵なので、興味のある人は検索してみてください。
というわけでまた。AK-10の概要については「図説 四輪駆動車」(山海堂)を参考にしました。
















































 チハからスタートして、ここまで行き着いたのは凄いなあと。Ⅲ号戦車よりも小さいのに、、、。
チハからスタートして、ここまで行き着いたのは凄いなあと。Ⅲ号戦車よりも小さいのに、、、。



 というわけで、やっぱり一回では紹介し切れませんでした(笑)。次回は建物とか兵士のディテールを紹介したいと思います。
というわけで、やっぱり一回では紹介し切れませんでした(笑)。次回は建物とか兵士のディテールを紹介したいと思います。
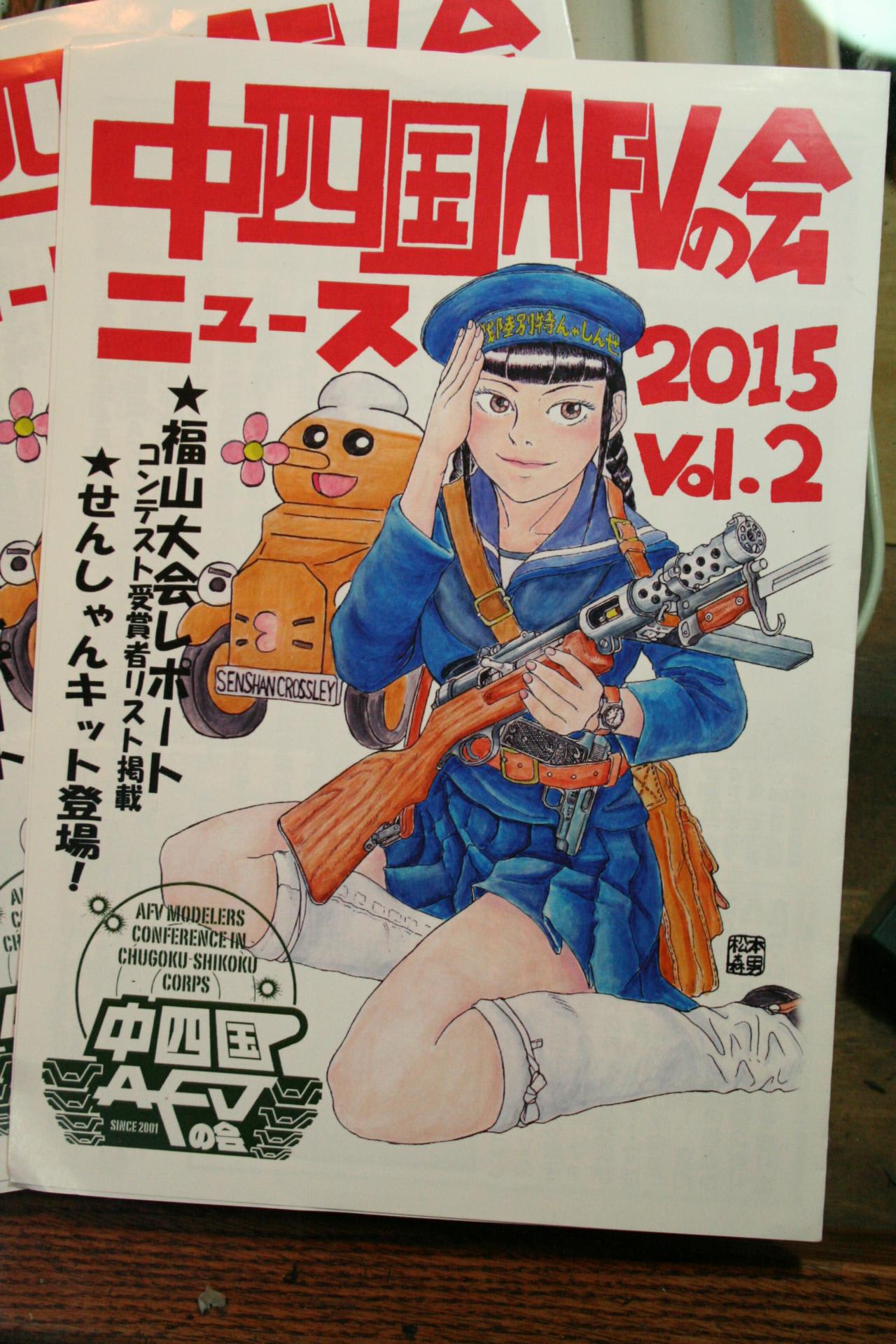













 鹵獲して、砲塔の上に置いているという設定。
鹵獲して、砲塔の上に置いているという設定。 とてもいいプロポーションなので、フロント・リアサイトを追加、2脚を作り直すなど、手を入れれば入れるだけ良くなるので作業が楽しいです。で、ドイツ小火器セットの傑作ぶりからすると、アメリカ小火器セットはちょっと分が悪いですね。同じ時期の製品なのに、なぜこんなに仕上がりが違うのか、、。MP40、98K、P08、P38などなど、どれも今でも最高レベルなのに、ガーランドやトンプソン、グリースガンは、「、、、、、」(ノーコメント)。気合の問題なのでしょうか。
とてもいいプロポーションなので、フロント・リアサイトを追加、2脚を作り直すなど、手を入れれば入れるだけ良くなるので作業が楽しいです。で、ドイツ小火器セットの傑作ぶりからすると、アメリカ小火器セットはちょっと分が悪いですね。同じ時期の製品なのに、なぜこんなに仕上がりが違うのか、、。MP40、98K、P08、P38などなど、どれも今でも最高レベルなのに、ガーランドやトンプソン、グリースガンは、「、、、、、」(ノーコメント)。気合の問題なのでしょうか。
 樽は木の丸棒に杉の薄板の細切を張って、麻紐を木工ボンドで寄り合わせたものを巻いてます。七輪は紙粘土と板鉛。カマスはエポパテ。塗装後、麻紐で車体にくくりつけます。
樽は木の丸棒に杉の薄板の細切を張って、麻紐を木工ボンドで寄り合わせたものを巻いてます。七輪は紙粘土と板鉛。カマスはエポパテ。塗装後、麻紐で車体にくくりつけます。 これは以前に紹介した四式試作型のもので、三式のも多分こんな風になります。V・S・O・Pです(笑)。
これは以前に紹介した四式試作型のもので、三式のも多分こんな風になります。V・S・O・Pです(笑)。
 完成しても出来栄えがあまり気に入らなかった上、引越しや移動のために徐々に壊れていき、最後には標的戦車ならぬ試験塗装戦車(試し塗りとかの実験台)となって長いこと作業机の上に陣取っていたのですが、ずっとそれを見ていたら不憫になってきたのでした、、、。また、三式中戦車はその後の四-五式に比べてちょっと弱っちいイメージがあるので、何とか強そうにできないかなあと、だんだんやる気になってきたわけです。とはいえ、何をするといえば、例によってキャタピラの増加装甲しかないわけです(笑)以前タミヤのマーダーⅡを作ったとき、増加装甲でアウトラインがちょっと変わって、違う形に見えて新鮮だったのでもう一度やってみたかったというのもあります。
完成しても出来栄えがあまり気に入らなかった上、引越しや移動のために徐々に壊れていき、最後には標的戦車ならぬ試験塗装戦車(試し塗りとかの実験台)となって長いこと作業机の上に陣取っていたのですが、ずっとそれを見ていたら不憫になってきたのでした、、、。また、三式中戦車はその後の四-五式に比べてちょっと弱っちいイメージがあるので、何とか強そうにできないかなあと、だんだんやる気になってきたわけです。とはいえ、何をするといえば、例によってキャタピラの増加装甲しかないわけです(笑)以前タミヤのマーダーⅡを作ったとき、増加装甲でアウトラインがちょっと変わって、違う形に見えて新鮮だったのでもう一度やってみたかったというのもあります。

 全体的に小うるさく、ガチャガチャした感じになりましたが、必死な感じが出てるっぽいのでこれでいいかな、と思います。チェーンを使ったらイカツクなってよかったなあと、ひとり悦に入ってます(笑)
全体的に小うるさく、ガチャガチャした感じになりましたが、必死な感じが出てるっぽいのでこれでいいかな、と思います。チェーンを使ったらイカツクなってよかったなあと、ひとり悦に入ってます(笑) 最初は車体前部上面が全て埋まるまでキャタピラを載せていたのですが、さすがに重すぎだろうということで、ムシロ製の土嚢を積んだことにしました。エポパテを載せて車体に馴染ませ、硬化し始めくらいのときにデザインナイフで目をつけます。弾がかすったか砲弾の破片かで破けたようにしました。塗装後、中の土がデローっと出たような表現をするつもりです。
最初は車体前部上面が全て埋まるまでキャタピラを載せていたのですが、さすがに重すぎだろうということで、ムシロ製の土嚢を積んだことにしました。エポパテを載せて車体に馴染ませ、硬化し始めくらいのときにデザインナイフで目をつけます。弾がかすったか砲弾の破片かで破けたようにしました。塗装後、中の土がデローっと出たような表現をするつもりです。 紙粘土で作りました。バリエーションは無限にありますので、雰囲気重視で。そういえば、これも気がつくと街からいつの間にかなくなってたアイテムですね。うちの近所にもあって、通学の時毎日目に入ってたのですが、あれは一体いつどこにいったんだろう、、、。
紙粘土で作りました。バリエーションは無限にありますので、雰囲気重視で。そういえば、これも気がつくと街からいつの間にかなくなってたアイテムですね。うちの近所にもあって、通学の時毎日目に入ってたのですが、あれは一体いつどこにいったんだろう、、、。 ちょ、ちょっとつらいっす、、。94式拳銃も
ちょ、ちょっとつらいっす、、。94式拳銃も 「、、、、」といった感じ、、、。
「、、、、」といった感じ、、、。 「ぴしーっ」としてるでしょ?なんで昔のほうがいいんだろ? ちなみに、96式と99式の区別の仕方は、マガジンのカーブがゆるいのが99、きついのが96です(弾丸の形状が違うので。上の写真でもわかります。そこは評価したいです)あと、銃床に単脚があるのが99、ないのが96です。でも96の外観で口径は7・7ミリという引っ掛け問題みたいな個体(過度期の試作品?)もあるそうなので注意したいところです。どーでもいいですかそうですか。
「ぴしーっ」としてるでしょ?なんで昔のほうがいいんだろ? ちなみに、96式と99式の区別の仕方は、マガジンのカーブがゆるいのが99、きついのが96です(弾丸の形状が違うので。上の写真でもわかります。そこは評価したいです)あと、銃床に単脚があるのが99、ないのが96です。でも96の外観で口径は7・7ミリという引っ掛け問題みたいな個体(過度期の試作品?)もあるそうなので注意したいところです。どーでもいいですかそうですか。



 フェンダーも薄いので、手やプライヤーで曲げれば簡単にダメージが表現できます。塗装は、クレオスのジャーマングレーに白や青を混ぜて明るくしています。ジャーマングレーはちょっと明るくて青っぽいほうが好みです。
フェンダーも薄いので、手やプライヤーで曲げれば簡単にダメージが表現できます。塗装は、クレオスのジャーマングレーに白や青を混ぜて明るくしています。ジャーマングレーはちょっと明るくて青っぽいほうが好みです。 これ以上圧力がかかると、次に装甲板の溶接が割れ、車体が潰れるのではないかと。でも、Ⅰ号戦車クラスの車両でも、何トンの圧力がかかるとぺったんこに潰れるのか、ちょっとわからないですね。まあ、わかっても仕方がないんですが。
これ以上圧力がかかると、次に装甲板の溶接が割れ、車体が潰れるのではないかと。でも、Ⅰ号戦車クラスの車両でも、何トンの圧力がかかるとぺったんこに潰れるのか、ちょっとわからないですね。まあ、わかっても仕方がないんですが。


 強い(とされている)ドイツ軍の戦車が、弱い(とされている)ポーランド軍の戦車に負けているという構図はとても新鮮でした。逃げる情けないドイツ戦車兵もインパクトがありました。ドイツ兵って、カッコよくするのが前提みたいな感じでしたから、目からウロコでした。
強い(とされている)ドイツ軍の戦車が、弱い(とされている)ポーランド軍の戦車に負けているという構図はとても新鮮でした。逃げる情けないドイツ戦車兵もインパクトがありました。ドイツ兵って、カッコよくするのが前提みたいな感じでしたから、目からウロコでした。 こうやってみると、元ネタにさせていただいたことがわかっていただけるのではないかと思います。土居氏にはこの場をお借りして、無断拝借をお詫びするとともに、心よりお礼申し上げます(事後報告で申し訳ないのですが、、、)。
こうやってみると、元ネタにさせていただいたことがわかっていただけるのではないかと思います。土居氏にはこの場をお借りして、無断拝借をお詫びするとともに、心よりお礼申し上げます(事後報告で申し訳ないのですが、、、)。
 雑誌作例としてホビージャパン誌2014年5月号に掲載され、「ホビージャパンムック 戦車模型製作の教科書 MENG編」に再掲載されたものです。もしよろしければぜひご覧下さい。
雑誌作例としてホビージャパン誌2014年5月号に掲載され、「ホビージャパンムック 戦車模型製作の教科書 MENG編」に再掲載されたものです。もしよろしければぜひご覧下さい。
 昔からキットがほしい戦車のひとつでしたが、さすがにマイナーすぎて無理だろうと思ってました。なのでモンモデルがリリースを発表した時はびっくりしました。
昔からキットがほしい戦車のひとつでしたが、さすがにマイナーすぎて無理だろうと思ってました。なのでモンモデルがリリースを発表した時はびっくりしました。 タミヤエナメルでウオッシングし、チッピング。それから下地の近似色で明度を変えた塗料を塗り広げ、色の深みを出します。ここはほんとは油彩の仕事なのですが、乾く時間が遅いのでエナメルで同じようにできないかやってみたところ、まあまあそれっぽくなりました。「なんちゃって油彩」ですね。
タミヤエナメルでウオッシングし、チッピング。それから下地の近似色で明度を変えた塗料を塗り広げ、色の深みを出します。ここはほんとは油彩の仕事なのですが、乾く時間が遅いのでエナメルで同じようにできないかやってみたところ、まあまあそれっぽくなりました。「なんちゃって油彩」ですね。

 緑の場所のチッピングは、ダークイエローと錆色の二種でやるとそれっぽくなりますね。ダークイエローのチッピングはハンブロールの154番を使用。ハンブロールはほぼ初めて使ったのですが(何種類かは以前買って在庫していたのですが、ほとんど使ってなかったのです)、この種の色調の割には伸びと発色がとても良くて使いやすかったです。さすが、、。マフラーもガビガビにします。でも凹みとかはつけてません。錆は、パステルで。
緑の場所のチッピングは、ダークイエローと錆色の二種でやるとそれっぽくなりますね。ダークイエローのチッピングはハンブロールの154番を使用。ハンブロールはほぼ初めて使ったのですが(何種類かは以前買って在庫していたのですが、ほとんど使ってなかったのです)、この種の色調の割には伸びと発色がとても良くて使いやすかったです。さすが、、。マフラーもガビガビにします。でも凹みとかはつけてません。錆は、パステルで。
 泥はいつもの百均の木粉粘土を水で溶いて塗りつけたものに、エナメルを染み込ませています。キャタピラがメチャ長いので、大変です。
泥はいつもの百均の木粉粘土を水で溶いて塗りつけたものに、エナメルを染み込ませています。キャタピラがメチャ長いので、大変です。
 上と同じ写真をいじったのですが、違い、わかります?これくらいがバランスが良くて、しかもちょっと強そう(笑) 昔なら、キットを改造するしかなかったのですが、今はこうやってお手軽にシミュレーションできるわけで、いい時代になったものです。でも、実際にちょっとやってみたかったりして(笑)
上と同じ写真をいじったのですが、違い、わかります?これくらいがバランスが良くて、しかもちょっと強そう(笑) 昔なら、キットを改造するしかなかったのですが、今はこうやってお手軽にシミュレーションできるわけで、いい時代になったものです。でも、実際にちょっとやってみたかったりして(笑) うわあ、、、29年前かあ、、。当時はお小遣いが月1000円とかで、模型雑誌を買うのは死ぬ思いでした。この号は、特に気になる記事があったわけではないのですが、何故か買ったわけです。誕生日とかで祖父母からお金をもらって余裕があったのかな?(どーでもいい)
うわあ、、、29年前かあ、、。当時はお小遣いが月1000円とかで、模型雑誌を買うのは死ぬ思いでした。この号は、特に気になる記事があったわけではないのですが、何故か買ったわけです。誕生日とかで祖父母からお金をもらって余裕があったのかな?(どーでもいい) しかし、580円の模型雑誌の前で「買うたやめた音頭」を踊る最低辺の身分の私が、3000円のレジンキット(でも今考えるとフェアリーのキットって、物価上昇率を考慮しても割と安いですね、、)を通販という複雑怪奇な手続きを経て買えるわけはなく、そしてもし入手できたとしても完成させるスキルがあるはずもなく、文字通り指をくわえてみているだけだったのでした。
しかし、580円の模型雑誌の前で「買うたやめた音頭」を踊る最低辺の身分の私が、3000円のレジンキット(でも今考えるとフェアリーのキットって、物価上昇率を考慮しても割と安いですね、、)を通販という複雑怪奇な手続きを経て買えるわけはなく、そしてもし入手できたとしても完成させるスキルがあるはずもなく、文字通り指をくわえてみているだけだったのでした。
 左のポーチ(弾丸入れ)がそれです。水筒の紐も同様です。ポーチは、エポパテが半乾きのときにガーゼを当てました。紐は、デザインナイフでスジを入れてます。
左のポーチ(弾丸入れ)がそれです。水筒の紐も同様です。ポーチは、エポパテが半乾きのときにガーゼを当てました。紐は、デザインナイフでスジを入れてます。 腰のナイフは、米軍のトレンチナイフ。まあ、見ての通りケンカ用のナイフです。懐剣のつもり。九四式拳銃とかにしようかな、とも思いましたが、重武装過ぎてやりすぎかなあと思ってやめました。
腰のナイフは、米軍のトレンチナイフ。まあ、見ての通りケンカ用のナイフです。懐剣のつもり。九四式拳銃とかにしようかな、とも思いましたが、重武装過ぎてやりすぎかなあと思ってやめました。 「女子学徒挺身隊」は松本次郎氏の漫画「地獄のアリス」から。まあ、これも誰も気付かないですね。ははは。麻布区は、ほんとにあった区です。32年から47年まで、東京は35区あったそうです。その後統廃合され、23区になったとのこと。麻布区は港区の一部でした。これは、覚えておくといつか役に、、、立たないですね。
「女子学徒挺身隊」は松本次郎氏の漫画「地獄のアリス」から。まあ、これも誰も気付かないですね。ははは。麻布区は、ほんとにあった区です。32年から47年まで、東京は35区あったそうです。その後統廃合され、23区になったとのこと。麻布区は港区の一部でした。これは、覚えておくといつか役に、、、立たないですね。

 そもそもは、機関銃を持ってるだけの想定でした。ふと思いついて日章旗を付けてみると、一番手前の空間がぴったりと埋まり、「決まった!」と思いました(バカみたいですけど)。で、「ああ、自分はこれを作りたかったんだ」と頭がスカーッと抜けたような気がしました。
そもそもは、機関銃を持ってるだけの想定でした。ふと思いついて日章旗を付けてみると、一番手前の空間がぴったりと埋まり、「決まった!」と思いました(バカみたいですけど)。で、「ああ、自分はこれを作りたかったんだ」と頭がスカーッと抜けたような気がしました。 会場や誌面で、吉岡氏に過分な選評をいただき、感無量でした。で、翌月の静岡HSで、吉岡氏にお願いして台の裏にサインをいただきました。家宝です。吉岡氏には、この場をお借りして心よりお礼申し上げます。
会場や誌面で、吉岡氏に過分な選評をいただき、感無量でした。で、翌月の静岡HSで、吉岡氏にお願いして台の裏にサインをいただきました。家宝です。吉岡氏には、この場をお借りして心よりお礼申し上げます。



