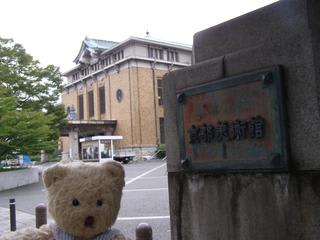ブログを見たら、金魚をクリックしてね
京都に暮らし始めたミモロ。「せっかく京都にいるんだから、何か習い事をしたいなぁ」と。ふとしたきっかけで知ったのが、「古筆(こひつ)」を習う文化サロンです。
ミモロは、秋のはじまりの頃、文化サロンが開催される京都祇園の花見小路へ出かけました。

「祇園の真ん中で習い事って、なんか素敵!京都らしいー」と、東京生まれのミモロは、ワクワク。
訪れたのは、花見小路沿いの料理屋さん「津田楼」です。

ここは、かつて芸妓さんや舞妓さんがいたお茶屋さんだったところ。現在は、お食事が楽しめる料理屋さんであり、夜は、バーになるお店です。大正期の歴史的な建物が、当時の風情を漂わせるお座敷が、お稽古の会場です。
元お茶屋さんだけあって、玄関にも町家ならではの風情が。
「こんな素敵な場所で、習えるんだー。さすが京都だね」と、ちょっとドキドキするミモロです。
「あのーごめんください」とお玄関で声をかけると。

「あ、古筆(こひつ)のご予約のミモロさまですね。どうぞお2階へお上がり下さい」と言われ、トコトコ階段を上り、2階のお座敷に進みます。
そもそも「古筆(こひつ)」とは、「古今和歌集」に代表される平安~鎌倉時代初期の和歌を記した美しいかな書のこと。ここでは、現在残る美しい古筆を題材に、かなの書き方などを習うと共に、その書の意味、歴史的背景や当時の社会状況などを、先生のお話から学びます。
「はじめまして、ミモロと申します。どうぞよろしくお願いします」と、まずはきちんとご挨拶。

すでに先生と生徒さんがお座敷に。

このお教室の先生は、十三世茂山千五郎に師事し、狂言師としても活躍していた柳本勝海先生。また古筆と出会い20年以上稽古を続けると共に、古筆の研究や多数の作品を発表。京都「鳩居堂」の書道教室で、島田雨城先生の助手を務めていらっしゃる方です。
「ようこそいらっしゃいました。さぁ、こちらに座ってください」との柳本先生の言葉に従い席に。
「古筆というから、もっと御歳を召した、怖そうな先生かと思った・・・よかったー」と、心の中でつぶやくミモロです。
さっそく机に着くミモロ。いよいよ授業が始まります。

「では、はじめていらした方もいますが、まずは、前回の続きの『源氏物語』のお話から始めます」と先生。
ミモロの前には、今日の授業の資料や、お手本が置かれています。

柳本先生が、半紙に書いてくださったお手本には、流れるように美しい文字が。
「いつか、こんな美しいかな文字が書けるようになるのかなぁ?今は、何を書いているか、わからないけど・・・」と、ミモロは、期待と不安がまぜこぜに。
筆を持つ前に、まずは、その日、古筆で練習する和歌の時代背景や意味などのレクチャーが行われます。

「今日は『源氏物語」の御幸の部分です。この場面というのは・・・・・」
ミモロも、神妙な面持ちで資料に目を通します。

「ここでは、玉蔓という女性・・あの夕顔の娘ですね。彼女が・・・」

「うーまずい!『源氏物語』って、光源氏というイケメンの主人公が、いろいろな恋をしてゆくお話っていうぐらいしか、知らないんだった・・・」。
それでも、柳本先生の隣りで配られた資料を見ながら、真剣に話に耳を傾けるミモロです。
『源氏物語』に登場する複雑な人のつながりを書いた図を前に、
「えーと、光源氏の恋人は・・子供は・・・たくさん登場人物がいて、わかんなくなちゃうー。なんでこんなにいろいろの女性と恋をするーもうー」と、ミモロは、お手上げ。

ミモロ、大丈夫?付いてゆけるの?
ちょっと先行き心配なミモロです。
そんなミモロを見て「今は細かい部分より、『源氏物語』の世界に興味を持つことから、はじめればいいんですよ。知らないことは、少しずつ学びましょうね。まずは、雅な世界を楽しんでくださいね」と、柳本先生。
「ハーイ・・・クスン」。ついていけないかも・・・と、不安になり、ちょっと泣きべそをかきかけたミモロです。資料を読み込むことは、後にして、先生のそばで、ともかく登場人物の生き生きとした姿が想像できるお話を、楽しむことに。

「『源氏物語』を詳しく読むのは、初めてだから、知らないことが、いっぱい・・・でも、なんか面白そう・・・。紫式部って、すごい作家さんだね。たくさんの登場人物や複雑な話の流れが、よく混乱しないね。どうやって物語の構成を考えたんだろ?宮中のお仕事もしながら、こんな大作を書き上げるなんて、大変だよね・・・。だって、電気もないんでしょ。暗いから、夜は、なかなか書けないよー。一体、いつ、どうやって書いてたんだろ?そして、どうやって、いろんな人に読んでもらったんだろ?印刷技術も発達してないのにー。紫式部は、ほかにも作品を書いたの?」。ミモロの『源氏物語』への興味は、物語そのものより、ほかの部分に・・・。
いつか、先生に伺ってみましょうね。
ともかく、軽妙な語り口で話される先生のわかりやすく、興味を刺激するお話に、すっかり惹きこまれたミモロです。
























 岩手の山に入って集めた野生のぶどうの蔓を、本当にたくさんの手間暇かけて、編める素材を作り、丁寧に編み込んだ籠です。一見、武骨な感じの籠ですが、見るほどに、手仕事ならではの温かさと味わいが伝わってきます。
岩手の山に入って集めた野生のぶどうの蔓を、本当にたくさんの手間暇かけて、編める素材を作り、丁寧に編み込んだ籠です。一見、武骨な感じの籠ですが、見るほどに、手仕事ならではの温かさと味わいが伝わってきます。
 ミモロは、毛織物の中にすっぽり包まれて、しあわせそう。
ミモロは、毛織物の中にすっぽり包まれて、しあわせそう。