「大きな桶を作るところ、ミモロちゃん見学しませんか?」と、1月のある日、ミモロは、[近畿民具学会」のメンバーの方にお声を掛けて頂きました。向かったのは、大阪堺市にある「藤井製桶所」です。


ちなみに「近畿民具学会」は、時の流れと共に失われてゆく民具を調査、収集、研究、保存などを目的に発足した学会で、近畿の博物館や民具館などの学芸員をはじめ、さまざまな分野の方々が参加なさっているもの。国宝や重要文化財などに指定される美術品や芸術品と異なり、民具は、生活の変化などにより、廃棄されたり、新しいものに取って代わられ、どんどん失われてゆきます。でも、そこには、その時代の人々の暮らしを知る上で、大切なことがいろいろ見ることができます。
民具に深い知識をもつ会員の皆様とご一緒できるのは、ミモロにとっては、何よりうれしいことなのです。
京都から京阪電車とJRを乗り継いで、約1時間半。「鳳」という駅から、みんなで歩くこと15分。この地域には、さまざまなモノづくりの工場が集まっています。
製作所の中は、床から天井まで、さまざまな工具や部品が積み重ねられています。


そして、体育館のように広い工場の中央に、大きな桶が置かれていました。「すご~い!」

「はい、みなさま、よくいらっしゃいました~」と、この日、桶づくりをご説明下さるのは、大正11年ごろ創業の「藤井製桶所」の三代目の上芝雄史さん。「よろしくお願いします」とミモロも挨拶。

酒、醤油、味噌など、古来から日本人の食に欠かせない品々を仕込むのが、桶。今や生産性および衛生管理などの面から、桶を使う仕込みは、全国の生産者から姿を消しつつあります。かつて、堺は、桶の産地で50軒以上の製作所があったそう。でも、なんと今は、大きな桶が作れるのは、ここ「藤井製桶所」だけになりました。
上芝さんは、わかりやすく、そして深く、さまざまな桶のお話をしてくださいます。そのお話にミモロは、耳をぴくぴくさせながら聞き入りっています。

「あの~桶と樽って、どこが違うんですか?」と、日本民具学会の方なら当たり前の知識でしょうが、ミモロは知らないので質問します。
「あのね。樽は、お酒や醤油などを入れて、保存、運搬するためのもので、蓋が閉じられている容器です。一方、桶は、蓋が閉じられていない容器で、生活のいろいろな場面で使われています。桶の場合、いろいろな形があるので、使う道具は、樽の何倍もあるんですよ」と。
「これは、蓋があっても桶なんだ~」。そう、お風呂も、洗面器は桶ですね。ワインやウィスキーなどを入れるのは、樽です。つまり長期保存および運搬に使われるのが樽です。

さて、話を桶づくりに戻しましょう。
桶に使われる木材は、樹齢100年以上の杉で、多くは吉野地方のものを使っているそう。

また、使用する木材のカットの仕方も独特のものがあるそう。年輪を見ると、赤い部分と白い部分があり、水分の滲み方に違いがあり、その境目を巧みに使い製材します。

そのため、大きな丸太でも、とれる部分は限られているのです。製材されたのち、桶の大きさに合わせ、微妙な角度で削られてゆきます。
「ここの部分・・・大好きなバームクーヘンみたいなところだ~」と、思わずよだれが…

さて、ミモロの後ろでは、何やら作業が行われています。小さな木材を削っています。「なんだろ?」と興味津々。


それは、竹釘。
桶の木材をつなぐもの。桶の大きさによって、何枚か組み合わされ、その後、鉋をかけ、それらを組み立て桶を形作ります。


製作所には、杉の香りが漂います。
「では、これから、桶の大切な部分である箍(たが)の製作をご覧にいれます~」と上芝さん。

ミモロたちの目は、いっそう輝きます。
ブログを見たら 金魚をクリックしてね ミモロより
 人気ブログランキング
人気ブログランキングミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら
ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro1888@gmail.comまで
京都に遊びにきてくださ~い!!















 「大きい~」
「大きい~」











 いろいろな木で作られた、これぞ木琴。「チョウチョ、チョウチョ…」と歌いながら演奏。
いろいろな木で作られた、これぞ木琴。「チョウチョ、チョウチョ…」と歌いながら演奏。
















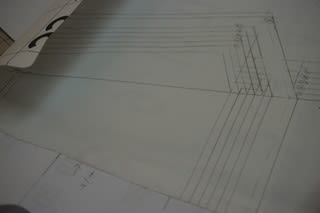





 「はい、大丈夫ですよ~」
「はい、大丈夫ですよ~」

















 「ちょっと太っちゃったかも~」
「ちょっと太っちゃったかも~」

 う~こんなにスラリと雅な雰囲気になれるかどうか・・・。でもネコにも衣装・・・どんな風になるか、今から楽しみです。
う~こんなにスラリと雅な雰囲気になれるかどうか・・・。でもネコにも衣装・・・どんな風になるか、今から楽しみです。









 角、だるま、リザーブなど、20代によく飲んだもの。懐かしさが募ります。でも、学生時代は、レッドが多かったかな~。
角、だるま、リザーブなど、20代によく飲んだもの。懐かしさが募ります。でも、学生時代は、レッドが多かったかな~。
 「ここだけしか売ってないんだって~。もっと食べたい~」とミモロ。
「ここだけしか売ってないんだって~。もっと食べたい~」とミモロ。





