ミモロが、最近、「行きた~い!」と言い出したのが、滋賀県の信楽にある「山田牧場」です。
陶器の町で知られる信楽の山里にある、明治時代から酪農に携わる山田一族が営む牧場です。

ここは、観光牧場ではなく、本物の牛乳を生産すると共に、酪農教育ファームとして一般に公開されています。


「わ~牛さん、いっぱい~」暑い夏、牛もなんとなくのんびり。「ここの牛さんたち、自由に好きなところで寛いでる~」とミモロは、以前行った酪農家で、牛がみんな同じ方向を向いて並んでいたことを思いだしました。
ここでは、搾乳の時間になると、順番に牛が搾乳の場所に移動するのだそう。
搾乳体験というプログラムもあって、毎日11時に、申し込むと体験できます。
「あ、ここ牛さんの幼稚園?」別の場所には、仔牛たちが集められ、思い思いに時間を過ごしています。


「仔牛って、なんか鹿に似てる~」つぶらな瞳がかわいい仔牛です。
「こんにちは~ようこそ、ミモロちゃん」と、笑顔で出迎えてくださったのは、牧場長の山田さん。
 「やっと来れました~」とミモロ。実は、以前にもお目にかかったことがあり、そのとき、「絶対行く~」と約束していたのでした。
「やっと来れました~」とミモロ。実は、以前にもお目にかかったことがあり、そのとき、「絶対行く~」と約束していたのでした。さて、「山田牧場」の歴史は、日本の酪農の歴史に重なります。
明治になり、文明開化は、日本の食生活にも大きな変化をもたらしました。食の西洋化が始まり、明治後期、横浜や北海道など乳牛が飼育され、人々も牛乳を飲むようになりました。
その時代、「山田牧場」の創始者である石川県出身の山田豊次郎さんは、牧童として、全国をまわり酪農技術を学び、乳牛の飼育技術で一目置かれる存在に。
そして昭和初期に、京都の百万遍で「山田牧場」を創業します。
「え~京大がある百万遍に牧場があったの?」と、その辺りは、よく自転車で通る場所。
そこで、京大農学部の牛の世話もしていたそう。そんなご縁で、京大の教授の助言で、乳酸菌飲料や飲用牛乳の商品開発を行い、京都の市内で宅配販売もしていたのだそうです。
戦後、百万遍エリアは、急激に宅地化が進み、そこから、修学院エリアへと移転することに。
しかし、そこも宅地化が進み、昭和48年に、滋賀県の信楽に移転し、今日に至ります。
「え~修学院から、何も信楽まで移転しなくても、もっと近くになかったのかな~」と、思うミモロです。
でも、乳牛には、良質の水が必要。「良質の牛乳のためには、良質の水を飲まないといけないんだ~」と。信楽は、水にも恵まれた場所なのです。
現在、「山田牧場」では、オリジナルブランド牛乳が生産されています。それは、低温殺菌による、ノンホモ牛乳で、牛から絞ったそのままの状態を味わえる牛乳なのです。

「美味しいね~。なんか味が濃い気がする~」と、牛乳好きのネコらしく、なかなか味にうるさいミモロです。
ちなみに、ノンホモ牛乳とは、乳脂肪中の脂肪球を細かく砕き、安定した状態にするホモライズ(均質化)をしていないノンホモライズ牛乳の略です。
ところで、乳牛は、仔牛を産んだお母さん牛。つまり、仔牛を産まないと、おっぱいは出ないわけで、本当は、仔牛に与える乳を人間は分けてもらってることになります。
仔牛は、成長し、2歳になる前に、人工授精で妊娠します。仔牛が生まれるとしばらく乳を与え、仔牛に抵抗力をつけさせ、その後は、仔牛は、別の場所で、育てられます。仔牛たちには、健やかな成長を促す飼料が与えられるのだそう。
「え~ママと別れて暮らすんだ~。ママのおっぱい、ずっと飲めないんだ~」と、ちょっと複雑な思いを抱くミモロです。
母牛は、しばらくすると乳の出が悪くなってきます。そこで、また人工授精で妊娠へ。
つまり、子供が産める期間は、何度も妊娠を繰り返すことになります。
「乳牛さんって、大変なんだね~。仔牛にあげるおっぱいをミモロたち、もらってるんだ~。牛さんに感謝しなくちゃ~」と、いっそう味わいながら牛乳を飲むミモロです。
ここ「山田牧場」では、牛舎の中で、牛たちは自由に動き回れる飼育法をとっています。でも、この方法は、実は、それほど多くの酪農家が行っている方法ではありません。手間もかかるし、また生産性も高くないということからかも…。
良質の牛乳は、ストレスの少ない乳牛から…。そんな思いが、ここの牛乳にはあるのです。
「ホント、牛さんたちのんびり寛いでる~」牛舎のあちこちにいる乳牛たち。

「つまりここって、ママ会みたいなところなんだ~。仲良しのママ友でおしゃべりしてるみたい~」

山田牧場長の手は、ものすごく大きくて、厚みがたっぷり。

「ずっと乳搾りしてきましたからね~」と山田さん。「大きいけど、柔らかい~」と、触らせてもらったミモロ。
「お相撲さんより大きいんですよ~」と笑います。
「この大きな手で牛さんを大切に育ててるんだ~」と思うミモロでした。
「ミモロちゃん、チーズ工房見学に行きましょ!」とお友達。
「うん、行く~」と、牛舎から駆け出しました。
ブログを見たら 金魚をクリックしてね ミモロより
 人気ブログランキング
人気ブログランキングミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro1888@gmail.comまで






















 「ここに糸を通すには、そうとう時間がかかるんだって~」丸1日はかかるとか。
「ここに糸を通すには、そうとう時間がかかるんだって~」丸1日はかかるとか。 「それは止める道具です」と。織りあがった織物を切って機から外すための留め金のような働きをします。「ムカデっていうんだって~。見たままのお名前だね~」
「それは止める道具です」と。織りあがった織物を切って機から外すための留め金のような働きをします。「ムカデっていうんだって~。見たままのお名前だね~」

 「使い込んでる~」。今やコンピューターが使われることも多くなっていますが、伝統の技法で作る錦織には、今も「もんがみ」は欠かせません。
「使い込んでる~」。今やコンピューターが使われることも多くなっていますが、伝統の技法で作る錦織には、今も「もんがみ」は欠かせません。
 「ここ回すの~」
「ここ回すの~」
 「よく見える~」
「よく見える~」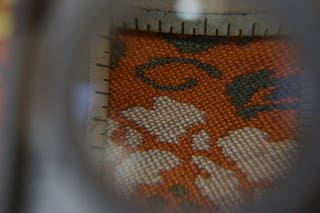





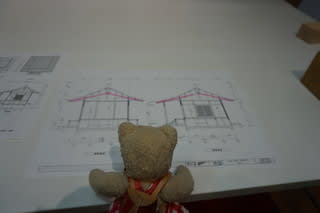






 「この奥も細工されてる~」
「この奥も細工されてる~」

 中央部分。
中央部分。 軒先部分。
軒先部分。



 江戸時代の作というしのぎ
江戸時代の作というしのぎ










 「こんなに似合うなんて~」
「こんなに似合うなんて~」


 「あのね~ミモロ、日本髪のカツラ持ってるんですけど、それに合う花簪欲しいんです~」とダイレクトな申し出。
「あのね~ミモロ、日本髪のカツラ持ってるんですけど、それに合う花簪欲しいんです~」とダイレクトな申し出。 「おや、日本髪よくお似合いですね~。ホホホ~」と思わず笑いが。「そうね。じゃミモロちゃんのために、素敵な花簪作りましょうね~」ということになりました。「え~ホント?やった!」と大喜びのミモロ。
「おや、日本髪よくお似合いですね~。ホホホ~」と思わず笑いが。「そうね。じゃミモロちゃんのために、素敵な花簪作りましょうね~」ということになりました。「え~ホント?やった!」と大喜びのミモロ。


 「なんか細かい~」
「なんか細かい~」
 あまり近くで見ると、ミモロの鼻息でも飛んでしまいそう。
あまり近くで見ると、ミモロの鼻息でも飛んでしまいそう。






 「ダメだ~細かい作業、できない~」と諦めるミモロ。とても小さな花びらなので、そう簡単にできる技ではありません。
「ダメだ~細かい作業、できない~」と諦めるミモロ。とても小さな花びらなので、そう簡単にできる技ではありません。 ミモロは、そばで真剣に見つめます。
ミモロは、そばで真剣に見つめます。 「きゃ~すごい~かわいい」
「きゃ~すごい~かわいい」
 「わ~ピッタリ~」
「わ~ピッタリ~」





