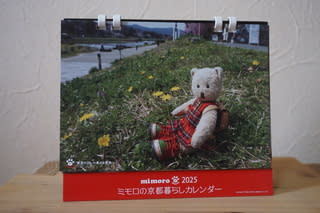今年1月から一般公開された京都の新たな名所。それが東山にある「對龍山荘」です。

ミモロは、さっそく春のある日出かけました。
「南禅寺」の「金地院」のそばにある「對龍山荘」

 「ここだ~」拝観時間は、午前と午後の2回。事前予約なしでOKです。尚、3月下旬から12月の入場料は3000円。それ以外は、2000円です。
「ここだ~」拝観時間は、午前と午後の2回。事前予約なしでOKです。尚、3月下旬から12月の入場料は3000円。それ以外は、2000円です。
「南禅寺」周辺は、明治時代に財界人の別荘地として発展したエリアで、今も多くの別荘が当時の姿を留めています。

ここ「對龍山荘」は、明治29年に薩摩出身の実業家 伊集院兼常によって造営され、その後、彦根出身の呉服商 市田弥一郎が譲り受け、庭園および建物が現在の姿に整えられたそう。
庭園を手掛けたのは、「平安神宮」の神苑など、七代目小川治兵衛。また建物は、名工の島田藤吉の手によるもの。
現在の所有者は、「株式会社ニトリホールディングス」の似鳥昭雄会長。それまで非公開だった山荘を、「多くの人に見て欲しい」という思いから、一般公開に踏み切りました。
「建物とお庭を見学するのに1時間くらいは掛かるんだって~でも、ゆっくり見たいから、時間に余裕をもって訪れたいね~」と、お腹が空かない限り、滞在する時間が気にならないミモロです。では、まずは、建物の中から、見学順路に沿って進みます。
建物内には、さりげなく美術品や工芸品が展示されています。
 橋本雅邦の「雲龍図」に迎えられて、ミモロは奥へと歩みを進めました。「あ、土蔵がある~」厚い扉の土蔵も美術館になっています。
橋本雅邦の「雲龍図」に迎えられて、ミモロは奥へと歩みを進めました。「あ、土蔵がある~」厚い扉の土蔵も美術館になっています。



「これだけ扉が厚かったら、火災でも残るね~」と。その中には、会長が収集した貴重な工芸品・美術品が納まっているのです。


「すごい美術館だ~」とミモロは展示されている作品に目を凝らします。
柿右衛門の作品、浜田庄司の器などをはじめ、


蒔絵の硯箱など、見事な工芸作品がそこに…

「もしかして、ここ建物全体が美術館なんじゃないの?」とミモロ。そう、それは確かに言えるかも…さぁ、もっと建物の中を見てゆきましょう。
 「次に何に出会えるのかなぁ?」と、ワクワクしながら歩くミモロです。
「次に何に出会えるのかなぁ?」と、ワクワクしながら歩くミモロです。
*「對龍山荘」の詳しい情報はホームページから
*現在、ブログのお引っ越しが進んでいます。しばらくは、「はてなブログ」の「ネコのミモロの京都くらし」と並行してアップして、状態を見ています。「ちょっと待っててくださいね~ママがまだ作業に馴れなくて…」とミモロに心配されています。トホホ~
<ブログを見たら 金魚鉢をクリックしてね 応援よろしく!ミモロより 人気ブログランキング
人気ブログランキング
ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro1888@gmail.comまで






























 1つ600円です。
1つ600円です。