レンズーリ氏といえば、
「『ギフテッドネス』についての解釈を広げた」とされる教育学者です。
レンズーリ氏の研究が画期的なのは、
「ギフテッドネスとは開発していくもの」という視点を示したこと。
レンズーリ氏は、
「どういう人がギフテッドか?」といったことよりも、
「何がギフテッドネスを作るのか?」
「どうしたらギフテッドネスを開発していくことができるのか?」
ということを研究し続けたんです。
その方法のひとつが、
「全校拡充学習or全校総合学習モデル
(SEM: The schoolwide enrichment model)」です。
「ギフテッドの3輪概念」
レンズーリ氏は、
以下の「3つの輪」を用い「ギフテッドネス」について説明します。

1.平均以上の能力(Above Average Ability)
一般的能力:情報処理力、体験の統合、抽象的思考、言語的数的論理性、空間認識、記憶、言語の流暢性など、IQや学力など伝統的な方法でとらえられる能力。
特別な能力:知識を獲得する容量、技術、もしくは、限られた範囲のアクティビティーで発揮される力。実際の生活で発揮される。例えば、化学、バレー、数学、作曲、彫刻、写真撮影など。化学や数学は、従来のテストではかることができるものの、アート、身体力、リーダシップ、計画性、人間関係スキルなどの多くの「特別な能力」は、テストなどでは簡単にはかることできない。よって「観察」が必要になる。
2.創造性(Creativity)
流暢さ、柔軟性、思考のオリジナリティー、体験へのオープンさ、刺激への敏感さ、積極的にリスクを犯す、など。
3.課題へのコミットメント( Task Commitment)
やりぬく力、忍耐、ハードワーク、自信、特定の物事への魅了など、モーティベーションが行為として表れること。
これら「3つの輪」が合わさることで、
「ギフテッド的行為」が花開くというわけです。
そしてこれら「3つの輪」を育むことが「ギフテッドネスの開発」、
つまり、「全校拡充学習or全校総合学習モデル
(SEM: The schoolwide enrichment model)」が目指すものなんですね。
レンズリー氏の「ギフテッドネス」について研究抜粋
・「消費するだけ」より「生み出すことのできる創造的」な人材を育むことこそ「ギフテッド教育」。
・IQや統一テストのスコアの高さと、社会に出てからの貢献は関連しない。
・特に「創造性」は、IQや統一テストスコアとは何の関連もないどころか反比例することもある。
・「知性」とは何かを見直すことが大切。
心理学者のハワード・ガードナー(Howard Gardner)氏の提唱した
「多重知能理論(Multiple Intelligence)」などを用い
「知性(intelligence)」についてより幅広くとらえる大切さを説く。
*多重知能:
・「学校内ギフテッドネス」と「創造的生産的なギフテッドネス」が存在する。
IQや学力のみでギフテッドネスをはかるならば、
前者だけが「ギフテッド」と認められてしまう。
「創造的生産的なギフテッドネス」こそ、
世界に影響を与え物事を変化させる力となり、
「ギフテッド教育」とは、「創造的生産的なギフテッドネス」開発を目指すものなのだから、
従来の「IQ上位○パーセントがギフテッド」などの認識や判定基準を改めることが重要。
レンズリー氏のSEM、
これから創造性がますます必要になるだろう世界に向け、
学び場で実践されてほしいですね。
みなさん、新しい週、よい日々を!
参考資料:
・’The Three-Ring Conception of Giftedness: A Developmental Model For Promoting Creative Productivity’ by
Joseph S. Renzulli The University of Connecticut
・’Renzulli's Three-Ring Conception of Giftedness’ by Matthias Giger
http://www.gigers.com/matthias/gifted/three_rings.html
・現在も、米国コネチカット大学の
「創造性、ギフテッド教育、タレント開発のためのレンズーリセンター
(Renzulli Center for Creativity, Gifted Education, and Talent Development)」では、
レンズリー氏の提唱する論の実践&研究がすすめられています。










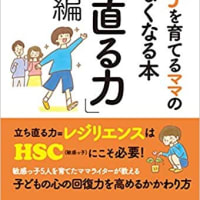





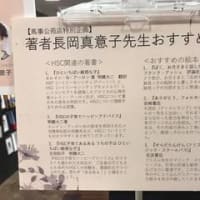

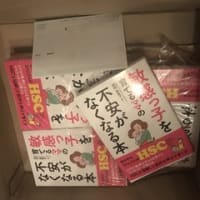

レンズーリの考えをざっくりまとめてくださって、とても参考になります。
>・「消費するだけ」より「生み出すことのできる創造的」な人材を育むことこそ「ギフテッド教育」。
これはまさに!と共感しました。日本でもいま求められていることなんではないかと。
そして「3つの輪」の理論おもしろいです。ギフテッドというとやはり1の平均以上の能力(Above Average Ability)を思い浮かべますし、生まれつき固定のものって印象を持ちますが、それって2.創造性(Creativity)と、これがしたい!という本人の自発的な動機によって3.課題へのコミットメント( Task Commitment)ができれば後からついてくる、というふうにも読めますね。
そして、多重知能というのは、従来の知能の定義から一歩進めて8つの知能を提唱しているとのことですが、これも興味深いです。
いまなんとなく考えていたのが、学校や幼稚園で評価される才能ってとても限られているけど、人にはもっといろいろな才能があるよな、ということなのです。中には計りにくいものとか評価が難しいものとかあるでしょうけど、とにかく存在はしてると思うのです。球体をイメージしてその360度あらゆる方向に才能の方向があると考えたら、いま評価されているものって数パーセントじゃあ?とか。でもレンズーリの拡充学習モデルを、各家庭で実践することで、あらゆる方向の才能を認めて伸ばしていくことができるんでは?とか。そしたらみんながギフテッドなんでは?とか。そんなこと考えるとおもしろいですよね。
またいろいろ教えてください!
これは本当に、これからますます世界中で求められていく力なのでしょうね。
にも関わらず、以前にもあげた創造性についての記事や、今回の記事にあげたレンズーリ氏の論文の記述にもあるように、今の一般的な学校教育というのは、創造性を育む場からはかけ離れているといえるのでしょうね。
学校が「優秀」として子ども達に与える評価と、創造性の高さとが「反比例」しているというデータさえあるわけですから。
確かに、逐一テストスコアではかられ、「失敗するなするな」と言われ続けたら、創造性など隠れてしまいますよね。
このレンズーリ氏のギフテッドについての研究は、発表当時、学会でも全く関心を得ることがなかったといいます(70年代、3つの学会誌から掲載拒否)。まさしく「上位○パーセント」という考えに占められていましたから。
それでも今では、最も注目を集める「ギフテッド研究」のひとつです。
私自身も、「ギフテッドネス」というのは、動態的でダイナミックなものだと思うんです。そして「IQや学力の上位○パーセント」なんていう「ものさし」では、とてもとても掬い取ることなどできないものだと。
この「平均以上の能力」というのは、ガードナーの「8つの知能」など、既存のテストなどではとらえにくく、丁寧に観察することで見えてくるものも含まれているといいます。対人関係スキルでも、内省する力でも、何か「きらっと光るもの」を見出していく。
同時に、「創造性」や、「モーティベーションを行為にする力」を培うことで、ギフテッドネスが開花するということなんですよね。
>>球体をイメージしてその360度あらゆる方向に才能の方向があると考えたら、いま評価されているものって数パーセントじゃあ?
私もまさしく同じように感じています。今の人が用いている「ものさし」など、人の持てる力にとうてい追いついていないと。
それらの「まだまだ評価されない力」を、どんどん見出し伸ばしていけるといいですよね。レンズーリ氏の拡充学習モデルは、「ひとつのメソッド」となりますね。そして、それぞれの家庭にそのエッセンスが生かされていったらいいですよね!
考えていると、楽しくなります!
こちらこそ、tamakiさんの思いや活動にブログを通して触れられること、楽しみにしていますね!
追記:こちらも記事の紹介は、全く問題ありません!