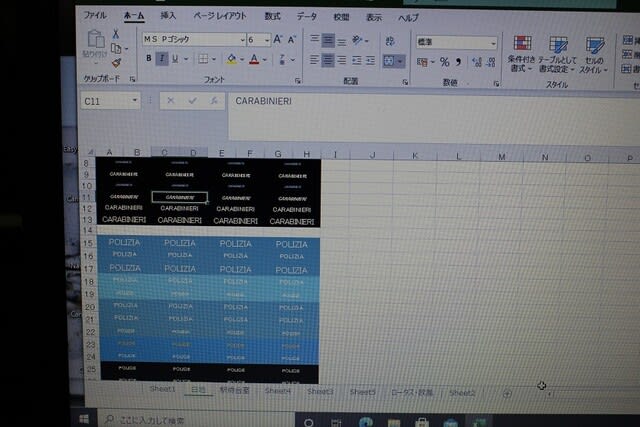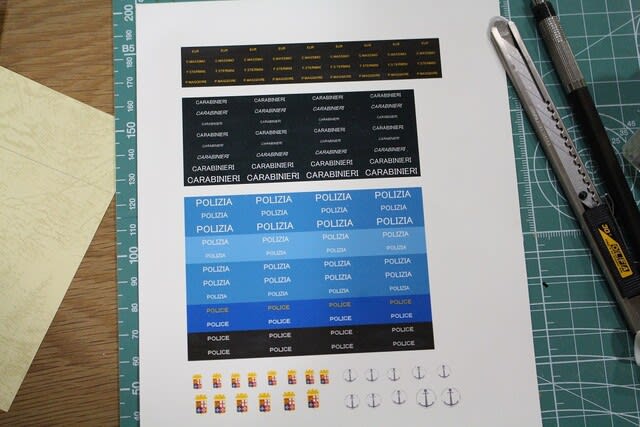この2回でイタリア警察のパトカーやヘリコプターをご紹介しましたが、カラビニエリ(憲兵)は、その特徴的な制服やパトカーの見た目などもあって、模型や玩具の世界でも人気です。
HO(1/87)の人形で有名なプライザーからも、カラビニエリの隊員セットと騎馬隊員のセットが出ています。
隊員のセットは人形5体とバイク2台が入っていて、人形のうち2体はバイクのライダー姿です。


特徴的な制服も再現されています。こんな情景も手軽にできます。

(ずいぶん状態のいいチンクエチェントだねえ)
騎馬隊員の方は馬と共に2体入りです。こんな光景、ローマやフィレンツェを旅行された方なら見たことがあるのでは。

騎馬隊員は大都市で見かけることが多いので、イタリア型でレイアウトを作るにしても、路面電車が走る街中のシーンなど、用途が限られそうです。
ちなみに国家警察のパトカーなどは、1/87でいくつか製品を見かけています。

左からフィアット・ティーポ、アウディA6(いずれもリーツェ製)、フィアットデュカート(ブッシュ製)ですが、それぞれ微妙に色調が違います。ティーポやアウディはドイツ語・イタリア語の双方が記載されており、こちらも場所が限定されそうです。
プライザーではお隣のフランスの国家憲兵も製品化しています。フランスにも憲兵がいて、同じように警察業務を担っています。ケピ帽と呼ばれる特徴的な制帽姿の隊員が入っているようです。やはり特徴がある方が製品化しやすいし、人気もあるのでしょう。
プライザーだけでなく、玩具の世界でもカラビニエリは人気のようです。前々回の記事に登場した1/24のミニカーはブラーゴ製で、カラビニエリだけでなく、国家警察、財務警察のパトカーも製品化されていました。玩具に近い出来ですし、おもちゃ屋さんで見かけることが多いわけですが、アルファロメオのパトカー、カラビニエリの塗装が一番決まっています。また、ドイツのミニカーブランドSiku(日本でも量販店などで売っていますね)でも、イタリア市場限定だと思いますが、カラビニエリの塗装に塗られたアウディのパトカーがラインナップにありました。フィレンツェの玩具店と模型店を兼ねた大きなお店で甥っ子のお土産として購入しました。
ドイツのメーカーということではプレイモービルもイタリア市場向けと思いますが、カラビニエリ仕様の製品を発売しています。

こちらのバイクの隊員ですが、ヘルメットにちゃんとカラビニエリの紋章が入っているあたりはプレイモービルらしい芸の細かさです。
さて、前々回のテーマでしたNゲージサイズのイタリア警察関連のパトカーですが、いろいろ写真に撮ったりして遊んでみました。

トミーテックのレンガ造りの教会をバックにしています。教会も屋根やレンガの色を塗り替えたり、汚しをかけたりすることでより欧州風に見えます。
「大尉殿、こちらがラファエロの絵が盗まれた教会です」
「えっ。ここの教会ラファエロなんて持ってたの?どこかの国みたいに国立博物館に寄託してればこんなことにならないのに・・・。ところで財務警察も来ているみたいだけど、何やっているのかなあ」

国家警察のパトカーがいますね。お巡りさんは夏服です。右の車輛は昔出ていたワーキングビークルというシリーズのテレビ中継車を塗り替えて、イタリア公共放送仕様の中継車にしたものです。教会の入り口には立派な黒塗りのセダンがいます。
「司教様、随分立派な車に乗っているね」
「今度の教皇様は贅沢を慎めと言っているようだけど」

(写真はその教皇様です。プライザー得意の有名人単体ものです)
いろいろ遊んでみましたが、そろそろ工作に戻りましょう。大きな声では言えませんが北北西に進路を取ったりしたものですから(分かる人だけ分かってくださいね)、だいぶ財布の方は厳しくなってしまっております。お金がなくても模型は楽しめるし、なにせキットもたくさんありますので、仕掛中のものから仕上げてまいりましょう。
この記事の締めくくりはは今月発売のRMモデルズの付録を使って、現場に急行の様子でございます。

HO(1/87)の人形で有名なプライザーからも、カラビニエリの隊員セットと騎馬隊員のセットが出ています。
隊員のセットは人形5体とバイク2台が入っていて、人形のうち2体はバイクのライダー姿です。


特徴的な制服も再現されています。こんな情景も手軽にできます。

(ずいぶん状態のいいチンクエチェントだねえ)
騎馬隊員の方は馬と共に2体入りです。こんな光景、ローマやフィレンツェを旅行された方なら見たことがあるのでは。

騎馬隊員は大都市で見かけることが多いので、イタリア型でレイアウトを作るにしても、路面電車が走る街中のシーンなど、用途が限られそうです。
ちなみに国家警察のパトカーなどは、1/87でいくつか製品を見かけています。

左からフィアット・ティーポ、アウディA6(いずれもリーツェ製)、フィアットデュカート(ブッシュ製)ですが、それぞれ微妙に色調が違います。ティーポやアウディはドイツ語・イタリア語の双方が記載されており、こちらも場所が限定されそうです。
プライザーではお隣のフランスの国家憲兵も製品化しています。フランスにも憲兵がいて、同じように警察業務を担っています。ケピ帽と呼ばれる特徴的な制帽姿の隊員が入っているようです。やはり特徴がある方が製品化しやすいし、人気もあるのでしょう。
プライザーだけでなく、玩具の世界でもカラビニエリは人気のようです。前々回の記事に登場した1/24のミニカーはブラーゴ製で、カラビニエリだけでなく、国家警察、財務警察のパトカーも製品化されていました。玩具に近い出来ですし、おもちゃ屋さんで見かけることが多いわけですが、アルファロメオのパトカー、カラビニエリの塗装が一番決まっています。また、ドイツのミニカーブランドSiku(日本でも量販店などで売っていますね)でも、イタリア市場限定だと思いますが、カラビニエリの塗装に塗られたアウディのパトカーがラインナップにありました。フィレンツェの玩具店と模型店を兼ねた大きなお店で甥っ子のお土産として購入しました。
ドイツのメーカーということではプレイモービルもイタリア市場向けと思いますが、カラビニエリ仕様の製品を発売しています。

こちらのバイクの隊員ですが、ヘルメットにちゃんとカラビニエリの紋章が入っているあたりはプレイモービルらしい芸の細かさです。
さて、前々回のテーマでしたNゲージサイズのイタリア警察関連のパトカーですが、いろいろ写真に撮ったりして遊んでみました。

トミーテックのレンガ造りの教会をバックにしています。教会も屋根やレンガの色を塗り替えたり、汚しをかけたりすることでより欧州風に見えます。
「大尉殿、こちらがラファエロの絵が盗まれた教会です」
「えっ。ここの教会ラファエロなんて持ってたの?どこかの国みたいに国立博物館に寄託してればこんなことにならないのに・・・。ところで財務警察も来ているみたいだけど、何やっているのかなあ」

国家警察のパトカーがいますね。お巡りさんは夏服です。右の車輛は昔出ていたワーキングビークルというシリーズのテレビ中継車を塗り替えて、イタリア公共放送仕様の中継車にしたものです。教会の入り口には立派な黒塗りのセダンがいます。
「司教様、随分立派な車に乗っているね」
「今度の教皇様は贅沢を慎めと言っているようだけど」

(写真はその教皇様です。プライザー得意の有名人単体ものです)
いろいろ遊んでみましたが、そろそろ工作に戻りましょう。大きな声では言えませんが北北西に進路を取ったりしたものですから(分かる人だけ分かってくださいね)、だいぶ財布の方は厳しくなってしまっております。お金がなくても模型は楽しめるし、なにせキットもたくさんありますので、仕掛中のものから仕上げてまいりましょう。
この記事の締めくくりはは今月発売のRMモデルズの付録を使って、現場に急行の様子でございます。