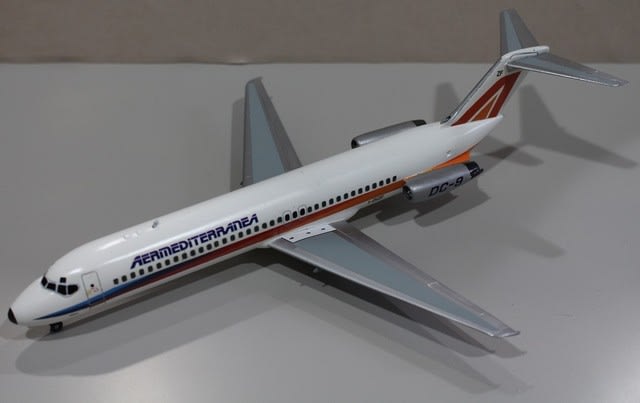そんなタイトルのイタリア映画が以前ありました。心臓発作で同じ時に病院に搬送された二人の男の心の交流を描いた物語でしたが、今日から何回かに分けてお届けする記事は飛行機のハート(心臓)=エンジンにまつわる話です。
日独伊の三機の戦闘機が並んでいます。

このブログの読者ならばこれらの機体の名称と、それぞれに共通する特徴をご存知の方も多いでしょう。メッサーシュミットBf109E-3、三式戦闘機「飛燕」一型丁、マッキMC202戦闘機で、これらはみな、ダイムラー・ベンツDB601エンジンとそのライセンス生産されたエンジンを積んだ、いわば同じハートを持った機体です。日独伊の枢軸国三国が、それぞれ共通するエンジンを運用していたわけですが、それぞれに物語があったわけです。久々にテーマを決めて何か作ってみようと思い、年明けの2月くらいから春にかけて作っていたのがこれらの機体です。あちこち寄り道しておりましたので、ご紹介するのが夏になってからとなりました。なお、キットはBf109E-3と飛燕がタミヤ、マッキMC202はハセガワで、いずれも1/72です。
実は今までほとんどご縁が無かったのがドイツ機でした。私自身日の丸のついた機体を作ることがほとんどで、たまに米軍機、イギリス機、イタリア機あたりを組むのですが、日本でもファンの多い第二次大戦のドイツ機を組んだことがほとんどなく、Bf109は今回が初めてでございます。プラモデルと40年つきあってメッサーを初めて作るなんて!と驚かれている方もいらっしゃると思いますが、私も新鮮な気持ちで組むことができました。


Bf109については資料も数多くありますし、実機の解説は他にお任せしますが、このE-3については第二次大戦初期に主力だった機体で、バトル・オブ・ブリテンにも投入されています。航続距離の短さが仇となって航空優勢を取れず・・・という話は有名です。
今回、複数のメーカーのキットを組んで感じましたが、最近(少なくとも1990年代以降)のキットですのでどれも組みやすく、大きな破綻もないのですが、タミヤの大戦機については組みやすいだけでなく、説明書も分かりやすく、かなり親切にできています。順序よく進めていくことでゴール(完成)まで導いてくれるような感じがしました。飛行機を組むことはめったに無いけど、有名な機体だから作ってみるかという方や、出戻りモデラーで飛行機のプラモデルは久しぶり、という方でも迷わず作れるのではないかという気がしました。もちろん、組みやすいキットですからディティールアップをしたい、とかジオラマを作りたい、という方にとっても好適かと思います。
塗装とマーキングですが、塗り分けが直線的で簡単なアドルフ・ガーランドの乗機としました。タミヤカラーの塗装指示をMr.カラーのそれに置き換えてエアブラシで塗装しました。後はファレホのグレー系の塗料で軽く墨入れをした程度です。
出来上がった機体を見ると「Bf109って意外に小さいな」という印象を持ちました。零式艦上戦闘機をはじめ「日本機は狭くて小さい」という刷り込みのようなものが昔からあり、日本機は小さく、欧米の機体は大きいという先入観を持っていました。このため、Bf109については「あれっ、日本機よりもっとコンパクトな飛行機だ」と思ったわけです。ただ、スマートなラインと角ばった風防はまさにドイツ機であり、それを立体で確認できるのがまた、模型の素晴らしいところです。
今回はBf109E-3にとどまらず、余勢を駆って(?)Bf109F-4も作ってみました。こちらはファインモールド1/72のキットです。

そのまま組んでデカールを貼れば「アフリカの星」マルセイユ大尉の機体になるのですが、あまのじゃくな私はマルタ島攻防戦の機体にしたくて、XTRADECAL X72-162マルタ島攻防戦・枢軸側の機体の別売りデカールを使いました。1942年3月、シチリア島に展開した機体だそうです。このキット、ファインモールドさんらしく説明書も丁寧で、アフリカ戦線と絡めて実機解説もされていますし、どこまで組み立てを進めたら機体全体の塗装をするか、といったガイドもされています。また、このキットのいいところはエンジンカバーを外すことができることで、改良されたDB601エンジンや機銃も再現されています。

オーバーにならない程度にウェザリングを施しています。

大きな苦労をすることなく、もう一つのBf109ができました。

本ブログでも以前ご紹介したモデルアートの元ライター・故黒須吉人さんは、ほとんどドイツ機と縁がなかったそうで(確かに米軍機、日本機、共産圏の機体、ヘリコプターといった作例が多かったように記憶しています)、生前所属されていた同人がその年はドイツ機をテーマにして作品展に出展したことで「こんな機会でもなければ自分からドイツ機を作ることは無いと思う」といった趣旨のコメントを作品に寄せていました。偉大なモデラーと比べることなど失礼もいいところですし、このブログは非常に個人的なものではありますが、私もブログという場が無かったらこういった機体を優先的に作ることは無かったかもしれません。
同じ系統のエンジンを積んだ飛行機の話、まだ続きます。
日独伊の三機の戦闘機が並んでいます。

このブログの読者ならばこれらの機体の名称と、それぞれに共通する特徴をご存知の方も多いでしょう。メッサーシュミットBf109E-3、三式戦闘機「飛燕」一型丁、マッキMC202戦闘機で、これらはみな、ダイムラー・ベンツDB601エンジンとそのライセンス生産されたエンジンを積んだ、いわば同じハートを持った機体です。日独伊の枢軸国三国が、それぞれ共通するエンジンを運用していたわけですが、それぞれに物語があったわけです。久々にテーマを決めて何か作ってみようと思い、年明けの2月くらいから春にかけて作っていたのがこれらの機体です。あちこち寄り道しておりましたので、ご紹介するのが夏になってからとなりました。なお、キットはBf109E-3と飛燕がタミヤ、マッキMC202はハセガワで、いずれも1/72です。
実は今までほとんどご縁が無かったのがドイツ機でした。私自身日の丸のついた機体を作ることがほとんどで、たまに米軍機、イギリス機、イタリア機あたりを組むのですが、日本でもファンの多い第二次大戦のドイツ機を組んだことがほとんどなく、Bf109は今回が初めてでございます。プラモデルと40年つきあってメッサーを初めて作るなんて!と驚かれている方もいらっしゃると思いますが、私も新鮮な気持ちで組むことができました。


Bf109については資料も数多くありますし、実機の解説は他にお任せしますが、このE-3については第二次大戦初期に主力だった機体で、バトル・オブ・ブリテンにも投入されています。航続距離の短さが仇となって航空優勢を取れず・・・という話は有名です。
今回、複数のメーカーのキットを組んで感じましたが、最近(少なくとも1990年代以降)のキットですのでどれも組みやすく、大きな破綻もないのですが、タミヤの大戦機については組みやすいだけでなく、説明書も分かりやすく、かなり親切にできています。順序よく進めていくことでゴール(完成)まで導いてくれるような感じがしました。飛行機を組むことはめったに無いけど、有名な機体だから作ってみるかという方や、出戻りモデラーで飛行機のプラモデルは久しぶり、という方でも迷わず作れるのではないかという気がしました。もちろん、組みやすいキットですからディティールアップをしたい、とかジオラマを作りたい、という方にとっても好適かと思います。
塗装とマーキングですが、塗り分けが直線的で簡単なアドルフ・ガーランドの乗機としました。タミヤカラーの塗装指示をMr.カラーのそれに置き換えてエアブラシで塗装しました。後はファレホのグレー系の塗料で軽く墨入れをした程度です。
出来上がった機体を見ると「Bf109って意外に小さいな」という印象を持ちました。零式艦上戦闘機をはじめ「日本機は狭くて小さい」という刷り込みのようなものが昔からあり、日本機は小さく、欧米の機体は大きいという先入観を持っていました。このため、Bf109については「あれっ、日本機よりもっとコンパクトな飛行機だ」と思ったわけです。ただ、スマートなラインと角ばった風防はまさにドイツ機であり、それを立体で確認できるのがまた、模型の素晴らしいところです。
今回はBf109E-3にとどまらず、余勢を駆って(?)Bf109F-4も作ってみました。こちらはファインモールド1/72のキットです。

そのまま組んでデカールを貼れば「アフリカの星」マルセイユ大尉の機体になるのですが、あまのじゃくな私はマルタ島攻防戦の機体にしたくて、XTRADECAL X72-162マルタ島攻防戦・枢軸側の機体の別売りデカールを使いました。1942年3月、シチリア島に展開した機体だそうです。このキット、ファインモールドさんらしく説明書も丁寧で、アフリカ戦線と絡めて実機解説もされていますし、どこまで組み立てを進めたら機体全体の塗装をするか、といったガイドもされています。また、このキットのいいところはエンジンカバーを外すことができることで、改良されたDB601エンジンや機銃も再現されています。

オーバーにならない程度にウェザリングを施しています。

大きな苦労をすることなく、もう一つのBf109ができました。

本ブログでも以前ご紹介したモデルアートの元ライター・故黒須吉人さんは、ほとんどドイツ機と縁がなかったそうで(確かに米軍機、日本機、共産圏の機体、ヘリコプターといった作例が多かったように記憶しています)、生前所属されていた同人がその年はドイツ機をテーマにして作品展に出展したことで「こんな機会でもなければ自分からドイツ機を作ることは無いと思う」といった趣旨のコメントを作品に寄せていました。偉大なモデラーと比べることなど失礼もいいところですし、このブログは非常に個人的なものではありますが、私もブログという場が無かったらこういった機体を優先的に作ることは無かったかもしれません。
同じ系統のエンジンを積んだ飛行機の話、まだ続きます。