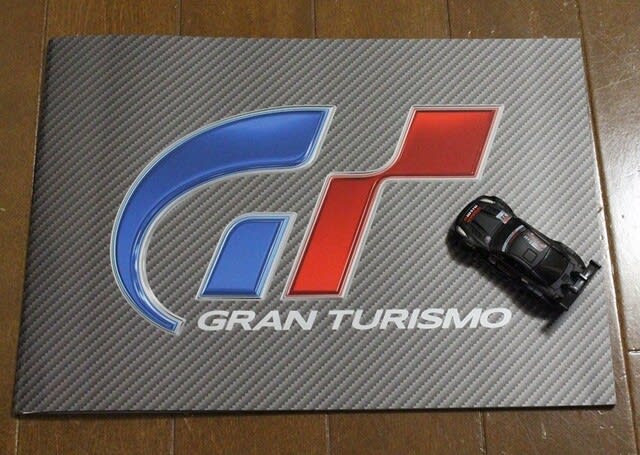今日は久しぶりに映画の話です。アメリカのシンガーソングライターであり、ノーベル文学賞受賞者であるボブ・ディランの若き日を描いた「名もなき者」を観てきました。

舞台は1961年から1965年頃のアメリカということで、公民権運動、キューバ危機、ケネディ暗殺、ベトナムへの介入という時代です。ニューヨークにやってきた青年・ロバート・アレン・ジママンが歌手ボブ・ディランとして見いだされ、成功を手にし、そして・・・という物語です。この時代にアメリカの音楽界ではフォークミュージックの「復興」運動もあり、その中でディランもフォーク歌手というくくりで捉えられ、多くの聴衆の支持を得て、大きな成功を手にします。しかし、ジャンルにはめられるのを嫌う彼は、彼をメジャーに引き上げてくれたピート・シーガーが主催するフォーク・フェスのトリである行動に出る、というのがストーリーです。
この映画、なんと言っても主演のティモシー・シャラメがディランそのもの、というくらい風貌などが似せて作っていました。音楽が好きで内気な青年が時間を経ても本質は変わらないところまで、彼自身のディラン像を作り上げていました。しかもあの特徴ある声や歌唱、演奏も吹き替えではなくシャラメ本人によるものだそうで、これも驚きでした。聞くところでは数年かけて体得していったということで、ものまねレベルではない感じがしました。
ディランをめぐる人々もまた個性的でして、恋人のシルヴィ(本作のオリジナルキャラクターですが、モデルはスージー・ロトロといって、ディランのアルバム「フリーホイーリン」にディランと共にジャケットに映っている女性です)、ディランが登場した時点で既にメジャーとなっており、後に共同制作者でもあり、ディランと関係も持っていたジョーン・バエズ(態度がでかいところも含めて(失礼)モニカ・バルバロが好演)、その才能を評価し、ジャンルにとらわれない、という意味でもディランが自分の良き理解者として接し、心を通わせていたジョニー・キャッシュ、この時代には既に療養中の身ではありながら、見舞いに訪れたディランの才能を見抜いたウディ・ガスリー、フォーク歌手ピート・シーガーの日系人の妻トシ(初音映莉子が好演)は一歩離れたところからディランを見つめながら、時には理解者でもあり、ということで音楽と人間のドラマが展開します。本作のジェームズ・マンゴールド監督は事前にディラン本人と話す機会を持ったということですし、モニカ・バルバロはバエズ本人と電話で話す機会を持つなど、存命中の人物を採り上げる映画ということもあり「本人公認」となっているようです。主演のティモシー・シャラメに対してもディラン自身が好意的な評価をSNSでしたことも話題になりましたし、シルヴィ役のエル・ファニングはもともとディランの大ファンというのも興味深いところです。
そんな中でディランは流されず、時には自分の思いを強く通し、ということで「おいおい、そんなことしたら友達も恋人もなくしちゃうぞ」なわけですが、本人は「自分は作りたい曲を作り、歌いたい詩をそれに乗せて歌うだけ」で「歌手として生きることは社会運動でもなければ勝ち負けでもない」と思っていた節があるのではないでしょうか。自分の思いを通す、生き方を通す、というのはとても難しいし、覚悟もいるわけですが、それを20代の若者が体現していたということでしょう。
実在するミュージシャンの映画というと最近ではボヘミアンラプソディーが有名で、あちらは主人公の人生がジェットコースターのように展開しますが、本作はそこまでの派手さはなくとも、音楽が好きなら若い方であっても気に入ると思います。余談ですが「ボヘミアン~」のハイライトでもある1985年のライブエイドではアメリカ側のステージにディランもバエズも出演しています。当時のMTVで人気を博した演者に歓声が送られる中、二人とも「過去の人」になっていたというのが、まさに「時代は変わる」を体現してしまったように思います。
本作は私が生まれるよりさらに前の時代を描いているせいもあってか、タバコのシーンも多くて、今どき珍しいくらいだな、というのもまた、この数十年の変化でしょう。映画を観たのは寒い日でしたので、上映後はディランのように背中を丸め、ポケットに手を入れてニューヨークのグリニッジビレッジならぬ歌舞伎町を歩く「ボク・ディラン(Ⓒみうらじゅん)」でした。
映画の話をもうひとつ。昨年のイタリア映画祭で上映された「まだ明日がある(C'e ancora domani)」ですが「ドマーニ!愛のことづて」として公開されています。イタリア映画とて上映館も少ないようですが、じわじわ人気になってほしいな、と思っています。コメディエンヌでもあるパオラ・コルテレージ監督・主演作品ということもあり、ヨーロッパ映画、そして女性の権利というテーマの小難しさはコメディで包んでいますので、ヨーロッパの映画なんて、と食わず嫌いしないで観てほしいです。