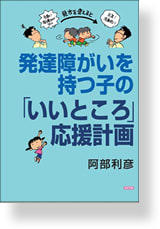前々回のBLOGで書いた教育再生会議の第二次報告のこと
議事録のリンクがうまくできてなくてすみませんでした。
ここに一部を掲載させていただきます。
ここの内容は 星槎教育研究所が今回実施しているセミナーの趣旨に
つながるものです。
それで品川さんにも 十一元三先生 水野薫先生に引き続き
講演をお願いいたしております。
http://seisa.ed.jp/npo/seminar01.html#2
★
【議事録P29より】
というのは、「特別支援教育」イコール「障害児教育」では
もうないということでございます。
「特別支援教育は、通常学級の中にいる子どもの個々のニーズに応じて
支援をする」ことであり、こういうふうに「障害のある子供」と
書いてしまった瞬間から矛盾が生じます。
と申しますのは、LD やADHD やアスペルガーの子供たちは、
診断を受けていない子供もたくさんおります。
学校現場で先生が「何かあの子、困った子だね」とか
「大変な子だね」というような形で、
時に子どもが怠けているからとかしつけが悪いからというような、
教師側の認識不足で見過してきた子供たちを、
その子のデコボコをしっかり見て指導していこうということです。
「困った子」に対して安易に診断を求めるような教師が増えているのですが、
ここに「障害のある子供」と書いた瞬間から、
そういう教師の本末転倒の言動に対して拍車をかけてしまいます。
診断のない子、たとえば家庭に介護などストレスがあったり
愛着障害等を起こしている子でも『困った子』という見方をされるのですが、
みんながみんな発達的な課題があるわけではありません。
また、本当に診断が必要なのかという問題もあります。
診断できる専門家が少ないという現状もあります。
環境が整えば『困った子』ではなくなる子もたくさんいます。
教師から見て「困った子」なのではなくて、「本人が困っている」んです。
そこを指導するのが特別支援教育のはずです。
となりますと、診断がない子はまたしてもニッチに落ち込んでしまって適切な指導が受けられなくなりますので、この表現はぜひ変えてください。
そうしませんと、適切な指導を必要としながら
診断のない子は対象外になってしまいます。
そういう子がやがて不登校やひきこもりになったりいじめられたり、
非行に走ったりなど二次的な課題、社会不適応を起こしていっている
現状があり、それらを見過ごすことはできません。
ここはぜひ、いつも私が申し上げておりますような
「すべての子供の認知と多様性に応じた指導」というふうに書いていただければ、いろいろな子供も入ってきます。
これは、その次の大学のところもまさに同じで、
大学生については、本当に診断がないまま大学にテストだけ受かって入ってきて、
それで人間関係ができなくて、社会人、就職の段階で失敗して、
結果的に若年ホームレスになったりですとか引きこもったり
家庭内暴力に走ったりするケースが少なくないんですね。
「障害」と書いてしまうと、ICF モデルが広まっていない現状では、
またそこのところが落ち込んでしまうので注意が必要だというのが2点目です。