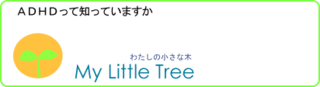mitsuです★
GAKKEN特別支援教育WEBマガジン 『自立をめざして』は
ときどき読んで参考にしていました。
2007 2008星槎教育研究所セミナーのDVDを取り寄せてくださった先生が
この
『障害児医療から/カルテに書かないこと』に連載なさっていたので
再度読み直し、またまた頷くことしきり。
有名なサイトですので
すでに読んでいらっしゃるかたもたくさんいらっしゃると思いますが
ぜひ・・・お薦めします。
★
その中から 同感するところを少し抜粋
(吉野 邦夫先生 前・国立秩父学園園長
現・西多摩療育支援センター小児科医)
私の外来では、まず「お困りノート」と言って、
大学ノートに1日1行の困ったことや迷ったこと、苦悩したことを書いてもらう。
もちろん、時には嬉しかったこともいいが、主体は困りごとである。
1日1行だと、だいたい1か月で1ページになる。
それを持参してもらって、具体的な困りごとの内容や構造、
その優先順位や準備すべきことなどを、一緒に分析や解析をし、
方針を立てるのである。
1日に3ページも4ページも書きたい人がいるが、
日記風の感情的吐露では冷静に自分を見つめる道具になりにくい。
数年間はこうしたノートをとりながら通ってもらって、
障害特性の具体性や対応方法を理解してもらうだけではなく、
自分を客観視する練習をしてもらうのもねらいである。
以前の私の診療では、6か月待ちが普通だったので、
「療育ワードピクチャー」というフォーマットにまとめて書いてもらっていたが、
今後は「お困りノート」を卒業した段階でワードピクチャーになる。
先日もこのワードピクチャーを持って数年外来に通ってくれた
アスペルガー障害児を持つお母さんが、いみじくも語ってくれた。
「これが何の役に立つだろうかと疑問でしたが、
今振り返ると、子どもが見えるようになったし、
自分がずいぶん変わったことがよく分かります。
どんな子か分からなくて苦しみ焦りましたが、今は愛しくたまりません」。
私にとって、至福のときである。
何よりもお母さんが努力しながら、子どもの成熟が待てたのである。
サ行(洗濯、炊事、掃除)のお母さんから、
考えて、記録して、工夫して、計画して、行動するカ行のお母さんへ、
というスローガンは、そのむかし、農協のパンフレットにあったものからの
借用であるが、「お困りノート」はその手始めである。
家族の成熟は、子どもの成長発達にとって最も重要で力強い武器である。
(以上 引用)
★
「お困りノート」すばらしいと思う。
星槎教育研究所でも 家庭内暴力の相談が多いが
そのかたがたには、ノートやメモを書いてもらっている。
日付・暴力のようす・きっかけとなった言葉や行動・・・
どの言葉が「地雷」になっているか?
を知りたいこともあるが、
一番のねらいは周囲の人たちが自分の言動の傾向性に
気づいてほしいから・・・
「過去と他人は変えられない 未来と自分は変えられる」ということは
誰しも解っていても
自分がどう変わればいいかがわからないことが多い。
ノートを書くと客観的に自分の言動に気づける。
気づきが一番。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ふわっとサポートできるクラスに
みんなが居心地のよいクラスに
イジメのないクラスに
U_SST ソーシャルスキルワーク
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

年間指導計画実例・1年~6年までのプログラム一覧・紙面見本・パンフレットはこちらをご覧ください






 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・