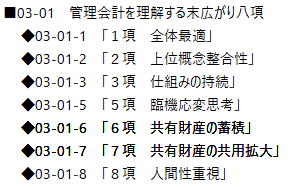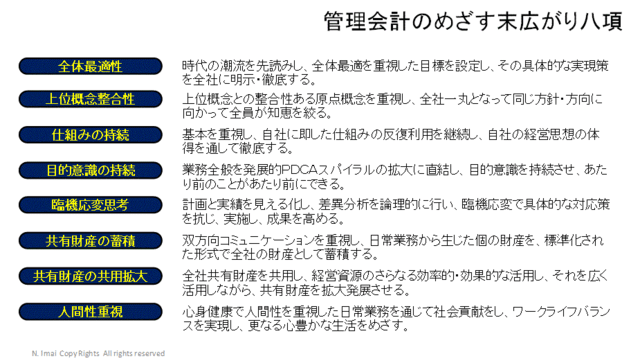■■【経営コンサルタントのお勧め図書】508 知っていたいIFRSの基礎

「経営コンサルタントがどのような本を、どのように読んでいるのかを教えてください」「経営コンサルタントのお勧めの本は?」という声をしばしばお聞きします。
日本経営士協会の経営士・コンサルタントの先生方が読んでいる書籍をご紹介します。

■ 今日のおすすめ
『IFRS国際会計基準の基礎(第4版)』(監修:平松 一夫 中央経済社)

■ IFRSを知らないでは済まない時代に入った(はじめに)
今日の紹介本は2015年3月の発行です。IFRS関連の著書では最新版に属するでしょう。しかし、この紹介本が発行されてからも、IFRSの適用に向けた流れは、その速さを増しています。その流れを追ってみましょう。
【IFRSの適用に向けた日本の流れ‐任意適用される「修正国際基準」の公表】
2015年6月30日に企業会計基準委員会(金融庁の諮問機関‐主に上場企業向けの会計基準を策定)は「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」の公表をしました。公表の内容をかみ砕いて表現すると次のようになります。『当委員会は2012年12月31日現在で公表されている国際会計基準(IFRS=国際財務報告基準:13本、IAS=国際会計基準:28本、IFRIC=IFRS解釈指針:17本、SIC=SIC解釈指針:8本計66本〈Full〉+「財務報告に関する概念フレームワーク」)のうち、「企業結合(IFRS第3号)」「金融商品:開示(IFRS第7号)」「金融商品(IFRS第9号‐2010年)」「財務諸表の表示(IAS第1号)」「従業員給付(IAS第19号)」「関連会社及び共同支配会社に対する投資(IAS第28号)」の5本については一部「削除又は修正」を加える(国際会計基準の「エンドースメント(修正適用)」と言う)。それ以外については、日本の会計基準として採用する。但し「財務報告に関する概念フレームワーク」についてはエンドースメントの対象から外す』。これに基づき、修正国際基準として、上記5本についての「削除又は修正」がなされた『企業会計基準委員会による基準:基準1号(「のれんの会計処理」)と基準2号(「その他の包括利益の会計処理」)』が公表され、同時に、金融庁は2016年3月31日以降に終了する会計年度に係る連結財務諸表等に適用すべく、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」等についての改正案を公表し、コメント終了を経て、平成27年8月以降の早い時期に「同規則」を改正するとしています。
【日本における国際会計基準の任意適用会社の増加】
2010年3月31日以降に開始する事業年度から、必要性と対応力があると認められた企業が、「指定国際会計基準(アドプション=全面適用=と言う)」に準拠する連結財務諸表を作成し提出されることが認められました。
任意適用上場企業は、2012年12月末現在では3社であったが、2015年3月末では73社に増加し時価総額の25%を占めるまで拡大した。「修正国際基準(エンドースメント)」による提出が認められると、任意適用基準が2つになり、任適用企業が300社、時価総額の50%を占めるまで拡大すると見込まれています。(2015年6月28日日経新聞朝刊)
【国際会計基準のコンバージョンス=IFRSと日本基準の統合】
IFRSに関し、意外と見過ごされている事があります。それは、企業会計基準委員会(ASBJ)と国際会計基準審議会(IASB)が、2007年8月「会計基準のコンバージェンスの加速化に向けた取り組みへの合意」(いわゆる「東京合意」)に基づき、コンバージェンス(統合)項目を決め、既に、全ての上場企業の連結財務諸表等への適用を図っている事です。
その主なものは、「連結包括利益の表示(2013年9月13日企業会計基準‐以下単に基準と表示‐第25号)」、「退職給付会計(2012年5月17日基準第26号)」「固定資産の減損会計(2009年3月27日基準運用指針第6号)」「新株予約権とストックオプション会計(2013年9月13日基準第8号)」「企業結合会計(2013年9月13日基準第21号)」「リース会計(2007年3月30日基準第13号)」「四半期財務諸表(2014年5月16日基準第12号)」「関連当事者の開示(2010年12月26日基準第11号)」「賃貸等不動産の時価開示(2011年3月25日基準第20号)」「資産除去債務会計(2010年3月31日基準第18号)」です。(日付は最新改正日。)
【IFRS適用に関する世界の流れ】
アジア各国の状況は、2007年中国がIFRSをベースとする新中国会計基準を導入したことをきっかけに、2011年に韓国とタイが、2012年にマレーシアとインドネシアが、2013年には台湾が、IFRSまたはIFRSをベースとする自国会計基準を導入しました。
シンガポールは「『会計のハブ』国家戦略」のもと、2018年よりIFRSを導入の予定です。インドは2016年よりIFRSとコンバージェンスした自国会計基準を段階的に強制適用するロードマップを公表しています。
アジア以外では、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、チリ、ブラジル、南アフリカ等が導入しています。EU諸国は当然導入しています。米国は、外国企業にはIFRS適用を認めていますが、国内企業には、IFRSに懸念事項があるとの表明をし、未だ強制適用には至っていません。
2009年、2010年、2011年のG20の首脳サミットで「国際会計基準の各国会計基準へのコンバージョン(統合)を進めること」を決議しており、IFRSを会計基準の世界標準とする流れは変わりません。
【中小企業への対応】
2009年7月に、国際会計基準審議会(IASB)は、「中小企業のための国際会計基準(IFRS for SMEs=Small and Medium-sized Entities)」を発表した。海外展開をしている中小企業の場合は、海外展開に伴う資金調達や諸取引(事業取引、企業提携、 M&A等)にIFRSを適用した財務諸表等を求められるケースが予想されます。上場企業に適用されるIFRSに比し、簡易化(概念フレームワーク+35本)されつつも、基本はIFRS(概念フレームワーク+66本〈Full〉)に添っている、「IFRS for SMEs」の存在を意識して置きたいです。
■ IFRSの適用のメリット
【海外売上高の多い企業にメリット】
最近の上場企業の連結ベースでの海外売上高比率を見るとびっくりします。連結海外売上高比率が50%を超える企業は、全上場日本会社(3500社強)の39.2%です。輸出は横這いでも、海外売上高比率は年々上がっています。M&A等により海外事業所・子会社が増えているからです。このような企業にとっては、グループの決算日を同一にし、同一の会計基準で経営をすることは、メリットと言うよりは必須の課題ではないでしょうか。会計を通じたマネジメント・アプローチの共通化、内部統制に伴う業務プロセス管理の共通化は必須ではないでしょうか。
2015年4月15日に発表された、金融庁の「IFRS適用レポート」は、IFRS適用75社のうちの40社、2015年2月末までに適用予定を取引所に公表した29社合計69社のヒアリング調査の結果を纏めています。80ページ弱のレポートですが、メリットだけではなく、準備に必要な時間や費用も分かり参考になります。本レポートは、安部内閣の「『日本再興戦略』改定2014(IFRSの任意適用拡大促進が掲げられている)」の閣議決定の一環として作成されたものです。
■ IFRSに関心を持とう(むすび)
私の私見ですが、IFRSは世界標準会計基準としては、発展途上にあります。IFRS適用・適用予定各国の会計基準設定主体とIASB(国際会計基準審議会=在ロンドン)との間で議論が重ねられ、各国が同意適用できる基準へとシナジーしていくのではないでしょうか。
また、連結、単体とIFRSの距離感の問題もあります。税法や自国会社法等各国の特殊性を配慮せざるを得ない単体と、国際的統一基準を目指す連結では、そう簡単に溝が埋まりません。EUのドイツやフランスでも単体は各国基準です。一方単体に日本基準を適用している日本では、IFRSの連結へのコンバージョンスにより、単体への影響(純資産の部の表示など)を見逃すことはできません。
更には中小企業も、IFRSと無関係ではいられません。海外展開している中小企業では、現地での資金調達や事業提携・買収などでIFRSと係りを持つケースもあるでしょう。国内事業のみの中小企業であっても取引相手がIFRSの任意適用企業であれば、IFRS基準(売上計上など)での契約を求められることもあるでしょう。
この様な点から、企業経営に関係する皆様にとっては、IFASに関心を持っておく必要が有ると思うのです。
IFRSを完全に理解するのは簡単ではありませんが、基礎的なことを頭に入れておこうと思われる方は、今日の紹介本を開いて下さい。具体的な開示例や日本基準とIFRSとの比較表等で分かりやすくIFRSについて説明がされています。

【酒井 闊プロフィール】
10年以上に亘り企業経営者(メガバンク関係会社社長、一部上場企業CFO)としての経験を積む。その後経営コンサルタントとして独立。
企業経営者として培った叡智と豊富な人脈ならびに日本経営士協会の豊かな人脈を資産として、『私だけが出来るコンサルティング』をモットーに、企業経営の革新・強化を得意分野として活躍中。
http://www.jmca.or.jp/meibo/pd/2091.htm

【 注 】
著者からの原稿をそのまま掲載しています。読者の皆様のご判断で、自己責任で行動してください。

■■ 経営コンサルタントへの道 ←クリック
経営コンサルタントを目指す人の60%が見るというサイトです。経営コンサルタント歴40年余の経験から、経営コンサルタントのプロにも役に立つ情報を提供しています。