この人の取材力と上質な小説のような、人を引き込ませる文体に、一気に読んでしまった。
気骨ある政治家と、官僚の情報操作に踊らされるバカなマスコミ。
田中角栄、小泉元総理がどれだけ自分を持っていたか。
反対をすることだけで存在していた無能な野党の悲劇。
すごい、エンターテイメントな一冊。


気骨ある政治家と、官僚の情報操作に踊らされるバカなマスコミ。
田中角栄、小泉元総理がどれだけ自分を持っていたか。
反対をすることだけで存在していた無能な野党の悲劇。
すごい、エンターテイメントな一冊。
| From ありぞな読書 |


僕が、尊敬する龍馬と同じ高知出身。
戦争に行って餓えを体験し、戦争が終わって正義が逆転するのを目のあたりにしたやなせさん。
戦争の正義は、戦争している両国にお互い必ず存在し、勝った国が正義になる。
戦争は、絶対してはいけないもの。
地球はある年齢がくると爆発し、太陽もいつか燃え尽きてしまう、人間なんて宇宙のバイキンみたいなもの。
ジタバタしてもしょうがないけど、人間はなるべく楽に生きたいと、簡単な表現で彼の哲学が語られる。
逆転しない正義は、愛と献身と言い切る。
子供の頃、親の愛情も受けず自殺まで試みる生活を送り、漫画家としても遅咲きで劣等感だらかけの青春。
そんなやなせさんは、絵本500冊、詩集50数冊、画集、エッセイ、数限りなく。
そうだ うれしいんだ
生きる よろこび
たとえ 胸の傷がいたんでも
なんのために 生まれて
なにをして 生きるのか
こたえられないなんて
そんなのは いやだ!
偉大な、アンパンマンを世に出した遅咲きの努力の天才。
いい一冊でした。
戦争に行って餓えを体験し、戦争が終わって正義が逆転するのを目のあたりにしたやなせさん。
戦争の正義は、戦争している両国にお互い必ず存在し、勝った国が正義になる。
戦争は、絶対してはいけないもの。
地球はある年齢がくると爆発し、太陽もいつか燃え尽きてしまう、人間なんて宇宙のバイキンみたいなもの。
ジタバタしてもしょうがないけど、人間はなるべく楽に生きたいと、簡単な表現で彼の哲学が語られる。
逆転しない正義は、愛と献身と言い切る。
子供の頃、親の愛情も受けず自殺まで試みる生活を送り、漫画家としても遅咲きで劣等感だらかけの青春。
そんなやなせさんは、絵本500冊、詩集50数冊、画集、エッセイ、数限りなく。
そうだ うれしいんだ
生きる よろこび
たとえ 胸の傷がいたんでも
なんのために 生まれて
なにをして 生きるのか
こたえられないなんて
そんなのは いやだ!
偉大な、アンパンマンを世に出した遅咲きの努力の天才。
いい一冊でした。
| From ありぞな読書 |
今日のネットで拾った面白写真 - 一応、ヘッディング?
少し、サボっていた本の紹介、第3作目は、読みやすいマーケティング入門書の「透明人間の買いもの」
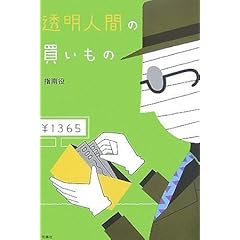
Amazon.co.jp
この本の著者は、「指南役」という草場滋、津田真一、小田朋隆の3人からなるエンターテイメント企画集団、とよくわからないが、そう言う事になっているらしい。
彼らは、透明人間を目に見えない巨大マーケットと言っている。
透明人間とは誰か?
その答えの前に、この本は透明人間でない人たちを挙げている。
それは、アフターファイブにお一人様レストランに行くOL(こんな物の存在自体を知らなかった自分)、プチ家出して渋谷に一週間寝泊りする女子高生、成田空港に韓流スターを見に行く主婦、等々だ。
何故、彼等が透明人間ではないか?
彼等はマスコミでよく取り上げられるが、自分の身近にこんな人いない。
際立った個性と(本当は流行に流されているだけなので個性でも何でもないのだが)、奇抜な行動で、マスコミ的には面白い材料だが、極めて少数派だから。
ここでは、極々一般のサイレント・マジョリティーが透明人間で、その巨大マーケットの謎を解き明かす本だ、そうだ。
ここからは、この本で書かれている透明人間たちに少し触れてみたい。
「人は、会議で口火を切りたがらない」、「会議で大事なのは、何を言うかじゃなく、誰が言うか」
確かに、日本の会議ではピッタリ当てはまりそうだ。それも5-6人の会議ではなく、20-30人の会議になるとなおさらだ。
そして誰か、それもそれなりの地位の人、が意見を言い、多数が賛同すると透明人間は、抵抗なくその意見を受け入れる。
マスコミでの評論家、文化人と呼ばれる人達の言動に影響されるのも同様だ。
アメリカではこの傾向が少ない。反対に、会議で意味もなく発言、質問をしたがる人がいる。
口を開く事が自分の存在意義だと思っている人だ。こういう人は、10回に1回ぐらいは、的を得た事をいうが、それ以外は、わりと邪魔な存在。
閑話休題
「iPodで聴くより、ラジオで聴くほうが楽しい」
同じ歌でも一人iPodで聴くより、車のラジオから流れてくる曲を聴く方が、新鮮に楽しく聴けるという事。
これは、今この曲を自分以外の人たちも同時に聴いているという一体感がこう感じさせるそうだ。
「時代に寄り添った作品は、長続きしない」
透明人間は、普遍的な魅力を持ち続ける作品やミュージシャンが好き。
今でも、リアルタイムで聞いたことのない歌をカラオケでよく聴くそうだ。
例えば、今井美樹「プライド」、ZARD「揺れる想い」、ドリカム「未来予想図II]等々。
我が家の子供たちは、長淵剛、南こうせつ、チューリップ、久保田利伸、加山雄三等々が好きだが、これは親父のせい。
またまた閑話休題
この本では、時代に寄りかかったものと普遍的な魅力の違いについて、ピンクレディー対キャンディーズ、または「積み木崩し」対「ふぞろいの林檎たち」を挙げている。
まだまだ、他にもいろいろな視点から透明人間マーケットを分析しているが、最後にもう一つだけ紹介してみる。
「透明人間は、まだビリーズブートキャンプを開封していない」
これに関しては、自分も含めてドキッとする人が多いだろう。(もちろんビリーズブートキャンプは買っていないが)
なんで、あんなの買ったんだろうとか、あんなに夢中になったんだろうと、後から考えると恥ずかしくなる事がある。
この本では、吉野家の牛丼の2006年の復活騒ぎ、バーガー・キングの2007年の復活に700人の行列の他に、Jリーグ、小泉ブーム、日韓W杯、郵政選挙、ハンカチ王子等を例に挙げている。
自分は、是非カーリングとハンドボールも入れておきたい。
それにしてもバーガー・キングに2時間並ぶ人を、アメリカ人に見せてやりたい。
大衆心理を上手く説明した、とてもわかり易いマーケティング書だ。
もちろん、マーケティングのこのなどに興味がなくても、一般書として十分楽しめる。
まだ読んでいない、この本の前編になる「キミがこの本を買ったワケ」を次に読んでみたい。

Amazon.co.jp
今日の一言
人生は、できることに集中することであり、できないことを悔やむことではない。
(スティーブン・ホーキング)
管理人: そうそう、世界に一つだけの花。
クリックお願いします。

 テクノラティプロフィール
テクノラティプロフィール
管理人のホームページを見てみる
少し、サボっていた本の紹介、第3作目は、読みやすいマーケティング入門書の「透明人間の買いもの」
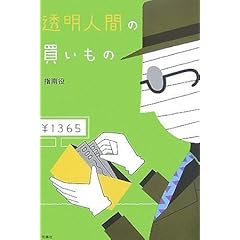
Amazon.co.jp
この本の著者は、「指南役」という草場滋、津田真一、小田朋隆の3人からなるエンターテイメント企画集団、とよくわからないが、そう言う事になっているらしい。
彼らは、透明人間を目に見えない巨大マーケットと言っている。
透明人間とは誰か?
その答えの前に、この本は透明人間でない人たちを挙げている。
それは、アフターファイブにお一人様レストランに行くOL(こんな物の存在自体を知らなかった自分)、プチ家出して渋谷に一週間寝泊りする女子高生、成田空港に韓流スターを見に行く主婦、等々だ。
何故、彼等が透明人間ではないか?
彼等はマスコミでよく取り上げられるが、自分の身近にこんな人いない。
際立った個性と(本当は流行に流されているだけなので個性でも何でもないのだが)、奇抜な行動で、マスコミ的には面白い材料だが、極めて少数派だから。
ここでは、極々一般のサイレント・マジョリティーが透明人間で、その巨大マーケットの謎を解き明かす本だ、そうだ。
ここからは、この本で書かれている透明人間たちに少し触れてみたい。
「人は、会議で口火を切りたがらない」、「会議で大事なのは、何を言うかじゃなく、誰が言うか」
確かに、日本の会議ではピッタリ当てはまりそうだ。それも5-6人の会議ではなく、20-30人の会議になるとなおさらだ。
そして誰か、それもそれなりの地位の人、が意見を言い、多数が賛同すると透明人間は、抵抗なくその意見を受け入れる。
マスコミでの評論家、文化人と呼ばれる人達の言動に影響されるのも同様だ。
アメリカではこの傾向が少ない。反対に、会議で意味もなく発言、質問をしたがる人がいる。
口を開く事が自分の存在意義だと思っている人だ。こういう人は、10回に1回ぐらいは、的を得た事をいうが、それ以外は、わりと邪魔な存在。
閑話休題
「iPodで聴くより、ラジオで聴くほうが楽しい」
同じ歌でも一人iPodで聴くより、車のラジオから流れてくる曲を聴く方が、新鮮に楽しく聴けるという事。
これは、今この曲を自分以外の人たちも同時に聴いているという一体感がこう感じさせるそうだ。
「時代に寄り添った作品は、長続きしない」
透明人間は、普遍的な魅力を持ち続ける作品やミュージシャンが好き。
今でも、リアルタイムで聞いたことのない歌をカラオケでよく聴くそうだ。
例えば、今井美樹「プライド」、ZARD「揺れる想い」、ドリカム「未来予想図II]等々。
我が家の子供たちは、長淵剛、南こうせつ、チューリップ、久保田利伸、加山雄三等々が好きだが、これは親父のせい。
またまた閑話休題
この本では、時代に寄りかかったものと普遍的な魅力の違いについて、ピンクレディー対キャンディーズ、または「積み木崩し」対「ふぞろいの林檎たち」を挙げている。
まだまだ、他にもいろいろな視点から透明人間マーケットを分析しているが、最後にもう一つだけ紹介してみる。
「透明人間は、まだビリーズブートキャンプを開封していない」
これに関しては、自分も含めてドキッとする人が多いだろう。(もちろんビリーズブートキャンプは買っていないが)
なんで、あんなの買ったんだろうとか、あんなに夢中になったんだろうと、後から考えると恥ずかしくなる事がある。
この本では、吉野家の牛丼の2006年の復活騒ぎ、バーガー・キングの2007年の復活に700人の行列の他に、Jリーグ、小泉ブーム、日韓W杯、郵政選挙、ハンカチ王子等を例に挙げている。
自分は、是非カーリングとハンドボールも入れておきたい。
それにしてもバーガー・キングに2時間並ぶ人を、アメリカ人に見せてやりたい。
大衆心理を上手く説明した、とてもわかり易いマーケティング書だ。
もちろん、マーケティングのこのなどに興味がなくても、一般書として十分楽しめる。
まだ読んでいない、この本の前編になる「キミがこの本を買ったワケ」を次に読んでみたい。

Amazon.co.jp
今日の一言
人生は、できることに集中することであり、できないことを悔やむことではない。
(スティーブン・ホーキング)
管理人: そうそう、世界に一つだけの花。
クリックお願いします。

 テクノラティプロフィール
テクノラティプロフィール管理人のホームページを見てみる
今日のネットで拾った面白写真 - シャワー
本の紹介、第2作目は、僕が大好きな役者、デンゼル・ワシントン著の「僕が大切にしている人生の知恵を君に伝えよう 」
」
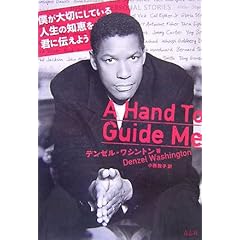
Amazon.co.jp
この本は、アメリカのあらゆる分野で成功した40人以上の人に、彼らに大きな影響を及ぼした大切な人から学んだエピソードが紹介している。
最初の章では、デンゼル・ワシントン自らが、自分の生い立ちから役者になるまでを、大切な人との出会い、彼らから学んだことを中心に描いている。
いかにも彼らしく、これまでの人生の紆余曲折と、大きな成功を、いやみもなく、謙虚な姿勢で紹介している。
その後は一気に40数名のエピソードが書かれている。
その有名人達は、元大統領クリントン、元国務長官コリン・パウエル、メジャーリーガー アレックス・ロドリゲス、元プロボクサー モハメド・アリや、映画俳優、アメリカ最大の文房具メーカーや貸しビデオ会社の社長等と多岐にわたっている。
彼みたいな成功者が、他の人からの影響や導きをとても大切にしているのが、とても共感を受ける。
この本は、彼の次のメッセージで締めくくられている。
「誰もが導きの手を1つか2つ、3つえているんだ。それは深い知恵の言葉だったり、叱咤激励だったり、立派な人の人生の模倣することだったりするよね。
たとえ過ちをおかしても、こういったものから何かを学んで出直して、人生の花を咲かせることもできる。
だからいつも心をオープンにして可能性やチャンスや感動を見逃さないこと」
この感銘を受けた本で1つだけ気に入らなかったのは、邦題。
原題は「A Hand To Guide Me」
何で彼が謙虚に人の意見に耳を傾けようというメッセージの本に、いかにも押し付けがましいタイトルをつけるのか、どうも納得いかない。
今日の一言
人間は笑うという才能によって、他のすべての生物よりすぐれている。
(トーマス・エジソン)
管理人: ユダヤ人は、あのアウシュビッツでさえもユーモアをわすれなかったという。
クリックお願いします。

 テクノラティプロフィール
テクノラティプロフィール
管理人のホームページを見てみる
本の紹介、第2作目は、僕が大好きな役者、デンゼル・ワシントン著の「僕が大切にしている人生の知恵を君に伝えよう
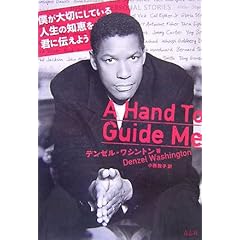
Amazon.co.jp
この本は、アメリカのあらゆる分野で成功した40人以上の人に、彼らに大きな影響を及ぼした大切な人から学んだエピソードが紹介している。
最初の章では、デンゼル・ワシントン自らが、自分の生い立ちから役者になるまでを、大切な人との出会い、彼らから学んだことを中心に描いている。
いかにも彼らしく、これまでの人生の紆余曲折と、大きな成功を、いやみもなく、謙虚な姿勢で紹介している。
その後は一気に40数名のエピソードが書かれている。
その有名人達は、元大統領クリントン、元国務長官コリン・パウエル、メジャーリーガー アレックス・ロドリゲス、元プロボクサー モハメド・アリや、映画俳優、アメリカ最大の文房具メーカーや貸しビデオ会社の社長等と多岐にわたっている。
彼みたいな成功者が、他の人からの影響や導きをとても大切にしているのが、とても共感を受ける。
この本は、彼の次のメッセージで締めくくられている。
「誰もが導きの手を1つか2つ、3つえているんだ。それは深い知恵の言葉だったり、叱咤激励だったり、立派な人の人生の模倣することだったりするよね。
たとえ過ちをおかしても、こういったものから何かを学んで出直して、人生の花を咲かせることもできる。
だからいつも心をオープンにして可能性やチャンスや感動を見逃さないこと」
この感銘を受けた本で1つだけ気に入らなかったのは、邦題。
原題は「A Hand To Guide Me」
何で彼が謙虚に人の意見に耳を傾けようというメッセージの本に、いかにも押し付けがましいタイトルをつけるのか、どうも納得いかない。
今日の一言
人間は笑うという才能によって、他のすべての生物よりすぐれている。
(トーマス・エジソン)
管理人: ユダヤ人は、あのアウシュビッツでさえもユーモアをわすれなかったという。
クリックお願いします。

 テクノラティプロフィール
テクノラティプロフィール管理人のホームページを見てみる
今日のネットで拾った面白写真 - 社会の窓
「ホームレス中学生 」はここから始まった。
」はここから始まった。
出演している、笑い精鋭たちが全く敵わない話が展開されてます。

今日の一言
読書もとよりはなはだ必要である、ただ一を読んで十を疑い百を考うる事が必要である。
(寺田 寅彦)
管理人: 流されない読書をしなければ。
クリックお願いします。

 テクノラティプロフィール
テクノラティプロフィール
管理人のホームページを見てみる
「ホームレス中学生
出演している、笑い精鋭たちが全く敵わない話が展開されてます。

今日の一言
読書もとよりはなはだ必要である、ただ一を読んで十を疑い百を考うる事が必要である。
(寺田 寅彦)
管理人: 流されない読書をしなければ。
クリックお願いします。

 テクノラティプロフィール
テクノラティプロフィール管理人のホームページを見てみる
今日のネットで拾った面白写真 - もったいない
アメリカにいるのに結構、日本の本を読むほうなので、ここで紹介していこうと突然思い立ちました。
栄えある第一冊目は、「ホームレス中学生 」麒麟 田村裕/著
」麒麟 田村裕/著

Amazon.co.jp
この本は、発売2ヶ月でミリオンセラーになったお化け本だ。
中学2年の1学期の最後の日に、突然父親から「解散!」の通告を受けた主人公が1ヶ月の公園生活も含め、周りの人に助けられながら一生懸命に生きていく自叙伝。そして、大好きだった母親へのメッセージでもある。
貧困の中でも、光り続ける彼の明るさと、周りの人の親切は、一種の奇跡だ。
少し長いけど、この本で彼が一番書きたかったと思うところを引用してみる。
「お母さんと過ごした十一年間の記憶はいつまでも消えることなく、思い出すたび色濃くなっていきます。
僕があんなにたくさん甘えなければ、もしかしたらもっとお母さんと一緒の時間を過ごすことが出来たのかもと考えてしまいます。
中略
情けないことに、今でも僕はお母さんに会いたくて仕方がありません。死にたいということではないけれど、お母さんに直接に会っていっぱい喋りたいです。
もしお母さんに会えたときに喋ることがいっぱいあるように、僕はいろんなことをたくさん経験しておきます。いつまでも話が尽きないように。
だからそのときは昔のように優しく聞いてください。
きっとそれが最後のワガママです。
中略
いつか、僕を見て周りの人が、僕でなくお母さんのことを褒めてくれるような立派な人間を目指して。」
世間がバブル時代のお金第一に戻りつつある中で、心の豊かさの大切さを考えさせられ、生きる勇気を与えてくれる本だった。
今日の一言
「闇があるから光がある」
そして闇から出てきた人こそ、一番本当に光のありがたさがわかるんだ。
(小林 多喜二)
管理人: 田村君も、いま少しの光を浴び始めたようだ。
クリックお願いします。

 テクノラティプロフィール
テクノラティプロフィール
管理人のホームページを見てみる
アメリカにいるのに結構、日本の本を読むほうなので、ここで紹介していこうと突然思い立ちました。
栄えある第一冊目は、「ホームレス中学生

Amazon.co.jp
この本は、発売2ヶ月でミリオンセラーになったお化け本だ。
中学2年の1学期の最後の日に、突然父親から「解散!」の通告を受けた主人公が1ヶ月の公園生活も含め、周りの人に助けられながら一生懸命に生きていく自叙伝。そして、大好きだった母親へのメッセージでもある。
貧困の中でも、光り続ける彼の明るさと、周りの人の親切は、一種の奇跡だ。
少し長いけど、この本で彼が一番書きたかったと思うところを引用してみる。
「お母さんと過ごした十一年間の記憶はいつまでも消えることなく、思い出すたび色濃くなっていきます。
僕があんなにたくさん甘えなければ、もしかしたらもっとお母さんと一緒の時間を過ごすことが出来たのかもと考えてしまいます。
中略
情けないことに、今でも僕はお母さんに会いたくて仕方がありません。死にたいということではないけれど、お母さんに直接に会っていっぱい喋りたいです。
もしお母さんに会えたときに喋ることがいっぱいあるように、僕はいろんなことをたくさん経験しておきます。いつまでも話が尽きないように。
だからそのときは昔のように優しく聞いてください。
きっとそれが最後のワガママです。
中略
いつか、僕を見て周りの人が、僕でなくお母さんのことを褒めてくれるような立派な人間を目指して。」
世間がバブル時代のお金第一に戻りつつある中で、心の豊かさの大切さを考えさせられ、生きる勇気を与えてくれる本だった。
今日の一言
「闇があるから光がある」
そして闇から出てきた人こそ、一番本当に光のありがたさがわかるんだ。
(小林 多喜二)
管理人: 田村君も、いま少しの光を浴び始めたようだ。
クリックお願いします。

 テクノラティプロフィール
テクノラティプロフィール管理人のホームページを見てみる













