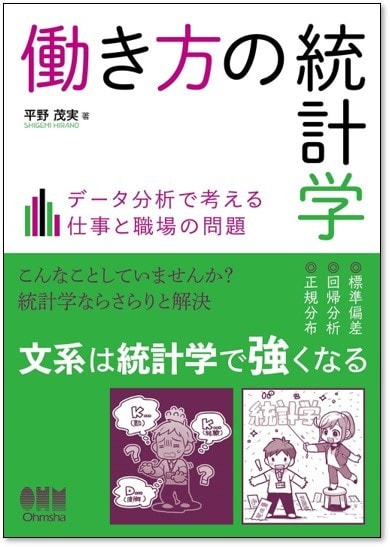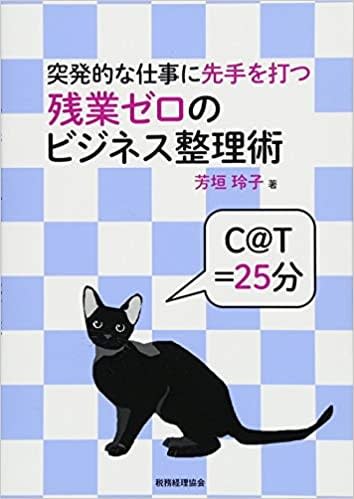「すべての社員がイキイキ働くようになる」仕組みと研修を提供する人材育成社です。
「反省する人は成功する。誰でもそうやけど、反省する人はきっと成功するな。 本当に正しく反省する。・・・」
ご存知の方も多いかと思いますが、これはあの松下幸之助氏の言葉です。この言葉のとおり、松下氏自身もその日あったことに思いを巡らし、失敗体験を振り返り「次はこうしよう、こうすればうまくいくかもしれない」と考え、反対にうまくいったことに対しても、そのままにしておくのでなく、ことがうまく運んだ理由を考えて次にもっとうまくやるためにはどうすればよいか、日々考えていたとのことです。
おそらく、多くの人たちは子どもの頃から松下氏の言葉のように「失敗したら反省すること、次に同じようなことが起きた際には前の失敗を活かすように」と周囲の大人から繰り返し言われてきたと思います。そのため、特に意識することなく「日々反省をしている」ように思うのです。
しかし、先日タレントのタモリ氏が「反省しないことをモットーにしている」との話をしているのを聞いて、新鮮に感じたのと同時にその理由に「なるほど」と思わされました。
今年喜寿を迎えるタモリ氏は、同一司会者による長寿番組のギネス記録を2つ持っているそうですが、長く番組を続ける秘訣の質問に対して、「反省しないこと。過去のことをいくら反省してあの時こう言えばよかった、こうすればよかったと言っても、一生同じ状況になることはない。だからそれを反省してもしょうがない。それよりも、未来に目を向けましょう」と答えていました。
「反省」とは過去の時間に思いを巡らすことです。それよりも、「同じ時間を使うのであれば未来を考えることが大切だ」というタモリ氏の言葉は、私にはすっと腑に落ちるように感じられました。
確かに、32年間続いたフジテレビの「笑っていいとも」の最終回の際にも、周囲の出演者が感傷的になっている中で、タモリ氏が淡々と番組の終わりを迎えていたことが強く印象に残っています。このときも、32年という過ぎ去った時間を振り返るのではなく、タモリ氏の目は既に未来に向いていたということなのでしょう。実際に、「笑っていいとも」終了後に、やりたいと考えていたことにいろいろ取り組んだとのことです。
振り返ってみて、私自身は日ごろから失敗したら反省し、次に活かすことが大切だと考えてきたのですが、タモリ氏の言葉に刺激を受けて、2022年は反省の時間は大切にしつつも、より「未来のために今の時間を使うこと」をモットーに取り組んでみたいと考えています。
新年の始まりにあたり、皆さんはどう思われますか。