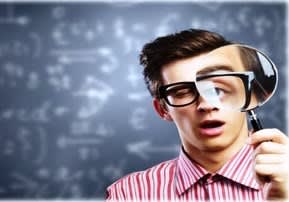「偉大なことを成しとげるには2つのことが必要である。1つは計画、1つは時間。ただし、不足気味の時間が」
これは今年、生誕100年を迎えるレナード・バーンスタインの言葉です。アメリカが生んだ偉大な指揮者であり、作曲家であるバーンスタインですが、生誕100年ということで、ここのところ様々なメディアなど取り上げられています。
バーンスタインの名を初めて聞いたという方もいらっしゃるでしょうが、バーンスタインが作曲した曲は間違いなく耳にしたことがあるはずです。たとえば「ウエストサイドストーリー」の「トゥナイト」や「アメリカ」を聞けば、多くの方が「ああ、その曲なら知っている」と思われることでしょう。
バーンスタインはその生涯で7度、来日したそうですが、私自身は残念ながらバーンスタインの公演に行くことはできなかったのです。しかし、あるとき冒頭の言葉を知ってから、一方的に非常に身近な存在だと感じているとともに、研修やコンサルの仕事を続けている日々の中で、この言葉の重みをかみしめています。
近年、「働き方改革」が大変な話題になっています。テレビや様々な書籍をはじめ、「働き方改革」を目にしない日はないと言ってもいいくらいです。弊社は会社設立時から「仕事の生産性の向上」をメインテーマの1つとして研修やコンサルに取り組んできていますが、実はその中でバーンスタインのこの言葉を何度も拝借しています。
弊社が行う研修では、受講者に様々な演習に取り組んでいただきますが、その際はじめにバーンスタインの話(特に「不足気味の時間」の部分)をしてから課題の締め切りを伝えると、納期管理を強く意識して課題に取り組んでいただけています。
私はバーンスタインの言葉の肝は「不足気味の時間」であり、つまりは「足りない時間を意識しつつ、ものごとを行う」というところにあると思っていますので、その点を強調して話をしています。
すると、その結果、受講者は締め切りをきちんと守り、さらには質の高い成果を出してくれます。いつも心の中で「さすがはバーンスタインの言葉」と思っているのです。
この言葉のように、予め「時間」を意識して、仕事に取り掛かる際にはまず納期を明確にし、そこから逆算して段取りを組むということを日常的に行えば、仕事の生産性を上げることができるということを研修の中で体験していただいているわけです。これを受講者それぞれが実際に職場に戻ってから実践していただければ、職場全体の生産性も間違いなく向上できると考えています。
皆さんも仕事に取り掛かる際には、ぜひバーンスタインのこの言葉を思い出してみてはいかがでしょうか。
さて、本人に断りもなく、これだけバーンスタインの言葉を拝借している私ですので、今年は生誕100周年を祝うコンサートに行く予定でいます。
コンサートに行く計画はしたのであとは時間だけですが、こればかりはコンサートの時間が不足しないように、十分に確保します。