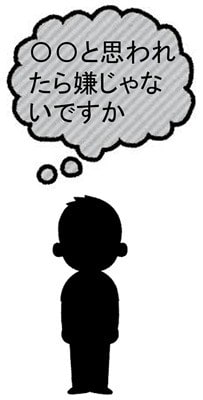「社員がイキイキ働くようになる」仕組みと研修を提供する人材育成社です。
「昔、戦争とかあったみたいじゃないですか」
これは以前、私がある金融機関の窓口での手続きの中で「戦争免責」について説明を受けていた際に、担当者から聞いた言葉です。その担当者は20代半ば位に見受けられましたが、かつて日本が体験した戦争を「あったみたいじゃないですか」というように表現をしたことに少々驚いたことを覚えています。
先日、JR福知山線脱線事故(2005年4月25日発生、乗客・運転士合わせて107名が死亡、562名が負傷)から20年が経過したという報道がありました。あの大事故を経て、JR西日本では「安全基本計画」を策定し、社員からの報告を抽出・評価して重大事故などにつながる可能性を取り除く「リスクアセスメント」を導入するなど、安全教育を徹底しているとのことです。しかし事故から20年が経ち、そのときに在籍していた社員は3割ほどとなり、7割強の社員は事故後に入社しているとのことです。
また、今年は1985年に起こった日本航空機の墜落事故からも40年になりますが、こちらはさらに多くの時間が経っていることから、事故当時に在籍していた約1万4千人の社員のうち、現在も現役で働いているのはわずか0.5%、人数にして77人(2024年時点)とのことです。つまり、事故当時を直接知る社員は、極僅かしかいないということです。
これらの数字が改めて示しているのは、「時間の経過とともに、人は入れ替わっていく」ということです。もちろん、組織の新陳代謝という点からも人が入れ替わること自体は必要なものであり、いたし方ないことではあります。しかし、その結果として事故などをはじめとして将来にきちんと引き継いで行かなければならない記憶や経験といったものがだんだんと薄れて、風化していってしまわないかということが危惧されます。
こうした記憶や経験が風化していってしまうと、冒頭の金融機関の窓口の担当者のように、戦争が起こったということですら、「昔、あったらしい」こととして片づけられてしまうのかもしれません。そして、いずれはJR西日本の事故や日本航空機の事故も、さらには先の戦争も経験者から直接伝え聞くことが出来ないくらいの時間が経ってしまったら、あったという事実さえもが風化してしまうのではないかと、とても心配になります。
では、教訓として必ず引き継いでいかなければならないような記憶や経験を風化させないためには、私たちはどうすればよいのでしょうか。多くの例が示しているように、簡単に答えが出せるものではないのかもしれません。しかし、まずは「(何もしなければ)人は時間の経過とともに物事を忘れ、その記憶や経験も風化していってしまうものだ」ということを前提にして、事実や経験を正確に記録して、それをしっかり継承していくこと、たとえば継承していくための機会を意識的に、定期的に設けること(新入社員研修などで必ずその事実に触れ、見学なども行うなど)が有効な方法ではないかと考えます。
記憶や経験の風化を防ぐということは、事故などの悲惨な体験を覚えておくということだけではなく、同時にそこから何を学び、将来にどう生かしていくかを考え続けていくということでもあるのではないでしょうか。
人は物事を案外とすぐに忘れてしまう。だからこそ、「体験をした人はそれを次世代へつないでいく責任を持っている」ということを、私達は心に留めておく必要があるのではないかと考えています。