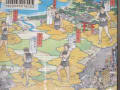約40年ぶりに小学校の恩師、ゴリ橋先生と連絡を取り、思わぬ行き違いに翻弄されながらも無事に先生が保管してくれていた卒業記念の木彫りを引き取ってから2週間が過ぎた。「・・・引取り完了」編の末尾に紹介したようなメッセージを作り、某SNSやメールなど知っているクラスメートには直接送り、また連絡先を知っているという知人に頼んで中継してもらった。さらに中継もあってメッセージが届いたと思われるクラスメートは10人余り、文中に入れた連絡用アドレスに返信等くれたのはこれまで数人というところだ。送った木彫り写真を見て「どれが自分の物か判別できた!」という、ある意味御縁のある人はわずか1名。。。その他の人は「できることは何でも協力するが、あいにく他のクラスメートとは連絡取れない」という予想通りのものだった。ネットや人づて以外に、数十年ぶりに消息の分からない人と連絡先を調べようとすると、頼りになるのは卒業アルバムだけである。
以前も書いたが、昨今は個人情報漏洩や詐欺を警戒するあまり、仮に各人の実家などがまだアルバム通りだったとしても、かなり詳しく説明しないと事情を分かってもらえないようだ。また家族であっても「個人情報を他人に教える時は本人の同意が必要」というそれなりに意識のある人も少なくない。さらに完全に他人になってしまうと、詐欺や勧誘と決めつけられ、「言われのない口撃」を受けて嫌な思いをすることもあるだろう。「できることは協力・・・」というのは「一定以上は踏み込まない」という意志の裏返しであり、仕方がないと思う。卒業後キリのいい年次だからか他クラスでも木彫り配付や同窓会の動きが活発なようで、中でも4年がかりでクラスメートを6割集め、担任を囲んだという組は幹事が見事な采配を奮っていた。「楽しんでやった」というこだが、それまでの苦労話も色々聞いてみたいものだと思う。担任の先生はゴリ橋先生よりもはるかにご高齢のようだったが、さぞ喜んだことだろう。
さて、その「サッチー先生」(仮称)だが、何と本を出版しているそうで、ひょんなきっかけからそれを読んでみる機会を得た。実際は約20年前にエジプト・イスラエルを2週間ほどかけて訪れており、その際に見聞したことを綴ったもののようだ。さてサッチー先生は社会科専攻だったか、実際に教わっていないのでよく分からないし、仕事上の当該地の知識や思い入れ、ご経験なども存じ上げないので、場合によっては失礼な物言いになってしまうかもしれないが、一読した感想は「我々と同じ一旅行者目線で書かれていると」というものだった。吉村作治さんのようなこの方面の地政、歴史などが専門の深い学者ではなく、ひょうきん由美さん(古いなー)のように世界各国を巡るリポーターというわけでもない。我々のように初めて訪れる「ポット出の旅行者」という感じ(この辺り違っていたら大変失礼なんだが)がして、身近なものを感じたのだ。専門家の書やベテランのガイドブックなどに感じる見えない溝がないのである。
あとがきを読むと(順番が逆だが)どうもサッチー先生は退職を機会に「自分探し」を思い立って参加した旅行らしい。永年務めた仕事を終えたときに自分の時間が有限なことに気付く。80歳まで生きたとしても自分に残された時間は20年そこそこ、それも保証されているわけでもない。その貴重な時間を輝かせようと自分が選んで行くことはないだろうと思われた友人の紹介によるエジプト、イスラエルの旅にノッたそうである。あとがきに共感するというのも妙だが、ぼちぼち先生の境涯に近づきつつある私にとって、「節目にはこんなきっかけでどこかに行くことになろう」と容易に想像できた。もっとも普通はふらない「わき目」だらけでここまでやってきた私は自分の「これまで」がいかに「結果オーライ」だったのか知っているので、今更自分を探す必要はないと思っているのだが。
さて約20年前のだいぶ今とは情勢が変わっていると思われるが、最初の渡航地はエジプトだった。成田からロンドン経由で17時間かかってカイロへ。午前4時半に街中に流れるコーランの唱和を目覚ましとする。タイトルは「砂漠は語る」である。ナイル川沿いのグリーンベルト沿いにしか住むには適さない国土で何時間もバスに揺られながら、ピラミッド、博物館のミイラを見学していく、「(あー、自分もこんな感想を持って、こんな記事にするだろうな)」というところもあるが、経験や感性は段違い、5000年前に国王だったジュセル王のミイラとの心の会話が印象深い。「エジプト人は王様の功績を守って、変化を好まない。私達日本人は変化を続けて今に至った」良いとか悪いという話ではないが、私の少年時代、万能の行き付け医師だった戦艦長門の軍医長は、生涯の旅行の憧れをエジプトと言い、同様なことを仰っていたような気がする。
地球儀や世界地図を見ると、「この水路を築いたのは人類きっての快挙」と思われるのが「スエズ運河」である。私の高校の担任が世界史の教師でローマ時代から中東・アラブの歴史を特に熱く語る人で、私も当時の一次試験に世界史を選択したこともあって、この辺りの歴史は満更知らないわけではない。フランス人レセップスに始まり、開通には日本人の技術が結構貢献、しかしその地理的な戦略価値から動乱の絶えない施設だった。私が最高傑作とするコミックの一つ「エリア88」でも「スエズ運河を制圧・支配する」という戦略実施が大きく動きを左右する。先生の参加したツアーには「出エジプト記」にまつわる「モーゼ山に登頂する」というのがメインイベントの一つだった(モーゼと言えばどちらかというと「海」なんだが)ようだが、これを平気で蹴飛ばし、スエズ運河で父子とキャンディーのやりとりを記述するところが、先に書いた「自分だったらそうだろう感」を感じて親近感を持った。
モーゼ山へのルートもそうだが、行き交う人や車もない岩砂漠をどこまでもバスで進む旅路だ。「もしここでガソリンが切れたらどうしよう」サッチー先生は外国旅行中の時に非常時用に「不時着パン」なる縁起でもない食料を持ち歩いているそうだ。私も移動を除く空の上、海の底、高山の上、砂漠などひとたびアクシデントが起こると生きていけない場所には行かないようにしているから、その心細さは共感できる。その後彼女はエジプトからシナイ半島を経て陸路イスラエルに無事入国している。死海、ユダヤ人、そして宗教の交差点、テロなど歴史的因縁の街という認識と、戦争によりいつもきな臭いニュースの尽きない国という印象が強い。こういう実際の紀行文を読まないと中々縁のない国のようだ。しかし食事は美味しく、意外にもヨットやウィンドサーフィンも眺められるリゾート地もあり、中々魅力あるところのようだ。
私もこの手の本を持っているが、ユダヤ人と言えばジョークが少しブラックで冴えわたり、商売がうまいということで定評がある。紹介されていた「金儲け」の話はまさしくこれを象徴するものだった。
「ある成功したビジネスマンが妻への土産にエメラルドを購入し友人に自慢気に見せる。購入価格は1万2千ドル、友人はこれに魅せられ1万4千ドルでこれを譲ってもらう。しかし持ち主はやはり妻への土産を取り戻したいと思い、1万6千ドルで再び買い戻す。これらのやり取りから、さらにこの指輪が欲しくなり2万ドルで譲ってもらおうと電話したところ、たまたまオフィスに来ていた別の友人に1万9千ドルで売ってしまう。それを聞いた友人が最後に言った言葉が『おまえはバカだな。二人で午後のうちだけでも何千ドルも儲け合っていたのにそのタネを売ってしまうなんて。これを毎日続けていれば我々はすぐに百万長者になれたのに』」
何か日本のバブル期を皮肉られているようにも思える。私は経済学を専攻していないので詳しくはないが、その本質が「循環」にあるというのを感じさせるウィットに富んだジョークだと思う。
もう一つ、イスラエル編で大きな印象のあったのが、「杉原千畝」さんの記念樹に触れたことである。ちょうど一月ほど前、このユダヤ人の中では最も有名な日本人の一人とも言える外交官の生涯をとある著書で読んだのだった。1940年、リトアニア駐在時にナチスドイツのポーランド侵攻を逃れてきたユダヤ人に日本通過ビザを発行し6000人の命を救った人とある。実は本国の許可を得ずにこのビザを発行したのである。しかも領事館を閉鎖され国外退去を強制されて列車が駅を出る瞬間まで「あと一枚、あと一枚・・・」とビザを書き続けるのである。その時に救った青年と後に日本で再会する感動のシーンがあった。最近読んだ本の中では久々にゾクゾクするほどの感銘を受けたものだった。イスラエルにはこの杉原千畝さんの記念樹であるヒマラヤスギがあり、サッチー先生がその樹と撮った写真が載っていたのである。何やらこの本とは不思議な御縁があるようだ。
サッチー先生の著書最後の章は聖書を携えて、宗教発祥の地を巡るものだった。何しろエルサレムといえば3つの宗教に聖地がひしめく奇跡の地である。ソロモンの神殿跡ノエルアクサ寺院ではイスラム教徒が祈り、嘆きの壁で祈るのはユダヤ教徒、イエスの苦しみを体験してヴィア・ドロロサというところを歩くのがキリスト教徒だという。本書では聖書の一節を引用しながら、「お告げの教会」「キリスト生誕教会」「奇跡の教会」、死海写本が発見された「クムラン洞穴」「祝福の山」「シオンの丘」そしてイエスが処刑された「ゴルゴダの丘」である。先生は大して強い信仰心は持っていないと自白している。私ももちろんその通りである。だから私が同じ場所に立っても聖地のアイテムそのものには大した実感は感じなかったかもしれない。しかし教徒の数千年にわたる敬虔な「祈り」が目に見えない媒体となって聖地たる空気を作り出しているように想像した。私もキリスト教幼稚園卒園の身、聖書のくだりのいくつかは覚えているが、残念ながらその内容に特段の感慨は覚えない。この本の「聖書」編では色々と書きたいことはあるが、「禁断」と言われた宗教論、キリスト教そのものよりも、これを信仰してきた教徒と呼ばれる人間の歩んだ歴史を語りたくなって、長くなりそうなのでそれは別の機会(いや、やめとくか)にしよう。
最後にサッチー先生がエジプト・イスラエルを訪れたのは約20年前だが、初版が著されたのは2003年となっている。旅を終えて5年くらいしてから執筆したようだが、どうやら後から本にしようという気になったらしい。例えば最初から旅行記にするつもりだったとすれば、行く先々で帰国後の執筆を思い浮かべて様々に「取材」し、編纂しやすいように記録を整然と残しておくものだと思われるが、当初はそういった予定がなく、いかにもつれづれ見聞しているようだから、数年たってこれほど細かく、まるでその場に立っているような著述ができるとは素晴らしい記憶力と起草力だ。さすがに学校の先生である。文中にも書いたが、私にも遠からずこういう「旅に出る」機会はやってくる。こんなすごい見聞録はとても書けないが、果たしてどこを訪れようか?私の場合は恐らく妻と一緒だろうから、おいおい相談してみようと思う。
先生を囲んだ同窓会はたいそう盛り上がったそうである。我がクラスが実現するかどうかは不明だが、面白いことに先に紹介した私のキリスト教幼稚園の卒園者が7名もいたそうだ。小学校よりもはるかに記憶が薄く誰がいたかも定かではないし、アルバムの類も全くないが、こういうことは何かのきっかけで急転直下進むものであり、実家の母親に「幼稚園時代の写真がないか」探してもらうよう頼みこみ、奇跡的なショットを発掘したのだった。まさしくツタンカーメンものだ・・・5000年とは言わないが、40年以上たっているからもう時効だろう。






以前も書いたが、昨今は個人情報漏洩や詐欺を警戒するあまり、仮に各人の実家などがまだアルバム通りだったとしても、かなり詳しく説明しないと事情を分かってもらえないようだ。また家族であっても「個人情報を他人に教える時は本人の同意が必要」というそれなりに意識のある人も少なくない。さらに完全に他人になってしまうと、詐欺や勧誘と決めつけられ、「言われのない口撃」を受けて嫌な思いをすることもあるだろう。「できることは協力・・・」というのは「一定以上は踏み込まない」という意志の裏返しであり、仕方がないと思う。卒業後キリのいい年次だからか他クラスでも木彫り配付や同窓会の動きが活発なようで、中でも4年がかりでクラスメートを6割集め、担任を囲んだという組は幹事が見事な采配を奮っていた。「楽しんでやった」というこだが、それまでの苦労話も色々聞いてみたいものだと思う。担任の先生はゴリ橋先生よりもはるかにご高齢のようだったが、さぞ喜んだことだろう。
さて、その「サッチー先生」(仮称)だが、何と本を出版しているそうで、ひょんなきっかけからそれを読んでみる機会を得た。実際は約20年前にエジプト・イスラエルを2週間ほどかけて訪れており、その際に見聞したことを綴ったもののようだ。さてサッチー先生は社会科専攻だったか、実際に教わっていないのでよく分からないし、仕事上の当該地の知識や思い入れ、ご経験なども存じ上げないので、場合によっては失礼な物言いになってしまうかもしれないが、一読した感想は「我々と同じ一旅行者目線で書かれていると」というものだった。吉村作治さんのようなこの方面の地政、歴史などが専門の深い学者ではなく、ひょうきん由美さん(古いなー)のように世界各国を巡るリポーターというわけでもない。我々のように初めて訪れる「ポット出の旅行者」という感じ(この辺り違っていたら大変失礼なんだが)がして、身近なものを感じたのだ。専門家の書やベテランのガイドブックなどに感じる見えない溝がないのである。
あとがきを読むと(順番が逆だが)どうもサッチー先生は退職を機会に「自分探し」を思い立って参加した旅行らしい。永年務めた仕事を終えたときに自分の時間が有限なことに気付く。80歳まで生きたとしても自分に残された時間は20年そこそこ、それも保証されているわけでもない。その貴重な時間を輝かせようと自分が選んで行くことはないだろうと思われた友人の紹介によるエジプト、イスラエルの旅にノッたそうである。あとがきに共感するというのも妙だが、ぼちぼち先生の境涯に近づきつつある私にとって、「節目にはこんなきっかけでどこかに行くことになろう」と容易に想像できた。もっとも普通はふらない「わき目」だらけでここまでやってきた私は自分の「これまで」がいかに「結果オーライ」だったのか知っているので、今更自分を探す必要はないと思っているのだが。
さて約20年前のだいぶ今とは情勢が変わっていると思われるが、最初の渡航地はエジプトだった。成田からロンドン経由で17時間かかってカイロへ。午前4時半に街中に流れるコーランの唱和を目覚ましとする。タイトルは「砂漠は語る」である。ナイル川沿いのグリーンベルト沿いにしか住むには適さない国土で何時間もバスに揺られながら、ピラミッド、博物館のミイラを見学していく、「(あー、自分もこんな感想を持って、こんな記事にするだろうな)」というところもあるが、経験や感性は段違い、5000年前に国王だったジュセル王のミイラとの心の会話が印象深い。「エジプト人は王様の功績を守って、変化を好まない。私達日本人は変化を続けて今に至った」良いとか悪いという話ではないが、私の少年時代、万能の行き付け医師だった戦艦長門の軍医長は、生涯の旅行の憧れをエジプトと言い、同様なことを仰っていたような気がする。
地球儀や世界地図を見ると、「この水路を築いたのは人類きっての快挙」と思われるのが「スエズ運河」である。私の高校の担任が世界史の教師でローマ時代から中東・アラブの歴史を特に熱く語る人で、私も当時の一次試験に世界史を選択したこともあって、この辺りの歴史は満更知らないわけではない。フランス人レセップスに始まり、開通には日本人の技術が結構貢献、しかしその地理的な戦略価値から動乱の絶えない施設だった。私が最高傑作とするコミックの一つ「エリア88」でも「スエズ運河を制圧・支配する」という戦略実施が大きく動きを左右する。先生の参加したツアーには「出エジプト記」にまつわる「モーゼ山に登頂する」というのがメインイベントの一つだった(モーゼと言えばどちらかというと「海」なんだが)ようだが、これを平気で蹴飛ばし、スエズ運河で父子とキャンディーのやりとりを記述するところが、先に書いた「自分だったらそうだろう感」を感じて親近感を持った。
モーゼ山へのルートもそうだが、行き交う人や車もない岩砂漠をどこまでもバスで進む旅路だ。「もしここでガソリンが切れたらどうしよう」サッチー先生は外国旅行中の時に非常時用に「不時着パン」なる縁起でもない食料を持ち歩いているそうだ。私も移動を除く空の上、海の底、高山の上、砂漠などひとたびアクシデントが起こると生きていけない場所には行かないようにしているから、その心細さは共感できる。その後彼女はエジプトからシナイ半島を経て陸路イスラエルに無事入国している。死海、ユダヤ人、そして宗教の交差点、テロなど歴史的因縁の街という認識と、戦争によりいつもきな臭いニュースの尽きない国という印象が強い。こういう実際の紀行文を読まないと中々縁のない国のようだ。しかし食事は美味しく、意外にもヨットやウィンドサーフィンも眺められるリゾート地もあり、中々魅力あるところのようだ。
私もこの手の本を持っているが、ユダヤ人と言えばジョークが少しブラックで冴えわたり、商売がうまいということで定評がある。紹介されていた「金儲け」の話はまさしくこれを象徴するものだった。
「ある成功したビジネスマンが妻への土産にエメラルドを購入し友人に自慢気に見せる。購入価格は1万2千ドル、友人はこれに魅せられ1万4千ドルでこれを譲ってもらう。しかし持ち主はやはり妻への土産を取り戻したいと思い、1万6千ドルで再び買い戻す。これらのやり取りから、さらにこの指輪が欲しくなり2万ドルで譲ってもらおうと電話したところ、たまたまオフィスに来ていた別の友人に1万9千ドルで売ってしまう。それを聞いた友人が最後に言った言葉が『おまえはバカだな。二人で午後のうちだけでも何千ドルも儲け合っていたのにそのタネを売ってしまうなんて。これを毎日続けていれば我々はすぐに百万長者になれたのに』」
何か日本のバブル期を皮肉られているようにも思える。私は経済学を専攻していないので詳しくはないが、その本質が「循環」にあるというのを感じさせるウィットに富んだジョークだと思う。
もう一つ、イスラエル編で大きな印象のあったのが、「杉原千畝」さんの記念樹に触れたことである。ちょうど一月ほど前、このユダヤ人の中では最も有名な日本人の一人とも言える外交官の生涯をとある著書で読んだのだった。1940年、リトアニア駐在時にナチスドイツのポーランド侵攻を逃れてきたユダヤ人に日本通過ビザを発行し6000人の命を救った人とある。実は本国の許可を得ずにこのビザを発行したのである。しかも領事館を閉鎖され国外退去を強制されて列車が駅を出る瞬間まで「あと一枚、あと一枚・・・」とビザを書き続けるのである。その時に救った青年と後に日本で再会する感動のシーンがあった。最近読んだ本の中では久々にゾクゾクするほどの感銘を受けたものだった。イスラエルにはこの杉原千畝さんの記念樹であるヒマラヤスギがあり、サッチー先生がその樹と撮った写真が載っていたのである。何やらこの本とは不思議な御縁があるようだ。
サッチー先生の著書最後の章は聖書を携えて、宗教発祥の地を巡るものだった。何しろエルサレムといえば3つの宗教に聖地がひしめく奇跡の地である。ソロモンの神殿跡ノエルアクサ寺院ではイスラム教徒が祈り、嘆きの壁で祈るのはユダヤ教徒、イエスの苦しみを体験してヴィア・ドロロサというところを歩くのがキリスト教徒だという。本書では聖書の一節を引用しながら、「お告げの教会」「キリスト生誕教会」「奇跡の教会」、死海写本が発見された「クムラン洞穴」「祝福の山」「シオンの丘」そしてイエスが処刑された「ゴルゴダの丘」である。先生は大して強い信仰心は持っていないと自白している。私ももちろんその通りである。だから私が同じ場所に立っても聖地のアイテムそのものには大した実感は感じなかったかもしれない。しかし教徒の数千年にわたる敬虔な「祈り」が目に見えない媒体となって聖地たる空気を作り出しているように想像した。私もキリスト教幼稚園卒園の身、聖書のくだりのいくつかは覚えているが、残念ながらその内容に特段の感慨は覚えない。この本の「聖書」編では色々と書きたいことはあるが、「禁断」と言われた宗教論、キリスト教そのものよりも、これを信仰してきた教徒と呼ばれる人間の歩んだ歴史を語りたくなって、長くなりそうなのでそれは別の機会(いや、やめとくか)にしよう。
最後にサッチー先生がエジプト・イスラエルを訪れたのは約20年前だが、初版が著されたのは2003年となっている。旅を終えて5年くらいしてから執筆したようだが、どうやら後から本にしようという気になったらしい。例えば最初から旅行記にするつもりだったとすれば、行く先々で帰国後の執筆を思い浮かべて様々に「取材」し、編纂しやすいように記録を整然と残しておくものだと思われるが、当初はそういった予定がなく、いかにもつれづれ見聞しているようだから、数年たってこれほど細かく、まるでその場に立っているような著述ができるとは素晴らしい記憶力と起草力だ。さすがに学校の先生である。文中にも書いたが、私にも遠からずこういう「旅に出る」機会はやってくる。こんなすごい見聞録はとても書けないが、果たしてどこを訪れようか?私の場合は恐らく妻と一緒だろうから、おいおい相談してみようと思う。
先生を囲んだ同窓会はたいそう盛り上がったそうである。我がクラスが実現するかどうかは不明だが、面白いことに先に紹介した私のキリスト教幼稚園の卒園者が7名もいたそうだ。小学校よりもはるかに記憶が薄く誰がいたかも定かではないし、アルバムの類も全くないが、こういうことは何かのきっかけで急転直下進むものであり、実家の母親に「幼稚園時代の写真がないか」探してもらうよう頼みこみ、奇跡的なショットを発掘したのだった。まさしくツタンカーメンものだ・・・5000年とは言わないが、40年以上たっているからもう時効だろう。



















 」面倒くさそうに指差した妻の指示は「カブを洗う」作業だった。(相手は言わばプロだが、何となさけないことだ)
」面倒くさそうに指差した妻の指示は「カブを洗う」作業だった。(相手は言わばプロだが、何となさけないことだ)