
広報は、社会の価値観や組織の事情により、取り組む仕事の内容もさまざまに変化します。広報に絡んでの判断や意思決定も、なかなか難しいことでいっぱい、というのが現実です。総務や庶務といった、その不定形こそが価値といえる仕事もそうですが、違うのは、組織の根幹を揺るがすような出来事などがあれば、突然水平ではなく、垂直思考になるところがあったり、トップ以上に頼りにされたりということがあったりするのが広報の仕事です。
ですから、「広報とは何か」を説明するには十分な思慮が必要になります。例えばですが、その広い概念を地図だと考えて、説明しようという領域をを”懐中電灯”で照らすようにして、そのスポット部分について説明する、という演出が賢い方法ということになります。でも、それでは、広報の中心部を話したことにならず、担当者は悶々として悔しい思いで涙です。
でも病院広報では、周りが心配するほど自らの”商品”、つまりは医療というサービス商品およびその”販売”についての知識・関心がなくても、それほど心配は要らないのかもしれません。それはそう、医療の商品知識の本質部分は、医師をはじめとする専門職が受けもってけれますし、販売もそうした人材が同時的にやってしまいます。専門職がテシオにかけた目には見えない商品価値を患者さんに伝え、気にいって利用してもらうよう説明する、これまさしく”販売”ではないでしょうか。広報がやることは「信頼の巧みがお届けする」といわんばかりの、医療商品の”付加価値”についてする”説明”だけということになります。
そこで、やおら広報からでてくるのが、その説明のための広報誌やホームページなど、オウンド・メディア(自作媒体)による情報伝達ということになります。それらの制作進行マネジメントを担当することが、いつの間にか「広報」だという文化が出来あがってしまいました。
これが経営的あるいは広報の使命にとっていいことなのかどうか、考えてみる必要があります。最終的には、生産の効率をどうする必要か、広報をやることで全体の生産性を求めるなら、広報にも十分な投資、そして少なくても自院における「広報の定義」だけはほしいところです。それらの自家製モノづくりに隠れる悪癖は、外部と交じろうとしない自己満足文化です。広報はもっと経営に乗り込んでいくべきだし、大きな視野をもつべきです。モノづくりは、信念を育てやすいのです。信念を持つべきで曲げてはいけないことは確かです。しかし信念は曲げるべきときには曲げてこそ、新な信念を創造できるのではないでしょうか。
ですから、「広報とは何か」を説明するには十分な思慮が必要になります。例えばですが、その広い概念を地図だと考えて、説明しようという領域をを”懐中電灯”で照らすようにして、そのスポット部分について説明する、という演出が賢い方法ということになります。でも、それでは、広報の中心部を話したことにならず、担当者は悶々として悔しい思いで涙です。
でも病院広報では、周りが心配するほど自らの”商品”、つまりは医療というサービス商品およびその”販売”についての知識・関心がなくても、それほど心配は要らないのかもしれません。それはそう、医療の商品知識の本質部分は、医師をはじめとする専門職が受けもってけれますし、販売もそうした人材が同時的にやってしまいます。専門職がテシオにかけた目には見えない商品価値を患者さんに伝え、気にいって利用してもらうよう説明する、これまさしく”販売”ではないでしょうか。広報がやることは「信頼の巧みがお届けする」といわんばかりの、医療商品の”付加価値”についてする”説明”だけということになります。
そこで、やおら広報からでてくるのが、その説明のための広報誌やホームページなど、オウンド・メディア(自作媒体)による情報伝達ということになります。それらの制作進行マネジメントを担当することが、いつの間にか「広報」だという文化が出来あがってしまいました。
これが経営的あるいは広報の使命にとっていいことなのかどうか、考えてみる必要があります。最終的には、生産の効率をどうする必要か、広報をやることで全体の生産性を求めるなら、広報にも十分な投資、そして少なくても自院における「広報の定義」だけはほしいところです。それらの自家製モノづくりに隠れる悪癖は、外部と交じろうとしない自己満足文化です。広報はもっと経営に乗り込んでいくべきだし、大きな視野をもつべきです。モノづくりは、信念を育てやすいのです。信念を持つべきで曲げてはいけないことは確かです。しかし信念は曲げるべきときには曲げてこそ、新な信念を創造できるのではないでしょうか。


















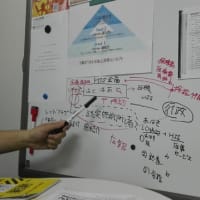

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます