
共有する言語を超えていくチカラとは?
「香りの記号論」という書籍がある。著者は狩野博美さんで、出版社は「人間と歴史社」。私の「呼吸する環境」というヒーリング・エンバイロメンツについての翻訳本を出してくれた東京の出版社である。副題が「香りの心的エネルギーの世界」といい、2002年の出版となっている。このブログの主題が「見る」であるが、こちらは「嗅ぐ」である。外付けの鼻と書く嗅神経で、「隠れている事物」を探る感覚がテーマになっている。相互に理屈抜きに「非言語」という原始的で多様な人間のコミュニケーションを掘り下げている。
香りの効用で、一般的によく知られるのはアロマテラピーだろう。研究された香りの要因が嗅覚の反応を引き出し、人の感覚・行動を促すという原理を集約した治療などに利用する。そのひとつが視覚コミュニケーションの記号・非言語として包括的な活用できるのである。いつの場合であっても心地よい香りが、ものごとの認識や記憶にとって、気ままな気分と態度によい効果があることは多くの経験が示すところである。味覚や音楽においても、人間の生はただ合理性の選択・追求だけに終始するものではないことは周知のとおりである。
人は一人一人の自己を調整を図りながら、常に他との関係を育み、相互の調和のために自ら社会を構成して「よりよく」生きようとしている。より強固な姿勢を示すには、自らの強化だけではどうもうまく行かない。ここには双方の思慮や納得が求められる。つまり感覚世界の共有や同調、双方が「ともに見える関係」でのコミュニケーションがなくてはならない。それを引き出してくれるのは、いま紹介した書籍、香りの記号論副題に見るような「心的エネルギー」の交換であり、相互による同レベルの理解と認識ではないだろうか。
しかし、ここで殊更に制度や策としての感覚テラピーを求めるのではない。時にはキャンペーンがあってもいい。が美しいものを美しいと真に反応する人体になろうとする個々の生き方がどうかという目線が求められる。そのためには、小さくても「心地よい体験」を求める日常が重要である。また、観念的な好き嫌いをいうのでもない。心地よい場や時がどこからやってくるのか、自分が求める快適とはどんなことなのか。非言語は、共有する言語を超えていくチカラを鍛える必要がある。かりに発案者がひとり、受信者がひとりであっても。20190506
6月29日(土)午後:HIS広報プランナー認定200回記念講座のご案内
横浜みなとみらい クイーンズタワー5階会議室
講師:ジェリイ・フォリー(イメージャス代表)
テーマ:「病院広報はデザインと広報で強くなる」
受講申込受付中! 案内はこちらhttp://www.j-his.jp/
「香りの記号論」という書籍がある。著者は狩野博美さんで、出版社は「人間と歴史社」。私の「呼吸する環境」というヒーリング・エンバイロメンツについての翻訳本を出してくれた東京の出版社である。副題が「香りの心的エネルギーの世界」といい、2002年の出版となっている。このブログの主題が「見る」であるが、こちらは「嗅ぐ」である。外付けの鼻と書く嗅神経で、「隠れている事物」を探る感覚がテーマになっている。相互に理屈抜きに「非言語」という原始的で多様な人間のコミュニケーションを掘り下げている。
香りの効用で、一般的によく知られるのはアロマテラピーだろう。研究された香りの要因が嗅覚の反応を引き出し、人の感覚・行動を促すという原理を集約した治療などに利用する。そのひとつが視覚コミュニケーションの記号・非言語として包括的な活用できるのである。いつの場合であっても心地よい香りが、ものごとの認識や記憶にとって、気ままな気分と態度によい効果があることは多くの経験が示すところである。味覚や音楽においても、人間の生はただ合理性の選択・追求だけに終始するものではないことは周知のとおりである。
人は一人一人の自己を調整を図りながら、常に他との関係を育み、相互の調和のために自ら社会を構成して「よりよく」生きようとしている。より強固な姿勢を示すには、自らの強化だけではどうもうまく行かない。ここには双方の思慮や納得が求められる。つまり感覚世界の共有や同調、双方が「ともに見える関係」でのコミュニケーションがなくてはならない。それを引き出してくれるのは、いま紹介した書籍、香りの記号論副題に見るような「心的エネルギー」の交換であり、相互による同レベルの理解と認識ではないだろうか。
しかし、ここで殊更に制度や策としての感覚テラピーを求めるのではない。時にはキャンペーンがあってもいい。が美しいものを美しいと真に反応する人体になろうとする個々の生き方がどうかという目線が求められる。そのためには、小さくても「心地よい体験」を求める日常が重要である。また、観念的な好き嫌いをいうのでもない。心地よい場や時がどこからやってくるのか、自分が求める快適とはどんなことなのか。非言語は、共有する言語を超えていくチカラを鍛える必要がある。かりに発案者がひとり、受信者がひとりであっても。20190506
6月29日(土)午後:HIS広報プランナー認定200回記念講座のご案内
横浜みなとみらい クイーンズタワー5階会議室
講師:ジェリイ・フォリー(イメージャス代表)
テーマ:「病院広報はデザインと広報で強くなる」
受講申込受付中! 案内はこちらhttp://www.j-his.jp/


















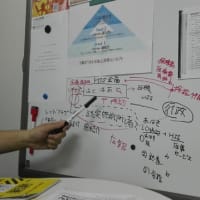

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます