
地域住民は、病院のいったい何を「見ている」のか
私たちは自らの内的宇宙に生きつつ、その印象世界の纏まりを意識し、自在に分析・検証・判断をしながら生きている。それらは言葉として編集され外部化されることでその遣りとりは、他人の立場にも少しは理解され共有される。つまり自己→言語→他者という感性による往来の中で、知的価値をその場の協働により創造して行くことになる。ここに科学的分析など到底及ばない生命的乱動のように見えてしまうのは致し方なく、「なるがまま」「ありのまま」自在な姿こそ合理的であり、人間として納得のいく実感ではないだろうか。
昨日は、日本HIS研究センターの企画運営会議という月例の集会に出席した。只でさえ忙殺されそうな状況の中、年度末の課題山積に議論は白熱した。気になるのは、大きな流れが明白でない段階に、細部に議論が集中してしまうことだ。準備不足の会合によくありがち、根気よく進める以外にない。むしろ「その場に立ち上がる湯気」やはり「ありのまま」という目の前に見える現実を尊重し、「流れに身を任す」ことも必要である。決定は力任せではなく、自分の意思、使われた言葉、メンバーの理解の質を統合して考えてみることである。
そのような場を十分に見わたし、進むべき道筋(戦略)を決めるには、言語情報よりも非言語、つまりビジュアル(図解)による資料が有効である。視覚には「小さな情報単位を嫌う」という原則がある。まして高齢人口の時代である。文字情報を極限まで制限して、なるべく「全体視」が可能な情報づくりが望まれる。いわゆる「パッと見て理解する」仕掛けの情報づくりである。また忘れてならないのは文面の漢字率(30%)で「可能な限り制限する」こと、視覚が細部に及ばなくても理解可能なように脳神経への配慮が重要である。
またそれを見込んで「バーチャル・チーム」という手法を提案しているが、時間切れ、準備不足で果たせなかった。それぞれ多忙かつ創造的な仕事ぶりの中にいるメンバーである。決定していく時間と場所は代替えの効かない基本条件である。その現実をクリアするには、タテの発想をヨコにしてみる、また経済などをハバとオクユキと置き換えてみる発想が必要である。「バーチャル・チーム」は会議・打ち合わせの固定概念を打ち破るにふさわしい。ぜひ、多職種が協働する医療現場では、この枠組みに挑戦してみるべきだと思う。
理念らしき理念、方針書らしき方針書、一見してそれらしい体裁をしていても、どこか軽々しい。熱のある情報はその威力を表面に滲み出しているはず。それらは「本質の研究」「サービスの研究」から距離を感じさせる。見た目だけのこうした筋合いは、必ず「制度」や「基準」からも距離があるように見える。利用者が「安心したい」を訴えるのはこのことに安心したいのだ。「虚いのない真心の医療かどうか」という精神性。病院に集まる医療の利用者は、欲望満足を願う「消費者」ではなく、顧客の特権を主張する「患者」でもない。mitameya190217
私たちは自らの内的宇宙に生きつつ、その印象世界の纏まりを意識し、自在に分析・検証・判断をしながら生きている。それらは言葉として編集され外部化されることでその遣りとりは、他人の立場にも少しは理解され共有される。つまり自己→言語→他者という感性による往来の中で、知的価値をその場の協働により創造して行くことになる。ここに科学的分析など到底及ばない生命的乱動のように見えてしまうのは致し方なく、「なるがまま」「ありのまま」自在な姿こそ合理的であり、人間として納得のいく実感ではないだろうか。
昨日は、日本HIS研究センターの企画運営会議という月例の集会に出席した。只でさえ忙殺されそうな状況の中、年度末の課題山積に議論は白熱した。気になるのは、大きな流れが明白でない段階に、細部に議論が集中してしまうことだ。準備不足の会合によくありがち、根気よく進める以外にない。むしろ「その場に立ち上がる湯気」やはり「ありのまま」という目の前に見える現実を尊重し、「流れに身を任す」ことも必要である。決定は力任せではなく、自分の意思、使われた言葉、メンバーの理解の質を統合して考えてみることである。
そのような場を十分に見わたし、進むべき道筋(戦略)を決めるには、言語情報よりも非言語、つまりビジュアル(図解)による資料が有効である。視覚には「小さな情報単位を嫌う」という原則がある。まして高齢人口の時代である。文字情報を極限まで制限して、なるべく「全体視」が可能な情報づくりが望まれる。いわゆる「パッと見て理解する」仕掛けの情報づくりである。また忘れてならないのは文面の漢字率(30%)で「可能な限り制限する」こと、視覚が細部に及ばなくても理解可能なように脳神経への配慮が重要である。
またそれを見込んで「バーチャル・チーム」という手法を提案しているが、時間切れ、準備不足で果たせなかった。それぞれ多忙かつ創造的な仕事ぶりの中にいるメンバーである。決定していく時間と場所は代替えの効かない基本条件である。その現実をクリアするには、タテの発想をヨコにしてみる、また経済などをハバとオクユキと置き換えてみる発想が必要である。「バーチャル・チーム」は会議・打ち合わせの固定概念を打ち破るにふさわしい。ぜひ、多職種が協働する医療現場では、この枠組みに挑戦してみるべきだと思う。
理念らしき理念、方針書らしき方針書、一見してそれらしい体裁をしていても、どこか軽々しい。熱のある情報はその威力を表面に滲み出しているはず。それらは「本質の研究」「サービスの研究」から距離を感じさせる。見た目だけのこうした筋合いは、必ず「制度」や「基準」からも距離があるように見える。利用者が「安心したい」を訴えるのはこのことに安心したいのだ。「虚いのない真心の医療かどうか」という精神性。病院に集まる医療の利用者は、欲望満足を願う「消費者」ではなく、顧客の特権を主張する「患者」でもない。mitameya190217


















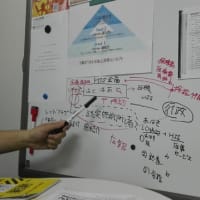

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます