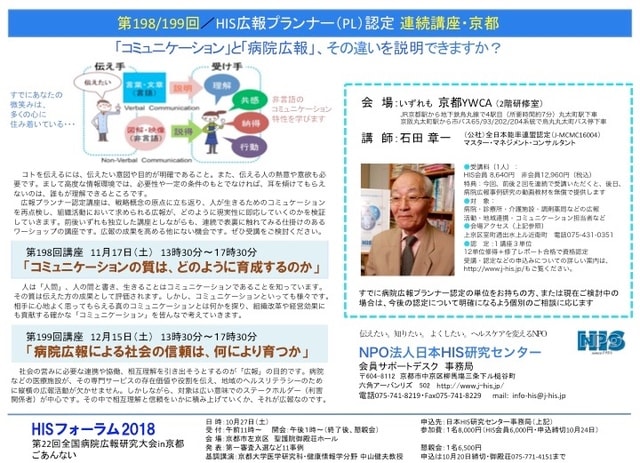言葉に優しく、その働きに労いの眼差しを
いつも何の考えもなく使っている「言葉」には、意味や概念だけでなく、反射的に置き換えられる「見える世界」を変えることで、さまざまな印象のバリエーションに繋ぐことができる。言葉の伝える意味は、決して一定ではないことは日常のコミュニケーションによっても理解することができる。しかしながら、それだけ変幻自在の言葉であったとしても、常々の表現に、それほど大きな揺れは感じないのだが、一旦それを疑ったり、鬱陶しいと思たりすると、頭の中は混乱して大騒ぎになることもある。人知れずする、身体の悩みである。
たとえば「卵」という言葉。平凡には、我々が食卓に上がる鶏の玉子が前列に並び、なんの違和感もなく暮らしの中に溶け込んでいる。だからこそ玉子であるが、これが「煮抜き」という理解が強制されたりすると、もう少しリアルな印象が増してしまい、卵や玉子の認識でいる相手には、多少でもギャップという腫れ物ができてギクシャクするのかも知れない。人との心の距離感は、そんな健気な痛みから生まれてくるようで、言葉についての印象や自覚も、常々揺れ動いているように思が、それも人間的成長であるのかも知れない。
自分が認識している言葉の印象と他者が認識している印象は、大きく違うのだが、人はその違いを堪えているに違いない。その違いの場に出会いそうになると、手近な階段を見つけて駆け下りるように避けていくのではないか。適切な言葉を使うと、相互の理解が進み、共感のある関係が生まれるというが、ほんとうだろうか。言葉がもっている印象という身体的理解やその背景となる環境に一定の共通性がなければ、同じような相似形の理解や共感というは難しいのではないか。そもそも手にもとれない印象を比較できるのだろうか。
言葉は想像以上に大切である。何気なく口に出した一言が、相手を傷つけ自分を錯乱させてしまう。言葉自体にも変質の跡が残ったのか、以後あまり見た形跡もなく、使いたくもないこともある。沢山の言葉を知ることも必要だが、その意味で主張する意味合いや価値観を我が身に引き寄せておけないものか。言葉に優しく、働きに労いの眼差しを注げるようになれば、表情はより豊かになれるのではないか。言葉を我が子のように抱き上げ、優しくアヤしながら話しかければ、心の平安がどこまでも広がり、隣人の笑顔が近くまできて囁くのだ。mitameya 181019
10月27日のHISフォーラムでは参加者審査を実施します。常々、広報の視点で仕事をする大学関係者らを審査員に
審査をお願いしてきましたが、医療の現場で広報に関わっている参加者との間に、どのような差があるか、
それを見てみようという会場外プログラムです。
締め切りまであと5日、お早めの思い仕込みをお願いします。
病院広報の精神は「鐘鼓(ショウコ)」、「鐘を鳴らそう、鼓を打とう」です。
昔の人は、こういって魂の村起しをしたと言います。
それがショウコに、BHI最優秀賞には、「鐘の鳴る木」を、BHIデザイン賞には、「連結太鼓」を送ります。
いつも何の考えもなく使っている「言葉」には、意味や概念だけでなく、反射的に置き換えられる「見える世界」を変えることで、さまざまな印象のバリエーションに繋ぐことができる。言葉の伝える意味は、決して一定ではないことは日常のコミュニケーションによっても理解することができる。しかしながら、それだけ変幻自在の言葉であったとしても、常々の表現に、それほど大きな揺れは感じないのだが、一旦それを疑ったり、鬱陶しいと思たりすると、頭の中は混乱して大騒ぎになることもある。人知れずする、身体の悩みである。
たとえば「卵」という言葉。平凡には、我々が食卓に上がる鶏の玉子が前列に並び、なんの違和感もなく暮らしの中に溶け込んでいる。だからこそ玉子であるが、これが「煮抜き」という理解が強制されたりすると、もう少しリアルな印象が増してしまい、卵や玉子の認識でいる相手には、多少でもギャップという腫れ物ができてギクシャクするのかも知れない。人との心の距離感は、そんな健気な痛みから生まれてくるようで、言葉についての印象や自覚も、常々揺れ動いているように思が、それも人間的成長であるのかも知れない。
自分が認識している言葉の印象と他者が認識している印象は、大きく違うのだが、人はその違いを堪えているに違いない。その違いの場に出会いそうになると、手近な階段を見つけて駆け下りるように避けていくのではないか。適切な言葉を使うと、相互の理解が進み、共感のある関係が生まれるというが、ほんとうだろうか。言葉がもっている印象という身体的理解やその背景となる環境に一定の共通性がなければ、同じような相似形の理解や共感というは難しいのではないか。そもそも手にもとれない印象を比較できるのだろうか。
言葉は想像以上に大切である。何気なく口に出した一言が、相手を傷つけ自分を錯乱させてしまう。言葉自体にも変質の跡が残ったのか、以後あまり見た形跡もなく、使いたくもないこともある。沢山の言葉を知ることも必要だが、その意味で主張する意味合いや価値観を我が身に引き寄せておけないものか。言葉に優しく、働きに労いの眼差しを注げるようになれば、表情はより豊かになれるのではないか。言葉を我が子のように抱き上げ、優しくアヤしながら話しかければ、心の平安がどこまでも広がり、隣人の笑顔が近くまできて囁くのだ。mitameya 181019
10月27日のHISフォーラムでは参加者審査を実施します。常々、広報の視点で仕事をする大学関係者らを審査員に
審査をお願いしてきましたが、医療の現場で広報に関わっている参加者との間に、どのような差があるか、
それを見てみようという会場外プログラムです。
締め切りまであと5日、お早めの思い仕込みをお願いします。
病院広報の精神は「鐘鼓(ショウコ)」、「鐘を鳴らそう、鼓を打とう」です。
昔の人は、こういって魂の村起しをしたと言います。
それがショウコに、BHI最優秀賞には、「鐘の鳴る木」を、BHIデザイン賞には、「連結太鼓」を送ります。