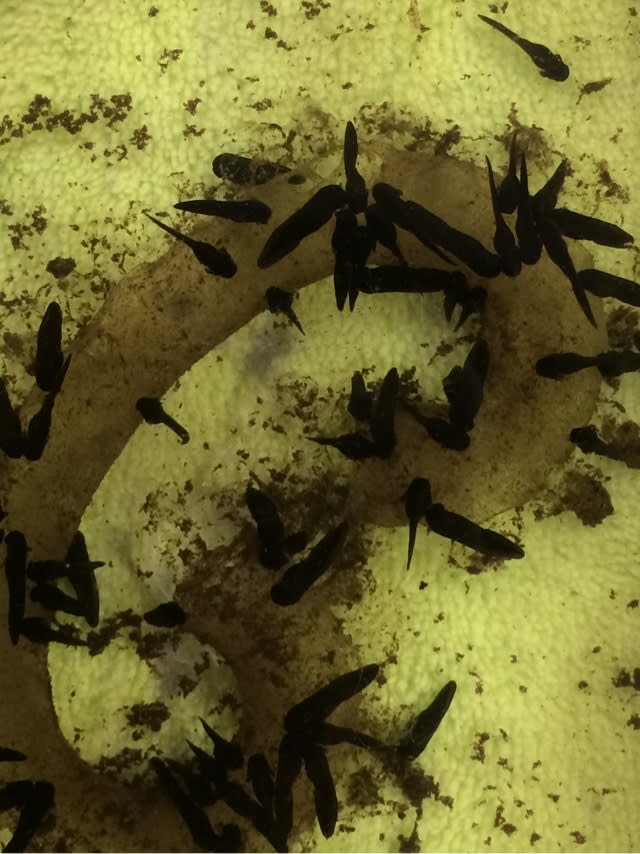コブシとハクモクレン。モクレン科の白く大きな花が梢にたくさん咲く季節になりました。遠くから見ると似たように見える花ですが、花弁の数や花のつきかたなど、よく見ると違いがあることがわかります。

ハクモクレンは上向き、あまり開かないため中心は見えにくいです。そして花被片は外花被合わせて9枚!コブシよりも肉厚。
見えにくい中心部分についてはこちらの記事を参照ください。

コブシの花は、花被片が開き中の蕊が見えます。花被片の数は外花被を合わせて6枚。
外花被というのは、もとは萼だったものが花弁と同じように変化したもの。この場合、本来の花弁は内花被と呼びます。
チューリップやアヤメなどもこのような花の作りです。
チューリップやアヤメなどもこのような花の作りです。

モクレンの仲間は日当たりを好むそうで、森の中では日当たりの良い高い枝にだけ咲いていることも多いです
遠目にはやはり似たような雰囲気。
そして、森の中に点々と灯るように咲く純白の花は「ああ春だなぁ」と見る人の心を和ませてくれます。
そして、森の中に点々と灯るように咲く純白の花は「ああ春だなぁ」と見る人の心を和ませてくれます。

モクレンの仲間はさまざまな園芸種も出回っていて、学名(属名)のマグノリアと呼ばれているようです。