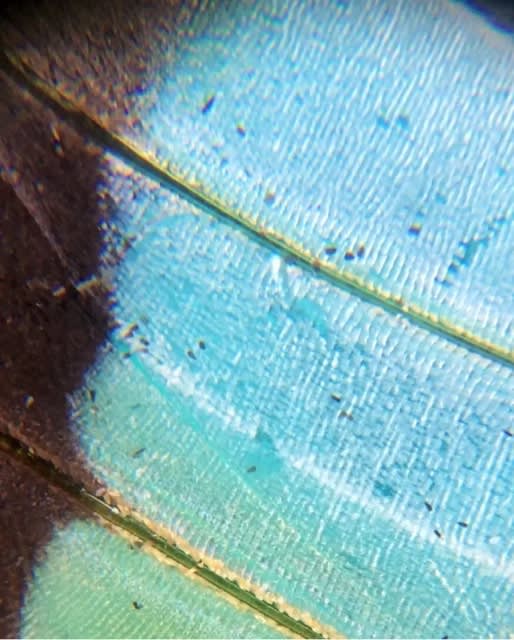成虫で厳しい冬を越えたテントウムシ。啓蟄ともなると、活動も活発になり、早くも産卵するものが登場します。ナナホシテントウやナミテントウが有名ですが、国内だけでも20種類以上もの仲間がいます。
ナナホシテントウ(テントウムシ科)
分布: アジア、ヨーロッパ、北アフリカ
ナナホシテントウは全国に分布し、よく見かけるテントウムシ。赤地に黒い点が7つ。よく目立つ姿は敵から身を守るための警告色と言われています。
触ると脚の関節から嫌な匂いのする黄色い体液をだしたり、死んだふりをしたり、そもそも体内にアルカロイド系の毒を持つので、鳥に捕食されることはまずありません。
それは幼虫も同じ。
このゴツゴツとしたヤツがテントウムシの幼虫。
上の写真はナミテントウの幼虫ですが、ナナホシテントウの幼虫もこれによく似ています。
ちなみに蛹はこんな形でやっぱり奇天烈!!!
幼虫やさなぎで越冬するトホシテントウは、もはや地球外生命体といっても良いのでは!?
↓↓↓
なお、ナナホシテントウやナミテントウなど、多くのテントウムシは成虫で越冬します。ナミテントウは集団で越冬することが有名ですが、ナナホシテントウをはじめ、多くのテントウムシ、単独、もしくは少数で冬を越します。
さてさて、ナナホシテントウはアブラムシを食べてくれるので、農家の皆様やガーデナーには益虫として大事にされています!!
幼虫は1日に20匹、成虫は100匹程度食べるそうです!!
ハウス栽培などでは、農薬の代わりにテントウムシを使うところもあるようで、そのためのテントウムシが商品化されていたりもします。飛べないヤツとか…。役だ出てるんですねぇ〜
でも、同じテントウムシでも、葉っぱを食べる害虫もいるので要注意。
例えばこちら↓
 ニジュウヤホシテントウ
ニジュウヤホシテントウ
ジャガイモをはじめ、ナス科植物が大好物。
てんとう虫の寿命は孵化から羽化までが20日、成虫になってからが2ヶ月ほだと言われています。ただし、秋に羽化したものは越冬し、アブラムシが現れる頃産卵して、その命を引き継ぎます。
 2020.2.21
2020.2.21
この黄色いつぶつぶがナナホシテントウの卵。写真は2月の下旬に見つけたもの。
こんなに早く産卵して餌はどうするのかなぁって心配していたら、ちゃんとアブラムシも活動を始めていました!!
 2020.3.4
2020.3.4
生き物ってすごいなぁ…!!!!!
ところで、ナナホシテントウのメスは短い一生のうちに1回に30 個、平均1600個近くの卵を生むってwikiに書いてあったのですが、本当かなぁ????
単純計算で53回産まなきゃならないわけで、つまり成虫になったら毎日ひたすら産み続けるってことですよねΣ(゚д゚lll)
でもって、その卵が育つために必要なアブラムシは…
幼虫時代 20匹×20日 400匹
成虫時代 100匹×60日 6000匹
で、1匹の雌が産卵する数が1600匹
6400×1600=約1000万
もちろん途中で命を落として最終的には雌雄1対が残るのでしょうが、途中まではアブラムシを食べるとして、
その数1割としても100万匹!!!!!
可愛い姿をして、実はかなり獰猛なのです。
なお、テントウムシに対抗するアブラムシの生き残り作戦に興味がある方はこちらの記事を→アブラムシ物語
なお、目のように見えるのは体の模様。
これはキイロテンウですがナナホシテントウやナミテントウも同じように「目に見える模様」があります。何か意味があるのでしょうか???
本物の目はこちら↓
けっこうびっくりー!
目の模様は、「胸」の部分についているのですね。「頭」はその先にちょこんとついています。
最後にこれまで出会ったテントウムシたち。日本だけで25種以上いるそうなので、まだまだ探したりませんが…(^^;;
 ナミテントウ(5〜8mm)
ナミテントウ(5〜8mm)
キイロテントウ(4〜5mm)
ニジュウヤホシテントウ(6〜7mm)

ヒメカノコテントウ(4mm)
シロボシテントウ(3〜4mm)
ハラグロオオテントウ(11〜12mm)
ムーアシロホシテントウ
ウスキホシテントウ(3〜4mm)
ーーーーーーーーーーーーーー
ホームページ
Instagram
ーーーーーーーーーーーーーーー