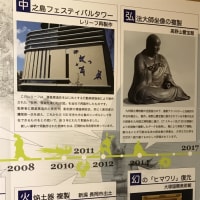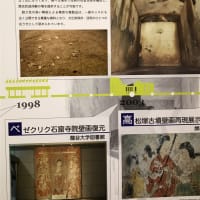首相の号令で「右向け右」で改革が進んでいますという進軍ラッパもいいが、実際に機能するかをきちんとモニタリングしたほうがいいと思う。
(以下引用部下線は筆者)
子育て支援拡充へ新制度、政府の会議が今夏に指針
(2013/4/26 日本経済新聞)
政府は26日、2015年度に施行する新たな子育て支援制度の細部を詰める「子ども・子育て会議」の初会合を開いた。(中略)
新制度の実施主体となるのは市町村だ。都市部や過疎地などでそれぞれ異なるニーズに合わせ、どのような子育て支援を提供するかを5カ年の事業計画にまとめる。この計画作りを手助けするのが、政府の子ども・子育て支援会議の最初の役割だ。計画の各項目の作り方や手続きなどを夏までに指針として示し、市町村に参考にしてもらう。(以下略)
認可保育所:月内にも株式会社の参入全面解禁へ 厚労省
(2013年5月2日 毎日新聞)
厚生労働省は、約2万5000人の保育所待機児童の解消に向け、認可保育所への株式会社の参入を月内にも全面解禁する方針を固めた。当初は2015年4月から解禁する予定だったが、安倍晋三首相が女性の就労支援を成長戦略の中核に据えたことを踏まえ、大幅に前倒しする。
厚労省が2日の規制改革会議で表明し、認可権限を持つ都道府県や政令指定都市、中核市に通知する。
株式会社は児童福祉法上は今でも認可保育所に参入できる。しかし、企業の経営状況に保育所の存廃が左右されかねないことや、既存の社会福祉法人への配慮などから、株式会社の参入を認可しない自治体も多く、株式会社が運営する認可保育所は12年4月現在、376カ所と全体の2%にも満たない。
15年4月の子ども・子育て関連3法施行後は、自治体は株式会社であることを理由に認可を拒めなくなるが、これを前倒しする。
それはそれで早く進めてもらえばいいのだが、厚生労働省が規制改革会議に提出した資料
待機児童の速やかな解消に向けて
(平成25年3月21日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局)
の参考資料p3(全体の14枚目)をみるとこのようにある。
③ 認可制度の改善等により保育需要の増大に対応
◇ 認可制度の見直しにより、大都市部の保育の需要増大に対応
・欠格事由に該当したり、需給調整が必要な場合を除き、質を満たしたものを「認可するものとする」(認可の恣意性の排除)ことで、大都市部の保育需要に機動的な対応が可能。
株式会社であることを理由に認可を拒むことはできないが、需給調整を理由に認可を拒むことはできることになる。
そうすると、市町村・東京都の特別区においては、新規参入による競争激化を懸念する既存の社会福祉法人が市議・区議経由で圧力をかける可能性は否定できない。
またそれ以上に問題だと思うのは、認可・需給調整含めて市町村・区単位になっていること。
特に東京都では、区境いに住んでいると居住地の住所と最寄駅が違う区にあることは往々にしてある。(たとえばマンション名では「吉祥寺」とつけられているのが多い練馬区立野町とか、東横線の駅が近い世田谷区下馬など。)
それに、通勤の問題がクリアされれば母親の勤め先に近い場所での保育所ニーズもあると思う。
保育所への補助が基礎自治体単位だから需給調整も基礎自治体単位でやりましょう、というのでは、潜在的なニーズを掘り起こすことができないのではないか。
「家の近く、しかも同じ市区町村内で働く」という人が少数である以上は、保育所も越境通所を前提に考えるべきで、越境児童については居住地の自治体が補助金予算を融通するなどの方策をとるべきではないか。
そこに至る前でも、自費負担をすれば認可保育所に入ることができる、という仕組みをつくれば、需要はより顕在化し「需給調整」もより現実的なものになるのではないか?
「金持ち優遇」という批判があるかもしれないが、そういうニーズがあるのはいわゆる富裕層ではなく、育児しながら就業を続けたいというワーキングマザーだと思うので、彼女たちが自腹を切ってまで通所したいというのであれば、それを否定する理由はないように思う(本来は自腹を切らずに通所できるのが一番なのだが)。
規制「改革」というなら、制度の枠組みから見直してみるべきではないだろうか。