昨日のエントリにコメントをいただき、もう少し考えてみようと弁護士の懲戒処分の事例をググってみました。
***********************
テレビ局の番組制作者の依頼を受け、戸籍謄本や住民票などを不正に取得
2004年1月 東京弁護士会 業務停止4月
毎月数十件受任した債務整理で法律の説明や返済計画立案を事務員に任せ、弁護士任務を怠った。
2006年1月 東京弁護士会 業務停止4月
自己破産などの依頼を長期間放置した上、着手金の返還に応じなかった
2006年2月 熊本弁護士会 業務停止1年2ヶ月
パソコンソフトの説明をさせようと青葉区上杉6丁目の事務所に呼んだ出版社の男性社員に対し、「商品知識が足りない」と腹を立てて暴行を加え、胸に4週間のけがをさせた
2005年8月 仙台弁護士会 業務停止2月
相続放棄の手続きに絡み東京家裁名義の文書を偽造
2005年7月 東京弁護士会 業務停止1年
会社から任意整理を依頼されたが同10月解任され、その後1年近く預かった約3427万円を返還しなかった
2005年7月 東京弁護士会 業務停止2年
依頼人から「連絡がつかない」などの苦情が相次いだ。実際に音信不通となっていたことなどから失踪したと認定
2005年12月 福岡弁護士会 退会命令
上記の業務停止2月の懲戒請求期間中に、タクシー運転手を殴ったとして傷害容疑で逮捕され、起訴猶予処分
2006年2月 仙台弁護士会 退会命令
交通事故の保険金請求手続きで支払われた保険金約5800万円を依頼者に渡さなかった
2006年1月 第一東京弁護士会 除名
訴訟相手から受け取った和解金を依頼人に渡さず着服
2006年1月 横浜弁護士会 除名
依頼者の債務整理に当たり消費者金融から回収した金を無断で引き出したり、依頼者から預かった和解金を流用した
2006年2月 沖縄弁護士会 除名
*************************
googleでヒットした(=新聞報道された)だけでも結構あるものですね(整理していてちょっとめげました・・・)
ざっと見ると、被害金額の大小が処分の軽重に反映されているように見えますね。
でも、被害額の多寡の問題よりは依頼者の無知に乗じたかどうか、という悪性を基準にするほうが、個人的には納得する感じがします。
たとえば企業が依頼人で、相手方から受け取った和解金を弁護士が着服したような場合は、企業であるなら当然訴訟の経緯は見守っているはずですし、和解金が入金されなければおかしいと思うべきです。
一方で、個人が生まれて初めて弁護士に依頼するようなときは、何がどういう順序で進むか分からないのですから、そういう人には特に誠実にサービスを提供すべきではないでしょうか。
つまり、弁護士への依頼についても依頼者の自己責任を問えるケースと、消費者保護的な視点を考慮すべきケースに分かれるのでは、ということです。
でもそうすると、少額の個人事件はなおさら割に合わないので引き受けてがいなくなってしまうのかもしれませんね(労多くして診療報酬は少ない上にトラブルも多い小児科医の減少と似ているような・・・)
ところで上の事例を見ると、2006年になって立て続けに重い処分がなされていますが、これは世の中のコンプライアンスへの注目を反映して厳罰化が進んでいるのでしょうか、それとも悪い弁護士が増えているのかしら・・・
(おまけ)
日弁連のHPで弁護士職務基本規定というものを見つけました。
ご参考まで。
***********************
テレビ局の番組制作者の依頼を受け、戸籍謄本や住民票などを不正に取得
2004年1月 東京弁護士会 業務停止4月
毎月数十件受任した債務整理で法律の説明や返済計画立案を事務員に任せ、弁護士任務を怠った。
2006年1月 東京弁護士会 業務停止4月
自己破産などの依頼を長期間放置した上、着手金の返還に応じなかった
2006年2月 熊本弁護士会 業務停止1年2ヶ月
パソコンソフトの説明をさせようと青葉区上杉6丁目の事務所に呼んだ出版社の男性社員に対し、「商品知識が足りない」と腹を立てて暴行を加え、胸に4週間のけがをさせた
2005年8月 仙台弁護士会 業務停止2月
相続放棄の手続きに絡み東京家裁名義の文書を偽造
2005年7月 東京弁護士会 業務停止1年
会社から任意整理を依頼されたが同10月解任され、その後1年近く預かった約3427万円を返還しなかった
2005年7月 東京弁護士会 業務停止2年
依頼人から「連絡がつかない」などの苦情が相次いだ。実際に音信不通となっていたことなどから失踪したと認定
2005年12月 福岡弁護士会 退会命令
上記の業務停止2月の懲戒請求期間中に、タクシー運転手を殴ったとして傷害容疑で逮捕され、起訴猶予処分
2006年2月 仙台弁護士会 退会命令
交通事故の保険金請求手続きで支払われた保険金約5800万円を依頼者に渡さなかった
2006年1月 第一東京弁護士会 除名
訴訟相手から受け取った和解金を依頼人に渡さず着服
2006年1月 横浜弁護士会 除名
依頼者の債務整理に当たり消費者金融から回収した金を無断で引き出したり、依頼者から預かった和解金を流用した
2006年2月 沖縄弁護士会 除名
*************************
googleでヒットした(=新聞報道された)だけでも結構あるものですね(整理していてちょっとめげました・・・)
ざっと見ると、被害金額の大小が処分の軽重に反映されているように見えますね。
でも、被害額の多寡の問題よりは依頼者の無知に乗じたかどうか、という悪性を基準にするほうが、個人的には納得する感じがします。
たとえば企業が依頼人で、相手方から受け取った和解金を弁護士が着服したような場合は、企業であるなら当然訴訟の経緯は見守っているはずですし、和解金が入金されなければおかしいと思うべきです。
一方で、個人が生まれて初めて弁護士に依頼するようなときは、何がどういう順序で進むか分からないのですから、そういう人には特に誠実にサービスを提供すべきではないでしょうか。
つまり、弁護士への依頼についても依頼者の自己責任を問えるケースと、消費者保護的な視点を考慮すべきケースに分かれるのでは、ということです。
でもそうすると、少額の個人事件はなおさら割に合わないので引き受けてがいなくなってしまうのかもしれませんね(労多くして診療報酬は少ない上にトラブルも多い小児科医の減少と似ているような・・・)
ところで上の事例を見ると、2006年になって立て続けに重い処分がなされていますが、これは世の中のコンプライアンスへの注目を反映して厳罰化が進んでいるのでしょうか、それとも悪い弁護士が増えているのかしら・・・
(おまけ)
日弁連のHPで弁護士職務基本規定というものを見つけました。
ご参考まで。















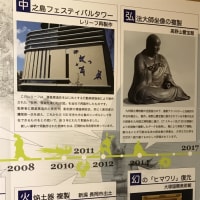
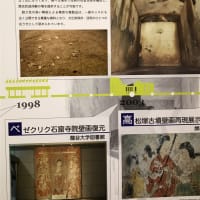









go2cさんのご指摘のように、消費者保護的な視点は必要ですね。確かに個人に過度に自己責任を要求するのは酷ですね。弁護士に説明義務があるのは当然ですが、本来は、弁護士と依頼人がお互いに信頼し合って良い関係を築くのが理想ではないでしょうか。私の思い過ごしかもしれませんが、依頼人の方でも、弁護士費用を、弁護士のサービスに対する対価ではなく、自分の得たい結果(判決等)に対する対価と勘違いしている人がいるような気がします。
訴訟相手側が敗訴後若しくは敗色濃厚になった時に、相手側の弁護士と内輪もめをしているのを、実際に2、3度、目の当たりにしたことがあります。どちらに非があったのかは分かりませんが(弁護士側が勝訴の確率が高いと吹き込んだのか、依頼人側が弁護士の意見に耳を貸さず、捕らぬ狸の皮算用をしていたのか)、非常に見苦しいと思いました。
>勉強不足を理由として懲戒という事例もありえますが、これは少数です
そうなんですか。そういう懲戒事由があること自体は弁護士自治が健全に機能している感じはします。
「弁護士職務基本規定」を改めて読んでみると、実際は依頼者の利益をはかったり、先進(先鋭?)的な弁護活動やリーガルアドバイスをされる方にとってはけっこう微妙な部分もありそうですね。
taghitさん
>弁護士費用を、弁護士のサービスに対する対価ではなく、自分の得たい結果(判決等)に対する対価と勘違いしている人がいるような気がします。
専門家に依頼すると、結果まで保証されるように思ってしまうのは仕方ない部分もあると思いますし、逆に常に「敗訴するかもしれない」と留保しまくりの弁護士では商売にならないので難しいところですね。
一方で弁護士の斡旋・紹介は弁護士法で禁じられてますので、いいマッチングというのは結構難しいのかもしれません(ビジネス誌の「人気弁護士ランキング」の記事などを見ると、投票の母数が100弱だったりしますしね)
なので、企業における弁護士選定もそうで、某有名(友好的)M&A案件の担当(彼は法務でなく経営企画とか社長室のような特命案件を受ける地位にいる)からその案件における弁護士選定の経緯を聞いたときは、ちょいと顎がはずれかけました(以下自粛)
そういう意味ではneon98さんのような新進気鋭の弁護士の方々がマーケット開拓する余地も十分にあるように思います。
(この項続きそうですw)