2月5日(火)の夜に、神宮球場脇にある日本青年館ホールで、文楽を見る。18時30分開演、15分の休憩を挟み20時40分の終演。日本青年館ホールは1階席800席、2階席450席ぐらいのホールだが、観客は1階席の半分も入っていなかった。これまで東京の会場になっていた国立小劇場は500席強、大阪の文楽劇場は700席ぐらいだから、1階席だけでもかなり大きい。観客は国立劇場時代よりも高齢者が減った印象。場所が変わって足が遠のいた可能性も高い。
日本青年館ホールは、1階席の傾斜がきちんとついていて見やすいホールだが、2階席もあり天井が高いので、文楽を聴くとかなりの違和感を感じた。三味線や太夫の声が響きにくく迫力が感じられないだけでなく、残響時間が長いので太鼓の音なども響きすぎる感じがある。演劇を上演しても大きすぎるような印象で、この大きさならば、ミュージカルかオペレッタ向きと感じられた。
国立劇場は再開発の業者も決まらず、いつ再開できるかわからないような状況だが、こうしたことならば、現在の国立劇場を修復して使った方がよいのではないかという気がする。
さて、演目の方は最初の「五条橋」は牛若と弁慶の出会いを描く20分弱の短い作品。若手の研修発表みたいな舞台だが、三味線の清志郎が引っ張った印象。
休憩の後、「双蝶々曲輪日記」だが、これは最初に「難波裏喧嘩の段」が付いているが、メインは「引窓」。前半の「喧嘩」は太夫がたくさん出て、役ごとに語る形式で、若手の発表会。注目は碩太夫で、最若手だろうが美声を響かせた。今後とも注目したい。「引き窓」は前半が芳穂太夫と三味線の錦糸。切が千歳太夫と三味線の富助。千歳太夫は相変わらずの熱演。今回は、濡髪の語りに力士らしいムードが漂い、一段と芸がよくなった感じ。現在の太夫の中では最も安心して聴ける。千歳太夫は切場語りとなったので、弟子が茶を出して、語りの間は床の脇に座って待機する習わしだが、今回は碩太夫がお茶を出すとすぐに引っ込んでしまった。舞台の作りの都合もあったのかも知れないが、伝統をなくしてほしくない。
まだ道路の横に雪が残っていて息が白くなる中を帰宅。ごぼうと人参の胡麻和え、けんちんうどんを食べる。飲み物は京都の純米大吟醸。
日本青年館ホールは、1階席の傾斜がきちんとついていて見やすいホールだが、2階席もあり天井が高いので、文楽を聴くとかなりの違和感を感じた。三味線や太夫の声が響きにくく迫力が感じられないだけでなく、残響時間が長いので太鼓の音なども響きすぎる感じがある。演劇を上演しても大きすぎるような印象で、この大きさならば、ミュージカルかオペレッタ向きと感じられた。
国立劇場は再開発の業者も決まらず、いつ再開できるかわからないような状況だが、こうしたことならば、現在の国立劇場を修復して使った方がよいのではないかという気がする。
さて、演目の方は最初の「五条橋」は牛若と弁慶の出会いを描く20分弱の短い作品。若手の研修発表みたいな舞台だが、三味線の清志郎が引っ張った印象。
休憩の後、「双蝶々曲輪日記」だが、これは最初に「難波裏喧嘩の段」が付いているが、メインは「引窓」。前半の「喧嘩」は太夫がたくさん出て、役ごとに語る形式で、若手の発表会。注目は碩太夫で、最若手だろうが美声を響かせた。今後とも注目したい。「引き窓」は前半が芳穂太夫と三味線の錦糸。切が千歳太夫と三味線の富助。千歳太夫は相変わらずの熱演。今回は、濡髪の語りに力士らしいムードが漂い、一段と芸がよくなった感じ。現在の太夫の中では最も安心して聴ける。千歳太夫は切場語りとなったので、弟子が茶を出して、語りの間は床の脇に座って待機する習わしだが、今回は碩太夫がお茶を出すとすぐに引っ込んでしまった。舞台の作りの都合もあったのかも知れないが、伝統をなくしてほしくない。
まだ道路の横に雪が残っていて息が白くなる中を帰宅。ごぼうと人参の胡麻和え、けんちんうどんを食べる。飲み物は京都の純米大吟醸。










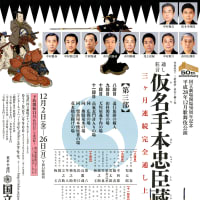
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます