つまらないことをずっと書いてるな、こいつ。
と思っている方。お待たせいたしました。これが最後です。
血液ガスなんて、電子カルテや部門システムに取り込まれているからそれで終了じゃん、と思うかもしれないが、これまたうまく行かない。
まず、FiO2が入力されていないことが多い。APACHEではA-aDO2、SAPSやSOFAではPF比を使用するので、どちらにしろFiO2が必要。臨床を考えてみても、これらの数字が計算されて画面に表示されていた方が便利だと思うのだが、僕の経験では入力している施設はだいたい4分の1程度。血液ガスを機械に入れるときに、バーコード認証とかベッド番号の入力とかをする機会があるが、その時にFiO2も入力すればいいだけなのに。
じゃあこれから入力しようと思っても、そうはいかない。血液ガスの機械が情報を部門システムや電子カルテに送らないといけないし、部門システム・電子カルテ側はそれを受け取ってかつ表示しないといけない。二つのシステムの変更が必要で、そのためには時間とお金がかかってしまう。
血液ガスの取り込み時には他にも問題がある。それは検体の種類。データベースへの取り込みに必要なのは動脈血の情報のみだけど、静脈血の血液ガスを見ることもある。pHとか電解質とか血糖とか乳酸とかも分かるからね。他にも、胸水のpHとか髄液の乳酸とかも測定することがある。ということは、血液ガス測定時にはFiO2だけじゃなくて検体情報も入力しないといけない。この習慣のない施設も珍しくない。
電子カルテ・部門システムの導入時・改訂時にFiO2の機能を追加すること、そして機械に検体を入れるときにFiO2と検体種類を入力する習慣を作ることが必要。
ただし、部門システムではこの対応をしてくれるけど電子カルテはしてくれない、ということが起こる。理由は不明。でも、電子カルテで血液ガスのFiO2も取り込んで表示しているという話は聞いたことがない気がする。
以上で終了。
他にも工夫はいくつかあるけど、主だったところは書いたと思う。
まとめると、
・自動取り込みは思っているほど簡単じゃない。
・システムの変更にはお金も時間もかかるので、導入時や改訂時に行うべき。
・機械の問題だけでなく、医療者の習慣の変化も必要。ただし、バイタルサインをちゃんと記録するとか、正しい日時を入力するとか、PF比を計算するためFiO2を入力するとか、データベースのためじゃなくて臨床においてするべきことをちゃんとやる。
・電子カルテによるデータベースに必要な情報の自動取り込みは現状では難しい。
という感じか。
上記を大変だと思うか、これだけやってしまえば後は簡単にデータ収集ができると思うか。
それはあなた次第。
と思っている方。お待たせいたしました。これが最後です。
血液ガスなんて、電子カルテや部門システムに取り込まれているからそれで終了じゃん、と思うかもしれないが、これまたうまく行かない。
まず、FiO2が入力されていないことが多い。APACHEではA-aDO2、SAPSやSOFAではPF比を使用するので、どちらにしろFiO2が必要。臨床を考えてみても、これらの数字が計算されて画面に表示されていた方が便利だと思うのだが、僕の経験では入力している施設はだいたい4分の1程度。血液ガスを機械に入れるときに、バーコード認証とかベッド番号の入力とかをする機会があるが、その時にFiO2も入力すればいいだけなのに。
じゃあこれから入力しようと思っても、そうはいかない。血液ガスの機械が情報を部門システムや電子カルテに送らないといけないし、部門システム・電子カルテ側はそれを受け取ってかつ表示しないといけない。二つのシステムの変更が必要で、そのためには時間とお金がかかってしまう。
血液ガスの取り込み時には他にも問題がある。それは検体の種類。データベースへの取り込みに必要なのは動脈血の情報のみだけど、静脈血の血液ガスを見ることもある。pHとか電解質とか血糖とか乳酸とかも分かるからね。他にも、胸水のpHとか髄液の乳酸とかも測定することがある。ということは、血液ガス測定時にはFiO2だけじゃなくて検体情報も入力しないといけない。この習慣のない施設も珍しくない。
電子カルテ・部門システムの導入時・改訂時にFiO2の機能を追加すること、そして機械に検体を入れるときにFiO2と検体種類を入力する習慣を作ることが必要。
ただし、部門システムではこの対応をしてくれるけど電子カルテはしてくれない、ということが起こる。理由は不明。でも、電子カルテで血液ガスのFiO2も取り込んで表示しているという話は聞いたことがない気がする。
以上で終了。
他にも工夫はいくつかあるけど、主だったところは書いたと思う。
まとめると、
・自動取り込みは思っているほど簡単じゃない。
・システムの変更にはお金も時間もかかるので、導入時や改訂時に行うべき。
・機械の問題だけでなく、医療者の習慣の変化も必要。ただし、バイタルサインをちゃんと記録するとか、正しい日時を入力するとか、PF比を計算するためFiO2を入力するとか、データベースのためじゃなくて臨床においてするべきことをちゃんとやる。
・電子カルテによるデータベースに必要な情報の自動取り込みは現状では難しい。
という感じか。
上記を大変だと思うか、これだけやってしまえば後は簡単にデータ収集ができると思うか。
それはあなた次第。











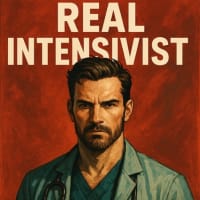












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます