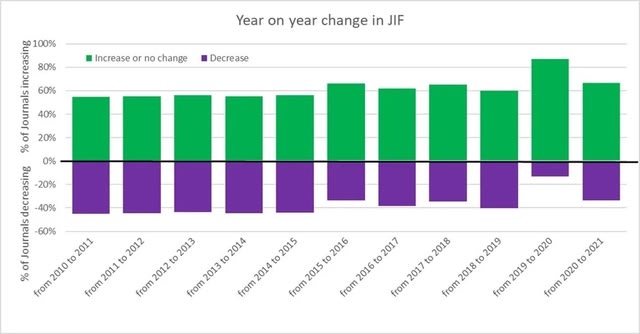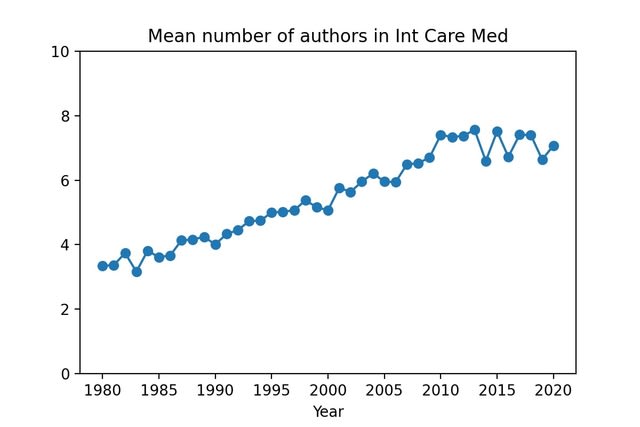Gathier CS, Zijlstra IAJ, Rinkel GJE, et al.
Blood pressure and the risk of rebleeding and delayed cerebral ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage.
J Crit Care. 2022 Dec;72:154124. PMID: 36208555.
100mmHg以下のMAPは再出血のリスク低下と関連し、60mmHg以下のMAPはDCIのリスク上昇と関連する。
Cacioppo F, Reisenbauer D, Herkner H, et al.
Association of Intravenous Potassium and Magnesium Administration With Spontaneous Conversion of Atrial Fibrillation and Atrial Flutter in the Emergency Department.
JAMA Netw Open. 2022 Oct 3;5(10):e2237234. PMID: 36260333.
AFではKとMgの投与と洞調律復帰に関連があったが、AFLではなかった。
SAHの患者さんでは血圧の話は必ずするし、AFになると必ず電解質が話題になる。でも、いまだに観察研究が行われているレベル。
まだまだ世の中には研究ネタがたくさん。ただしRCTのネタであって、これ以上観察研究を積み重ねても情報は増えない。
エネルギーのある方、お待ちしております。
Blood pressure and the risk of rebleeding and delayed cerebral ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage.
J Crit Care. 2022 Dec;72:154124. PMID: 36208555.
100mmHg以下のMAPは再出血のリスク低下と関連し、60mmHg以下のMAPはDCIのリスク上昇と関連する。
Cacioppo F, Reisenbauer D, Herkner H, et al.
Association of Intravenous Potassium and Magnesium Administration With Spontaneous Conversion of Atrial Fibrillation and Atrial Flutter in the Emergency Department.
JAMA Netw Open. 2022 Oct 3;5(10):e2237234. PMID: 36260333.
AFではKとMgの投与と洞調律復帰に関連があったが、AFLではなかった。
SAHの患者さんでは血圧の話は必ずするし、AFになると必ず電解質が話題になる。でも、いまだに観察研究が行われているレベル。
まだまだ世の中には研究ネタがたくさん。ただしRCTのネタであって、これ以上観察研究を積み重ねても情報は増えない。
エネルギーのある方、お待ちしております。