
「ラスコー展」の感想を続けます。

「ラスコーの洞窟画」を見て、思ったことは、とても臨場感があるひとつの世界に立ち会った、ということでした。

19000年前に、人類が絵というものを描き始めたとたんに、非常にレベルの高い絵画が描かれた、という事実に、驚くばかりでした。

そしてそれが、誰も行けないような真っ暗な洞窟を長い時間かけて通りながら、同じ洞窟内でもさまざまな方法で作られた壁画群が作られているということを確認しながら、明かりの無い洞窟内では「見る」ということ自体が不可能な状態で、それらを「見る」こと、、これはなんともふしぎな事態ではないでしょうか?

旧石器時代の洞窟壁画について調べようと思っても、資料自体がほとんどありませんでした。
「別冊宝島・ラスコーと世界の壁画」では、同「ラスコー展」監修者の海部陽介氏が次のように語っています。
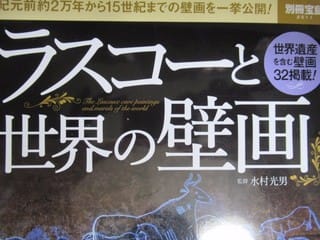
*****
(引用ここから)
●海部氏
現代の芸術家は、多くの人に作品を見てもらおうとしますが、洞窟の奥に描かれた壁画は、とても人に見てもらうために描かれたとは思えません。
絵に対する感覚が私達とは違っていたと思うので、現代のセンスで壁画を見てはいけないと思いますね。
この壁画は、「人間が他の生き物と変わり始めた」ことを示しているのだと思います。
生き物は、生きてゆくうえで絵なんか必要なく、描かなくてもいいんです。
でも、クロマニヨン人はわざわざ真っ暗な洞窟に入って、壁画を描いた。
これが人間の不思議さで、ここから「人間の世界が始まった」ということ。
これぞ「ホモ・サピエンス」なんです。
今までやらなかったことをやりだした、ということをどう理解するかだと思います。
〇質問
ラスコー壁画は、他の壁画と比べてどのような特徴があるのでしょうか?
●海部
一つは、「よく残っている」ということです。
クロマニヨン人の壁画でナンバー1を挙げろと言われたら、ラスコーですね。
ただ、ラスコーのすごさは現地に行って、実際に見ないと分からないですよ。説明のしようがないですね。
〇質問
今回の「ラスコー展」の見どころや、来場者に見てもらいたいポイントは、どこでしょうか?
●今回は実物大で立体的に再現された壁画が展示されるので、まずは壁画をよく見てもらいたいですね。
ぱっと見ただけでは分からないポイントがいくつもあって、壁画が単なる落書きではないことがよくわかると思います。
遠近法など、絵の技術、技量や、大きく描かれた牛と小さく描かれた馬の配置など、全体の構図も見てもらいたいです。
ちなみにラスコー壁画では、牛だけが大きく描かれていて、馬はどれも大きく描かれていないんですよ。
また、「井戸の場面」という壁画は、珍しく物語性を感じるもので、他の壁画が色彩豊かなのに比べて黒一色。
しかもこの描かれた空間は、洞窟の一番深いところにあって、他の空間が絵で満たされているのに対して、ここには「井戸の場面」と、描きかけの馬の絵があるだけと、実に不思議な空間なんです。
このように「ラスコーの洞窟」と一口に言っても、いろいろな部屋があって、それぞれに意図があります。
この展示会は「ラスコー」の全体を分かってもらえるようになっていますので、ぜひ会場に足を運んでいただき、実物大の「ラスコー壁画」を体感してほしいですね。
(引用ここまで)
*****

そこで、他の参考資料として、デヴィッド・ルイス・ウィリアムズ著「洞窟の中の心」を読んでみました。
とても分厚いです。本の「序文」を記してみましょう。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
*****
(引用ここから)
本書の出版は、後期旧石器時代の芸術調査に費やされた20世紀の100年間の終わりと、新しい世紀の幕開けを記念するものとなるだろう。
私たちの知識量は、確かにとてつもなく増大した。
大地の下に潜む遺跡に関しても、地上に残された遺跡に関しても、私たちは以前よりずっと多くを知っている。
だが、これだけの情報量があるにも関わらず、その時代の人々がフランスやスペインの、光の入らない鍾乳洞の奥深くに潜り込んでイメージを描いたのはどうしてなのか?
また彼らが洞窟の外、その近くの日当たりの良い場所でも、石や骨や牙や角の小片にイメージを刻んだのはなぜか?という謎には、まだまだ接近できていないように思える。
「私達はいかにして今日のような人間になり、またその途上で芸術を創造するようになったのか?」という考古学上の大問題は、いまだに私たちを悩ませている。
今日の研究において不足しているのは、私たちがすでに持っているデータに〝新たな意味″を与える方法である。
第1章では、19世紀になされた後期旧石器時代の芸術の発見が、ダーヴィンによる「進化論」の大きなインパクトと共に、私たちが「人間とは何か?」について抱いている考えや、自然や歴史の中における人類の位置づけを考える道筋に根本的な変化をもたらしたことを解説する作業から始める。
しかし、〝非物質的な領域の実在‴についての前ダーヴィン的な思考方法と信仰は、大幅に衰えたとはいえ、決して消滅したわけではなかった。
あらゆる生き物と地球は神の意思により出現した、とする唯一絶対の奇跡を論じる創造主義者は、全体としてみれば、未だに存在する。
現代人の思考に見られる、この居心地の悪い二重性は、人間の脳に深く根差しているということを、私はここで論じたい。
第2章では、脳の働きについての議論への布石として、後期旧石器芸術の発見を巡る時代状況や、当時の熱のこもった論争の状況を説明する。
第3章では、その後先史芸術に関する議論を前進させた一連の解釈を検証する。
人類の進化は、一つの道に沿ってきた。
つまり私たちは、ある明々白々な理由によって芸術を創造し始めた、ということである。
第4章では、根拠の確かな仮説と無意味な仮説とを峻別するために、〝先史時代における知性と意識の役割″について考察する。
多くの研究者は人間の意識というものの高度な複雑さから目を背けつつ、そのうちたった一片に注意を集中してきたということ。
また、心の活動と社会的なコンテクストの相互作用についての検証を行う。
ある共同体の中で共有されている、人間の経験を巡る思想は、個人の心的活動へといかにして侵入することになるのか?
また社会的にコントロールされた特定の心的状態へのアクセスが、いかにして社会的な差異意識の基礎となってゆくのか?
第5・6章には、心的な想念が、岩絵(ロックアート)へと翻訳される2つのケーススタディを提出した。
それらは南部アフリカのサン族と、北アメリカ西部の先住民族の例である。
しかし私は、これらのケーススタディからの類推によって、後期旧石器時代における西ヨーロッパの芸術について論じるつもりはない。
南部アフリカと、北アメリカの岩絵は、心的な想念が岩石や洞窟の上に描かれた視覚的イメージに変換される時、人間の中で何が起こるのかを知るための啓発的な事例にすぎない。
第7章では、後期旧石器人が私たちの言う「意識変容状態」を利用して社会を作り出してきたという可能性や、彼らが社会関係を確立したりそれを制限したりする手段として、想像力を活用してきた可能性を探求する。
ここでは「原初意識」と、「高次意識」という2つの種類の意識が検討に付される。
イメージの造形は、「高次意識」が発達を遂げることによって初めて可能になったのではないか、という議論をここで行う。
西ヨーロッパにイメージの制作(芸術)、宗教、社会的差異というものが現れるのは、まさにこの時期なのである。
この特定の時期と場所にあって(本書は全世界をカバーするものではない)イメージの制作、宗教社会的差異は、一まとめのパッケージセットとして現れたのだ。
第8章は、後期旧石器時代の洞窟芸術にまつわる非常に謎めいたある特徴に焦点をあてるために、本書の前の方の章で展開させた知見を応用する。
洞窟芸術という難問は、最初に私たちの前に現れた時のように解決不能な問題ではない。
そうではなくて、洞窟芸術は互いに重なり合い、多要素的ではあるが、統一的な意図を伴って、私たちの前に現れている。
その解釈の有効性を証明するために、私は後期旧石器芸術の幅広い現象そのものに注意を払う。
第9章に入り、2つの対照的な洞窟を採り上げる。
装飾された洞窟は、後期旧石器時代の社会とその思想の単なる反映ではない。
そうではなくて、洞窟芸術は同時代の人々の生活形成に深く関わっていたのである。
最後に第10章では、同じことを反対の視点から検証する。
ここでは人間社会の起源、その緊張関係、社会的地位の格差といった問題を扱う。
後期旧石器時代は、エデンの園ではない。
前人類的段階であることをやめ、完全な現生人類になるやいなや、私たちの祖先は禁じられた果実を味わったはずなのである。
わたしの思索にとって、後期旧石器時代に創造された西ヨーロッパの地下芸術ほど、考古学的な謎を感じさせるものはない。
狭く閉ざされた完全な闇に包まれた地下通路を1キロ以上も這いつくばって進み、ぬかるんだ起伏で足をすべらせながら、暗がりの湖や隠された河へと歩みを進めた者は、
その危険きわまりない旅の最後に、いまや絶滅した毛深いマンモスや堂々たるこぶを持つ野牛の絵画に遭遇する。
それを見た者の意識は、もはや後戻りできない変容を体験するだろう。
全身泥まみれになって、へとへとに疲れ果てながらも、洞窟の探求者はそこで、人間の心の中に果てしなく広がる「未知の大陸」に脅威の眼を見張ることになるのである。
(引用ここまで)
*****
非常に誠意のこもった論文なのですが、わたしにはなかなか、タイトルとなっている「洞窟の中の心」というものが、これだ、という感覚で理解できたとは言えませんでした。
しかし、問題は科学者が手順を踏んで慎重に実験を進めなければならないように、慎重に考察されなければならない、ということだけは理解できました。
次の記事で、各章を必要がある部分だけおおまかにまとめてみたいと思います。
人間は原初、世界をどうとらえたのか?という、一大テーマではあるのです。
 ブログ内関連記事
ブログ内関連記事
「古代人の音楽会・・3万5千年前のフルートはどんな音色だったのだろうか?」
「ネアンデルタール人と共に生きていたら。。彼らはなぜ滅びたのだろうか?」
「人類は何かを知っているのだ、だが何を?・・ナスカ・イカの線刻石の研究史(6)」
「クロマニヨン人はアトランティスからやってきたのだろうか?・・英文学者の海底探検」
 「その他先史文明」カテゴリー全般
「その他先史文明」カテゴリー全般















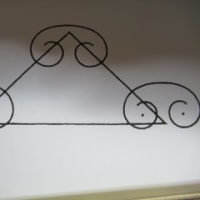







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます