
文学の講義でプラトンを教えているうちに、そのプラトンの説く“アトランティスの地”の探策に携わることとなったデビッド・ジンクさんの著書「海底大陸アトランティス」のまとめ部分の紹介を続けます。
古地磁気学や地球科学と、エドガー・ケーシーたちの言っていることを突き合わせて、整合性を見ようとしています。
内容は本の本篇の中で資料を集めて検証してあるものです。
長くなったので、また2つに分けます。
*****
ケーシーの資料によれば、アトランティス大陸のサッガーソ海地方(バハマ諸島沖合の大西洋上あたり)は、大陸が最終的に崩壊する7500年前の紀元前18200年に崩壊した。
200年後に(紀元前18000年)地球の磁場の両極が正常な状態に戻った。
そして紀元前15000年から10000年にかけて、北極の地軸がハドソン湾から現在の場所に移動した。
前にも示唆したように、この現象は地球の大変動に関係があり、地殻がますます不安定な状態になったのではないだろうか?
紀元前10700年。
ケーシーによれば、アトランティスが崩壊した最後の年だ。
彼はまたビミニが紀元前28000年以後に残ったアトランティスの2つの島の一つ、“ポセイディア”の一部だったとも言っている。
キャロルのリーディングによれば、アトランティス人がビミニその他の新世界の植民地に移住を開始したのもこの頃である。
紀元前10376年
ふたたび地球の磁場が逆転した年。
“イエーテボリの磁気宙返り”、、この逆転はチャールス・ハプグッドが主張している、紀元前15000年から10000年にかけての最後の磁極の転換と関連があるかもしれないし、またケーシーが唱えている年代とも非常に近い。
紀元前9600年
エミリアーニによれば、世界的な洪水の年。
酸素同位元素でメキシコ湾の地層を測定した結果から推定される。
高緯度で氷河が急速に溶け、洪積期が終わった。
紀元前9570年
プラトンがアトランティスの最後とした年。
ケーシーとプラトンでは1100年程違いがあるが、これは地球の天変地異が一度ではなく、2度あったことを示唆しているのではないだろうか。
紀元前6031年
キャロルによると、地殻の激変がビミニの市街地を破壊した。
この頃ビミニロードは海面上9.6メートル、あるいは、24メートル上にあったと推定される。

紀元前4021年
ビミニ遺跡と関係のある文明が、この地域を放棄した。
この後、少なくとも独立した環カリブ海文明である“ルカヤ・インディアン文化”によって最終的に支配されるまでの間に、エジプト人、フェニキア人、ケルト人などが大西洋を渡ってきて、ビミニ文明に強い影響を及ぼしたものと推定される。
フェニキア人とケルト人はニューハンプシャーのミステリーヒルに、巨石に刻みこんだ碑文を残している。
サンライズ・ゴードンは紀元前3000年から1200年ごろにかけて、青銅器時代の海の首領たちが、大西洋を渡って航海をしていたと推測している。
エジャートン・サイクスは、ビミニは有史時代以降、常に占領されてきたと考えている。
*****
とてもややこしい文章ですが、筆者はビミニはアトランティスの一部であるというケーシーの説と、アトランティスと同時期に存在した別のものでアトランティス人を受け入れたという説を同時に述べているように思います。
また、ビミニに住んでいたアトランティス人あるいはその末裔が、ビミニを捨てた後に、別の文明が存在した痕跡がある、と言っているのだと思います。
ビミニの海底という一つの場所に、重層的にいくつもの文明が堆積しているのを、直観しているのではないかと思われます。
写真は、同著より「アトランティスの大洪水からの脱出を描いたと見られるマヤの石の小壁」
Wiki古地磁気学より
古地磁気学(こちじきがく、paleomagnetism)とは、岩石などに残留磁化として記録されている過去の地球磁場を分析する地質学の一分野。
火山岩や堆積岩には、それができた時のできた場所の磁場が記録されており、それを分析することで、地磁気の逆転や大陸移動の様子などを調べることができる。
残留磁気からは伏角と偏角が得られ、偏角からは極の方角、伏角からは極の距離がわかる。
当初は火成岩に対してしか使えなかった。しかし、1950年代に磁力計の感度が大きく向上し、堆積岩にも使えるようになった。
また、洋上から深海底(ほぼ全てが玄武岩)の残留磁気を測定できるようにもなった。
わかるのは厳密には極ではなく磁極である。
ただし、磁極と極は過去においても大きくは違わないと考えられ、また、数千年以上の時間スケールで均せば、磁極の分布の中心は極に一致すると考えられている。
伏角を得るためには当時の水平面を推定する必要がある。
wiki地球科学より
地球科学は、地球磁気圏から地球内部のコアに至るまで地球に関するあらゆる学問を総称した名称であり、内容は地球の構造や環境、歴史などを目的として多岐にわたる。
地球に関する研究は、石炭の発掘などの実用的な目的の中で地層の層序や堆積構造などを解明する地質学が発達したことに始まるが、自然史学的な色彩が濃かったために比較的進歩は遅く、20世紀になってようやく地球に対する認識が大きく進展してプレートテクトニクスの発見などの飛躍を見せた。
しかしながら地球に関してはまだ解明されていないことが多く、まだ本格的な研究は始まったばかりと言っても過言ではない。
地球は実質的に人類の生活できる唯一の星であり、資源の利用法など、人類の進歩のためにその解明の必要性はむしろ高まりつつある。
また、近年大きな関心を寄せられている地震予知や環境問題、火星探査などに直接関わる分野として注目され始めており、今後の更なる発展が期待される学問である。
地球科学あるいは地球惑星科学は、ひとつの学問体系というよりは地球に関する様々な学問分野の総称であり、地質学・鉱物学・地理学・地球物理学・地球化学などに細分化されているのが現状である。
またその研究対象も分野によって大気圏・表層環境・生命圏・地球内部・太陽系など多様であるが、最近ではこれらの相互関係に重点を置いて地球全体をひとつのシステムとしてとらえ総合的に研究しようとする地球システム学(惑星システム学)が提唱されている












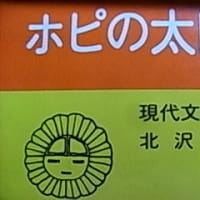

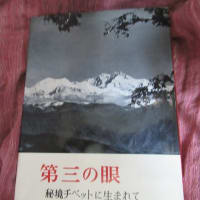







ローマの上にイタリアがある。というような感じですね。
ヨーロッパの元にガリアがあって・・・みたいな。
その方が、自然ですよね。
私も『地球の内部で何が起こっているのか?』
という本で、読んだのですが、地軸の移動は
何度も起こっているそうですね。
日本列島も、2500年ぐらい前に、
今のカタチに扇状にぱっくり開いたのではないか?
というのが、日本海の海底の火成岩?の調査で
わかったそうです。
最近は、いろいろな説がありながらも、真実は1つではなく
両方また全部のことが多い。と個人的に思っています。
コメント、ありがとうございます。
筆者はたいへん苦悩しつつ書いているんです。
なぜならば、彼はケーシーや霊能者の言うことを否定する根拠をもたず、それらと科学を同時に認めることに学者魂を捧げているからです。
そのため、話がばらばらと散らかった印象になり、まるで印象派の絵画のように像を結ばないかっこうになっています。
筆者は、先史文明を調べれば調べるほど、人類はかつて大いなる文明を持っていたと思わざるをえず、世界中に広がる先住民族はその末裔である可能性があることを知るのです。
先住民族たちは驚くべき伝承を持ち、驚くべき出自を語ることに直面することになるのです。
その出自とは、プレアデス星やシリウス星であり、その主張は不思議なほど世界中で一致しています。
デビッド・ジンクさんも、プレイオンなるプレアデス星の人々がアトランティスを作ったという説を説いているのですが、あまりにも混沌としてしまうので、今回は引用しないつもりですが、これは避けて通れない話なのだと、わたしは思っています。
それらの関連を辿ることが本ブログのテーマなのですが、デビッド・ジンクさんも、すっかりミイラ取りがミイラになって、先史文明のとりこになっていますね。