一般的な歩行では、手足交差型の動作になるため腰をひねりながら移動する。
このときの体幹のねじれをなくして、古来の日本人が着物が着崩れないよう自然にしていたと推測される動きがナンバである。
ところが、トップアスリートのランニング動作を解析すると、意外にも「ナンバ」の動きに相通ずる動きが見られるという。
『コーチング・クリニック』5月号(ベースボール・マガジン社) の巻頭企画、新連載「スポーツ動作分析最前線」によると、一流のスプリンターでは腰のひねりによらずに推進力を生み出していることがわかったそう。(深代千之先生執筆記事)
(2年ほど前、深代先生の著書『運動会で1番になる方法』(アスキー刊)に載っていた股関節活性化ドリルを実施したおかげで、ハーフのタイムが急激に短縮された体験がある。やりすぎて故障もしてしまったが……)
「以前は、スプリント走においても、歩行と同じように、ヒップスイング(骨盤の回転)によってストライドを伸ばすと考えられていました。
実際のランニング中に、本当にトップアスリートは上体と骨盤がねじれて、ヒップスイングが起きているでしょうか」
調べてみると、ウォーキングとは逆のヒップスイングであることがわかってきた。
「ランニング速度が速くなるほど、肩が少し先取りして回転し、骨盤が追随して回転するというように、徐々にほぼ同時に同じ方向に回転することがわかりました。
つまり、ウォーキングでは腰をひねりながら移動し、ランニングでは腰をひねることなく移動しているということです。
ランニングでは、接地期においては、キック脚側の骨盤は常に前方回転の加速度が大きいほど走スピードが大きいという結果が得られたのです。
すなわち、ウォーキングでは骨盤の回転の大きさでストライドやスピードを稼いでいて、スプリント走では骨盤回転の一瞬の力でスピードを導いているのです」
ひねらずに腰が前方回転している状態のとき、無理なくスピードが出るということらしい。
そういえば刀水ACでご指導いただいているFコーチが、「ナンバと言わなくても、速いランナーの自然な動きの中に、ナンバと呼ばれる動きが含まれている」と、かねがね語っておられたのは、このことか。
この骨盤回転が、「腰の切れ」といわれる、スピードの原動力のようである。
ところで、スプリント小説と駅伝小説がノミネートされ話題となった今年の「本屋大賞」の受賞作が昨日発表され、短距離が勝利をおさめた。なにせ全3巻物で揃い価5000円近く、まさに「本屋さんが売りたい本」であるから、予想通りの結果ではあった。
朝、近所で唯一の土の小道 (往復で300mほど) を一本歯の高下駄でナンバ歩き30分。(約2km) 散歩の犬たちとその飼主が不審な目で見る。
最新の画像[もっと見る]


















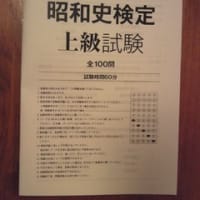








今夜は兄弟で名残を惜しんでトランプ大会です。
こちらは丸一日がかりで大掃除で、くたびれ果てた……。
帰宅したら、家中がきれいになっていて、すがすがしいです。感謝感激!