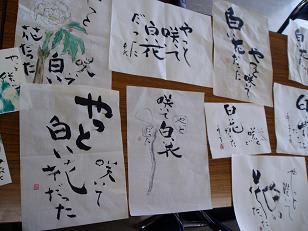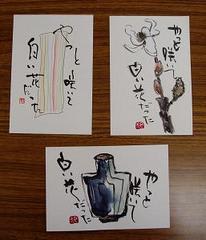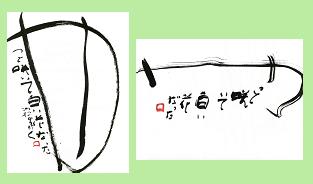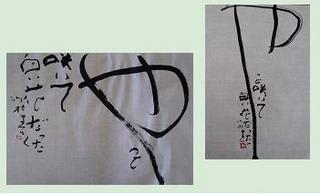龍門造像記 節臨 (半紙大 和紙)
臨書は古典ありきで、その書き手との「対話」が魅力。
臨書とは、古典や手本を見ながら書くこと。(節臨は一節を臨書したこと)
絵でいうところのデッサンかな・・。
臨書は、逆に一切のことから解放されて、自由に生きられる場所が
そこにあるという、無限の創造の世界が広がっている。
臨書は、技術だけでは表現できないものだと思う。
古典の書の、点画の位置や長さ、角度をいくら研究して同じに書けても
それは、マニュアル通りに注文を繰り返す、どこぞやの店員さんと同じで
感激も体温も感じない。
ソツなく書かれたものには、ふ~んって思うだけで、きっと震えない
古典と向き合ったとき、どんなものでもいい、心の底からの感動の
リズムを発見できなければ、本物の臨書にはならない。
感受する、そして感じたものを、包み隠さずさらけ出せたとき、
「個性」が見つかるのかもしれないですね。
それはたぶん、書だけに限らず、人との関わりも同じ。
今の若い世代(20代位?)は、争いたくないから、
人と深く関わることを避けるらしいです
でも人に興味がないから、自分も見つけられないんじゃないかな。。
人は人の中にいて初めて、自分を知るんだと思うから
臨書をしていて、ふとそんなことを考えた。
かく言う私も、まだまだ、隠しているのかもしれないけれど。。
臨書は古典ありきで、その書き手との「対話」が魅力。
臨書とは、古典や手本を見ながら書くこと。(節臨は一節を臨書したこと)
絵でいうところのデッサンかな・・。
臨書は、逆に一切のことから解放されて、自由に生きられる場所が
そこにあるという、無限の創造の世界が広がっている。
臨書は、技術だけでは表現できないものだと思う。
古典の書の、点画の位置や長さ、角度をいくら研究して同じに書けても
それは、マニュアル通りに注文を繰り返す、どこぞやの店員さんと同じで
感激も体温も感じない。
ソツなく書かれたものには、ふ~んって思うだけで、きっと震えない

古典と向き合ったとき、どんなものでもいい、心の底からの感動の
リズムを発見できなければ、本物の臨書にはならない。
感受する、そして感じたものを、包み隠さずさらけ出せたとき、
「個性」が見つかるのかもしれないですね。
それはたぶん、書だけに限らず、人との関わりも同じ。
今の若い世代(20代位?)は、争いたくないから、
人と深く関わることを避けるらしいです

でも人に興味がないから、自分も見つけられないんじゃないかな。。
人は人の中にいて初めて、自分を知るんだと思うから

臨書をしていて、ふとそんなことを考えた。
かく言う私も、まだまだ、隠しているのかもしれないけれど。。













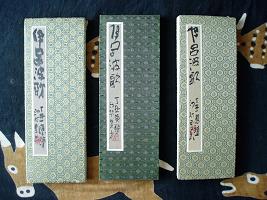
 ←表紙はこんな感じ
←表紙はこんな感じ 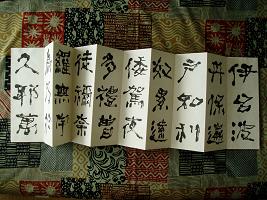
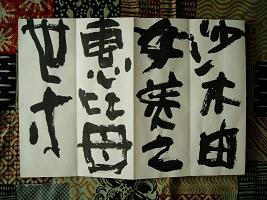
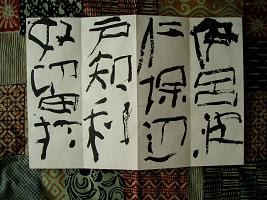
 ?
? って思った・・・に違いない。
って思った・・・に違いない。 どうだ~」攻撃をして下さった。
どうだ~」攻撃をして下さった。 」
」
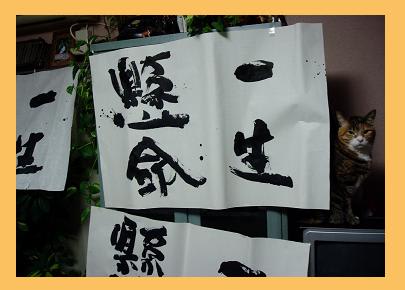
 書いた。
書いた。

 !
!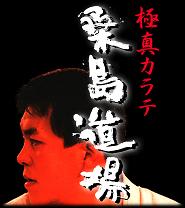



 ほんとだ。
ほんとだ。