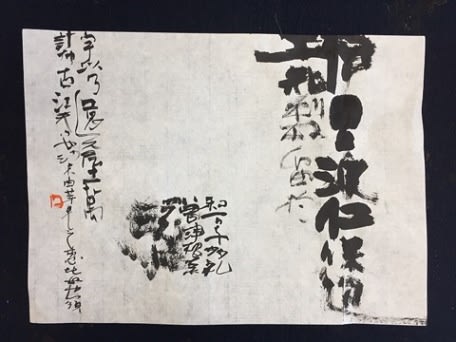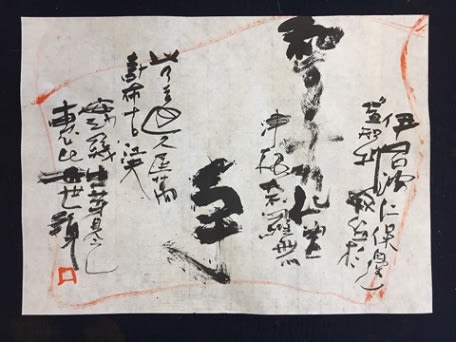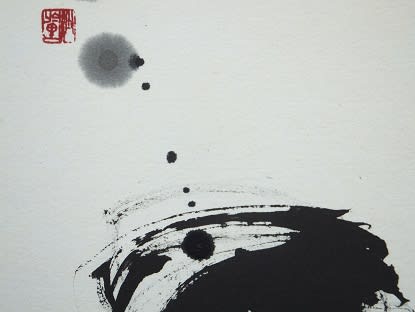「あっけらかん笑」
断捨離中の反古紙から出てきた「笑」。
一時期、「笑」のバリエーションを書いて書いて書いていた。
線と空間だけで、感性を表現できたら。
線も、線が創る造形も無限。
雲・空・海・花・光・風・雨・樹・風・・・
生・悲・楽・寂・怒・悼・夢・心・愛・力・許・失・探・・・
漢字一字に内在するドラマを想像すると、書きたくなる。
創造は想像力。
線は人。空間は時間。
書に向かうことは、無限のドラマを探し、許容すること。
そんな風に感じながら、書を、私を、探して、書いています。
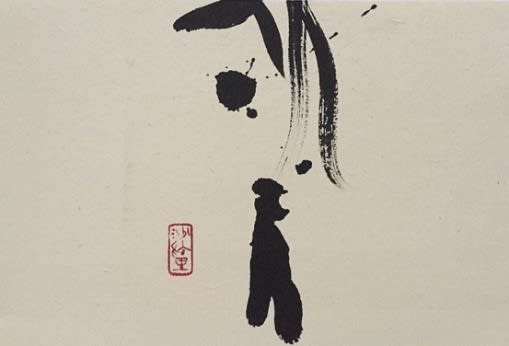
「照れ笑い」
今日の1曲は~Tom Waits - Train Song
ううう・・ 沁みるうううう・・・
断捨離中の反古紙から出てきた「笑」。
一時期、「笑」のバリエーションを書いて書いて書いていた。
線と空間だけで、感性を表現できたら。
線も、線が創る造形も無限。
雲・空・海・花・光・風・雨・樹・風・・・
生・悲・楽・寂・怒・悼・夢・心・愛・力・許・失・探・・・
漢字一字に内在するドラマを想像すると、書きたくなる。
創造は想像力。
線は人。空間は時間。
書に向かうことは、無限のドラマを探し、許容すること。
そんな風に感じながら、書を、私を、探して、書いています。
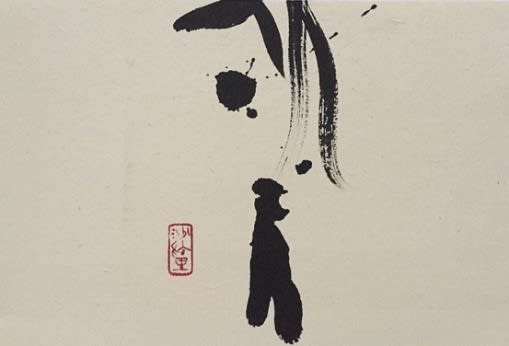
「照れ笑い」
今日の1曲は~Tom Waits - Train Song
ううう・・ 沁みるうううう・・・