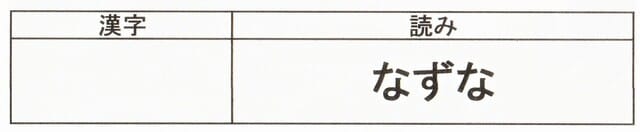図書館から借りていた、藤沢周平著、「市塵」(上)(下)(講談社)を読み終えた。本書は、貧しい浪人生活から儒者の道に入り、甲府藩主徳川綱豊に仕えることなった新井白石が、5代将軍綱吉の死後、藩主綱豊が6代将軍家宣となって以後、御側用人間部詮房に請われ、将軍家宣からも厚い信頼を受け、政治顧問として権力の中枢に身を置き、幕政改革の理想に燃えるものの、家宣の死後、さらに7代将軍家継の死で、運命は大きく変わり、市塵に帰っていくという新井白石の全てを物語る長編歴史小説で、なかなか読み応えがある作品である。藤沢周平作品には、下級武士物、市井物が多いが、本書は、歴史上の人物を描いた物で、しかも、斬り合いの場面等一切無し、幕府の政治、経済改革等を中心とした激論、権力争い等、やや重い小説でもある。
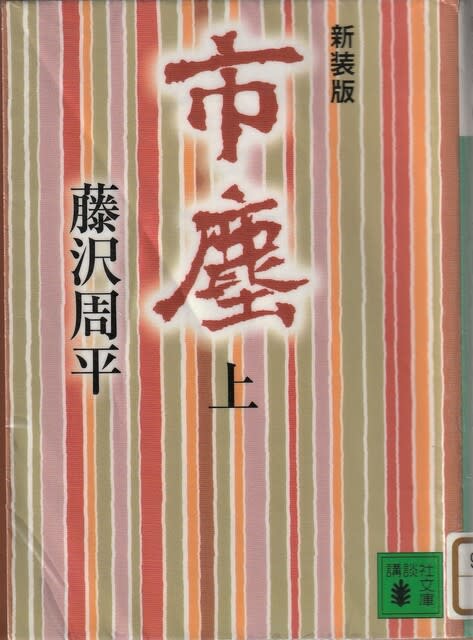
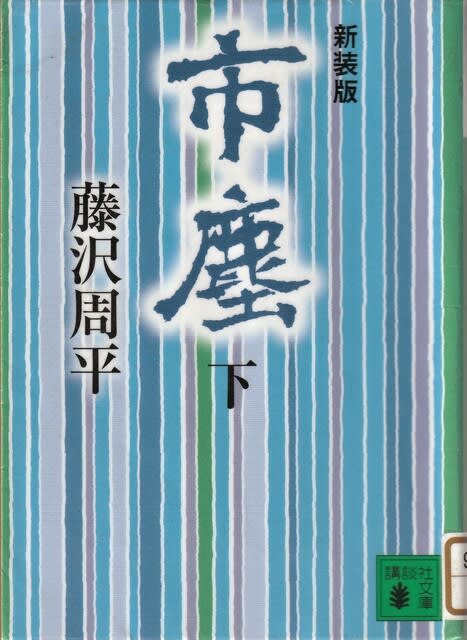
▢目次
(一)~(五十)、解説・伊集院静、
▢主な登場人物
新井白石(新井勘解由、新井筑後守)
明卿、伝、長、
伊能佐一郎、土肥源四郎、佐七
間部詮房(間部越前守)
萩原重秀、
林大学頭信篤、
雨森芳州、室鳩巣、
ヨハン・バッティスタ・シドッチ
趙泰億、
土屋政道、阿部正喬、
第5代将軍徳川綱吉、
徳川綱豊→第6代将軍徳川家宣(いえのぶ)
鍋松→第7代将軍徳川家継(いえつぐ)
第8代将軍徳川吉宗
月光院、絵島、生島新五郎、
大岡忠相(普請奉行→江戸町奉行)
本書の表題「市塵(しじん)」の意味合いがしみじみ感じられる文が、最終章(五十)に見られる。6代将軍家宣、7代将軍家継に仕え、儒者でありながら、政治の世界に踏み込み、ある意味では立身出世し、権力を得て天下を動かしているという自負、快さを持ち続けていた新井白石だが、8代将軍徳川吉宗の時代となり、居場所は無くなってしまい、悲哀を感じる場面だ。
「怒りは少し鎮まって、白石はかわりに深い失望感にとらわれていた。だがその失望感の中に、残された道が鮮明に見えていることもたしかだっった。・・・市塵の中に・・・。帰るべしということなのだ、と白石は思った。」
そして、人里離れた内藤宿六軒町に落ち着いた新井白石は、
「深夜の内藤宿六軒町は、物音ひとつ聞こえず静まり返っていた。家を取り巻く厚くて濃い闇が四方から迫って来るような夜だった。その闇のはるかかなたで、また犬が啼き出した。その声にしばらく耳を傾けてから、白石は筆を取り上げ、「史疑」の記述に取りかかった。命がようやく枯渇しかけているのを感じていたが、「史疑」を書き上げないうちは死ぬわけにはいかぬと思った。行燈の灯が、白髪蒼顔の、疲れて幽鬼のような相貌になった老人を照らしていた。」
で、物語が終わっている。
新井白石は、「日本史」で必ず登場する人物であり、その名は誰でも知る歴史上の人物であるが、余程勉強熱心でもなければ、サラッと触れるだけではないかと思う。本書では、藤沢周平氏ならではの丹念な時代考証で、単なる時代小説というより、新井白石の全てを深く深く掘り下げた歴史書とも言える気がする。これまでぼんやりとしか知り得なかった新井白石の人物像が鮮やかに浮かび上がり、「へー!、そうだったのか」・・・目から鱗・・・である。