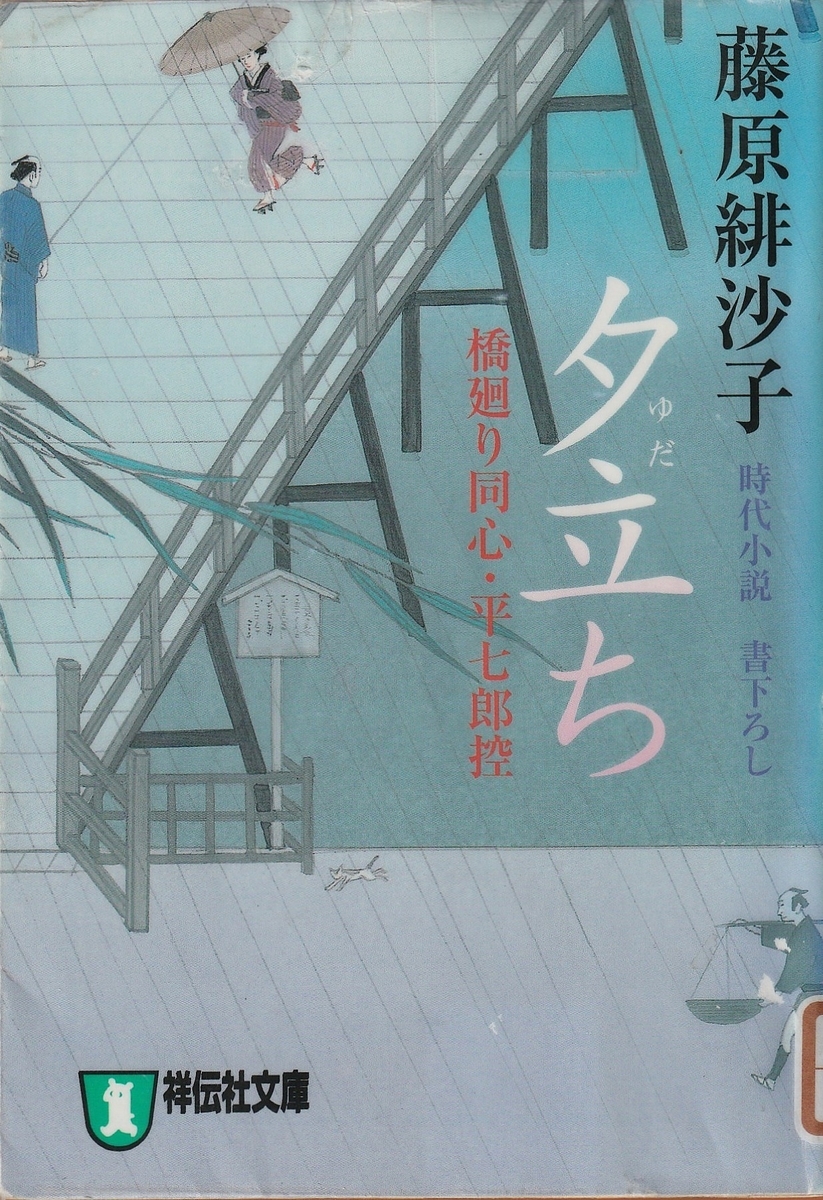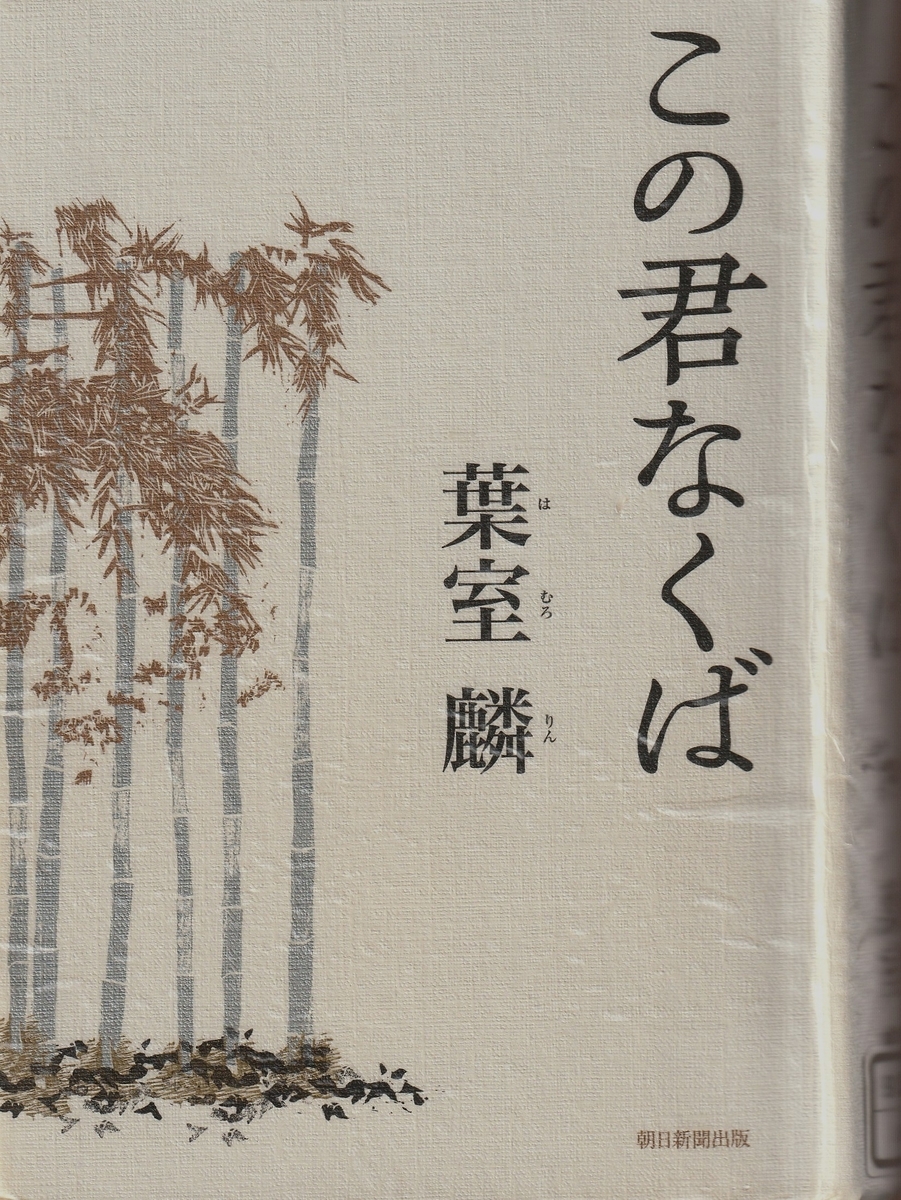図書館から借りていた、藤原緋沙子著 「冬萌え」 (祥伝社文庫)を読み終えた。
本書は、著者の長編時代小説、「橋廻り同心・平七郎控・シリーズ」の第5弾の作品で、「第一話 菊一輪」「第二話 白い朝」「第三話 風が哭く」「第四話 冬萌え」の、連作短編4篇が収録されている。
「橋廻り同心・平七郎控・シリーズ」は、江戸北町奉行所の「橋廻り同心(はしまわりどうしん)」となり、北町奉行榊原主計頭忠之(さかきばらかずえのかみただゆき)から、「歩く目安箱」としての特命を受けた立花平七郎が、新人同心平塚秀太、読売屋(瓦版)「一文字屋」の女主人おこう、その使用人辰吉、元船宿「おふく」のお抱え船頭源治等と共に、橋にまつわる様々な事件に対して、その事情を探り、絡み合う悪事や謎を解明、愛憎乱れる深い闇を、剣と人情で解決していくという、悲喜こもごもの長編時代小説である。
「橋廻り同心」とは、正式には、「定橋掛の同心」のこと。
「定橋掛(じょうばしがかり)」とは、縦横に水路が張り巡らされ、125余の橋が存在した江戸で、その橋や下の川を点検管理をする、南、北奉行所の一部門で、それぞれの奉行所で、与力一名、同心2名が担当していたのだという。
「橋廻り同心」の仕事も重要な仕事だったはずだが、奉行所内では、十手をかざして華々しく事件捜査をする部門「定町廻り同心」に比して、十手ではなく、木槌を手にして橋桁や欄干等を叩いて回り点検管理する姿は、侮蔑の目で見られ、年老いたり、問題を抱えた、与力、同心が就く、閑職と認識されていたのだという。
生前、「大鷹」と異名をとった「定町廻り同心」の父親の後を継ぎ、北辰一刀流免許皆伝で、かって、「黒鷹」と呼ばれる程、活躍していた平七郎が、曰く、事情が有って、「橋廻り同心」に左遷されてしまうが、持ち前の正義感、人情で、「橋廻り同心」の職掌を越えて、多くの事件を解決していくという痛快物語であり、ヒロインとも言えるおこうとの恋模様が織り込まれた物語である。

読んでも読んでも、そのそばから忘れてしまう老脳。
読んだことの有る本を、うっかりまた借りてくるような失態を繰り返さないためにも、
その都度、備忘録として、ブログ・カテゴリー「読書記」に、書き留め置くことにしている。
「第一話 菊一輪」
・主な登場人物
岩五・おみつ、
岡村金之助(筑前国秋月藩御用掛岡村孫太夫の嫡男)・綾瀬、
いたちの儀蔵、伊之助、
・あらすじ等
吾妻橋を行ったり来たりする男岩五、実は、以前奉公した主君への忠義を全うせんと
して、惚れた女房おみつを飯盛女にし、泥棒を企てようとするが・・・。
意外な展開となり・・・。
「へい、いたちのとっつぁんに貰った命大切に致しやす」
「第二話 白い朝」
・主な登場人物
お愛・太一、緒方勇之進、
上村左馬助、妙、
高田屋治兵衛、
山路屋益之助、北山一馬、
・あらすじ等
平七郎の無二の親友で、剣術道場主上村左馬助の様子がおかしい?、妙が失踪?、
一方、弁慶橋の竹森稲荷で、親とも慕っていた治兵衛殺害現場を目撃してしまった
少年太一は堅く口を閉ざしてしまい・・・、その理由は?、
「平七郎様、おいら、クロを待つよ」、哀しげに太一は言った。
「第三話 風が哭く」
・主な登場人物
新八・弥兵衛
お咲、善七、
富蔵、平助、
松屋庄兵衛・お美津、林格之進、
・あらすじ等
凶悪犯捕縛に協力したお咲は奉行者からの褒美を拒み、暦売りに脅迫されている
との情報有り、平七郎、お香、辰吉等が真相探索・・、
蓬莱橋・・お美津の「二年間待って」という約束を胸に、罪を肩代わりしながら
懸命に待ち続けるお咲。その心と体を解放してやらないと・・・・。
「お咲・・・」、平七郎が声をかけると、お咲が振り向き・・、
「風が哭いてます・・・、お役人様、風が・・・」
「第四話 冬萌え」(表題作)
・主な登場人物
淡路屋徳三郎、与之助、
治助・お文・お小夜、
茂助・おさん、
総兵衛(おこうの亡父)、辰五郎(辰吉の父親)、
・あらすじ等
世間では仏の徳三郎と呼ばれている両替商の淡路屋徳三郎だが・・・、
お小夜に言い寄る淡路屋の番頭与之助、真相が暴かれ・・・、
古川橋(麁朶(そだ)橋)・・亡き父親総兵衛の秘密を追い、父の深い愛情を知る
おこうの切ない思い・・、
「冬萌え・・・」「ええ・・・、私、それを見て涙が出ました。それでここに
来たのです」
「解説」ー「見えない絆」を描く橋物語 小梛治宣
(つづく)
弊ブログの「コメント欄」は、
2025年4月20日をもって、閉じることに致しました。
以後、弊ブログにコメントをお寄せいただく場合は、
引っ越し先ブログ ⇨ 「たけじいの残日雑記懐古控」
の上記と同記事の最下段、
「コメントを書く」をクリック、入力、「投稿する」で
お願い申し上げます。
(ネットから拝借フリーイラストGIF)
追記
引っ越し先のHatenaBlog「たけじいの残日雑記懐古録」の方では、
「設定」→「コメントの許可」→「誰でもコメントを書き投稿出来る」、
に、しています。
先日、HatenaBlogユーザー以外の方に、
テストしていただきましたところ、
特に問題無く、コメントすることが出来るようです。
今のところ、
goo blogが、終了するまで、
古屋、新居、2つのブログを、管理していきたいと
思っております。
昨年までは、夢にも思っていなかった2つのブログ管理、
初体験であり、これも、脳トレの一つ?・・と
決め込んで・・・。