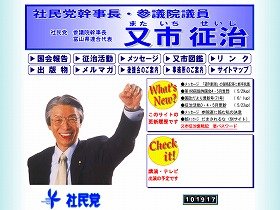沖縄戦戦った元米兵 来沖、激戦地巡る

展示された写真に見入る(左から)デンカーさんとクーパーさん=20日、北中城村立中央公民館
沖縄戦を戦った2人の元米兵が沖縄を訪れている。陸軍第96歩兵師団に所属したドーン・デンカーさん(82)=ウィスコンシン州=と陸軍第七歩兵師団にいたビル・クーパーさん(82)=カリフォルニア州=が家族ら7人で来沖、上陸地点や激戦地などを巡っている。
クーパーさんは「自分が死ぬ覚悟をした地を見せたい」と妻マリオンさん(81)を伴って戦後2度目の来沖。激戦地だった西原町翁長はサトウキビが生い茂り、戦の名残はなかったというが、マリオンさんは「彼が19歳を過ごした場所に来られてよかった」と話した。
戦後11回目の来沖で初めて三女リンさん(48)を連れてきたデンカーさんは「(糸満市)大里と新垣が忘れられない。一番激しく戦い、仲間もだいぶ命を失った」と当時を思い浮かべた。
デンカーさんは、元米兵から託された5枚の写真も持参した。沖縄から持ち帰ったもので、赤ん坊を抱いた女性や学生などが写っている。裏には「大城」「阿部」「道輪千恵子」などの文字がはっきりと読み取れる。写真を預かった琉米歴史研究会では持ち主を捜している。写真は表裏ともホームページ(http://www.ryubei.com/)で公開している。
(6/21 琉球新報 16:13)
◇
6月に入ってからの地元紙の沖縄戦に関する報道は、日に日に異常さを増している。
今朝の琉球新報朝刊は一面トップ記事を初めに、六面を費やして「日本兵の残虐」を糾弾している。
文化面ではサヨク学者を三人も動員してこれを後押しさせる熱心さ。
琉球新報でさえこうだから、沖縄タイムスは推して知るべしだろう。(この時間、同紙サイトには未だアップされていない)
これらの記事にまともに突っ込みを入れるのは、
蟷螂の斧より厳しいものがある。
まるでベニヤ板の特攻舟艇で「鉄の暴風」を降らす米艦隊にに立ち向かう日本兵の辛さを感じさせる。
まぁ、これについては稿を改めるとして。
ある本土出身の記者は沖縄メディアの異常な加熱振りを評して
>沖縄にはこの意見書(教科書検定)に反対だと沖縄県民でない、「非国民」みたいな雰囲気があります。
次のようなことを漏らした記者さんもいた。
>物言えばくちびる寒し・・・
ところで、上記引用の記事。
一連の特集記事の後で読むと、
「沖縄戦は日本軍と沖縄住民の戦いだった」という錯覚に陥る。
そして「残虐非道な日本軍を追い出して、沖縄住民を解放したのは米軍だ」と。
ここでは沖縄住民に無差別に「鉄の暴風」を降らした加害者米軍への視点は完全に欠落している。
広島の慰霊碑・銘文と同じ精神構造だ。
そういえば高嶋琉球大学教授は「よくぞアメリカは日本に原爆を落としてくれた、これで仇が討てた」という言葉を講演会で言っていた。
沖縄に戦没者の慰霊に来るのに元日本兵の身分を明かすのは勇気が要る。
”残虐な”元日本兵がコソコソと慰霊に来る一方、“ヒューマニズム”あふれる元米兵は沖縄では暖かく報道される。
正に大田元知事の歴史観を地元紙が忠実に実行していることになる。
以下に引用する大田前沖縄県知事の著書「沖縄の決断」の紹介文にこれが凝縮されている。
≪まぎれもなく、沖縄はかつて日本国の植民地であった。
古くは薩摩の過酷な搾取に支配され、太平洋戦争で沖縄県民は軍務に活用され、やがて切り捨てられ、そして卑劣にも虐待された歴史がある。
その意味では、沖縄戦のあとに上陸してきたアメリカ軍は沖縄にとって解放軍のはずだった。≫
(大田昌秀著「沖縄の決断」朝日新聞社刊)