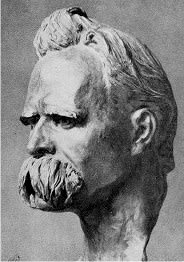
ニーチェに関する著書を読んでいますと必ず出てくる言葉に「永劫回帰」または「永遠回帰」という言葉があります。ニーチェの代表作『ツァラトゥストラはかく語りき』におけるツァラトゥストラの根本思想なのですが、超訳『ニーチェの言葉』の白取春彦先生は、
040少しの悔いもない生き方を
今のこの人生を、もう一度そっくりそのままくり返してもかまわないという生き方をしてみよ。
『ツァラトゥストラはかく語りき』
とニーチェの言葉を意訳しています。
永劫回帰については、私はこれまでにもブログに書いてきましたが、どちらかというと「今の状態が永遠に続くとしたら自分は変わる必要があるか。否か」というニュアンスで心にとめ活用しています。
白取先生の意訳は、非常に優しい投げ掛けの言葉になっていることに新鮮さを受けます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
このツァラトゥストラの永劫回帰は、『悦ばしき知識』に凝縮されたかたちで出てきます。
最大の重し・・・・・・・もしある日あるいはある夜、おまえのこのうえない孤独のなかに悪魔が忍び込みこう告げたとしたらどうか。
「おまえが現に生きており、また生きてきたその生を、おまえはもう一度、いやさらに無限回にわたって、生きねばならぬ。
そこには何ひとつとして新しいことはなく、あらゆる苦痛とあらゆる快楽、あらゆる思いとあらゆるため息、おまえの生の言い尽くせぬ大小すべてのことが、おまえに回帰して来ねばならぬ。
しかしすべてが同じ順序と脈絡において(中略)と。・・・・・おまえは身を投げ出し、歯ぎしりして、その悪魔を呪うのではないか。
それとも、おまえは突如としてとてつもない瞬間を体験し、「あなたは神だ、私はかつて一度もこれほど神々しいことを聞いたことがない!」
と答えるであろうか。
もし生の回帰という考えが、お前を圧倒したとすれば、それは現在のおまえを変えてしまい、砕きつぶしてしまうかもしれない。
何事につけても
「おまえはもう一度、いやそれどころかさらに無限回、それを欲するするか」
という問いが最大の重しとなっておまえのうえにのしかかるだろう!そうはならずに、生の回帰というその究極的で永遠的な確証と確認のほかにはもう何もいらないと思うためには、おまえは自分自身とその生とをどれほどいとおしまねばならぬことであろうか。(『悦ばしき知識』341)
※ 講談社現代新書『これがニーチェだ』永井均著引用
永井先生は永遠回帰としますが、ニーチェの言おうとしているところはここにあるようです。
ニーチェの哲学ですから、ニーチェの発想でありニーチェの創作です。
哲学者によって「永遠」「永劫」の言葉で解説されるのですが清水真木先生は、この創作(清水先生は仮説とします)の経過を次のように解説しています。
永劫回帰
すべての事象が全体として同一の順序に従って繰り返し生起すること。正確には、「等しきものの永劫回帰」と言います。これは仮説であって、事実を指し示す表現ではありません。したがって、永劫回帰が本当に生じることを観察し確認できるのかといったことは問題にもなりません。また、輪廻や時問体験などの非H常的な出来事とも関係ありません。永劫回帰は、あらゆることがすでに無限回にわたって繰り返し生起しているから、私たちがこれから試みるすべてのことの結果が予め決定されていること、したがって努力や希望や責任がすべて無駄であり、生存が無意味で苦痛に満ちたものであることの可能性を暗示する、認識の実験のために産出されたペシミスティックな仮説ないし妄想に過ぎません。
生存が無意味であり苦痛に満ちたものであることを承認するばかりではなく、生作が一屈旧無意味で、一層多くの苦痛に満たされることを求め、自ら進んでペシミスティツクな妄想を産出し、自らの生存を試煉にかける意欲、これこそ健康と強さの証でした。それゆえ、もっともペシミスティックな認識が真なるものであることを承認し願う者は、権利上もっとも健康でもっとも強い人間・・・・すなわち「超人」・・・・であるはずです。永劫回帰は、「人問を箭にかけ、弱者にも強者にも決断を迫る一つの見解」(1884年初めのノート)、もっとも健康でもっとも強い人問としての超人を選び出すための「試金石」として機能すべきもっともペシミスティックな仮説に他なりません。「試みの時代。私は大いなる試煉を課する。つまり、誰が永劫回帰の思想に耐えるのかを試す。・・・・『いかなる救済も存在しない』という命題によって根絶されてしまうような者を死なせてしまおうではないか……」(1884年初めのノート)。
二ーチェが永劫回帰の仮説を乎に入れたのは、1881年夏のことです。1881年7月、シルス・マリアを偶然発見し、夏のあいだここに滞在していた二ーチェは、白分宛の郵便物を局留めにして受け取ることにしていました。「千紙は予告なしの訪問であり」と二ーチェは語ります。「郵便配達人は失礼な不意打ちの仲介者である。千紙を受け取るためには毎週一時間が充てられるべきであり、そのあとで入浴すべきである」(『漂泊者とその影』)。そのため、村の東側に広がる湖を挟んで反対側にある隣村の郵便局まで数Hおきに散歩を兼ねて出かけるのが習慣になっていました。8月上旬のある日、いつものように郵便物を受け取るため、湖畔の道を隣村に向って歩いていたとき、二ーチェの心に、すべてが永遠に回帰するとしたら……というアイディアが浮かびます。シルス・マリアで二ーチェが使っていたノートのある頁には、「等しきものの回帰」という標題を持つ断章が記されており、最後には「1881年8月上旬、海抜六千フィート、人間と時代からはさらに高く隔ったシルス・マリアにて」と記されています。二ーチェが永劫回帰を思いついて立ち止まった場所には、湖に突き出した小さなピラミッド型の岩があり、「ツァラトゥストラの岩」と呼ばれています。永劫回帰は、翌年公刊された『悦ばしき知識』の341番の断章・・「最大の重し」・・においてペシミスティツクな問(「お前はこのことをもう一度、否、際限なく繰り返し欲するか」一として予告されたのち、主著『ツァラトゥストラはこう語った』(1883~1885年)、特にその第2部の「幻影と謎」や「恢復しつつある者」などの章において、明確な表現を与えられます。「……万物は行き、万物は帰って来る。存在の輸は永遠に回る。万物は死に、万物は再び花咲く。存在の年は永遠に巡り駆ける……」。(『知の教科書 ニーチェ』清水真木著 講談社選書メチエP96~P98から)
長い引用ですが、私自身の意が入らないためです。
ニーチェの「永遠回帰」「永劫回帰」をどのように捉えるか。自分の人生に生かす言葉にするか、捨ておくか。・・・・・・・
何事も、生かすも、殺すも、自分自身です。 このブログは、ブログ村に参加しています。
このブログは、ブログ村に参加しています。



















