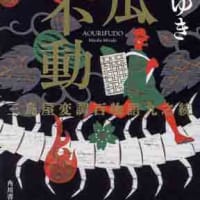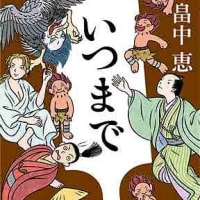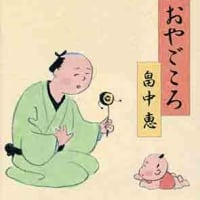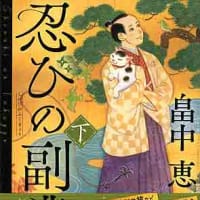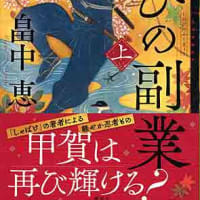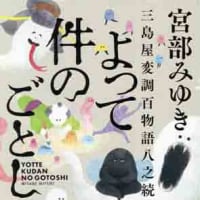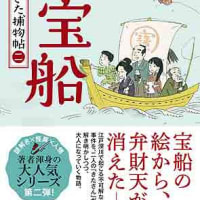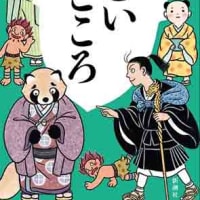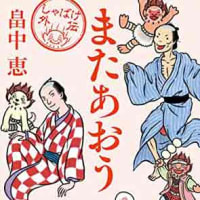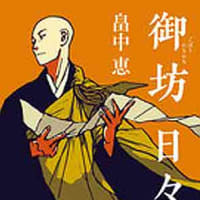井上ひさし
 1985年12月発行
1985年12月発行
元禄15年12月15日未明、赤穂浪士47名が両国の吉良邸に討入り本懐を達成した。この義挙に参加しなかった旧赤穂藩士。彼らはなぜ討入りを行わなかったのか。その理由と彼ら19名のその後の生き様を一話完結で綴った短編集。
厳密な歴史考証と豊かな想像力でを問い直した、「第20回吉川英治文学賞」受賞の傑作。
小納戸役 中村清右衛門
江戸留書役 岡田利右衛門
大坂留守居役 岡本次郎左衛門
江戸家老 安井彦右衛門
江戸賄方 酒寄作右衛門
馬廻 橋本平左衛門
江戸給人百石 小山田庄左衛門
江戸歩行小姓頭 中沢弥市兵衛
江戸大納戸役 毛利小平太
小姓 鈴木田重八
浜奉行代行 渡辺半右衛門
在々奉行 渡辺角兵衛
武具奉行 灰方藤兵衛
馬廻 片山忠兵衛
近習 村上金太夫
江戸留書役 大森三右衛門
舟奉行 里村津右衛門
元ノ絵図奉行 川口彦七
江戸給人百石 松本新五左衛門 計19編の短編
小納戸役 中村清右衛門
主要登場人物
語部 越前屋定七...神田明神下一膳めし屋の主
聞手 熊...神田明神下の大工
六...神田明神下の左官職
登場人物 中村清右衛門...神田明神下中村道場の主、播磨国旧赤穂藩浅野家小納戸役
吉富五左衛門...肥後国熊本藩細川家小姓組(磯貝十郎左右衛門の介錯人)
理由 内匠頭が何故に上野介に対峙し、突かずに振りかぶって切りつけたのか。殺すつもりなら突くべきだった。また、音曲嫌いの内匠頭には、長時間に渡る饗応の能が辛く、癪もちでもあったことなどから、逆上し突発的に斬り付けたのではないかとの疑念を大石内蔵助に打ち明けたところ、「討ち損じた時の二陣に残れ」と命じられた。
江戸留書役 岡田利右衛門
主要登場人物
語部 梶川与惣兵衛頼照...旗本・大奥御台所付き留守居番(内匠頭の凶行を止めた人物)
聞手 織田刈右衛門(岡田利右衛門)...梶川家物書役、播磨国旧赤穂藩浅野家江戸留書役
登場人物 丹六...大坂道頓堀西竹本座の表方
理由 殿中にて吉良を討ち果たせなかった内匠頭の無念を、それを留めた梶川与惣兵衛頼照に向け、刺客として同家に潜入。だが、梶川の人物や当時の回想を聞くにつけ、思いは果たせず、梶川家物書役として書き留めた松の廊下の事件を浄瑠璃の本に書き留める。
大坂留守居役 岡本次郎左衛門
主要登場人物
語部 向井将監忠勝...旗本・江戸船手頭
聞手 岡本次郎左衛門...向井家用人、播磨国旧赤穂藩浅野家大坂留守居役
理由 身体が不自由で討入りに参加できないため、付け火をし、仲間が吉良邸の図面を書くための手引き役。
江戸家老 安井彦右衛門
主要登場人物
語部 高梨武太夫...安井家用人
多胡外記...岩見国津和野藩亀井家筆頭家老
登場人物 安井彦右衛門...隠棲、播磨国旧赤穂藩浅野家江戸詰家老
日庸取頭...前川忠太夫の手下
理由 内匠頭の性格からして一波乱あることを案じ、竹に肩代わりを願うも、内匠頭の逆鱗に触れ、「大役を務めた後は、汝の首をはね てやる」と脇息投げ付けられ、この時点で浅野家を去る決意を固める。
江戸賄方 酒寄作右衛門
主要登場人物
語部 妙海尼...泉岳寺側清浄庵庵住、元堀部家下女・お順
酒寄作右衛門...白金四丁目そば茶屋の主、播磨国旧赤穂藩浅野家江戸賄方
登場人物 堀部弥兵衛金丸...播磨国旧赤穂藩浅野家前江戸留守居
堀部安兵衛武庸...播磨国旧赤穂藩浅野家馬廻役
理由 討入りに参加せず、商人になった旧藩士たちが不忠者とされ、商いが立ち行かなくなったのを案じた妙海尼が、彼らは縁の下で義士を支えていたと論じ、それを受け、酒寄作右衛門も己も縁の下の義士であったと話して欲しいと頼む。
※脱退の理由はなしだが、義士への献金のための商いか?また、妙海尼は、堀部安兵衛の妻を名乗るも実は下女であった。
馬廻 橋本平左衛門
主要登場人物
語部 近松門左衛門(信盛)...戯作者、元越前国吉江藩松平家家臣
天満屋惣兵衛(佐々小左衛門)...大坂曽根崎新地蜆川遊女屋の(雇われ)主、播磨国旧赤穂藩浅野家足軽頭
登場人物 橋本平左衛門...播磨国旧赤穂藩浅野家馬廻役
理由 死地に向かう前に、馴染みの遊女を身請けして善行を施そうと刀を売りに出したのを、仲間に詰られ、死を恐れぬ潔白の為に、遊女・お初と相対死(心中)を果たす。
「早見家文書」によれば、淡路屋のお初という遊女と元禄14年11月6日の夜に心中。
江戸給人百石 小山田庄左衛門
主要登場人物
語部 小山田一閑(十兵衛)...庄左衛門の父親、元播磨国旧赤穂藩浅野家山鹿素行学問指南
大石内蔵助良雄...播磨国旧赤穂藩浅野家筆頭家老
聞手 堀内伝右衛門...肥後国熊本藩細川家白金下屋敷用人
理由 娘の婚家に身を寄せる父が肩身の狭い思いをしているのを案じ、旧浅野家御抱医師の息子・寺井玄達金策するも適わず出奔。25両を盗んで出奔かとおもわせる。
事実は、同志の片岡高房から金5両と小袖を盗んで逃亡。父・一閃は詳細を知りこれを恥じて12月18日に切腹。
江戸歩行小姓頭 中沢弥市兵衛
主要登場人物
語部 白壁屋勘八...麻布今井町豆腐屋の主
登場人物 市兵衛(中沢弥市兵衛)...白壁屋奉公人、播磨国旧赤穂藩浅野家歩行小姓頭
落合与左衛門...播磨国旧赤穂藩藩主・浅野内匠頭長矩室瑤泉院(阿久里)奥様衆
理由 内匠頭の後室・瑶泉院に懸想し、彼女の死に殉じて自刃。
江戸大納戸役 毛利小平太
主要登場人物
語部 木村岡右衛門貞行...播磨国旧赤穂藩浅野家馬廻役・絵図奉行
聞手 波賀清太夫...伊予国松山藩松平家三田中屋敷世話役
登場人物 毛利小平太...播磨国旧赤穂藩浅野家江戸大納戸役
大石主税良金...播磨国旧赤穂藩浅野家家臣
理由 茶器屋・岡崎屋の奉公人に化し、吉良邸の陣容を探中、間者であると知れ、吉良方の目を欺くため、討入り当夜、遊女屋への逗留を指示される。
小姓 鈴木田重八
主要登場人物
語部 小関岡文之進...元上野国伊勢崎藩酒井家旗組小頭
聞手 村尾勘兵衛...上野国伊勢崎藩酒井家目付役
登場人物 玉野平八(鈴木田重八)...本所林町五丁目堀内道場食客、播磨国旧赤穂藩浅野家小姓
理由 潜伏中に名乗った名が、仇持ちだったため、間違われて付け狙われ重傷を負い討入りならず。
浜奉行代行 渡辺半右衛門
主要登場人物
語部 青山武助...三河国岡崎藩水野家小姓組(間十次郎の介錯人)
渡辺半右衛門...播州赤穂新浜塩田の浜男、播磨国旧赤穂藩浅野家浜奉行代行
登場人物 間十次郎光興...播磨国旧赤穂藩浅野家勝手方吟味役
理由 幼少の頃より、間十次郎光興と事を興すと、第三者に禍が降り掛かるため、どちらかが討入りを断念し、互いの老いた親の面倒を見るといった盟約の籤に外れたため。
在々奉行 渡辺角兵衛
主要登場人物
語部 渡辺角兵衛...肥前国佐賀藩鍋島家領内・金立村黒土原にて隠棲、播磨国旧赤穂藩浅野家在々奉行
聞手 田代又左衛門陣基...肥前国佐賀藩鍋島家御書物役
登場人物 山本神右衛門...元肥前国佐賀藩鍋島家御書物役、金立村黒土原にて隠棲
理由 山本神右衛門常朝に主君のために命を捨てるのは下下下の忠であり、上上吉の大忠節とは、主君の御心入れを直し、藩を固め申すこと」。「大石は、あらかじめ主君が間違いを起こさぬよう気配りをなし、国家の安泰をはかるべきだった」と説かれ、感銘を受ける。
武具奉行 灰方藤兵衛
主要登場人物
語部 灰方藤兵衛...京都伏見御香宮門前にて隠棲、播磨国旧赤穂藩浅野家武具奉行
聞手 村木隼人...京都伏見御香宮門前にて隠棲、元常陸国牛久沼山口家(旗本領)浪人→元京伏見御香宮門前江戸元結店の主
登場人物 お丹...藤兵衛の長妹、播磨国旧赤穂藩浅野家京留守居役・小野寺十内の妻
理由 村木隼人と出会い、互いに恋に落ちる。その後、村木は身を呈して、灰方家の窮地を救い失明。村木の面倒を見ながら共に暮らす決意をする。
馬廻 片山忠兵衛
主要登場人物
語部 片山忠兵衛...奥絵師・狩野常信の弟子、播磨国旧赤穂藩浅野家馬廻役
聞手 鎌田軍之助...肥後国熊本藩細川家用人
理由 第3代肥後国熊本藩主・細川綱利の亡き愛妾・花宴を描く依頼を受けるも、その絵の内股の黒子(片山忠兵衛は筆が落ちたと説明)に激怒した綱利の命で、詮議のために細川家に軟禁される。
近習 村上金太夫
主要登場人物
語部 徳治...廻り髪結
聞手 鵜飼惣右衛門...長門国長府藩毛利家家中(前原伊助の介錯人)
理由 乞食に身をやつし吉良邸の抜け穴の在り処を探っていたところ、酔った長屋の住人たちに、生き埋めにされる。
江戸留書役 大森三右衛門
語部 竹村一学...馬喰町町医者、元信濃国上田藩仙石家大納戸方
聞手 大森三右衛門...播磨国旧赤穂藩浅野家江戸留書役
登場人物 弓削佐次馬...信濃国上田仙石家内証用人
理由 信州上田藩千石家内証用人・弓削佐次馬と、蕎麦饅頭の食べ比べの末、口論となり刃傷に及び、その弟・竹村一学により仇持ちとなる。主君の恨みを晴らすまでの猶予を懇願するも、「自縄自縛だ」と、己の運命を感じ入る。
討たれたのだろうと思わせる。
舟奉行 里村津右衛門
語部 里村津右衛門...讃岐国丸亀近く塩浜(塩田)の親方、播磨国旧赤穂藩浅野家舟奉行
聞手 間喜兵衛...播磨国旧赤穂藩浅野家お勝手吟味役、里村津右衛門の義兄弟・従兄弟
新六...間喜兵衛の二男、里村津右衛門の養子
理由 殿中で刀を抜けば、身は切腹。家臣は路頭に迷う。天下の御法に反して上野介の首級を上げれば、残されて泣くのは女であるの思いから、内匠頭と大石を非難し、武士を捨てる。
だが、元里村家の養子であった新六の激しい罵りに、腰抜けでないことの証のために石見銀山を服毒し自裁。
元ノ絵図奉行 川口彦七
語部 林兵助...肥後国熊本藩細川家接伴人
聞手 潮田又之丞...播磨国旧赤穂藩浅野家筆頭国絵図奉行
登場人物 川口彦七(久造)...公義表絵師・狩野良信の弟子、播磨国旧赤穂藩浅野家元ノ絵図奉行
渡辺一蔵...南町奉行所年番与力
理由 川口彦七が顔を潰された遺骸で見付かり、下手人として久造が捕まる。その久造は、どんな拷問にも口を割らなかったが、赤穂浪士が討入ったと聞くと、己が川口彦七であると名乗るのだった。川口彦七であるとなれば殺し自体が成立しなくなる。果たして久造は川口彦七なのか…。
江戸給人百石 松本新五左衛門
語部 お咲...八郎右衛門新田の開拓者八郎右衛門の孫、元津田家・安基姫付き下女
聞手 坊ちゃん...小普請組旗本・津田家の跡取り、松本新五左衛門の嫡男
登場人物 安基姫...津田家の娘
松本新五左衛門...播磨国旧赤穂藩浅野家江戸給人・松本隼人の養子→津田家(安基姫)婿養子
三枝左兵衛...小普請組旗本、松本新五左衛門の実兄
理由 浅野家断絶により、実兄から旗本・津田家への婿養子にいかされ、討入りを断念。だが、討入り後、浪士が義士と崇められるや、養子縁組解消と自刃を迫られ切腹。
討入りの後、そこに名を連ねなかった旧赤穂藩士の置かれた立場と辿った道。そして彼らは討入りを如何に受け止めたのだろうか。
彼らが、討入り不参加を選ぶに至った過程と、現況を、実存した旧赤穂藩士19名の近しい人物が語り部となり物語は進行する。
小説になっているが、緻密な背景考証により、かなり真実に近い証言となっている。
特に、最後の最後まで盟約に名を連ね、討入り当日の配置も裏門方に記録されている毛利小平太の失踪は謎のままであり、多くの作家が手腕を振るう読ませどころとなり、ドラマチックなシーンの筆頭に上げられる人物である。
その毛利小平太を井上氏がどう料理するのか、興味があった。
また、19人ものその後を史実に忠実に脚色しながらも、全てがドラマになるようなストーリに仕上がっており、読み応えあり。切ない結末も多く、華々しく散った46人よりもなお、深みのある死や無念の死を感じ得た。
四十七士の忠臣蔵よりも、遥かに資料も資料も少なかったであろう彼らをここまで書き分けるとは、頭が下がる。井上氏の達者な文章力もさることながら、名作と言っても過言ではないだろう。
また、本文中には、浪士潜伏中の住まいや商い、好みの食べ物から、当時の風潮、討入り便乗商売など多岐に渡り織り込まれている。元禄時代、そして赤穂浪士「忠臣蔵」を知る上で、資料としてもかなり興味深く、「忠臣蔵」よりも正確かつ中身の濃い一冊である。
かなり共鳴を受けた一冊であるが、読むのにかなりの時間を要した。歴史好きで浅野内匠頭刃傷事件に詳しいと自負する当方でさえ、背景や氏素性に混乱する場面もあったので、時代小説好きだけでは些か難解かも知れないだろう。当方も、更に読み返すつもりである。そしてもっと簡潔かつ統一性をもたせて書き直し更新します。
日本人の忠義の美徳とされる「忠臣蔵」ファンにとっては目から鱗の真実がここにある。
余談ではあるが、当方は、荻生徂徠が説いた「浅野内匠頭は吉良上野介との諍いにて切腹に至ったのではなく、殿中での法度に触れた為である」の節に賛同。
松の廊下の事件以前にも、江戸城内での刃傷は3件あったが、いずれも切腹、御家断絶である。
中でも、春日局の曾孫に当たる稲葉石見守に至っては、その場で滅多切りにされている。
大石内蔵助をもってしてこの事実を知らない筈もなく(何せ平成のど町人の当方さへ知っているのだ)、思うに赤穂浪士の討入りより丁度30年前の寛文12年2月3日の浄瑠璃坂の仇討を手本に、浪士たちの仕官を狙っての事と思うのだが、如何だろうか。
 書評・レビュー ブログランキングへ
書評・レビュー ブログランキングへ
 にほんブログ村
にほんブログ村
 1985年12月発行
1985年12月発行元禄15年12月15日未明、赤穂浪士47名が両国の吉良邸に討入り本懐を達成した。この義挙に参加しなかった旧赤穂藩士。彼らはなぜ討入りを行わなかったのか。その理由と彼ら19名のその後の生き様を一話完結で綴った短編集。
厳密な歴史考証と豊かな想像力でを問い直した、「第20回吉川英治文学賞」受賞の傑作。
小納戸役 中村清右衛門
江戸留書役 岡田利右衛門
大坂留守居役 岡本次郎左衛門
江戸家老 安井彦右衛門
江戸賄方 酒寄作右衛門
馬廻 橋本平左衛門
江戸給人百石 小山田庄左衛門
江戸歩行小姓頭 中沢弥市兵衛
江戸大納戸役 毛利小平太
小姓 鈴木田重八
浜奉行代行 渡辺半右衛門
在々奉行 渡辺角兵衛
武具奉行 灰方藤兵衛
馬廻 片山忠兵衛
近習 村上金太夫
江戸留書役 大森三右衛門
舟奉行 里村津右衛門
元ノ絵図奉行 川口彦七
江戸給人百石 松本新五左衛門 計19編の短編
小納戸役 中村清右衛門
主要登場人物
語部 越前屋定七...神田明神下一膳めし屋の主
聞手 熊...神田明神下の大工
六...神田明神下の左官職
登場人物 中村清右衛門...神田明神下中村道場の主、播磨国旧赤穂藩浅野家小納戸役
吉富五左衛門...肥後国熊本藩細川家小姓組(磯貝十郎左右衛門の介錯人)
理由 内匠頭が何故に上野介に対峙し、突かずに振りかぶって切りつけたのか。殺すつもりなら突くべきだった。また、音曲嫌いの内匠頭には、長時間に渡る饗応の能が辛く、癪もちでもあったことなどから、逆上し突発的に斬り付けたのではないかとの疑念を大石内蔵助に打ち明けたところ、「討ち損じた時の二陣に残れ」と命じられた。
江戸留書役 岡田利右衛門
主要登場人物
語部 梶川与惣兵衛頼照...旗本・大奥御台所付き留守居番(内匠頭の凶行を止めた人物)
聞手 織田刈右衛門(岡田利右衛門)...梶川家物書役、播磨国旧赤穂藩浅野家江戸留書役
登場人物 丹六...大坂道頓堀西竹本座の表方
理由 殿中にて吉良を討ち果たせなかった内匠頭の無念を、それを留めた梶川与惣兵衛頼照に向け、刺客として同家に潜入。だが、梶川の人物や当時の回想を聞くにつけ、思いは果たせず、梶川家物書役として書き留めた松の廊下の事件を浄瑠璃の本に書き留める。
大坂留守居役 岡本次郎左衛門
主要登場人物
語部 向井将監忠勝...旗本・江戸船手頭
聞手 岡本次郎左衛門...向井家用人、播磨国旧赤穂藩浅野家大坂留守居役
理由 身体が不自由で討入りに参加できないため、付け火をし、仲間が吉良邸の図面を書くための手引き役。
江戸家老 安井彦右衛門
主要登場人物
語部 高梨武太夫...安井家用人
多胡外記...岩見国津和野藩亀井家筆頭家老
登場人物 安井彦右衛門...隠棲、播磨国旧赤穂藩浅野家江戸詰家老
日庸取頭...前川忠太夫の手下
理由 内匠頭の性格からして一波乱あることを案じ、竹に肩代わりを願うも、内匠頭の逆鱗に触れ、「大役を務めた後は、汝の首をはね てやる」と脇息投げ付けられ、この時点で浅野家を去る決意を固める。
江戸賄方 酒寄作右衛門
主要登場人物
語部 妙海尼...泉岳寺側清浄庵庵住、元堀部家下女・お順
酒寄作右衛門...白金四丁目そば茶屋の主、播磨国旧赤穂藩浅野家江戸賄方
登場人物 堀部弥兵衛金丸...播磨国旧赤穂藩浅野家前江戸留守居
堀部安兵衛武庸...播磨国旧赤穂藩浅野家馬廻役
理由 討入りに参加せず、商人になった旧藩士たちが不忠者とされ、商いが立ち行かなくなったのを案じた妙海尼が、彼らは縁の下で義士を支えていたと論じ、それを受け、酒寄作右衛門も己も縁の下の義士であったと話して欲しいと頼む。
※脱退の理由はなしだが、義士への献金のための商いか?また、妙海尼は、堀部安兵衛の妻を名乗るも実は下女であった。
馬廻 橋本平左衛門
主要登場人物
語部 近松門左衛門(信盛)...戯作者、元越前国吉江藩松平家家臣
天満屋惣兵衛(佐々小左衛門)...大坂曽根崎新地蜆川遊女屋の(雇われ)主、播磨国旧赤穂藩浅野家足軽頭
登場人物 橋本平左衛門...播磨国旧赤穂藩浅野家馬廻役
理由 死地に向かう前に、馴染みの遊女を身請けして善行を施そうと刀を売りに出したのを、仲間に詰られ、死を恐れぬ潔白の為に、遊女・お初と相対死(心中)を果たす。
「早見家文書」によれば、淡路屋のお初という遊女と元禄14年11月6日の夜に心中。
江戸給人百石 小山田庄左衛門
主要登場人物
語部 小山田一閑(十兵衛)...庄左衛門の父親、元播磨国旧赤穂藩浅野家山鹿素行学問指南
大石内蔵助良雄...播磨国旧赤穂藩浅野家筆頭家老
聞手 堀内伝右衛門...肥後国熊本藩細川家白金下屋敷用人
理由 娘の婚家に身を寄せる父が肩身の狭い思いをしているのを案じ、旧浅野家御抱医師の息子・寺井玄達金策するも適わず出奔。25両を盗んで出奔かとおもわせる。
事実は、同志の片岡高房から金5両と小袖を盗んで逃亡。父・一閃は詳細を知りこれを恥じて12月18日に切腹。
江戸歩行小姓頭 中沢弥市兵衛
主要登場人物
語部 白壁屋勘八...麻布今井町豆腐屋の主
登場人物 市兵衛(中沢弥市兵衛)...白壁屋奉公人、播磨国旧赤穂藩浅野家歩行小姓頭
落合与左衛門...播磨国旧赤穂藩藩主・浅野内匠頭長矩室瑤泉院(阿久里)奥様衆
理由 内匠頭の後室・瑶泉院に懸想し、彼女の死に殉じて自刃。
江戸大納戸役 毛利小平太
主要登場人物
語部 木村岡右衛門貞行...播磨国旧赤穂藩浅野家馬廻役・絵図奉行
聞手 波賀清太夫...伊予国松山藩松平家三田中屋敷世話役
登場人物 毛利小平太...播磨国旧赤穂藩浅野家江戸大納戸役
大石主税良金...播磨国旧赤穂藩浅野家家臣
理由 茶器屋・岡崎屋の奉公人に化し、吉良邸の陣容を探中、間者であると知れ、吉良方の目を欺くため、討入り当夜、遊女屋への逗留を指示される。
小姓 鈴木田重八
主要登場人物
語部 小関岡文之進...元上野国伊勢崎藩酒井家旗組小頭
聞手 村尾勘兵衛...上野国伊勢崎藩酒井家目付役
登場人物 玉野平八(鈴木田重八)...本所林町五丁目堀内道場食客、播磨国旧赤穂藩浅野家小姓
理由 潜伏中に名乗った名が、仇持ちだったため、間違われて付け狙われ重傷を負い討入りならず。
浜奉行代行 渡辺半右衛門
主要登場人物
語部 青山武助...三河国岡崎藩水野家小姓組(間十次郎の介錯人)
渡辺半右衛門...播州赤穂新浜塩田の浜男、播磨国旧赤穂藩浅野家浜奉行代行
登場人物 間十次郎光興...播磨国旧赤穂藩浅野家勝手方吟味役
理由 幼少の頃より、間十次郎光興と事を興すと、第三者に禍が降り掛かるため、どちらかが討入りを断念し、互いの老いた親の面倒を見るといった盟約の籤に外れたため。
在々奉行 渡辺角兵衛
主要登場人物
語部 渡辺角兵衛...肥前国佐賀藩鍋島家領内・金立村黒土原にて隠棲、播磨国旧赤穂藩浅野家在々奉行
聞手 田代又左衛門陣基...肥前国佐賀藩鍋島家御書物役
登場人物 山本神右衛門...元肥前国佐賀藩鍋島家御書物役、金立村黒土原にて隠棲
理由 山本神右衛門常朝に主君のために命を捨てるのは下下下の忠であり、上上吉の大忠節とは、主君の御心入れを直し、藩を固め申すこと」。「大石は、あらかじめ主君が間違いを起こさぬよう気配りをなし、国家の安泰をはかるべきだった」と説かれ、感銘を受ける。
武具奉行 灰方藤兵衛
主要登場人物
語部 灰方藤兵衛...京都伏見御香宮門前にて隠棲、播磨国旧赤穂藩浅野家武具奉行
聞手 村木隼人...京都伏見御香宮門前にて隠棲、元常陸国牛久沼山口家(旗本領)浪人→元京伏見御香宮門前江戸元結店の主
登場人物 お丹...藤兵衛の長妹、播磨国旧赤穂藩浅野家京留守居役・小野寺十内の妻
理由 村木隼人と出会い、互いに恋に落ちる。その後、村木は身を呈して、灰方家の窮地を救い失明。村木の面倒を見ながら共に暮らす決意をする。
馬廻 片山忠兵衛
主要登場人物
語部 片山忠兵衛...奥絵師・狩野常信の弟子、播磨国旧赤穂藩浅野家馬廻役
聞手 鎌田軍之助...肥後国熊本藩細川家用人
理由 第3代肥後国熊本藩主・細川綱利の亡き愛妾・花宴を描く依頼を受けるも、その絵の内股の黒子(片山忠兵衛は筆が落ちたと説明)に激怒した綱利の命で、詮議のために細川家に軟禁される。
近習 村上金太夫
主要登場人物
語部 徳治...廻り髪結
聞手 鵜飼惣右衛門...長門国長府藩毛利家家中(前原伊助の介錯人)
理由 乞食に身をやつし吉良邸の抜け穴の在り処を探っていたところ、酔った長屋の住人たちに、生き埋めにされる。
江戸留書役 大森三右衛門
語部 竹村一学...馬喰町町医者、元信濃国上田藩仙石家大納戸方
聞手 大森三右衛門...播磨国旧赤穂藩浅野家江戸留書役
登場人物 弓削佐次馬...信濃国上田仙石家内証用人
理由 信州上田藩千石家内証用人・弓削佐次馬と、蕎麦饅頭の食べ比べの末、口論となり刃傷に及び、その弟・竹村一学により仇持ちとなる。主君の恨みを晴らすまでの猶予を懇願するも、「自縄自縛だ」と、己の運命を感じ入る。
討たれたのだろうと思わせる。
舟奉行 里村津右衛門
語部 里村津右衛門...讃岐国丸亀近く塩浜(塩田)の親方、播磨国旧赤穂藩浅野家舟奉行
聞手 間喜兵衛...播磨国旧赤穂藩浅野家お勝手吟味役、里村津右衛門の義兄弟・従兄弟
新六...間喜兵衛の二男、里村津右衛門の養子
理由 殿中で刀を抜けば、身は切腹。家臣は路頭に迷う。天下の御法に反して上野介の首級を上げれば、残されて泣くのは女であるの思いから、内匠頭と大石を非難し、武士を捨てる。
だが、元里村家の養子であった新六の激しい罵りに、腰抜けでないことの証のために石見銀山を服毒し自裁。
元ノ絵図奉行 川口彦七
語部 林兵助...肥後国熊本藩細川家接伴人
聞手 潮田又之丞...播磨国旧赤穂藩浅野家筆頭国絵図奉行
登場人物 川口彦七(久造)...公義表絵師・狩野良信の弟子、播磨国旧赤穂藩浅野家元ノ絵図奉行
渡辺一蔵...南町奉行所年番与力
理由 川口彦七が顔を潰された遺骸で見付かり、下手人として久造が捕まる。その久造は、どんな拷問にも口を割らなかったが、赤穂浪士が討入ったと聞くと、己が川口彦七であると名乗るのだった。川口彦七であるとなれば殺し自体が成立しなくなる。果たして久造は川口彦七なのか…。
江戸給人百石 松本新五左衛門
語部 お咲...八郎右衛門新田の開拓者八郎右衛門の孫、元津田家・安基姫付き下女
聞手 坊ちゃん...小普請組旗本・津田家の跡取り、松本新五左衛門の嫡男
登場人物 安基姫...津田家の娘
松本新五左衛門...播磨国旧赤穂藩浅野家江戸給人・松本隼人の養子→津田家(安基姫)婿養子
三枝左兵衛...小普請組旗本、松本新五左衛門の実兄
理由 浅野家断絶により、実兄から旗本・津田家への婿養子にいかされ、討入りを断念。だが、討入り後、浪士が義士と崇められるや、養子縁組解消と自刃を迫られ切腹。
討入りの後、そこに名を連ねなかった旧赤穂藩士の置かれた立場と辿った道。そして彼らは討入りを如何に受け止めたのだろうか。
彼らが、討入り不参加を選ぶに至った過程と、現況を、実存した旧赤穂藩士19名の近しい人物が語り部となり物語は進行する。
小説になっているが、緻密な背景考証により、かなり真実に近い証言となっている。
特に、最後の最後まで盟約に名を連ね、討入り当日の配置も裏門方に記録されている毛利小平太の失踪は謎のままであり、多くの作家が手腕を振るう読ませどころとなり、ドラマチックなシーンの筆頭に上げられる人物である。
その毛利小平太を井上氏がどう料理するのか、興味があった。
また、19人ものその後を史実に忠実に脚色しながらも、全てがドラマになるようなストーリに仕上がっており、読み応えあり。切ない結末も多く、華々しく散った46人よりもなお、深みのある死や無念の死を感じ得た。
四十七士の忠臣蔵よりも、遥かに資料も資料も少なかったであろう彼らをここまで書き分けるとは、頭が下がる。井上氏の達者な文章力もさることながら、名作と言っても過言ではないだろう。
また、本文中には、浪士潜伏中の住まいや商い、好みの食べ物から、当時の風潮、討入り便乗商売など多岐に渡り織り込まれている。元禄時代、そして赤穂浪士「忠臣蔵」を知る上で、資料としてもかなり興味深く、「忠臣蔵」よりも正確かつ中身の濃い一冊である。
かなり共鳴を受けた一冊であるが、読むのにかなりの時間を要した。歴史好きで浅野内匠頭刃傷事件に詳しいと自負する当方でさえ、背景や氏素性に混乱する場面もあったので、時代小説好きだけでは些か難解かも知れないだろう。当方も、更に読み返すつもりである。そしてもっと簡潔かつ統一性をもたせて書き直し更新します。
日本人の忠義の美徳とされる「忠臣蔵」ファンにとっては目から鱗の真実がここにある。
余談ではあるが、当方は、荻生徂徠が説いた「浅野内匠頭は吉良上野介との諍いにて切腹に至ったのではなく、殿中での法度に触れた為である」の節に賛同。
松の廊下の事件以前にも、江戸城内での刃傷は3件あったが、いずれも切腹、御家断絶である。
中でも、春日局の曾孫に当たる稲葉石見守に至っては、その場で滅多切りにされている。
大石内蔵助をもってしてこの事実を知らない筈もなく(何せ平成のど町人の当方さへ知っているのだ)、思うに赤穂浪士の討入りより丁度30年前の寛文12年2月3日の浄瑠璃坂の仇討を手本に、浪士たちの仕官を狙っての事と思うのだが、如何だろうか。